マルーン
第五章 自分の手でなにかを
目が覚めると、すでに外は暗くなっていて、自分が長いこと眠り込んでしまっていたことに気づく。眠るときには倒していなかったはずの座席が倒されていて、その上で寝ていたぼくの体には毛布が丁寧にかけられていた。
慌ててまわりをうかがうと、ぼくのほかには誰も車の中にはおらず、車外からフョードルとシャロンの声が聞こえてきた。
車の窓から外をのぞいてみると、ふたりは何やらさかんに動き回っているところだった。
やはりふたりには、疲れているような様子はまったく感じられない。
あまりの体力差に絶望するしかなかった。フョードルもシャロンも気にしなくていいと言ってくれるけれど、二人の体力とぼくの体力とでは雲泥の差だった。
これからの数日間、また今日と同じようにくたくたになることもつらかったけれど、それよりも二人の足を引っ張ることが申し訳なかった。
なにより、シャロンの前で情けない姿を何度も見せてしまっているのが本当に恥ずかしかった。
──あぁ、やっぱりぼくはだめなやつだ‥‥。
「やっぱり、コロニーを出るべきじゃなかったのか」なんて考えがあたまをよぎったとき、突然車のドアが開かれた。
「あ、起きたんだね!ちょうどよかった!これから夜ご飯作るから、手伝って!」
近くに誰もいないのをいいことに、涙が流れそうになるのを放っておいたぼくは、入ってきたのがシャロンだと気づくと慌ててあくびをしていたフリをして誤魔化した。「わかったよ」と言って、目をこする。
シャロンは、今回はぼくが泣きそうになっていたことには気がつかなかったようで、「まってるね!」とだけ言うとすぐにまた戻って行ってしまった。
シャロンがいなくなって、車内がまたシーンと静まりかえったところで、ぼくはようやくシャロンの言葉に違和感を抱いた。
“夜ご飯をつくるから手伝って”
さっきのぼくは、シャロンに一刻も早く立ち去ってほしくて、とっさに「わかった」なんて言って流してしまったけれど、これはおかしな言葉だった。だって、ご飯は『AlicE』につくらせるはずだ。ぼくが手伝うことなんてないはずだった。
器を出したりするのを手伝ってほしいのか‥‥?いや、ユミを入れても四人しかいないぼくたちの食器を出すのは、別にそんなに手間のかかることじゃない。じゃあ、シャロンが言っていた“手伝い”というのは、一体なんなんだろうか?
疑問に頭をうめつくされて、考えても答えが分からなかったぼくは、とにかくふたりのところへ行ってみることにした。さっき返事をしてしまった以上、ふたりを待たせるわけにもいかなかった。
車の扉を開けて外に出ると、昨日の夜と同じように冷たい空気が肌をなでた。
寝起きで体温が下がっているので、余計に寒く感じる。空は昨日の夜と同じように、分厚い雲が覆っていて月の光すらない。
ぼくは上着を着ながら、ふたりのもとに向かった。
「おお、来たな。トーマはシャロンの方を手伝ってくれ」
フョードルは、なにやら腰を下ろして地面でごそごそと何かしていた。
今はその胸の中にユミはいない。ユミは、持ち運びのできるベビーベッドの上で、『AlicE』の保育機に世話されているようだった。
フョードルの手元には、細い枝木が集められて、その上に乾いた藁がのせられている。
ぼくにはそれがなんなのか、フョードルが今から何をしようとしているのかまったく分からなかった。
「なにをしているの‥‥?」
「火を熾すんだ」
フョードルはあっさりと言うと、また同じ作業に取りかかりはじめた。
しかし、ぼくはそれを慌てて止めに入る。
「火なんて、危ないじゃないか」
むかしの人間が火を使っていたことは知っている。
しかし、それはもう何千年前もむかしのことで、電気が発達してからは火はその役割をどんどん失っていった。
コロニーでは、どんな場所であっても火が検知されると、ただちに消化型『AlicE』が出動して火を消し止めに出動する。
もっとも、コロニー内で実際に火が発生したことは、ぼくが知る限りは一度もないけれど。
「使い方を間違えさえしなければ、火は人間の強い味方になるんだよ」
そう言って、フョードルは懐から木箱を取り出した。
木箱の中には、角張った綺麗な石と、金属の塊、そして木の枝と黒ずんだごみのようなものがそれぞれ区分けされて入っていた。
「この火打ち金と火打ち石を打ち合わせて、火種を落とすんだ」
そう言うと、フョードルは金属の塊と角張った石を両手に持つと、それら二つを勢いよく打ち合わせた。すると、打ち合わされた所から、星のようにきらめく火花が散って落ちた。きれいな光だった。
けれど、落ちた火種は藁につくことなく消えてしまった。
「消えちゃったよ」
ぼくが言うと、フョードルは笑いながら説明してくれる。
「火打ち金から落ちる火種は、この燃料に直接着火できるほど温度が高くないんだ。だから、これを使うのさ」
フョードルはそう言うと、区分された箱の中からあの黒いごみのようなものを示してみせた。
「これは火口といって、木綿を蒸し焼きにしたものだ。まず、ここに火種を落とすんだ」
そう言ってフョードルはその火口の上でもう一度激しく火打ち金と火打ち石を打ち合わせた。そこから落ちた火種が、今度は消えずに火口の中で静かに燃えている。しかし、その火はいつまで経っても大きくならない。
「火口は一度蒸し焼きにしたことで、炎を出すのに必要な揮発性分がなくなっているんだ。だから、こうして煙を出さずに静かに燃える。けれど、これではまだ燃料に火を移せない。そこで最後にこのつけ木を使って炎を移すんだ」
フョードルは箱の中から小さな木の棒を取り出すと、火口の火にそれをあてた。すると、一息に火がうつって、つけ木の先が炎をあげて燃えはじめた。
フョードルがその火を積んであった藁にあてると、そこからどんどん燃え広がって、あっという間に大きな炎がぼくたちの前に現れた。
肌を覆っていた冷たい空気が、にわかに暖かくなった。
はじめて見る炎の迫力に、ぼくはすこし恐ろしくなったけれど、同時にその姿をとてもきれいだと思った。
赤々とした輝きの中に、オレンジや黄色といった色が混ざり合って、さまざまな形や模様を生みだしては消えていく。風にゆらめいて輝きを放つ炎は、神秘的でありながら、威厳にも満ちていた。
炎に見惚れていると、シャロンがぼくを呼ぶ声が聞こえて、慌てて彼女の方に向かう。
シャロンは調理型『AlicE』と向き合って、中から食べ物を取り出しているところだった。どうやら量が多いらしく、取り出したものを腕に抱えながらぼくを呼んでいた。
あぁ、食べ物を運ぶのを手伝って欲しかったのか。
「遅くなってごめん、シャロン。運ぶの手伝うよ」
「ありがとう〜、材料多いから大変なんだ」
シャロンは笑いながらぼくの手に食べ物を渡してきた。しかし、手渡されたものは、ぼくの想像を裏切るようなものだった。
「はい」と言って手渡されたのは、完成した料理じゃなく、その素材だった。
「え、これ‥‥、調理されてないけど‥‥」
ぼくの反応を予想していたらしいシャロンが、悪戯っぽく笑った。
「調理はね、これから自分たちでするんです!」
得意顔で胸を張ったシャロンの言葉に、ぼくは旅に出てから何度目かわからない衝撃に襲われた。
たしかに、『AlicE』には完成した料理のデータだけでなく、素材としてのデータも搭載されていて、素材だけをつくることができる。
けれど、ぼくは料理なんてしたことがない。いや、ぼくだけじゃない。コロニーの人間はみんなそうだろう。そもそもぼくたちには、料理を自分でするなんていう発想がなかった。だって、そんなことは『AlicE』がすべてやってくれるから。
『AlicE』のつくる料理はどれも美味しいし、失敗しない限りは毎回まったく同じものができる。自分でつくったものが『AlicE』がつくったものより美味しくなるとは思わなかったし、自分で作ろうとする理由がなかった。
“自分たちで料理する‥‥”
そうか、フョードルがユミのミルクをわざわざ粉ミルクからつくっていたのは、別にユミのミルクが特別なわけじゃなかったのか。
ふたりにとっては、自分たちが食べるものも含めて、料理を自分たちでつくるということが普通だったのだ。
「でも、コロニーでは料理なんてしてなかったよね」
「自分たちで料理するための道具がなかったからね。実はずっと探して集めようとしてたんだけど、製造用『AlicE』に頼んでも、大体のものは危険物扱いでつくってくれなかったんだよ。他のお家を回っても見たけど、どのお家も『AlicE』に頼りっぱなしなんだもの。全然見つからなかった。火は仕方ないにしても、電磁誘導加熱機(IH)すらないとは思わなかったよ」
あぁ、そういうことだったのか。ということは、フョードルがおこした炎は暖をとるためじゃなく、料理に使うものなのか。
しかし、ぼくに料理なんてできるのだろうか‥‥。今この手の中にある素材に、なにをどうすればいいのかも見当がつかないというのに。
「トーマは料理するのはじめてでしょ。でも大丈夫!わたしが教えてあげるから!」
‥‥彼女はいつもぼくの不安を払いのけてくれる。胸を叩いて「まかせなさい!」と自信満々に言う彼女が眩しかった。臆病で心配性なぼくとは大違いだ。
──ぼくも、この世界を見てまわれば彼女のようになれるだろうか?
シャロンに言われるがまま、手を水と石鹸で洗って、腰の上くらいの簡易テーブルの前に立った。
シャロンはそれぞれの素材について、どういう処理をして、どういう状態にすればいいのかを一つ一つ丁寧に教えてくれた。
今のシャロンは、肩のあたりまである髪を後ろにくくっている。普段とは違った髪型のシャロンに見惚れていると、説明を聞き漏らして怒られてしまった。
「よし、それじゃあやっていくよー」
シャロンに言われたとおり、まず玉ねぎに手を伸ばした。
シャロン曰く、玉ねぎが肝心らしい。玉ねぎのパリパリとした皮をむいて、さっと水で流す。洗い終わった玉ねぎをまな板の上に置くと、シャロンはナイフを取り出した。
そのナイフは、フョードルがむかしほかのコロニーで手に入れたものらしい。コロニー5に入居する際に危険物として没収されていたらしいが、コロニーを出る時に返却されたそうだ。その鋭い切先に、ぼくはごくりと唾を飲んだ。
しかし、シャロンは怖がる様子もなく、器用に玉ねぎを切りはじめた。切り方にも種類があるらしく、この玉ねぎの切り方は「くし形切り」というらしい。
ぼくはいつ自分の出番が来るかと身構えていたけれど、シャロンは玉ねぎをそのまま全部切り終えてしまうと、バターと、あらかじめ塩コショウがふられたお肉と一緒にフョードルの所へ持っていってしまった。
肩透かしをくらったぼくは、戻ってきたシャロンに「玉ねぎとお肉はなるべく早く炒めはじめないとだから」と言われて謝られた。
シャロンは次に、鮮やかなオレンジ色のにんじんと皮に包まれたじゃがいもを手に取った。
ぼくもそれにならって、玉ねぎと同じように水で洗い流していく。洗い終わったところで、シャロンがまたナイフを取り出して、これまた器用に野菜の皮をむきはじめた。
シャロンが流れるような手つきで野菜な皮をむいていくのは見ていて気持ちよかったけれど、シャロンはもう一つのナイフを取り出すと、それをぼくにも渡してきた。‥‥ぼくにもやれということか‥‥。
おそるおそるナイフを受け取って、最初は手探りで、とりあえずシャロンを見ながら皮をむきはじめた。
しかし、すぐに横からダメ出しが入れられる。
「そんなに長く持ったら危ない!あと、ナイフは動かさないの!根元に近い刃もとをつかって、野菜の方を回してむくんだよ」
‥‥先に言って欲しかった。
けれど、シャロンのアドバイスにしたがうと、自分でも驚くほどむきやすくなったのがわかった。
さすがにシャロンほどはやく、きれいには出来ないけれど、くるくると野菜の皮がむけていくのは、なんだか楽しかった。
「次は、この野菜を切るよー。それぞれ切り方が違うからね。ニンジンはいちょう切りで、薄く切ります。ジャガイモは乱切りでゴロゴロに切ります」
シャロンはぼくの手を取って、ナイフの正しい持ち方を教えてくれた。ガチガチに固まった手で、ぼくはまた不器用に野菜を切りはじめたけれど、シャロンは「ゆっくりで、焦らなくていいからね」と言ってくれた。
シャロンの言葉に励まされながら、ぼくは少しずつ自信を持って野菜を切り進めた。
はじめはなかなか上手く切れなくて苦戦したけれど、少しずつ刃が通るようになっていくと、だんだんと楽しくなってきた。形も最初の不細工なものにくらべると、少しずつ整ってきた。
けれど、隣りのシャロンを見ると、やっぱりぼくとは比べものにならないくらいの速さと正確さで切り進めている。サクサクと小気味よいリズムで切っていくその手際はあざやかで、思わず「お見事です」と言ってしまいたくなった。
「よし、切れた!トーマもだいぶ慣れてきたねー!じょうずだよ!」
シャロンに褒められて嬉しくなったぼくは、つい調子に乗って切るスピードをあげた。
しかし、見栄を張った罰か、人差し指を少し切ってしまった。
「いっ!」
「あっ!切っちゃったの!?」
傷口から流れ出る血に気づいたシャロンが、慌ててぼくの手を取った。
あぁ、やってしまった‥‥。なんだかぼくは、シャロンの前で格好つけようとすると、いつもこうなる気がする‥‥。
調子に乗ったことを後悔していると、シャロンは突然、ぼくの傷口に口付けた‥‥。
「しゃしょしゃしょしょろん!?」
な、な、な、なにをしているんだ!?
え、え、え?いまなにがおきている?なにがおこってる!?
おちつけ‥‥!!冷静になれ‥‥!!
そうだ、シャロンはただ傷口から血を吸い出してくれているだけだ。
落ち着け‥‥。シャロンの唇、柔らかい‥‥、じゃなくて‥‥!!
「どう?血止まった?」
突然シャロンがぱっと唇を離した。唇が離れる時の、ちゅっという音が、ぼくの耳にはやけに大きく響いた。
シャロンは、思考がかき乱されて呂律すら回らない状態になっているぼくに気づかず、こてんと首を傾げてぼくの指を見ている。そのあどけない表情に、ぼくは余計に変な気分になってしまった。唇についたぼくの血が、シャロンの色素の薄い唇を口紅のように飾っている‥‥。
なんなんだ‥‥、いったいなんなんだ‥‥!!
「うん、止まったみたい!そんなに深く切らなかったんだね。よかった!でも、一応絆創膏はっておかないと!」
そう言ってシャロンは医療キットの中から絆創膏を取ってくると、ぼくの指に巻いてくれた。
けれど、ぼくはもう指の痛みなんかとっくに感じなくなっていた。ずっと頭がくらくらしていた。シャロンのさっきの行動も、シャロンが口を離したときに見えた濡れた指も、ずっと頭の中を駆け巡ってぼくの頭を沸騰させていた。
顔が熱い。きっと、今のぼくはものすごく顔が赤くなっている。
「最初は切っちゃうこともあるよ。わたしも何回も切ってきたもの。ちょっとずつ練習してできるようになればいいんだから、あんまり気にしないでね」
思考がまとまらず、押し黙ったままのぼくの様子に、シャロンはぼくが落ち込んだと勘違いしたのか、やさしく慰めの言葉をかけてくれた。
けれど、その慰めの言葉ですら、今のぼくにとってはシャロンへの気持ちを強める燃料にしかならなかった。
‥‥君は分かっているのだろうか。
今のぼくには、傷の痛みも、カッコつけようとして失敗した情けなさも、ぼくよりもずっとしっかりしている君への劣等感も、余計なほかの感情は一切なにもなく、そのこころのうちでは、ただ君への想いが溢れているということを。
──あぁ、ぼくはやっぱり彼女のことが好きなんだ。
はじめて言葉でこの気持ちを表した。こころの中で言葉に表したとたん、ぼくはまた、自分の世界を映すレンズが切り替わったのを感じた。
いや、ちがう。きっと、初めて彼女を見た時から、ぼくの世界は変わっていたんだ。ずっとむかしにいたというラグビー選手もびっくりするぐらいの鋭いタックルでひっくり返されたあの時、情けなく地面に転がりながら彼女の髪とその間にのぞく青い瞳を一目見た時から。
ぼくのこころの中では、フョードルがおこしたあの炎のように、シャロンへの想いが燃え上がっていた。
しかし、それはあの炎よりもずっと大きく、そして心地よい炎だった。
◆
ぼくが指を怪我してしまったあと、シャロンはぼくが担当していた分の野菜も全部切って、それを全部フョードルの所へ持って行ってくれた。
ぼくは、使い終わったナイフやまな板などの道具を洗っている。切ってしまった人差し指には、シャロンが絆創膏を巻いてくれたので、水に濡れても痛くない。
「助かったよトウマ〜、ありがとうー。二人でやるとやっぱり楽だね」
戻ってきたシャロンは、野菜を入れておいたボウルを自分で洗おうとしたので、ぼくはシャロンの手からボウルを受け取ると、代わりにそれを洗った。ぼくの切った野菜の量は、シャロンが切った量の半分くらいだ。だから、これくらいはしたかった。
「シャロンにほとんど切らせちゃったじゃん」
「いやいや!あれだけ切ってくれたらすっごく助かるんだよ!」
シャロンはそう言ってくれるが、ぼくとしてはもっと上達して、ちゃんとシャロンに頼りにされたかった。
今回の結果に満足できていないぼくに、シャロンはさらに言葉をつないだ。
「なによりさ、こうやってふたりで料理するの、とっても楽しかった!」
シャロンは心の底からの本音だというように、身体全体で今回の料理が楽しかったことを表してくれた。
たしかに、最初は不安だったけれど、やってみるととても楽しかった。途中で嬉しいような困るようなハプニングはあったものの、振り返ってみると、ぼくは料理をするのを楽しんでいた。
「うん、楽しかった。はじめてやったけど、なんだかすごく、楽しかったよ」
こころのうちの気持ちをうまく言葉にすることができないぼくに、シャロンは「うんうん」と嬉しそうにうなずいてくれる。
彼女のその顔を見ていたら、ぼくももっと嬉しい気持ちになった。
「フョードルが、もうそろそろ出来るって言ってたから、もうすぐ食べられるよ」
そこでぼくはやっと、今自分たちが何をつくっているのか知らないということに気がついた。さっきまでシャロンとふたりで一緒に行っていた野菜が何に使われるのかもわからない。
「フョードルは何をつくっているの?」
「あー、うーん、そうだなぁ。‥‥出来てからのお楽しみです!」
はぐらかされてしまった。フョードルといい、シャロンといい、この親子はぼくの疑問をはぐらかす癖があるみたいだ。
でも、もうすっかり慣れてしまった。それに、こんなふうに人差し指を口元にあてて、悪戯っぽい笑顔なんて向けられたら、ぼくはもう何も言えない。
おとなしく完成を待とうと決めて一息つこうとしたところで、なにやらいい匂いが風に乗ってふわりと漂ってきた。
「お、この匂いは‥‥。もう出来たみたいだね!」
シャロンの言うとおり、この匂いはどうやらフョードルが火の番をしている方向から来ているようだった。「はやく、はやく」とぼくを急かすシャロンと一緒にフョードルの所へ行くと、匂いはいっそう強くなった。
「匂いに釣られて腹ペコ子どもが二人も来たな」
フョードルが笑いながら言った。フョードルは、焚き火に鍋をかけて、その中身をかき混ぜている。ぼくたちが嗅ぎつけた匂いは、その鍋の中から漂ってきているようだった。
「シチューだよ!」
シャロンが「じゃじゃーん!」と得意気に言った。
──シチュー。肉や魚、野菜を煮込んだスープの料理だ。けれど、今フョードルがつくっているシチューは、ぼくの知っている茶色のソースで煮込まれたシチューじゃなくて、それとは正反対の真っ白なシチューだった。
ぐつぐつと煮える白いソースのなかに、柔らかそうにほぐれた鶏肉や、ごろりとしたじゃがいも、薄く切られたにんじん、長い時間煮込まれて飴色になった玉ねぎが浸かっていて、料理全体を色あざやかに彩っていた。あたりには、バターとクリームの甘い香りが漂い、ぼくのお腹は自然とぐーっとなってしまった。
「ホワイトシチューだ」
フョードルが、シャロンと同じように珍しくすこし得意気に言った。
“ホワイトシチュー”‥‥、はじめて聞く食べ物だった。けれど、食欲をかき立てるその料理に、ぼくはもう夢中だった。
興奮を抑えながら椅子に座って、フョードルが鍋からすくい取った白いシチューを見つめた。湯気と一緒に深い香りが運ばれてきて、口の中でよだれが溢れるのを感じる。
フョードルは丁寧にシチューを器によそうと、それをぼくに差し出してくれた。興奮と期待でその器を受け取る手が震えた。
はやる気持ちを抑えて、湯気を放つシチューに息を吹きかける。すこし冷めたのを見計らって、スプーンで大きくシチューをすくって一口食べた。すると、口の中に温かくてクリーミーな濃厚さと、優しい味わいがぶわっと広がった。鶏肉は柔らかく、口の中でとろけるようにほぐれ、じゃがいもと玉ねぎはほんのりと甘みを出して、濃厚なクリームの中にやさしい味わいを作り出していた。
「美味しい!本当に美味しい!」
ぼくが心からの声をあげると、フョードルも満足げに笑った。シャロンもぼくの反応を見て、嬉しそうににこにこしている。
「このシチューは、俺の師匠が教えてくれた料理でな。俺にとってこのシチューは、人生でちょっとした幸せを感じられる秘密のレシピなんだ」
幸せを感じる秘密のレシピ‥‥。たしかに、このシチューを食べたぼくは、こころがぽかぽかと温まって、幸せな気持ちになっている。
ただ一つフョードルの言葉と違っているのは、その幸せがちょっとじゃなくて、とても大きいことだった。
「ちょっとどころじゃないよ。ぼく今、すごく幸せな気持ちだ。こんなに美味しいもの、はじめて食べたよ」
フョードルは嬉しそうに「そうか」と言うと、ぼくの頭を撫でた。
このシチューは、ぼくが今まで一番好きだった、『AlicE』がつくったあのラーメンよりも、ずっとずっと美味しかった。こんなに何かを美味しいと感じたのは、人生できっとはじめてだ。
‥‥そういえば、『AlicE』のデータベースに、ホワイトシチューなんてものはなかったはずだ。料理のリストを全部見たことがあるわけじゃないけれど、コロニーの老人たちの口からも“ホワイトシチュー”なんて料理は聞いたことがなかった。
さっきフョードルは「秘密のレシピ」と言っていた。ということは、『Alice』のデータベースには登録されていない、オリジナルの料理なのだろうか?
「秘密ってことは、『AlicE』のレシピには載っていないの?」
ぼくは、自分が感じた疑問を素直にフョードルにきいた。すると、フョードルはやさしく笑いながら「ないな」と言った。
そうか。じゃあ、この味はぼくたちしか知らないのか。
そう思うと、この味が余計に特別なものに感じられた。けれど、フョードルはぼくの予想外の言葉を続けた。
「なにせ、俺のこのレシピは、毎回こまかい分量がちがっていて、作るたびに味が少しずつ変わるからな」
「え!?」
「というより、きちんと分量を量って作ったことなんてないから、そういう意味ではレシピなんて言えるものじゃないかもしれん。まあ、今日のこれはなかなか上手くできたと自分でも思っているがな」
ぼくの反応を見て、フョードルは大きく笑った。けれど、ぼくはそんなことはまったく気にならないくらい、フョードルの言葉に驚愕していた。
ぼくにとっての料理は、“絶対的に正しいレシピ”があって、それに従ってつくる“毎回同じ味のするもの”だった。
だって、『AlicE』がそうだったから。毎回同じ味のする食べ物を、正確につくりあげる。そして仮にレシピとの間に少しでも誤差が生まれれば、それは失敗作として破棄される。それが料理だと思っていた。
しかし、たった今、その考えは木っ端みじんに打ち砕かれた。
“正確なレシピがない”。そんな料理があったなんて‥‥。それになにより、そんな料理がこんなに美味しいなんて‥‥。
驚きと戸惑いで混乱しているぼくに、フョードルは「いや、すこし違ったな」と言ってホワイトシチューの料理について話しはじめた。
「この料理は俺が師匠から教わったものでな。俺の師匠は東の果ての島国から来た人だったんだが、この料理は何千年も前に、その師匠の故郷で、名前もわからない誰かが創り出したものだそうだ。だから、この料理ももともとは『AlicE』のデータベースにいわゆる“正しいレシピ”が登録されていたんだ。しかし、220年前の事件でそれが消失してしまった」
220年前の『AlicE』のデータの消失事件。その中には、世界中の文化に類するもの、つまり食事も含まれていた。
「『AlicE』のデータが消えて、世界中の人々の記憶からも忘れ去られてしまった後も、この料理は師匠のいた『見届ける者(ゲイザー)』の集落で、奇跡的に細々と受け継がれていたらしい。その作り方を、師匠が俺に教えてくれたんだ」
食事のデータ群もまた、他のデータ群と同じく、そこに保存されていた情報のうち、ぼくが好きだったラーメンや、ほかにも人気のあった料理のデータは復元することができた。
当時はもうすでに自分で料理をつくる人間は少なかったけれど、人気のある料理は、かろうじてそれをつくる人間が残っていたからだ。
ただ、そのほかのデータは、やはり二度と取り戻すことができなかった。一口に「料理のデータ」と言っても、世界中の、それもさまざまな時代の料理が登録されていたわけだから、その量は天文学的なものだったろう。このホワイトシチューも、その中に含まれていた料理の一つだったのか。まさか、そんな料理がめぐりめぐってぼくの口に入ることになるとは。
このホワイトシチューの辿ってきた不思議な歴史を思うと、ぼくはなぜだか自分の心が震えるのを感じた。
しかし、そこでぼくの中に一つの疑問が浮かんだ。
「でも、フョードルも、フョードルの師匠も、フョードルの師匠のコロニーの人たちも、どうして、このホワイトシチューのレシピを復元しようとしなかったの?“完全なレシピ”はわからなくても、大まかな作り方はわかっていたんだよね?」
分量を量るのが面倒くさくて毎回味が変わってしまうのなら、美味しくできた時の情報を学習させてしまえば、次からはもう失敗してしまうこともないだろう。そうすれば、毎回同じ、美味しい味のシチューが食べられる。
そうだ。こんなに美味しいなら、今回のこのレシピを“完全なレシピ”として『AlicE』に学習させてしまえば良いじゃないか!
ぼくは名案を閃いたと思って、興奮しながらそれをフョードルに伝えると、しかしフョードルは目を伏せて「うむ‥‥」と考え込んでしまった。
なにか、気に障るようなことを言ってしまっただろうか‥‥?
「たしかに、このホワイトシチューはいつもよりも上手くできた。何度も作ってきた俺にとっても、上位に入る美味さだな。たしかにこれを毎回食べることができれば良いかもしれない。‥‥しかしな、俺たちは失敗するということも、存外に悪くないと思っているんだ」
「え?」
意味がわからなかった。失敗することなんて、明らかに悪いことだろう。すくなくとも良いことではないはずだ。だって、料理を失敗してしまえば、それは食べられなくなってしまうじゃないか。
それが、どうして悪くないなんてことになるのだろう。
「料理に限った話じゃないが、俺は“完全”であったり、“絶対的に正しいもの”というのが、あまり好きじゃないんだ」
フョードルは、ぐつぐつと鍋の中で煮えるシチューを見ながら話しはじめた。
「『AlicE』のデータベースはたしかに素晴らしい技術だが、今の世界では、『AlicE』に登録されている料理のレシピが、“唯一絶対に正しいレシピ”として認識されているだろう?俺は、その認識が嫌いなんだ。俺は、人間がなにかをつくるということは、別の何かを元にして、ひとりひとりが「俺ならもっとこうする」、「私ならここはこうする」と新しいことを考えて、変化させていくということだと思っているんだよ」
たしかに、データベースに登録されるもとになった料理は、『AlicE』にレシピが登録されるまでは、人間の間でいろいろな工夫がされていたのだろう。『AlicE』のデータベースが充実していくにつれて、人間のそういった活動がどんどんなくなっていったのもたしかだ。
でも、やっぱり一度とても美味しいと思える料理ができたのなら、わざわざそのつくり方から外れてつくる必要はないんじゃないだろうか。
つくり方を決めておかないなら、次もまた上手くできるかはわからないのだから。
「‥‥でも、一度美味しくできたなら、ずっとその時と同じつくり方でつくった方が、次も絶対美味しいものが食べられるよ。それに、つくるのに失敗したら、ぼくはやっぱりがっかりすると思う」
「たしかに、上手くいかなかった時は残念だな。だが、もしかすると、前と違うやり方でつくった時の料理の方がもっと美味しいかもしれないだろう?もしくは、失敗したと思ったものでも、意外と美味しいかもしれない。実際、そうやって失敗だと思われたものが新しい料理として認められたことも山ほどある。すくなくとも、そうやって新しいことに挑戦した人間がいたからこそ、ここまで多くの料理が生まれたんだ。そして、そうやって創られたものを元にして、また新しいものが創られる‥‥、その繰り返しで、人間の世界はここまで回ってきたんだ。それに‥‥」
フョードルは一瞬深く考え込むような顔になったかと思うと、次の瞬間にはぼくの顔をすっと見据えてきた。
ぼくは、今から話されることが、なんだかとても大切なことであるような気がして、その言葉を聞き漏らさないようにしようと身体を寄せた。
「そもそも、人間は、失敗を繰り返す存在なんだよ」
フョードルは、慎重に言葉を選びながら、こころのうちを明かそうとしてくれているようだった。
「俺は、人間というのは、永遠に出ることのできない迷宮のような世界の中で、決して手に入らないものを探して彷徨い続ける存在だと思っている」
‥‥どういう意味だろう。よくわからなかったぼくは、思っていることがそのまま顔に出ていたのだろう。フョードルは静かに笑みを浮かべたけれど、すぐに真剣な表情に戻って話を続けた。
「‥‥これは師匠の受け売りなんだがな。そもそもこの世界には、“正しいもの”に限らず、“絶対的なもの”なんて何一つないんじゃないかと俺は思っているんだ。この世界は、ただここに存在しているだけで、そこには本来、“絶対に正しいこと”や“絶対に間違っていること”なんてものはない。そして、この世界に生きる人間もまた同じで、世界から見たときに“絶対的に正しいあるべき姿”‥‥、そして、“生まれてきた意味”なんていうものも、きっとないんだ」
フョードルは、“生まれてきた意味”という言葉を言うのに合わせてぼくの方へ顔を向け、目を合わせた。
その静かな視線に、しかしぼくはぞわっと背筋に冷たいものが走るのを感じた。“生まれてきた意味”‥‥。それは、ぼくがコロニーを出た理由だ。誰からも望まれずに生まれた自分の命の意味を、外の世界に探しに行くこと‥‥。
しかし、フョードルは今、“そんなものはない”とはっきりと口にした。
にわかに鳥肌が立って、心臓が不愉快な大きさと早さで鼓動をはじめる。
「この世界は、人間のために生まれたわけじゃないからな。世界が人間にとって“絶対に正しいもの”や“生まれてきた意味”なんてものを用意してくれているわけはない」
フョードルの言葉が進められていくたびに、冷や汗が出てくる
火に当たって暖かった空気が、急激に熱を失って冷えていくような気がした。
「しかし、人間は知恵を授かったことで、不安を抱くようになった。この大きすぎる世界で、どこにも寄る辺なく生きるのは辛いからな。自分たちの存在を肯定してほしくて、自分たちの存在の意味について考えるようになったんだ。だが、この世界にはそんなものは本来ないので、それを考えはじめた人間は、永遠にその答えを見つけることはできない。‥‥すべての人間が、この答えのない、永遠に出ることのできない迷宮のような世界の中にいるんだ。ただ、その世界が迷宮だと気付いた人間と、気付いていない人間とに分かれているだけで。そして、この世界が迷宮だと気付いてしまった人間は、永遠に出ることのできない迷宮の中で、決して手に入らないその答えを探して彷徨い続けるんだ。散々彷徨って、新しい答えを見つけて喜んでは、それが絶対的なものじゃなかったことを知って、傷ついて、また彷徨い出す‥‥、それをずっと繰り返していく」
炎を見つめながら静かに話すフョードルの眼差しは、炎の中で揺らめいては消えていくその形と模様の上に、フョードルが話す人間の姿を重ねて視ているかのようだった。
フョードルの言葉を通して、その目が視ているものの深さに触れた気がしたぼくは、ぞっと恐ろしくなった。
もしも、フョードルの言葉が真実だとしたら、この世界には‥‥、人間には‥‥、あまりに救いがなさすぎる。
「そんな‥‥」
けれど、フョードルが今話していることは、ぼくがこれまで散々思ってきたことだった。
人間は、3000年前に宇宙へと飛び出した頃には、科学こそがこの世界における絶対的なものだと信じて疑わなかった。そして、それよりさらにむかし、宇宙どころか空も飛べなかったころの人間は、“神”が絶対的なものだと信じきっていた。
しかし、それらふたつの拠り所は、世界というあまりに大きなものの前に、あっさりと時の流れの中に崩れ去ってしまった。ぼくには、人間の科学力も、神も、信じるものは何もなかった。
──あぁ、だからあの時‥‥、ゴシック建築を見た時に、ぼくは怒りが湧いたんだ。
後の時代に立つぼくは、かつての人間が無邪気に信じていたものが、絶対的なものじゃなかったことを知っている。
神なんていう、存在しないもののことを一方的に想って、あんな建物までつくってしまったその愚かさへの軽蔑と、どうしようもないやるせなさが、あの時のぼくの怒りの正体だった。
ゴシック建築を見た時だけじゃない。シャロンに「人間がつくったものが一番すごい」と言われた時も同じだ。
科学を絶対的なものと考え、それを操る自分たちのことを過信して、“世界は自分たちのためにある”だなんて幻想を抱いていた時代の人間に対しても、ぼくは「そんなわけないじゃないか」と冷めた目で見て、彼らに対して、神を信じていた時代の人間に対して抱いていたものと同じ、軽蔑とやるせなさを感じていたのだ。
そんなことを、ひとりでいじいじと考えていたぼくが、今更フョードルにそれと同じことを言われたところで、落ち込んでいるなという話だ。そんなことは、筋が通らないだろう。
けれど、自分の中で悲観的に考えていたことを、他の人から「事実だ」と言われてしまうのは、やはり辛かった。
──この世界に‥‥、人間に‥‥、ぼくたちに、救いはないのか‥‥?
どうやらぼくは、自分が、フョードルの言う“絶対に答えを得られない迷宮”の中にいると気付いた側の人間になってしまったようだ。
“自分の生きる理由”、“自分が生まれた意味”なんて、あるわけがないとわかっているのに、それがどこかにないものかと、必死に探し続けなければいけない永遠の迷宮に。
──暗い。なにも見えない。あぁ、辛い。だれか、助けて。誰でもいい。神でも、悪魔でも、誰でもいいから。誰か、ここから出してくれ‥‥。
目の前も見えない暗い迷宮で、ぼくはたしかに彷徨っていた。
しかし、そこへフョードルの声が凛と響いた。
「しかし、だからこそ俺は、人間と、人間が創り出したものを本当に偉大だと思っているし、愛おしく感じているんだ」
炎に照らされて、光と影が舞い踊っているフョードルの顔に笑みが浮かんだ。それは、シャロンやぼく、ユミに向けて時たま見せてくれるものと同じ、あのやさしい笑みだった。
「人間は、この理不尽な世界に産み落とされて、何も見えない、わからないところから、手探りで世界を探り、広げていった。たしかに、そこで人間が求めていた答えは見つからなかったし、その過程で何度も酷い過ちを犯してきたかもしれない。だが、そうやって彷徨うなかで、人間はこの世界に様々なものを創り出してきた。建築も、音楽も、文学も、映画も、ゲームも、そして食べ物も、すべては人間がこの世界を彷徨って、自分たちで世界に刻み込んだものだ。俺は、それこそがこの世界において、人間にとってたった一つだけ存在する“意味”なんじゃないかと思うんだ。“絶対的な意味”のないこの世界で、“願い”を込めて、自分たちでゼロから意味を創り出す‥‥。その過程こそが、人間が人間たる所以であり、“人間が生きる理由”そのものなんじゃないか、とな」
“願い”‥‥。シャロンも同じことを言っていた。
ぼくは、まだそれが何なのか掴めていない。けれど、フョードルの言葉は、迷宮を彷徨っていたぼくの前に突然射しこんできた一筋の光のように感じられた。
──ぼくもその“願い”が感じられるようになれば、ふたりのように人間を、この世界を愛せるようになるのだろうか。
──“ぼくが生きる理由”を、見つけることができるのだろうか。
湯気を放つホワイトシチューを美味しそうに食べながら、フョードルは言葉を続けた。
「だから、そうやって人間が紡いできた新しいものを創るという環を、その流れを、俺たち『見届ける者(ゲイザー)』は断ち切りたくない。‥‥“見届けたいんだ”」
そうだった。彼らは『見届ける者(ゲイザー)』だ。人間が遺したものを尊ぶ存在だ。“料理をする”という行為も、彼らにとっては人間が遺したものの一つなのだ。
「だから、フョードルとシャロンは、『AlicE』を使わずに、自分で料理をするんだね」
ぼくの言葉に、フョードルとシャロンは顔を見合わせて笑っている。
もしかして、違うのだろうか?
ふたりの反応に戸惑っていると、フョードルが微笑を浮かべながらシャロンの頭を撫でた。
「もともとはそういう考えでやっていたんだがな。師匠が亡くなって、一人になってからは“自分で料理をする”ということで自分の生きる理由を少しでも肯定したかったんだ。‥‥意固地になっていたんだな。だが、シャロンが生まれてからは、すこしちがう」
フョードルは、シャロンの頭を撫でながら、ぼくの方に目を向けた。
「トーマは、シャロンと料理をつくってみてどうだった?」
「え‥‥、」
「とってもたのしかったわ!」
シャロンはパァッと輝くような笑顔を見せながら答えた。
その笑顔を見ながら、ぼくも自分が楽しんでいたことを思い出す。そうだ、ぼくも、楽しかった。人生ではじめて、自分でなにかをつくったという達成感ももちろん得られたけれど、それよりもシャロンと料理するのは、なんだか胸が温まるような感じがして‥‥
「うん、楽しかった。‥‥それになんだか、幸せだったな」
あのときは上手く言葉にできなかったけれど、今、自分のこころを振り返ってみると、“ふたりで料理をつくった”、ただそれだけのことが、ぼくはとても大切で、幸せなことのように感じていたのだ。
ぼくがそう言うと、フョードルはやさしく笑みを浮かべながら、今度はぼくの頭を撫でてくれた。
「俺も、シャロンが生まれてからは料理をするのが楽しくなったんだ。それまでは、義務感のようなものに駆り立てられていたのが、ただ幸せな気持ちになるようになった。シャロンが大きくなって、一緒に作ってくれるようになると、その幸せはさらに大きくなった。‥‥なにより、自分でつくった料理を、人に美味そうに食べてもらえるのは、大きなよろこびだ。それこそ、それだけで生きていて良かったと思えるくらいに」
フョードルの言葉にはっとする。
そうだ。今、このシチューには、ぼくがさっき自分で切った野菜がたくさん入っている。綺麗に切られたじゃがいもやにんじんの中に、少し不恰好なかたちをして混ざっているのが、ぼくが切ったものだ。上手くつくることはできなかったけれど、それでもこんなに美味しいシチューを自分たちでつくったかと思うと、なんだかこのホワイトシチューが、ますます美味しく感じられたし、フョードルが言ったように、“生きていてよかった”という気持ちが溢れてきた。
「自分で作ることで、もしくは人につくってもらうことで、料理の味が変わる。気持ちの問題かもしれないが、そもそも人間というのは、感情が束になったような存在だ。身体とこころが結びついていたとしても、不思議じゃないだろう?」
ぼくは、コロニーの老人たちがくれたBLTサンドウィッチのことを思い出した。
昨日の昼に食べたあのサンドウィッチは、ぼくがそれまで食べてきたものとまったく同じもののはずだった。けれど、それを食べたぼくは、二つのサンドウィッチの間に、たしかな違いを感じた。あれは、自分と同じように『AlicE』を使ったものだとしても、誰かにつくってもらった物だから感じられた美味しさだったのか。
──待てよ、それじゃあ、ぼくがラーメンを美味しく感じられなくなったのは、もしかして‥‥
その時、突然ぼくの頭の中を電撃が走った。閃光が炸裂したかのように頭の中がちかちかして、あちこちに散らばっていたものが次々と結びついていった。
そういうことだったのか。ぼくを含めて、コロニーの老人たちがみんな同じように陥ってしまった『もう美味しくない病』‥‥、それまでは美味しかったはずのものが、どんどん美味しく感じられなくなっていくあの現象。あれは、『AlicE』の料理にあるものが欠けていたことで起こっていたんだ。それはきっと、“人間の感情”だ。
フョードルの話を聞き、実際にこのシチューを食べて、ぼくは、感情や情緒がどれだけ人間に影響するのかを実感した。人間はきっと、ぼくが思っている以上に繊細で、そして感受性が豊かなのだ。
ぼくも、コロニーの老人たちも、『AlicE』がつくる料理には、フョードルのこのホワイトシチューや、むかしの人間が自分たちでつくっていた料理にはあったはずの、“感情”が込められていないことを無意識に感じ取っていたのだろう。それが、徐々にぼくたちの“美味しい”と感じる部分を麻痺させていったのだ。
ずっと自分のこころを縛ってきた呪いの正体がわかったぼくは、興奮しながら、今ぼくが考えたことをふたりに伝えた。
ふたりは、ぼくたちの身にそんなことが起きていたということは知らなかったようで、驚くと同時に悲しそうな顔になってしまった。
「好きだった食べ物が美味しく感じられなくなっちゃうなんて‥‥、かわいそう‥‥」
シャロンは、元気のない声でそう言うと、しゅんと落ち込んでしまった。フョードルも言葉にはしなかったけれど、同じように感じているはずだった。
ずっと料理に向き合って、その素晴らしさを理解しているふたりだからこそ、“食べ物が美味しくなくなっていく”ということの絶望感が誰よりも深く理解できるのだろう。
ぼくはふと、『AlicE』さえ生まれなければ、こんなことにはならなかったのだろうか、と思った。
『AlicE』は人間を幸福にするために生み出されたものだ。けれど、それが結果的に食事という人間の幸せを奪ってしまったというなら、それは本末転倒だ。
「『AlicE』が人間の代わりをするようになったのは、よくなかったのかな‥‥」
「そうだよ。ぜんぶ人間がやっていたときの方が絶対よかったのに」
シャロンは、ぼくのつぶやきを即座に肯定した。シャロンは、はじめて会ったときから3Dプリンターでつくられた建物や、『AlicE』には興味を向けなかったから、ぼくは、「やっぱりそうか」と納得するのと同時に、どこか寂しさのようなものをおぼえた。
しかし、フョードルの答えはシャロンとはちがったものだった。
「いいや、それは違う。技術が進歩したことは、間違いなく人間を幸せにしたさ。今だって、俺たちがこうして安全に旅ができるのは、『AlicE』やほかの道具のおかげだろう?」
フョードルが、ユミを世話している『AlicE』や車、地図、GPS、さっき火をつけた道具、果ては鍋に至るまでまわりのものを順番に指差して示した。
「こういう便利な道具が生まれたことで、人間には選択肢ができた。何かを“する”、“しない”という選択肢だ。たとえば、車が生まれるまでは、人間が移動するには歩くしかなかっただろう?それこそ、急いでいる時や疲れている時もだ。だが、車が生まれたことで、人間は二つの選択肢から選ぶことができるようになった。急いでいたり、疲れている時は車を使えばいい。運動したかったり、ゆっくりと景色が見たい時には歩けばいい、というようにな。『AlicE』の調理機能も本来は同じだ。急いでいたり、疲れている時にはこれ以上に助かるものはない。実際、俺たちも今日の昼は、料理を作る時間を惜しんで、『AlicE』がつくった飯を食べただろう?」
フョードルがシャロンに問いかけると、シャロンは「うぅ‥‥」と声を詰まらせた。シャロンは納得しきれていないようだったけれど、フョードルの言葉を否定するだけの言葉は持っていない様子だった。
フョードルは「ただ、」と言葉を続けた。
「俺も、その道具を使うべき時について、人間はもっと深く考えるべきだとは思うがな」
使うべき時‥‥。使う時と、使わない時をちゃんと考えて選ぶということか。
たしかに、さっきの車の話で考えるとわかりやすい。急いでいるときは使って、そうじゃないときは歩く。至極簡単な話だった。
けれど、すべての技術がそこまで綺麗に割り切れるだろうか。
ましてや、『AlicE』のように、どんな状況、どんな時でも使える技術の場合は、その境界線はとても曖昧なものになってしまうんじゃないだろうか。
ぼくたちが、いつの間にかまったく自分で料理をしなくなってしまったのも、そこに原因がある気がした。
「それは、どうやって判断すればいいの?」
「道具を使うことで、“人間らしさ”が失われるかどうか、ということだ」
フョードルはきっぱりとそう言うと、膝の上で手を組んだ。
「これは俺の持論でしかないんだが‥‥。俺は、人間には等しくやるべきことがあると思っている。それは、“人間らしく生きること”だ」
フョードルは、ぼくとシャロンの顔を見ながら、ひとつひとつの言葉を丁寧に話していく。
「俺は、さっきも言ったように、“絶対的な意味”のないこの世界に、“自分たちで意味を創る”ことが人間らしさだと考えている。だが、これは“ゼロから物を創る”ということだけじゃない。すでに存在する何かに、“価値を与える”ということも含むんだ。‥‥難しいか?」
むずかしい。眉を下げながら聞いてくるフョードルには申し訳ないけれど、新しく出てきた“価値”という言葉がいまいちわからない。
フョードルが今話している価値というのが、昔使われていたという、お金に関わるような意味の言葉じゃないことは、なんとなくわかる‥‥。けれど、じゃあそれはなんなのかと言われると、よくわからなかった。
ただ、この話はシャロンも理解できていないようで、「むーん‥‥」と唸りながら頭を抱えている。
いつもはぼくに教えてくれる側のシャロンが、ぼくと同じように理解できずに苦しんでいるのを見るのは、なんだか新鮮だった。
「たとえばだ。俺たちが今食べているこのホワイトシチュー、これはさっきも言ったように、遠い昔に名前も知らない人間が創り出した食べ物だ。普通、食べ物はつくった分を食べてしまえばなくなるだろう?だからホワイトシチューは、本来なら創った人間が死んでしまえば、二度と現れることはないはずなんだ。だが、現に俺たちは今、ホワイトシチューを食べている。細かい味は違っても、それこそトーマが言ったように大まかな味は似ているだろう。これは、ホワイトシチューを“創った人間”のほかに、“この料理には価値がある”と考えた人間がいたからだ。そして、そうやってホワイトシチューに“価値”を感じた人間が、自分でホワイトシチューをつくって、それをまた他の人間に食べさせる。そして、それを食べた人間の中からまた、“この料理には価値がある”と考える人間が生まれる‥‥。この繰り返しで、ホワイトシチューは俺たちの生きている今まで繋がれてきたわけだ」
フョードルは一度そこで言葉を切って、ぼくたちの様子を確認した。
今のところはなんとかついていけてるはずだ。
つまり、ホワイトシチューは、それをはじめてつくった人間だけじゃなく、それを食べて“美味しい”と思った人間がいたから、今まで残されてきたということだろう。
ということは、ホワイトシチューにおける“価値”とは、“美味しさ”‥‥、いや、“美味しさ”そのものじゃなくて、“人間がそれを残そうとする気持ち”のことで、それが価値になるということだから‥‥
「‥‥つまり、“価値”っていうのは、それを大切に思う気持ちで‥‥、それを人間がなにかの物の中に感じることが、価値を与えるってことで、それが物の“意味”になるってこと‥‥?」
ぼくが自信なく聞くと、フョードルは目を輝かせて、興奮に満ちた表情で頷いた。
「そうだ!そういうことだよ、トーマ!」
フョードルが嬉しそうに頷くのを見て、ぼくはこころの中に安堵と達成感が溢れるのを感じた。シャロンも隣りで「あー!それだぁ!」と共感している。
「俺たちにとっては、人間が遺したものや、自然の光景がそれだ。だから、俺たちはなるべく移動するのに車を使わず、足を使う。そうして見える景色に“価値”を見出し、与えることが俺たちにとっては“人間らしい生き方”であり、“意味”だからだ。車を使ってしまったら、ひとつひとつの景色をよく見ることはできないだろう?」
たしかに、車に乗っていた時は、景色はあっという間に流れていってしまって、印象に残ったものは少なかったけれど、自分の足で歩くようになるとさまざまなものが目に入るようになった。そして、そこで目にしたものは、ぼくのこころをたしかに揺り動かした。
あぁ、ぼくはあの時、あの景色に価値を与えていたのか。
「今の俺たちは、まだ自分の足で移動することができるし、移動にかけられる時間が限られているわけでもない。だから、車はなるべく使わない。俺たちの目的を果たすのに、今それは必要ないからだ」
「それじゃあ、道具はどういう時に使うべきなの?」
ぼくの問いかけに、フョードルは笑いながら答える。
「必要になったら使うんだ。たとえば車なら、自分の足では歩けなくなってしまった時や、歩けるには歩けるが、時間が限られている時などだろうな。“人間らしく生きるためにやるべきこと”と、“その道具を使うことで失われてしまう部分”、この二つを鑑みて、“その道具を使うことで得られる人間らしさ”が“その道具を使うことで失われてしまう人間らしさ”を上回る時に、道具を使うべきだと俺は思っている」
なるほど。たしかにそれなら人間が“人間らしさ”を見失わない限り、人間は“正しく生きられる”はずだ。
‥‥あれ?でも、それだと道具を使うか否かは一人一人の判断に委ねられるわけで、その境界線は結局一人一人違ってくるんじゃないのか?そうなると、結局人によっては道具を使うべき時を間違えることになるんじゃないだろうか。
たとえば、世界にあるものすべてがどうでもよくて、何に対しても“価値”を見出さない人間がいたとしたら、その人間は道具を無制限に使うべきということになる。いや、そもそも何に対しても価値を与えることのない人間が本当にいたとしたら、それは人間じゃないのか?だってその人間は、フョードルが最初に言っていた“人間らしい生き方”をしていないのだから。
考えながら、ぼくは、コロニーの老人たちのことを思い出していた。
『スリープ計画』における最後の世代。世界の終わりと向き合って、すべての物に対する関心を失ってしまった人間たち。
彼らは、フョードルの考え方に照らし合わせると“人間らしく”生きてはいなかった。彼らは何物にも価値を見出さずに、熱中するものもなく枯れたように生きていた。
しかし、だからといって彼らが人間でないとは思えなかった。彼らは紛れもなく“人間”だったはずだ。じゃあ、ぼくの中に、フョードルが考えるものとはちがう“人間らしさ”の条件があるのだろうか‥‥。
考えれば考えるほど、わからなくなってしまう。
そもそも、“人間らしい生き方”にしてもそうだ。今のフョードルの話には、とても説得力があった。けれど、それはフョードルにとっての“人間らしさ”が、ぼくにとって納得のいくものだったからだ。
フョードルが価値を見出している“自然”やこの“ホワイトシチュー”には、ぼくも“これには価値がある!”と思った。だから、それを大切にすることが“人間らしさ”なんだと心の底から納得し、共感することができた。
けれど、仮に人を殺すことや人を傷つけることに“価値”を見出すような人間がいたとしたら、その人間にとっては、人を傷つけることが、彼にとっての“人間らしい生き方”ということになってしまう。でもそれは、ぼくにとっては正しいことだとは思えない。人間を傷つけるのは、“悪いこと”だ。そんなことは、誰でも知っている。
それは言ってしまえば、“絶対的に正しいこと”だ。
その時、恐ろしい考えがぼくの頭を走った。
──人を殺すことや、傷つけることが悪いことだと一体誰が決めたんだ?
フョードルの言葉が脳裏によみがえってきた。
“そもそもこの世界には、“正しいもの”に限らず、“絶対的なもの”なんて何一つないんじゃないかと俺は思っているんだ”
フョードルのあの言葉通りに考えるなら、“絶対的に正しいもの”だけでなく、“絶対的に悪いもの”というのも、この世界にはないんじゃないか?
そこまで考えて、ぼくはぞっとした。そして、その感覚に耐えられなくて、ぼくはその考えをフョードルに吐き出した。
「‥‥すべての人間が同じように“価値”を見出す何かはないんだよね。この世界に“絶対的なもの”は一つもないから。でも、仮にそうだとすると、たとえば人を殺したり、傷つけたりする人間が“悪い”っていう考え方自体、この世界には本当はないってこと‥‥?」
すこし震えを含んだ声になっていたと思う。「それはちがう」と言って欲しかった。ぼくの中に浮かんだおそろしい考えを否定して欲しかった。
しかし、フョードルは、ぼくの目を見据えてきっぱりと答えた。
「その通りだ。この世界には“絶対的に悪いこと”も存在しない。たとえそれが、殺人や、他人を踏みにじる行為であってもだ」
ぼくは頭を鈍器で殴られたかのような感覚になった。
さっきまでは、まるでこの世界の真実を見つけたかのようなよろこびに溢れていたのに、それは一息に消え去ってしまった。
つまり、フョードルが今まで話してくれたことは、必ずしも良い方向に向くものとは限らないのだ。人間によっては、悪い方向へと走る原因にもなるし、この考えを認めてしまったら、それを「絶対に悪いことだ」と咎めることもできなくなってしまう。
なぜなら、悪人を責めるための“根拠”‥‥、“絶対的に正しいこと”がなくなってしまうのだから。
しかし、ぼくの頭の中には、そのことに納得できてしまっている自分がいた。
だって、人間がしてきたことは、良いことばかりじゃない。むしろ、悪いことの方が多いくらいだ。
3000年前の人間にしてもそうだ。宇宙の終わりを前に、パニックになって、自分のことだけを考えて、怒りを撒き散らし、八つ当たりし、他人を傷つけた。これを悪と言わずになんと言おう?
しかし、ぼくが“悪いことだ”と思うことをした彼らは、全員がきちんと報いを受けたわけじゃなかった。さまざまな要因で、他人を明確に傷つけたにもかかわらず裁かれなかった人間はごまんといた。
それは、フョードルが言ったように、この世界には本来“善”も“悪”もないからこそ起こることだった。“絶対的に悪いこと”が本当にあるのなら、“悪人”は絶対に裁かれるのだから。
歴史を振り返れば、そういうことは数えきれないほどあっただろう。
個人の間の争い、組織の間の争い、国同士の争い‥‥、人間の活動は争いとは切っても切り離せない。その活動の中で、非道なことをしたにも関わらず、報いを受けずにのうのうと生きた人間がどれだけいることか。そのことを考えるだけで、ぼくの中にはとてつもない怒りが湧いてくる。
けれど、ぼくのこの怒りも、別に正しいわけじゃないのだ。なぜなら、この世界には彼らを咎める“絶対的な正義”なんてものはないのだから。
しかし、それはつまり、ぼくたちが正しい方向を向いているということを保証してくれるものが何もないという意味でもあって、ぼくたちは生き方の指針を完全に失ってしまうことになる。
結局のところ、ぼくたちはやっぱり迷宮の中を彷徨い続けているだけじゃないか。それも、この地球に生まれた時から、ずっと‥‥。
自分という存在の小ささと無力さに、とほうもない虚しさがこころに広がっていく。
しかし、フョードルはぼくの絶望を跳ね除けるような、はっきりとした力強い声で言葉を紡ぎはじめた。
「たしかに、“世界にとって”、“絶対的な悪いこと”は存在しない。だが、“人間にとって”、“絶対的な悪いこと”はこの世界にたしかに存在するんだ」
フョードルはぼくとシャロンの目を見て、言葉を続ける。
「それは、人間のルールの中での“善”と“悪”だ。ルールは単に法というわけじゃない。人間として冒してはならない規範や、生き方そのものだ。人間は、この世界に自分たちで“ルール”を創り出すことで、“善”と“悪”という概念を得たんだ。それは、この宇宙で物理法則以外に存在する唯一のルールなんだ」
しかし、それは人間の中にしか存在しないものじゃないか。そんなものに一体何の意味があるのだろう。
「でも、そんなもの本当は存在しないじゃないか。それは、ただの人間の勝手な“思い込み”で、偽物じゃないか‥‥。そんなものに、なんの意味があるって言うんだよ」
ぼくは、湧き上がる黒い感情のままにフョードルの言葉を否定していく。生意気なことを言っているのは分かっていた。
しかし、“本当はないもの”を“ある”と言うのは、それはただの“嘘”じゃないか。
「その通りだ。これは願いだ。“人間には持つべき規範がある”‥‥、いや、“あって欲しい”という、根拠のない願望だ。世界という大きな視点で見た時、そんなものはたしかに存在しないかもしれない。“悪いこと”をしても、それに自動で反応して悪人を裁いてくれる自然のシステムがあるわけじゃないしな。だが、だからこそ、俺たちはこの世界に“善悪は存在する”と言わなければいけないんだ。なぜなら、俺たち人間だけが、この宇宙で唯一“何かに価値を与えられる存在”なのだから」
その言葉に、ぼくははっとなって顔を上げた。
たしかに、人間がこの世界に価値を見出して、“意味”を与えられる存在ならば、人間自身が価値があると思ったものなら、それは実際に“意味”を持って、存在することになる。
フョードルは静かに、しかしはっきりと言葉を続けた。
「“人間の行為には“善”と“悪”があって、従うべき“規範”がある。そして、それに悖る行為が“悪”である”。そう信じることだけが、この世界に“絶対的に悪いこと”という価値観を生むんだ。人はそれを、“倫理”や“正義”と呼ぶ」
──“正義”
その言葉を思い起こすと、ぼくは自分の胸がカッと熱くなるのを感じた。そんなものがあれば、どんなにいいだろう。しかし、ぼくはまたそこに新たな問題を見出してしまった。
世界から見て“絶対的なもの”がない以上、一人一人が考えるルールはそれぞれ違っている。一つとして同じものがない以上、異なるルールを持つ者同士が出会ってしまえば、両者は衝突するのではないか。いや、絶対にするだろう。
「でも、一人一人のルール…、“正義”が違っていたら、結局ちがうルールを持つ人間同士が対立して、争いになってしまうよね‥‥?」
フョードルはこくりとうなずくと、すっとぼくに目を合わせた。
「そうだ。だから、ひとりひとりが常にちゃんと自分で考えて、自分を律しなければならないんだ」
フョードルの目には、見ている者を惹き込む不思議な力があった。
「人間は、それぞれ違った主観を持つ別の存在だ。他人が考えていることや感じていることは、どうやっても知ることができない。そして、自分の考えや感情もまた、どんな他人であっても知ることができない。だから、自分のこころには、自分で向き合うしかないんだ。“自分が何を大切に思っているのか”、“何を遺すべきと考えているのか”、そして、“どう生きるべきと感じているのか”。そうやって己を律すること自体が、紛れもない“人間らしさ”なんだよ」
フョードルの話は、まさにぼくに向けられたものだった。
その言葉のひとつひとつが、自分の胸に深く刻まれていくにつれ、ぼくの中ではフョードルへの尊敬の念が膨らんでいった。
フョードルは、一体どうやってここまで深く世界のこと、人間のこと、自分のことを考えられたのだろうか。
「フョードルは、どうやってそこまで辿りついたの?」
ぼくは、自分がフョードルのように世界を見ることができるようになるとは思えなかった。
「俺は、どこにも辿り着いていないよ。‥‥師匠の話に魅せられて、コロニーを飛び出して『ゲイザー』になった時から、俺も迷宮を抜け出そうともがいている人間の一人に過ぎない。ただ、もがいている時間がトーマたちよりすこし長いだけだ」
フョードルは、まるで古い記憶を辿るように、ぼんやりと遠くを見つめるような目をしていた。
「俺が特別なわけじゃない。俺の師匠や、それより前の世代の『ゲイザー』‥‥、すべての先人たちが、この迷宮の中を彷徨い、悩み、苦しんでいた。その中の誰一人として、絶対的な答えを見つけることはできなかったが‥‥。だが、俺は彷徨い続けた果てに、ようやく自分の心と向き合えた気がする」
フョードルは、ぼくとシャロンの頭をなでながら、ゆっくりと言葉をつないだ。
「さっき、ゼロから何かを生み出すことが人間にとっては唯一のたしかな“意味”だと言ったがな。あれは“人間”という大きな視点での話だ。俺という一人の人間にとっては、シャロン、そして今はトーマとユミの三人が、俺が“生まれた意味”で、“生きる理由”だ。‥‥生きていくなかで時たま感じられる、こういうちょっとした幸せの積み重ねが、最期自分が死ぬ時に、“幸せな人生だった”と思えることにつながるんじゃないかと俺は思っている」
胸が熱くなるのを感じた。その熱はじわじわと広がって、頭も心地よくのぼせていくようだった。
フョードルの言葉は、ぼくにはとても重く感じられた。
それは、フョードル自身が経験した長い旅路と、悠久の時代から紡がれてきた人間の歴史が積み重なった“時の重み”だった。何世代にもわたって引き継がれてきた人間の探求と苦悩は、ぼくには無数の人間が生きた証として淡い光を放っているように見えた。
一体どれだけの人間が、この時の流れの中に現れては消えて行ったのだろう。そして、どれだけ長い間、人間は苦悩し続けてきたのだろう。
計り知れない時を超え、ぼくの立つ場所まで繋がれてきたそれは、むしろなんだかとても大切なものであるような気がした。
──この時の流れの最後の場所に、ぼくは立っているのだ。
その時、突然ぶわっと背中のあたりが粟立って、それがうなじのあたりまで駆け昇ってくるのを感じた。
旧市街の街並みを見ていた時に感じたあの大きなものが、またすぐそこに現れた気がした。それも、前に現れた時よりもずっと近くに。
今回は掴めるかもしれない‥‥!
ぼくは姿の見えないそれを掴もうと、今まで聞いた言葉を必死でかき集めた。“絶対的なもの”、“願い”、“人間が生きる理由”、“価値”‥‥。
頭の中で言葉を唱えるたび、それはすこしずつこちらに寄ってくるのを感じた。いいぞ、そのままこっちに来い‥‥。
“人間が自分でつくったものには、意味が宿る”
──この世界には“絶対的なもの”はない‥‥
──しかし、人間は自分の存在を肯定するために、決して手に入らない意味を求めて彷徨う存在‥‥
──そして、この世界で唯一、“意味”を持つのは、人間がそこに“価値を与えたもの”、つまり“意味を創ったもの”だけ‥‥
──つまり、“世界の意味”は、人間が創るということ‥‥
見えないものに、指がかかった感触がした。もう少しだ‥‥、もう少しでわかる‥‥。
必死にその先を考える。“世界の意味は、人間が創る”‥‥、だから、だから‥‥。
あぁ、ダメだ。必死に頭を回しても、その先の言葉が出てこない。
あぁ、またいってしまう。もう指がかかっているのに、あとほんの少しで届きそうなのに。
いかないでくれ、頼む。知りたいんだ。この感覚の正体を、この胸をめぐるざわめきの正体を。
しかし、ぼくの願いも虚しく、指にかかっていた大きなものは、ふわりとぼくの指を離れると、あっという間にその気配を拡散させてしまった。
あぁ、また消えてしまった。あんなに間近に感じていたのに。もう手は届いていたというのに。
あと一歩のところまで迫っていた分、ぼくのこころは以前よりも強い失望感に襲われた。
あの時と同じように、フョードルはまた、がっくりとしているぼくの様子に気がついたようだった。
「また、何か掴めそうになったのか?」
「うん‥‥。でも、また掴めなかった‥‥」
フョードルは短く「そうか‥‥」と言って、ぼくのあたまをぽんぽんと叩いてくれた。
前回も、そして今回も、あの感覚はフョードルの話がきっかけでぼくのもとに訪れた。ぼくは、あの感覚をどうしても掴みたくて、シャロンがいるということも構わず、フョードルにもっと話を聞かせてくれるようにせがもうかとも思った。しかし、今さっきフョードルに“自分で考えなければいけない”と教えられたばかりで、そんなことはできなかった。
「残念だったな‥‥。だが大丈夫だ。いつか必ず掴むことがきるから」
「‥‥前もそうだったんだ。あの感覚は、フョードルの話を聞くといつも来るんだ‥‥」
フョードルはやさしく笑いながは首を振った。
「俺の話は、もしかしたらトーマがその感覚を掴むきっかけにはなったのかもしれない。だが、言っただろう?俺たち人間は、互いの考えていることや感じていることを理解できるわけじゃない。俺も同じような感覚になった経験があるが、それは似ているだけで同じじゃない。それは、トーマが、自分で感じ取らなければいけないものなんだよ」
つまり、フョードルも、ぼくのこの感覚の完全な正体はわからないということなのか。じゃあ、もしもぼくが自分で掴むことができなければ、もしかすると、この感覚は一生掴めないのかもしれない‥‥。そんなのは嫌だった。
「だがな、トーマ。逆に言えばその感覚は、この世界で唯一、“トーマだけのもの”なんだよ。他の誰にも知ることのできない、トーマだけの宝なんだ」
フョードルの言葉に、ぼくははっとした。そうだ、あれはぼくのものなのだ。あの感覚の気配を感じただけで、そこに指がかかっただけで、ぼくの中には大きなよろこびと興奮が沸き起こるのを感じた。間違いなく、あれはぼくの本質に関わるようなものだ。
きっと、あの感覚が、ぼくの旅の目的なんだ。
「トーマ。前も言ったが、焦らなくてもいいんだ。前にもそれは、掴みかけたものだろう?大丈夫だ。必ず分かる日が来る」
フョードルのその言葉も、ぼくの頭を撫でる手も、すべてがやさしさを帯びていた。その手に撫でられていると、何の根拠もないのに、なんだか本当に大丈夫な気がしてきて、沈んだ心がすこしずつ立ち直っていった。
そうだ。たしかに今回は、前よりもずっと近くに感じられたんだ。きっと次こそは、掴めるはずだ。
「さあ、長話が過ぎたな。せっかくの料理だ、冷めてしまう前に食べよう。美味い飯を食べて、よく寝れば疲れも取れるさ」
フョードルはそう言って話を締めると、空になった器にもう一度ホワイトシチューをよそうと、それを本当に美味しそうに食べはじめた。
その様子を見ていたぼくとシャロンも、自分のお腹がまた空腹を訴え出すのを感じて、ホワイトシチューをおかわりした。
シャロンは「美味しいなぁ、幸せだねぇ」としきりに言いながら、ぼくとフョードルに笑いかけてくる。
ぼくは目を閉じ、ホワイトシチューに込められたものをじっくりと味わった。料理の素晴らしさは、単に舌の上で感じる“味”にあるのではなく、そこに込められた感情を感じ取ることで心を癒し、幸せな気持ちにさせてくれることにあった。
一口食べるごとに、ぼくは、このホワイトシチューに新しい希望と、この世界を生きる勇気を与えられているような気がした。
マルーン
第五章 自分の手でなにかを
目が覚めると、すでに外は暗くなっていて、自分が長いこと眠り込んでしまっていたことに気づく。眠るときには倒していなかったはずの座席が倒されていて、その上で寝ていたぼくの体には毛布が丁寧にかけられていた。
慌ててまわりをうかがうと、ぼくのほかには誰も車の中にはおらず、車外からフョードルとシャロンの声が聞こえてきた。
車の窓から外をのぞいてみると、ふたりは何やらさかんに動き回っているところだった。
やはりふたりには、疲れているような様子はまったく感じられない。
あまりの体力差に絶望するしかなかった。フョードルもシャロンも気にしなくていいと言ってくれるけれど、二人の体力とぼくの体力とでは雲泥の差だった。
これからの数日間、また今日と同じようにくたくたになることもつらかったけれど、それよりも二人の足を引っ張ることが申し訳なかった。
なにより、シャロンの前で情けない姿を何度も見せてしまっているのが本当に恥ずかしかった。
──あぁ、やっぱりぼくはだめなやつだ‥‥。
「やっぱり、コロニーを出るべきじゃなかったのか」なんて考えがあたまをよぎったとき、突然車のドアが開かれた。
「あ、起きたんだね!ちょうどよかった!これから夜ご飯作るから、手伝って!」
近くに誰もいないのをいいことに、涙が流れそうになるのを放っておいたぼくは、入ってきたのがシャロンだと気づくと慌ててあくびをしていたフリをして誤魔化した。「わかったよ」と言って、目をこする。
シャロンは、今回はぼくが泣きそうになっていたことには気がつかなかったようで、「まってるね!」とだけ言うとすぐにまた戻って行ってしまった。
シャロンがいなくなって、車内がまたシーンと静まりかえったところで、ぼくはようやくシャロンの言葉に違和感を抱いた。
“夜ご飯をつくるから手伝って”
さっきのぼくは、シャロンに一刻も早く立ち去ってほしくて、とっさに「わかった」なんて言って流してしまったけれど、これはおかしな言葉だった。だって、ご飯は『AlicE』につくらせるはずだ。ぼくが手伝うことなんてないはずだった。
器を出したりするのを手伝ってほしいのか‥‥?いや、ユミを入れても四人しかいないぼくたちの食器を出すのは、別にそんなに手間のかかることじゃない。じゃあ、シャロンが言っていた“手伝い”というのは、一体なんなんだろうか?
疑問に頭をうめつくされて、考えても答えが分からなかったぼくは、とにかくふたりのところへ行ってみることにした。さっき返事をしてしまった以上、ふたりを待たせるわけにもいかなかった。
車の扉を開けて外に出ると、昨日の夜と同じように冷たい空気が肌をなでた。
寝起きで体温が下がっているので、余計に寒く感じる。空は昨日の夜と同じように、分厚い雲が覆っていて月の光すらない。
ぼくは上着を着ながら、ふたりのもとに向かった。
「おお、来たな。トーマはシャロンの方を手伝ってくれ」
フョードルは、なにやら腰を下ろして地面でごそごそと何かしていた。
今はその胸の中にユミはいない。ユミは、持ち運びのできるベビーベッドの上で、『AlicE』の保育機に世話されているようだった。
フョードルの手元には、細い枝木が集められて、その上に乾いた藁がのせられている。
ぼくにはそれがなんなのか、フョードルが今から何をしようとしているのかまったく分からなかった。
「なにをしているの‥‥?」
「火を熾すんだ」
フョードルはあっさりと言うと、また同じ作業に取りかかりはじめた。
しかし、ぼくはそれを慌てて止めに入る。
「火なんて、危ないじゃないか」
むかしの人間が火を使っていたことは知っている。
しかし、それはもう何千年前もむかしのことで、電気が発達してからは火はその役割をどんどん失っていった。
コロニーでは、どんな場所であっても火が検知されると、ただちに消化型『AlicE』が出動して火を消し止めに出動する。
もっとも、コロニー内で実際に火が発生したことは、ぼくが知る限りは一度もないけれど。
「使い方を間違えさえしなければ、火は人間の強い味方になるんだよ」
そう言って、フョードルは懐から木箱を取り出した。
木箱の中には、角張った綺麗な石と、金属の塊、そして木の枝と黒ずんだごみのようなものがそれぞれ区分けされて入っていた。
「この火打ち金と火打ち石を打ち合わせて、火種を落とすんだ」
そう言うと、フョードルは金属の塊と角張った石を両手に持つと、それら二つを勢いよく打ち合わせた。すると、打ち合わされた所から、星のようにきらめく火花が散って落ちた。きれいな光だった。
けれど、落ちた火種は藁につくことなく消えてしまった。
「消えちゃったよ」
ぼくが言うと、フョードルは笑いながら説明してくれる。
「火打ち金から落ちる火種は、この燃料に直接着火できるほど温度が高くないんだ。だから、これを使うのさ」
フョードルはそう言うと、区分された箱の中からあの黒いごみのようなものを示してみせた。
「これは火口といって、木綿を蒸し焼きにしたものだ。まず、ここに火種を落とすんだ」
そう言ってフョードルはその火口の上でもう一度激しく火打ち金と火打ち石を打ち合わせた。そこから落ちた火種が、今度は消えずに火口の中で静かに燃えている。しかし、その火はいつまで経っても大きくならない。
「火口は一度蒸し焼きにしたことで、炎を出すのに必要な揮発性分がなくなっているんだ。だから、こうして煙を出さずに静かに燃える。けれど、これではまだ燃料に火を移せない。そこで最後にこのつけ木を使って炎を移すんだ」
フョードルは箱の中から小さな木の棒を取り出すと、火口の火にそれをあてた。すると、一息に火がうつって、つけ木の先が炎をあげて燃えはじめた。
フョードルがその火を積んであった藁にあてると、そこからどんどん燃え広がって、あっという間に大きな炎がぼくたちの前に現れた。
肌を覆っていた冷たい空気が、にわかに暖かくなった。
はじめて見る炎の迫力に、ぼくはすこし恐ろしくなったけれど、同時にその姿をとてもきれいだと思った。
赤々とした輝きの中に、オレンジや黄色といった色が混ざり合って、さまざまな形や模様を生みだしては消えていく。風にゆらめいて輝きを放つ炎は、神秘的でありながら、威厳にも満ちていた。
炎に見惚れていると、シャロンがぼくを呼ぶ声が聞こえて、慌てて彼女の方に向かう。
シャロンは調理型『AlicE』と向き合って、中から食べ物を取り出しているところだった。どうやら量が多いらしく、取り出したものを腕に抱えながらぼくを呼んでいた。
あぁ、食べ物を運ぶのを手伝って欲しかったのか。
「遅くなってごめん、シャロン。運ぶの手伝うよ」
「ありがとう〜、材料多いから大変なんだ」
シャロンは笑いながらぼくの手に食べ物を渡してきた。しかし、手渡されたものは、ぼくの想像を裏切るようなものだった。
「はい」と言って手渡されたのは、完成した料理じゃなく、その素材だった。
「え、これ‥‥、調理されてないけど‥‥」
ぼくの反応を予想していたらしいシャロンが、悪戯っぽく笑った。
「調理はね、これから自分たちでするんです!」
得意顔で胸を張ったシャロンの言葉に、ぼくは旅に出てから何度目かわからない衝撃に襲われた。
たしかに、『AlicE』には完成した料理のデータだけでなく、素材としてのデータも搭載されていて、素材だけをつくることができる。
けれど、ぼくは料理なんてしたことがない。いや、ぼくだけじゃない。コロニーの人間はみんなそうだろう。そもそもぼくたちには、料理を自分でするなんていう発想がなかった。だって、そんなことは『AlicE』がすべてやってくれるから。
『AlicE』のつくる料理はどれも美味しいし、失敗しない限りは毎回まったく同じものができる。自分でつくったものが『AlicE』がつくったものより美味しくなるとは思わなかったし、自分で作ろうとする理由がなかった。
“自分たちで料理する‥‥”
そうか、フョードルがユミのミルクをわざわざ粉ミルクからつくっていたのは、別にユミのミルクが特別なわけじゃなかったのか。
ふたりにとっては、自分たちが食べるものも含めて、料理を自分たちでつくるということが普通だったのだ。
「でも、コロニーでは料理なんてしてなかったよね」
「自分たちで料理するための道具がなかったからね。実はずっと探して集めようとしてたんだけど、製造用『AlicE』に頼んでも、大体のものは危険物扱いでつくってくれなかったんだよ。他のお家を回っても見たけど、どのお家も『AlicE』に頼りっぱなしなんだもの。全然見つからなかった。火は仕方ないにしても、電磁誘導加熱機(IH)すらないとは思わなかったよ」
あぁ、そういうことだったのか。ということは、フョードルがおこした炎は暖をとるためじゃなく、料理に使うものなのか。
しかし、ぼくに料理なんてできるのだろうか‥‥。今この手の中にある素材に、なにをどうすればいいのかも見当がつかないというのに。
「トーマは料理するのはじめてでしょ。でも大丈夫!わたしが教えてあげるから!」
‥‥彼女はいつもぼくの不安を払いのけてくれる。胸を叩いて「まかせなさい!」と自信満々に言う彼女が眩しかった。臆病で心配性なぼくとは大違いだ。
──ぼくも、この世界を見てまわれば彼女のようになれるだろうか?
シャロンに言われるがまま、手を水と石鹸で洗って、腰の上くらいの簡易テーブルの前に立った。
シャロンはそれぞれの素材について、どういう処理をして、どういう状態にすればいいのかを一つ一つ丁寧に教えてくれた。
今のシャロンは、肩のあたりまである髪を後ろにくくっている。普段とは違った髪型のシャロンに見惚れていると、説明を聞き漏らして怒られてしまった。
「よし、それじゃあやっていくよー」
シャロンに言われたとおり、まず玉ねぎに手を伸ばした。
シャロン曰く、玉ねぎが肝心らしい。玉ねぎのパリパリとした皮をむいて、さっと水で流す。洗い終わった玉ねぎをまな板の上に置くと、シャロンはナイフを取り出した。
そのナイフは、フョードルがむかしほかのコロニーで手に入れたものらしい。コロニー5に入居する際に危険物として没収されていたらしいが、コロニーを出る時に返却されたそうだ。その鋭い切先に、ぼくはごくりと唾を飲んだ。
しかし、シャロンは怖がる様子もなく、器用に玉ねぎを切りはじめた。切り方にも種類があるらしく、この玉ねぎの切り方は「くし形切り」というらしい。
ぼくはいつ自分の出番が来るかと身構えていたけれど、シャロンは玉ねぎをそのまま全部切り終えてしまうと、バターと、あらかじめ塩コショウがふられたお肉と一緒にフョードルの所へ持っていってしまった。
肩透かしをくらったぼくは、戻ってきたシャロンに「玉ねぎとお肉はなるべく早く炒めはじめないとだから」と言われて謝られた。
シャロンは次に、鮮やかなオレンジ色のにんじんと皮に包まれたじゃがいもを手に取った。
ぼくもそれにならって、玉ねぎと同じように水で洗い流していく。洗い終わったところで、シャロンがまたナイフを取り出して、これまた器用に野菜の皮をむきはじめた。
シャロンが流れるような手つきで野菜な皮をむいていくのは見ていて気持ちよかったけれど、シャロンはもう一つのナイフを取り出すと、それをぼくにも渡してきた。‥‥ぼくにもやれということか‥‥。
おそるおそるナイフを受け取って、最初は手探りで、とりあえずシャロンを見ながら皮をむきはじめた。
しかし、すぐに横からダメ出しが入れられる。
「そんなに長く持ったら危ない!あと、ナイフは動かさないの!根元に近い刃もとをつかって、野菜の方を回してむくんだよ」
‥‥先に言って欲しかった。
けれど、シャロンのアドバイスにしたがうと、自分でも驚くほどむきやすくなったのがわかった。
さすがにシャロンほどはやく、きれいには出来ないけれど、くるくると野菜の皮がむけていくのは、なんだか楽しかった。
「次は、この野菜を切るよー。それぞれ切り方が違うからね。ニンジンはいちょう切りで、薄く切ります。ジャガイモは乱切りでゴロゴロに切ります」
シャロンはぼくの手を取って、ナイフの正しい持ち方を教えてくれた。ガチガチに固まった手で、ぼくはまた不器用に野菜を切りはじめたけれど、シャロンは「ゆっくりで、焦らなくていいからね」と言ってくれた。
シャロンの言葉に励まされながら、ぼくは少しずつ自信を持って野菜を切り進めた。
はじめはなかなか上手く切れなくて苦戦したけれど、少しずつ刃が通るようになっていくと、だんだんと楽しくなってきた。形も最初の不細工なものにくらべると、少しずつ整ってきた。
けれど、隣りのシャロンを見ると、やっぱりぼくとは比べものにならないくらいの速さと正確さで切り進めている。サクサクと小気味よいリズムで切っていくその手際はあざやかで、思わず「お見事です」と言ってしまいたくなった。
「よし、切れた!トーマもだいぶ慣れてきたねー!じょうずだよ!」
シャロンに褒められて嬉しくなったぼくは、つい調子に乗って切るスピードをあげた。
しかし、見栄を張った罰か、人差し指を少し切ってしまった。
「いっ!」
「あっ!切っちゃったの!?」
傷口から流れ出る血に気づいたシャロンが、慌ててぼくの手を取った。
あぁ、やってしまった‥‥。なんだかぼくは、シャロンの前で格好つけようとすると、いつもこうなる気がする‥‥。
調子に乗ったことを後悔していると、シャロンは突然、ぼくの傷口に口付けた‥‥。
「しゃしょしゃしょしょろん!?」
な、な、な、なにをしているんだ!?
え、え、え?いまなにがおきている?なにがおこってる!?
おちつけ‥‥!!冷静になれ‥‥!!
そうだ、シャロンはただ傷口から血を吸い出してくれているだけだ。
落ち着け‥‥。シャロンの唇、柔らかい‥‥、じゃなくて‥‥!!
「どう?血止まった?」
突然シャロンがぱっと唇を離した。唇が離れる時の、ちゅっという音が、ぼくの耳にはやけに大きく響いた。
シャロンは、思考がかき乱されて呂律すら回らない状態になっているぼくに気づかず、こてんと首を傾げてぼくの指を見ている。そのあどけない表情に、ぼくは余計に変な気分になってしまった。唇についたぼくの血が、シャロンの色素の薄い唇を口紅のように飾っている‥‥。
なんなんだ‥‥、いったいなんなんだ‥‥!!
「うん、止まったみたい!そんなに深く切らなかったんだね。よかった!でも、一応絆創膏はっておかないと!」
そう言ってシャロンは医療キットの中から絆創膏を取ってくると、ぼくの指に巻いてくれた。
けれど、ぼくはもう指の痛みなんかとっくに感じなくなっていた。ずっと頭がくらくらしていた。シャロンのさっきの行動も、シャロンが口を離したときに見えた濡れた指も、ずっと頭の中を駆け巡ってぼくの頭を沸騰させていた。
顔が熱い。きっと、今のぼくはものすごく顔が赤くなっている。
「最初は切っちゃうこともあるよ。わたしも何回も切ってきたもの。ちょっとずつ練習してできるようになればいいんだから、あんまり気にしないでね」
思考がまとまらず、押し黙ったままのぼくの様子に、シャロンはぼくが落ち込んだと勘違いしたのか、やさしく慰めの言葉をかけてくれた。
けれど、その慰めの言葉ですら、今のぼくにとってはシャロンへの気持ちを強める燃料にしかならなかった。
‥‥君は分かっているのだろうか。
今のぼくには、傷の痛みも、カッコつけようとして失敗した情けなさも、ぼくよりもずっとしっかりしている君への劣等感も、余計なほかの感情は一切なにもなく、そのこころのうちでは、ただ君への想いが溢れているということを。
──あぁ、ぼくはやっぱり彼女のことが好きなんだ。
はじめて言葉でこの気持ちを表した。こころの中で言葉に表したとたん、ぼくはまた、自分の世界を映すレンズが切り替わったのを感じた。
いや、ちがう。きっと、初めて彼女を見た時から、ぼくの世界は変わっていたんだ。ずっとむかしにいたというラグビー選手もびっくりするぐらいの鋭いタックルでひっくり返されたあの時、情けなく地面に転がりながら彼女の髪とその間にのぞく青い瞳を一目見た時から。
ぼくのこころの中では、フョードルがおこしたあの炎のように、シャロンへの想いが燃え上がっていた。
しかし、それはあの炎よりもずっと大きく、そして心地よい炎だった。
◆
ぼくが指を怪我してしまったあと、シャロンはぼくが担当していた分の野菜も全部切って、それを全部フョードルの所へ持って行ってくれた。
ぼくは、使い終わったナイフやまな板などの道具を洗っている。切ってしまった人差し指には、シャロンが絆創膏を巻いてくれたので、水に濡れても痛くない。
「助かったよトウマ〜、ありがとうー。二人でやるとやっぱり楽だね」
戻ってきたシャロンは、野菜を入れておいたボウルを自分で洗おうとしたので、ぼくはシャロンの手からボウルを受け取ると、代わりにそれを洗った。ぼくの切った野菜の量は、シャロンが切った量の半分くらいだ。だから、これくらいはしたかった。
「シャロンにほとんど切らせちゃったじゃん」
「いやいや!あれだけ切ってくれたらすっごく助かるんだよ!」
シャロンはそう言ってくれるが、ぼくとしてはもっと上達して、ちゃんとシャロンに頼りにされたかった。
今回の結果に満足できていないぼくに、シャロンはさらに言葉をつないだ。
「なによりさ、こうやってふたりで料理するの、とっても楽しかった!」
シャロンは心の底からの本音だというように、身体全体で今回の料理が楽しかったことを表してくれた。
たしかに、最初は不安だったけれど、やってみるととても楽しかった。途中で嬉しいような困るようなハプニングはあったものの、振り返ってみると、ぼくは料理をするのを楽しんでいた。
「うん、楽しかった。はじめてやったけど、なんだかすごく、楽しかったよ」
こころのうちの気持ちをうまく言葉にすることができないぼくに、シャロンは「うんうん」と嬉しそうにうなずいてくれる。
彼女のその顔を見ていたら、ぼくももっと嬉しい気持ちになった。
「フョードルが、もうそろそろ出来るって言ってたから、もうすぐ食べられるよ」
そこでぼくはやっと、今自分たちが何をつくっているのか知らないということに気がついた。さっきまでシャロンとふたりで一緒に行っていた野菜が何に使われるのかもわからない。
「フョードルは何をつくっているの?」
「あー、うーん、そうだなぁ。‥‥出来てからのお楽しみです!」
はぐらかされてしまった。フョードルといい、シャロンといい、この親子はぼくの疑問をはぐらかす癖があるみたいだ。
でも、もうすっかり慣れてしまった。それに、こんなふうに人差し指を口元にあてて、悪戯っぽい笑顔なんて向けられたら、ぼくはもう何も言えない。
おとなしく完成を待とうと決めて一息つこうとしたところで、なにやらいい匂いが風に乗ってふわりと漂ってきた。
「お、この匂いは‥‥。もう出来たみたいだね!」
シャロンの言うとおり、この匂いはどうやらフョードルが火の番をしている方向から来ているようだった。「はやく、はやく」とぼくを急かすシャロンと一緒にフョードルの所へ行くと、匂いはいっそう強くなった。
「匂いに釣られて腹ペコ子どもが二人も来たな」
フョードルが笑いながら言った。フョードルは、焚き火に鍋をかけて、その中身をかき混ぜている。ぼくたちが嗅ぎつけた匂いは、その鍋の中から漂ってきているようだった。
「シチューだよ!」
シャロンが「じゃじゃーん!」と得意気に言った。
──シチュー。肉や魚、野菜を煮込んだスープの料理だ。けれど、今フョードルがつくっているシチューは、ぼくの知っている茶色のソースで煮込まれたシチューじゃなくて、それとは正反対の真っ白なシチューだった。
ぐつぐつと煮える白いソースのなかに、柔らかそうにほぐれた鶏肉や、ごろりとしたじゃがいも、薄く切られたにんじん、長い時間煮込まれて飴色になった玉ねぎが浸かっていて、料理全体を色あざやかに彩っていた。あたりには、バターとクリームの甘い香りが漂い、ぼくのお腹は自然とぐーっとなってしまった。
「ホワイトシチューだ」
フョードルが、シャロンと同じように珍しくすこし得意気に言った。
“ホワイトシチュー”‥‥、はじめて聞く食べ物だった。けれど、食欲をかき立てるその料理に、ぼくはもう夢中だった。
興奮を抑えながら椅子に座って、フョードルが鍋からすくい取った白いシチューを見つめた。湯気と一緒に深い香りが運ばれてきて、口の中でよだれが溢れるのを感じる。
フョードルは丁寧にシチューを器によそうと、それをぼくに差し出してくれた。興奮と期待でその器を受け取る手が震えた。
はやる気持ちを抑えて、湯気を放つシチューに息を吹きかける。すこし冷めたのを見計らって、スプーンで大きくシチューをすくって一口食べた。すると、口の中に温かくてクリーミーな濃厚さと、優しい味わいがぶわっと広がった。鶏肉は柔らかく、口の中でとろけるようにほぐれ、じゃがいもと玉ねぎはほんのりと甘みを出して、濃厚なクリームの中にやさしい味わいを作り出していた。
「美味しい!本当に美味しい!」
ぼくが心からの声をあげると、フョードルも満足げに笑った。シャロンもぼくの反応を見て、嬉しそうににこにこしている。
「このシチューは、俺の師匠が教えてくれた料理でな。俺にとってこのシチューは、人生でちょっとした幸せを感じられる秘密のレシピなんだ」
幸せを感じる秘密のレシピ‥‥。たしかに、このシチューを食べたぼくは、こころがぽかぽかと温まって、幸せな気持ちになっている。
ただ一つフョードルの言葉と違っているのは、その幸せがちょっとじゃなくて、とても大きいことだった。
「ちょっとどころじゃないよ。ぼく今、すごく幸せな気持ちだ。こんなに美味しいもの、はじめて食べたよ」
フョードルは嬉しそうに「そうか」と言うと、ぼくの頭を撫でた。
このシチューは、ぼくが今まで一番好きだった、『AlicE』がつくったあのラーメンよりも、ずっとずっと美味しかった。こんなに何かを美味しいと感じたのは、人生できっとはじめてだ。
‥‥そういえば、『AlicE』のデータベースに、ホワイトシチューなんてものはなかったはずだ。料理のリストを全部見たことがあるわけじゃないけれど、コロニーの老人たちの口からも“ホワイトシチュー”なんて料理は聞いたことがなかった。
さっきフョードルは「秘密のレシピ」と言っていた。ということは、『Alice』のデータベースには登録されていない、オリジナルの料理なのだろうか?
「秘密ってことは、『AlicE』のレシピには載っていないの?」
ぼくは、自分が感じた疑問を素直にフョードルにきいた。すると、フョードルはやさしく笑いながら「ないな」と言った。
そうか。じゃあ、この味はぼくたちしか知らないのか。
そう思うと、この味が余計に特別なものに感じられた。けれど、フョードルはぼくの予想外の言葉を続けた。
「なにせ、俺のこのレシピは、毎回こまかい分量がちがっていて、作るたびに味が少しずつ変わるからな」
「え!?」
「というより、きちんと分量を量って作ったことなんてないから、そういう意味ではレシピなんて言えるものじゃないかもしれん。まあ、今日のこれはなかなか上手くできたと自分でも思っているがな」
ぼくの反応を見て、フョードルは大きく笑った。けれど、ぼくはそんなことはまったく気にならないくらい、フョードルの言葉に驚愕していた。
ぼくにとっての料理は、“絶対的に正しいレシピ”があって、それに従ってつくる“毎回同じ味のするもの”だった。
だって、『AlicE』がそうだったから。毎回同じ味のする食べ物を、正確につくりあげる。そして仮にレシピとの間に少しでも誤差が生まれれば、それは失敗作として破棄される。それが料理だと思っていた。
しかし、たった今、その考えは木っ端みじんに打ち砕かれた。
“正確なレシピがない”。そんな料理があったなんて‥‥。それになにより、そんな料理がこんなに美味しいなんて‥‥。
驚きと戸惑いで混乱しているぼくに、フョードルは「いや、すこし違ったな」と言ってホワイトシチューの料理について話しはじめた。
「この料理は俺が師匠から教わったものでな。俺の師匠は東の果ての島国から来た人だったんだが、この料理は何千年も前に、その師匠の故郷で、名前もわからない誰かが創り出したものだそうだ。だから、この料理ももともとは『AlicE』のデータベースにいわゆる“正しいレシピ”が登録されていたんだ。しかし、220年前の事件でそれが消失してしまった」
220年前の『AlicE』のデータの消失事件。その中には、世界中の文化に類するもの、つまり食事も含まれていた。
「『AlicE』のデータが消えて、世界中の人々の記憶からも忘れ去られてしまった後も、この料理は師匠のいた『見届ける者(ゲイザー)』の集落で、奇跡的に細々と受け継がれていたらしい。その作り方を、師匠が俺に教えてくれたんだ」
食事のデータ群もまた、他のデータ群と同じく、そこに保存されていた情報のうち、ぼくが好きだったラーメンや、ほかにも人気のあった料理のデータは復元することができた。
当時はもうすでに自分で料理をつくる人間は少なかったけれど、人気のある料理は、かろうじてそれをつくる人間が残っていたからだ。
ただ、そのほかのデータは、やはり二度と取り戻すことができなかった。一口に「料理のデータ」と言っても、世界中の、それもさまざまな時代の料理が登録されていたわけだから、その量は天文学的なものだったろう。このホワイトシチューも、その中に含まれていた料理の一つだったのか。まさか、そんな料理がめぐりめぐってぼくの口に入ることになるとは。
このホワイトシチューの辿ってきた不思議な歴史を思うと、ぼくはなぜだか自分の心が震えるのを感じた。
しかし、そこでぼくの中に一つの疑問が浮かんだ。
「でも、フョードルも、フョードルの師匠も、フョードルの師匠のコロニーの人たちも、どうして、このホワイトシチューのレシピを復元しようとしなかったの?“完全なレシピ”はわからなくても、大まかな作り方はわかっていたんだよね?」
分量を量るのが面倒くさくて毎回味が変わってしまうのなら、美味しくできた時の情報を学習させてしまえば、次からはもう失敗してしまうこともないだろう。そうすれば、毎回同じ、美味しい味のシチューが食べられる。
そうだ。こんなに美味しいなら、今回のこのレシピを“完全なレシピ”として『AlicE』に学習させてしまえば良いじゃないか!
ぼくは名案を閃いたと思って、興奮しながらそれをフョードルに伝えると、しかしフョードルは目を伏せて「うむ‥‥」と考え込んでしまった。
なにか、気に障るようなことを言ってしまっただろうか‥‥?
「たしかに、このホワイトシチューはいつもよりも上手くできた。何度も作ってきた俺にとっても、上位に入る美味さだな。たしかにこれを毎回食べることができれば良いかもしれない。‥‥しかしな、俺たちは失敗するということも、存外に悪くないと思っているんだ」
「え?」
意味がわからなかった。失敗することなんて、明らかに悪いことだろう。すくなくとも良いことではないはずだ。だって、料理を失敗してしまえば、それは食べられなくなってしまうじゃないか。
それが、どうして悪くないなんてことになるのだろう。
「料理に限った話じゃないが、俺は“完全”であったり、“絶対的に正しいもの”というのが、あまり好きじゃないんだ」
フョードルは、ぐつぐつと鍋の中で煮えるシチューを見ながら話しはじめた。
「『AlicE』のデータベースはたしかに素晴らしい技術だが、今の世界では、『AlicE』に登録されている料理のレシピが、“唯一絶対に正しいレシピ”として認識されているだろう?俺は、その認識が嫌いなんだ。俺は、人間がなにかをつくるということは、別の何かを元にして、ひとりひとりが「俺ならもっとこうする」、「私ならここはこうする」と新しいことを考えて、変化させていくということだと思っているんだよ」
たしかに、データベースに登録されるもとになった料理は、『AlicE』にレシピが登録されるまでは、人間の間でいろいろな工夫がされていたのだろう。『AlicE』のデータベースが充実していくにつれて、人間のそういった活動がどんどんなくなっていったのもたしかだ。
でも、やっぱり一度とても美味しいと思える料理ができたのなら、わざわざそのつくり方から外れてつくる必要はないんじゃないだろうか。
つくり方を決めておかないなら、次もまた上手くできるかはわからないのだから。
「‥‥でも、一度美味しくできたなら、ずっとその時と同じつくり方でつくった方が、次も絶対美味しいものが食べられるよ。それに、つくるのに失敗したら、ぼくはやっぱりがっかりすると思う」
「たしかに、上手くいかなかった時は残念だな。だが、もしかすると、前と違うやり方でつくった時の料理の方がもっと美味しいかもしれないだろう?もしくは、失敗したと思ったものでも、意外と美味しいかもしれない。実際、そうやって失敗だと思われたものが新しい料理として認められたことも山ほどある。すくなくとも、そうやって新しいことに挑戦した人間がいたからこそ、ここまで多くの料理が生まれたんだ。そして、そうやって創られたものを元にして、また新しいものが創られる‥‥、その繰り返しで、人間の世界はここまで回ってきたんだ。それに‥‥」
フョードルは一瞬深く考え込むような顔になったかと思うと、次の瞬間にはぼくの顔をすっと見据えてきた。
ぼくは、今から話されることが、なんだかとても大切なことであるような気がして、その言葉を聞き漏らさないようにしようと身体を寄せた。
「そもそも、人間は、失敗を繰り返す存在なんだよ」
フョードルは、慎重に言葉を選びながら、こころのうちを明かそうとしてくれているようだった。
「俺は、人間というのは、永遠に出ることのできない迷宮のような世界の中で、決して手に入らないものを探して彷徨い続ける存在だと思っている」
‥‥どういう意味だろう。よくわからなかったぼくは、思っていることがそのまま顔に出ていたのだろう。フョードルは静かに笑みを浮かべたけれど、すぐに真剣な表情に戻って話を続けた。
「‥‥これは師匠の受け売りなんだがな。そもそもこの世界には、“正しいもの”に限らず、“絶対的なもの”なんて何一つないんじゃないかと俺は思っているんだ。この世界は、ただここに存在しているだけで、そこには本来、“絶対に正しいこと”や“絶対に間違っていること”なんてものはない。そして、この世界に生きる人間もまた同じで、世界から見たときに“絶対的に正しいあるべき姿”‥‥、そして、“生まれてきた意味”なんていうものも、きっとないんだ」
フョードルは、“生まれてきた意味”という言葉を言うのに合わせてぼくの方へ顔を向け、目を合わせた。
その静かな視線に、しかしぼくはぞわっと背筋に冷たいものが走るのを感じた。“生まれてきた意味”‥‥。それは、ぼくがコロニーを出た理由だ。誰からも望まれずに生まれた自分の命の意味を、外の世界に探しに行くこと‥‥。
しかし、フョードルは今、“そんなものはない”とはっきりと口にした。
にわかに鳥肌が立って、心臓が不愉快な大きさと早さで鼓動をはじめる。
「この世界は、人間のために生まれたわけじゃないからな。世界が人間にとって“絶対に正しいもの”や“生まれてきた意味”なんてものを用意してくれているわけはない」
フョードルの言葉が進められていくたびに、冷や汗が出てくる
火に当たって暖かった空気が、急激に熱を失って冷えていくような気がした。
「しかし、人間は知恵を授かったことで、不安を抱くようになった。この大きすぎる世界で、どこにも寄る辺なく生きるのは辛いからな。自分たちの存在を肯定してほしくて、自分たちの存在の意味について考えるようになったんだ。だが、この世界にはそんなものは本来ないので、それを考えはじめた人間は、永遠にその答えを見つけることはできない。‥‥すべての人間が、この答えのない、永遠に出ることのできない迷宮のような世界の中にいるんだ。ただ、その世界が迷宮だと気付いた人間と、気付いていない人間とに分かれているだけで。そして、この世界が迷宮だと気付いてしまった人間は、永遠に出ることのできない迷宮の中で、決して手に入らないその答えを探して彷徨い続けるんだ。散々彷徨って、新しい答えを見つけて喜んでは、それが絶対的なものじゃなかったことを知って、傷ついて、また彷徨い出す‥‥、それをずっと繰り返していく」
炎を見つめながら静かに話すフョードルの眼差しは、炎の中で揺らめいては消えていくその形と模様の上に、フョードルが話す人間の姿を重ねて視ているかのようだった。
フョードルの言葉を通して、その目が視ているものの深さに触れた気がしたぼくは、ぞっと恐ろしくなった。
もしも、フョードルの言葉が真実だとしたら、この世界には‥‥、人間には‥‥、あまりに救いがなさすぎる。
「そんな‥‥」
けれど、フョードルが今話していることは、ぼくがこれまで散々思ってきたことだった。
人間は、3000年前に宇宙へと飛び出した頃には、科学こそがこの世界における絶対的なものだと信じて疑わなかった。そして、それよりさらにむかし、宇宙どころか空も飛べなかったころの人間は、“神”が絶対的なものだと信じきっていた。
しかし、それらふたつの拠り所は、世界というあまりに大きなものの前に、あっさりと時の流れの中に崩れ去ってしまった。ぼくには、人間の科学力も、神も、信じるものは何もなかった。
──あぁ、だからあの時‥‥、ゴシック建築を見た時に、ぼくは怒りが湧いたんだ。
後の時代に立つぼくは、かつての人間が無邪気に信じていたものが、絶対的なものじゃなかったことを知っている。
神なんていう、存在しないもののことを一方的に想って、あんな建物までつくってしまったその愚かさへの軽蔑と、どうしようもないやるせなさが、あの時のぼくの怒りの正体だった。
ゴシック建築を見た時だけじゃない。シャロンに「人間がつくったものが一番すごい」と言われた時も同じだ。
科学を絶対的なものと考え、それを操る自分たちのことを過信して、“世界は自分たちのためにある”だなんて幻想を抱いていた時代の人間に対しても、ぼくは「そんなわけないじゃないか」と冷めた目で見て、彼らに対して、神を信じていた時代の人間に対して抱いていたものと同じ、軽蔑とやるせなさを感じていたのだ。
そんなことを、ひとりでいじいじと考えていたぼくが、今更フョードルにそれと同じことを言われたところで、落ち込んでいるなという話だ。そんなことは、筋が通らないだろう。
けれど、自分の中で悲観的に考えていたことを、他の人から「事実だ」と言われてしまうのは、やはり辛かった。
──この世界に‥‥、人間に‥‥、ぼくたちに、救いはないのか‥‥?
どうやらぼくは、自分が、フョードルの言う“絶対に答えを得られない迷宮”の中にいると気付いた側の人間になってしまったようだ。
“自分の生きる理由”、“自分が生まれた意味”なんて、あるわけがないとわかっているのに、それがどこかにないものかと、必死に探し続けなければいけない永遠の迷宮に。
──暗い。なにも見えない。あぁ、辛い。だれか、助けて。誰でもいい。神でも、悪魔でも、誰でもいいから。誰か、ここから出してくれ‥‥。
目の前も見えない暗い迷宮で、ぼくはたしかに彷徨っていた。
しかし、そこへフョードルの声が凛と響いた。
「しかし、だからこそ俺は、人間と、人間が創り出したものを本当に偉大だと思っているし、愛おしく感じているんだ」
炎に照らされて、光と影が舞い踊っているフョードルの顔に笑みが浮かんだ。それは、シャロンやぼく、ユミに向けて時たま見せてくれるものと同じ、あのやさしい笑みだった。
「人間は、この理不尽な世界に産み落とされて、何も見えない、わからないところから、手探りで世界を探り、広げていった。たしかに、そこで人間が求めていた答えは見つからなかったし、その過程で何度も酷い過ちを犯してきたかもしれない。だが、そうやって彷徨うなかで、人間はこの世界に様々なものを創り出してきた。建築も、音楽も、文学も、映画も、ゲームも、そして食べ物も、すべては人間がこの世界を彷徨って、自分たちで世界に刻み込んだものだ。俺は、それこそがこの世界において、人間にとってたった一つだけ存在する“意味”なんじゃないかと思うんだ。“絶対的な意味”のないこの世界で、“願い”を込めて、自分たちでゼロから意味を創り出す‥‥。その過程こそが、人間が人間たる所以であり、“人間が生きる理由”そのものなんじゃないか、とな」
“願い”‥‥。シャロンも同じことを言っていた。
ぼくは、まだそれが何なのか掴めていない。けれど、フョードルの言葉は、迷宮を彷徨っていたぼくの前に突然射しこんできた一筋の光のように感じられた。
──ぼくもその“願い”が感じられるようになれば、ふたりのように人間を、この世界を愛せるようになるのだろうか。
──“ぼくが生きる理由”を、見つけることができるのだろうか。
湯気を放つホワイトシチューを美味しそうに食べながら、フョードルは言葉を続けた。
「だから、そうやって人間が紡いできた新しいものを創るという環を、その流れを、俺たち『見届ける者(ゲイザー)』は断ち切りたくない。‥‥“見届けたいんだ”」
そうだった。彼らは『見届ける者(ゲイザー)』だ。人間が遺したものを尊ぶ存在だ。“料理をする”という行為も、彼らにとっては人間が遺したものの一つなのだ。
「だから、フョードルとシャロンは、『AlicE』を使わずに、自分で料理をするんだね」
ぼくの言葉に、フョードルとシャロンは顔を見合わせて笑っている。
もしかして、違うのだろうか?
ふたりの反応に戸惑っていると、フョードルが微笑を浮かべながらシャロンの頭を撫でた。
「もともとはそういう考えでやっていたんだがな。師匠が亡くなって、一人になってからは“自分で料理をする”ということで自分の生きる理由を少しでも肯定したかったんだ。‥‥意固地になっていたんだな。だが、シャロンが生まれてからは、すこしちがう」
フョードルは、シャロンの頭を撫でながら、ぼくの方に目を向けた。
「トーマは、シャロンと料理をつくってみてどうだった?」
「え‥‥、」
「とってもたのしかったわ!」
シャロンはパァッと輝くような笑顔を見せながら答えた。
その笑顔を見ながら、ぼくも自分が楽しんでいたことを思い出す。そうだ、ぼくも、楽しかった。人生ではじめて、自分でなにかをつくったという達成感ももちろん得られたけれど、それよりもシャロンと料理するのは、なんだか胸が温まるような感じがして‥‥
「うん、楽しかった。‥‥それになんだか、幸せだったな」
あのときは上手く言葉にできなかったけれど、今、自分のこころを振り返ってみると、“ふたりで料理をつくった”、ただそれだけのことが、ぼくはとても大切で、幸せなことのように感じていたのだ。
ぼくがそう言うと、フョードルはやさしく笑みを浮かべながら、今度はぼくの頭を撫でてくれた。
「俺も、シャロンが生まれてからは料理をするのが楽しくなったんだ。それまでは、義務感のようなものに駆り立てられていたのが、ただ幸せな気持ちになるようになった。シャロンが大きくなって、一緒に作ってくれるようになると、その幸せはさらに大きくなった。‥‥なにより、自分でつくった料理を、人に美味そうに食べてもらえるのは、大きなよろこびだ。それこそ、それだけで生きていて良かったと思えるくらいに」
フョードルの言葉にはっとする。
そうだ。今、このシチューには、ぼくがさっき自分で切った野菜がたくさん入っている。綺麗に切られたじゃがいもやにんじんの中に、少し不恰好なかたちをして混ざっているのが、ぼくが切ったものだ。上手くつくることはできなかったけれど、それでもこんなに美味しいシチューを自分たちでつくったかと思うと、なんだかこのホワイトシチューが、ますます美味しく感じられたし、フョードルが言ったように、“生きていてよかった”という気持ちが溢れてきた。
「自分で作ることで、もしくは人につくってもらうことで、料理の味が変わる。気持ちの問題かもしれないが、そもそも人間というのは、感情が束になったような存在だ。身体とこころが結びついていたとしても、不思議じゃないだろう?」
ぼくは、コロニーの老人たちがくれたBLTサンドウィッチのことを思い出した。
昨日の昼に食べたあのサンドウィッチは、ぼくがそれまで食べてきたものとまったく同じもののはずだった。けれど、それを食べたぼくは、二つのサンドウィッチの間に、たしかな違いを感じた。あれは、自分と同じように『AlicE』を使ったものだとしても、誰かにつくってもらった物だから感じられた美味しさだったのか。
──待てよ、それじゃあ、ぼくがラーメンを美味しく感じられなくなったのは、もしかして‥‥
その時、突然ぼくの頭の中を電撃が走った。閃光が炸裂したかのように頭の中がちかちかして、あちこちに散らばっていたものが次々と結びついていった。
そういうことだったのか。ぼくを含めて、コロニーの老人たちがみんな同じように陥ってしまった『もう美味しくない病』‥‥、それまでは美味しかったはずのものが、どんどん美味しく感じられなくなっていくあの現象。あれは、『AlicE』の料理にあるものが欠けていたことで起こっていたんだ。それはきっと、“人間の感情”だ。
フョードルの話を聞き、実際にこのシチューを食べて、ぼくは、感情や情緒がどれだけ人間に影響するのかを実感した。人間はきっと、ぼくが思っている以上に繊細で、そして感受性が豊かなのだ。
ぼくも、コロニーの老人たちも、『AlicE』がつくる料理には、フョードルのこのホワイトシチューや、むかしの人間が自分たちでつくっていた料理にはあったはずの、“感情”が込められていないことを無意識に感じ取っていたのだろう。それが、徐々にぼくたちの“美味しい”と感じる部分を麻痺させていったのだ。
ずっと自分のこころを縛ってきた呪いの正体がわかったぼくは、興奮しながら、今ぼくが考えたことをふたりに伝えた。
ふたりは、ぼくたちの身にそんなことが起きていたということは知らなかったようで、驚くと同時に悲しそうな顔になってしまった。
「好きだった食べ物が美味しく感じられなくなっちゃうなんて‥‥、かわいそう‥‥」
シャロンは、元気のない声でそう言うと、しゅんと落ち込んでしまった。フョードルも言葉にはしなかったけれど、同じように感じているはずだった。
ずっと料理に向き合って、その素晴らしさを理解しているふたりだからこそ、“食べ物が美味しくなくなっていく”ということの絶望感が誰よりも深く理解できるのだろう。
ぼくはふと、『AlicE』さえ生まれなければ、こんなことにはならなかったのだろうか、と思った。
『AlicE』は人間を幸福にするために生み出されたものだ。けれど、それが結果的に食事という人間の幸せを奪ってしまったというなら、それは本末転倒だ。
「『AlicE』が人間の代わりをするようになったのは、よくなかったのかな‥‥」
「そうだよ。ぜんぶ人間がやっていたときの方が絶対よかったのに」
シャロンは、ぼくのつぶやきを即座に肯定した。シャロンは、はじめて会ったときから3Dプリンターでつくられた建物や、『AlicE』には興味を向けなかったから、ぼくは、「やっぱりそうか」と納得するのと同時に、どこか寂しさのようなものをおぼえた。
しかし、フョードルの答えはシャロンとはちがったものだった。
「いいや、それは違う。技術が進歩したことは、間違いなく人間を幸せにしたさ。今だって、俺たちがこうして安全に旅ができるのは、『AlicE』やほかの道具のおかげだろう?」
フョードルが、ユミを世話している『AlicE』や車、地図、GPS、さっき火をつけた道具、果ては鍋に至るまでまわりのものを順番に指差して示した。
「こういう便利な道具が生まれたことで、人間には選択肢ができた。何かを“する”、“しない”という選択肢だ。たとえば、車が生まれるまでは、人間が移動するには歩くしかなかっただろう?それこそ、急いでいる時や疲れている時もだ。だが、車が生まれたことで、人間は二つの選択肢から選ぶことができるようになった。急いでいたり、疲れている時は車を使えばいい。運動したかったり、ゆっくりと景色が見たい時には歩けばいい、というようにな。『AlicE』の調理機能も本来は同じだ。急いでいたり、疲れている時にはこれ以上に助かるものはない。実際、俺たちも今日の昼は、料理を作る時間を惜しんで、『AlicE』がつくった飯を食べただろう?」
フョードルがシャロンに問いかけると、シャロンは「うぅ‥‥」と声を詰まらせた。シャロンは納得しきれていないようだったけれど、フョードルの言葉を否定するだけの言葉は持っていない様子だった。
フョードルは「ただ、」と言葉を続けた。
「俺も、その道具を使うべき時について、人間はもっと深く考えるべきだとは思うがな」
使うべき時‥‥。使う時と、使わない時をちゃんと考えて選ぶということか。
たしかに、さっきの車の話で考えるとわかりやすい。急いでいるときは使って、そうじゃないときは歩く。至極簡単な話だった。
けれど、すべての技術がそこまで綺麗に割り切れるだろうか。
ましてや、『AlicE』のように、どんな状況、どんな時でも使える技術の場合は、その境界線はとても曖昧なものになってしまうんじゃないだろうか。
ぼくたちが、いつの間にかまったく自分で料理をしなくなってしまったのも、そこに原因がある気がした。
「それは、どうやって判断すればいいの?」
「道具を使うことで、“人間らしさ”が失われるかどうか、ということだ」
フョードルはきっぱりとそう言うと、膝の上で手を組んだ。
「これは俺の持論でしかないんだが‥‥。俺は、人間には等しくやるべきことがあると思っている。それは、“人間らしく生きること”だ」
フョードルは、ぼくとシャロンの顔を見ながら、ひとつひとつの言葉を丁寧に話していく。
「俺は、さっきも言ったように、“絶対的な意味”のないこの世界に、“自分たちで意味を創る”ことが人間らしさだと考えている。だが、これは“ゼロから物を創る”ということだけじゃない。すでに存在する何かに、“価値を与える”ということも含むんだ。‥‥難しいか?」
むずかしい。眉を下げながら聞いてくるフョードルには申し訳ないけれど、新しく出てきた“価値”という言葉がいまいちわからない。
フョードルが今話している価値というのが、昔使われていたという、お金に関わるような意味の言葉じゃないことは、なんとなくわかる‥‥。けれど、じゃあそれはなんなのかと言われると、よくわからなかった。
ただ、この話はシャロンも理解できていないようで、「むーん‥‥」と唸りながら頭を抱えている。
いつもはぼくに教えてくれる側のシャロンが、ぼくと同じように理解できずに苦しんでいるのを見るのは、なんだか新鮮だった。
「たとえばだ。俺たちが今食べているこのホワイトシチュー、これはさっきも言ったように、遠い昔に名前も知らない人間が創り出した食べ物だ。普通、食べ物はつくった分を食べてしまえばなくなるだろう?だからホワイトシチューは、本来なら創った人間が死んでしまえば、二度と現れることはないはずなんだ。だが、現に俺たちは今、ホワイトシチューを食べている。細かい味は違っても、それこそトーマが言ったように大まかな味は似ているだろう。これは、ホワイトシチューを“創った人間”のほかに、“この料理には価値がある”と考えた人間がいたからだ。そして、そうやってホワイトシチューに“価値”を感じた人間が、自分でホワイトシチューをつくって、それをまた他の人間に食べさせる。そして、それを食べた人間の中からまた、“この料理には価値がある”と考える人間が生まれる‥‥。この繰り返しで、ホワイトシチューは俺たちの生きている今まで繋がれてきたわけだ」
フョードルは一度そこで言葉を切って、ぼくたちの様子を確認した。
今のところはなんとかついていけてるはずだ。
つまり、ホワイトシチューは、それをはじめてつくった人間だけじゃなく、それを食べて“美味しい”と思った人間がいたから、今まで残されてきたということだろう。
ということは、ホワイトシチューにおける“価値”とは、“美味しさ”‥‥、いや、“美味しさ”そのものじゃなくて、“人間がそれを残そうとする気持ち”のことで、それが価値になるということだから‥‥
「‥‥つまり、“価値”っていうのは、それを大切に思う気持ちで‥‥、それを人間がなにかの物の中に感じることが、価値を与えるってことで、それが物の“意味”になるってこと‥‥?」
ぼくが自信なく聞くと、フョードルは目を輝かせて、興奮に満ちた表情で頷いた。
「そうだ!そういうことだよ、トーマ!」
フョードルが嬉しそうに頷くのを見て、ぼくはこころの中に安堵と達成感が溢れるのを感じた。シャロンも隣りで「あー!それだぁ!」と共感している。
「俺たちにとっては、人間が遺したものや、自然の光景がそれだ。だから、俺たちはなるべく移動するのに車を使わず、足を使う。そうして見える景色に“価値”を見出し、与えることが俺たちにとっては“人間らしい生き方”であり、“意味”だからだ。車を使ってしまったら、ひとつひとつの景色をよく見ることはできないだろう?」
たしかに、車に乗っていた時は、景色はあっという間に流れていってしまって、印象に残ったものは少なかったけれど、自分の足で歩くようになるとさまざまなものが目に入るようになった。そして、そこで目にしたものは、ぼくのこころをたしかに揺り動かした。
あぁ、ぼくはあの時、あの景色に価値を与えていたのか。
「今の俺たちは、まだ自分の足で移動することができるし、移動にかけられる時間が限られているわけでもない。だから、車はなるべく使わない。俺たちの目的を果たすのに、今それは必要ないからだ」
「それじゃあ、道具はどういう時に使うべきなの?」
ぼくの問いかけに、フョードルは笑いながら答える。
「必要になったら使うんだ。たとえば車なら、自分の足では歩けなくなってしまった時や、歩けるには歩けるが、時間が限られている時などだろうな。“人間らしく生きるためにやるべきこと”と、“その道具を使うことで失われてしまう部分”、この二つを鑑みて、“その道具を使うことで得られる人間らしさ”が“その道具を使うことで失われてしまう人間らしさ”を上回る時に、道具を使うべきだと俺は思っている」
なるほど。たしかにそれなら人間が“人間らしさ”を見失わない限り、人間は“正しく生きられる”はずだ。
‥‥あれ?でも、それだと道具を使うか否かは一人一人の判断に委ねられるわけで、その境界線は結局一人一人違ってくるんじゃないのか?そうなると、結局人によっては道具を使うべき時を間違えることになるんじゃないだろうか。
たとえば、世界にあるものすべてがどうでもよくて、何に対しても“価値”を見出さない人間がいたとしたら、その人間は道具を無制限に使うべきということになる。いや、そもそも何に対しても価値を与えることのない人間が本当にいたとしたら、それは人間じゃないのか?だってその人間は、フョードルが最初に言っていた“人間らしい生き方”をしていないのだから。
考えながら、ぼくは、コロニーの老人たちのことを思い出していた。
『スリープ計画』における最後の世代。世界の終わりと向き合って、すべての物に対する関心を失ってしまった人間たち。
彼らは、フョードルの考え方に照らし合わせると“人間らしく”生きてはいなかった。彼らは何物にも価値を見出さずに、熱中するものもなく枯れたように生きていた。
しかし、だからといって彼らが人間でないとは思えなかった。彼らは紛れもなく“人間”だったはずだ。じゃあ、ぼくの中に、フョードルが考えるものとはちがう“人間らしさ”の条件があるのだろうか‥‥。
考えれば考えるほど、わからなくなってしまう。
そもそも、“人間らしい生き方”にしてもそうだ。今のフョードルの話には、とても説得力があった。けれど、それはフョードルにとっての“人間らしさ”が、ぼくにとって納得のいくものだったからだ。
フョードルが価値を見出している“自然”やこの“ホワイトシチュー”には、ぼくも“これには価値がある!”と思った。だから、それを大切にすることが“人間らしさ”なんだと心の底から納得し、共感することができた。
けれど、仮に人を殺すことや人を傷つけることに“価値”を見出すような人間がいたとしたら、その人間にとっては、人を傷つけることが、彼にとっての“人間らしい生き方”ということになってしまう。でもそれは、ぼくにとっては正しいことだとは思えない。人間を傷つけるのは、“悪いこと”だ。そんなことは、誰でも知っている。
それは言ってしまえば、“絶対的に正しいこと”だ。
その時、恐ろしい考えがぼくの頭を走った。
──人を殺すことや、傷つけることが悪いことだと一体誰が決めたんだ?
フョードルの言葉が脳裏によみがえってきた。
“そもそもこの世界には、“正しいもの”に限らず、“絶対的なもの”なんて何一つないんじゃないかと俺は思っているんだ”
フョードルのあの言葉通りに考えるなら、“絶対的に正しいもの”だけでなく、“絶対的に悪いもの”というのも、この世界にはないんじゃないか?
そこまで考えて、ぼくはぞっとした。そして、その感覚に耐えられなくて、ぼくはその考えをフョードルに吐き出した。
「‥‥すべての人間が同じように“価値”を見出す何かはないんだよね。この世界に“絶対的なもの”は一つもないから。でも、仮にそうだとすると、たとえば人を殺したり、傷つけたりする人間が“悪い”っていう考え方自体、この世界には本当はないってこと‥‥?」
すこし震えを含んだ声になっていたと思う。「それはちがう」と言って欲しかった。ぼくの中に浮かんだおそろしい考えを否定して欲しかった。
しかし、フョードルは、ぼくの目を見据えてきっぱりと答えた。
「その通りだ。この世界には“絶対的に悪いこと”も存在しない。たとえそれが、殺人や、他人を踏みにじる行為であってもだ」
ぼくは頭を鈍器で殴られたかのような感覚になった。
さっきまでは、まるでこの世界の真実を見つけたかのようなよろこびに溢れていたのに、それは一息に消え去ってしまった。
つまり、フョードルが今まで話してくれたことは、必ずしも良い方向に向くものとは限らないのだ。人間によっては、悪い方向へと走る原因にもなるし、この考えを認めてしまったら、それを「絶対に悪いことだ」と咎めることもできなくなってしまう。
なぜなら、悪人を責めるための“根拠”‥‥、“絶対的に正しいこと”がなくなってしまうのだから。
しかし、ぼくの頭の中には、そのことに納得できてしまっている自分がいた。
だって、人間がしてきたことは、良いことばかりじゃない。むしろ、悪いことの方が多いくらいだ。
3000年前の人間にしてもそうだ。宇宙の終わりを前に、パニックになって、自分のことだけを考えて、怒りを撒き散らし、八つ当たりし、他人を傷つけた。これを悪と言わずになんと言おう?
しかし、ぼくが“悪いことだ”と思うことをした彼らは、全員がきちんと報いを受けたわけじゃなかった。さまざまな要因で、他人を明確に傷つけたにもかかわらず裁かれなかった人間はごまんといた。
それは、フョードルが言ったように、この世界には本来“善”も“悪”もないからこそ起こることだった。“絶対的に悪いこと”が本当にあるのなら、“悪人”は絶対に裁かれるのだから。
歴史を振り返れば、そういうことは数えきれないほどあっただろう。
個人の間の争い、組織の間の争い、国同士の争い‥‥、人間の活動は争いとは切っても切り離せない。その活動の中で、非道なことをしたにも関わらず、報いを受けずにのうのうと生きた人間がどれだけいることか。そのことを考えるだけで、ぼくの中にはとてつもない怒りが湧いてくる。
けれど、ぼくのこの怒りも、別に正しいわけじゃないのだ。なぜなら、この世界には彼らを咎める“絶対的な正義”なんてものはないのだから。
しかし、それはつまり、ぼくたちが正しい方向を向いているということを保証してくれるものが何もないという意味でもあって、ぼくたちは生き方の指針を完全に失ってしまうことになる。
結局のところ、ぼくたちはやっぱり迷宮の中を彷徨い続けているだけじゃないか。それも、この地球に生まれた時から、ずっと‥‥。
自分という存在の小ささと無力さに、とほうもない虚しさがこころに広がっていく。
しかし、フョードルはぼくの絶望を跳ね除けるような、はっきりとした力強い声で言葉を紡ぎはじめた。
「たしかに、“世界にとって”、“絶対的な悪いこと”は存在しない。だが、“人間にとって”、“絶対的な悪いこと”はこの世界にたしかに存在するんだ」
フョードルはぼくとシャロンの目を見て、言葉を続ける。
「それは、人間のルールの中での“善”と“悪”だ。ルールは単に法というわけじゃない。人間として冒してはならない規範や、生き方そのものだ。人間は、この世界に自分たちで“ルール”を創り出すことで、“善”と“悪”という概念を得たんだ。それは、この宇宙で物理法則以外に存在する唯一のルールなんだ」
しかし、それは人間の中にしか存在しないものじゃないか。そんなものに一体何の意味があるのだろう。
「でも、そんなもの本当は存在しないじゃないか。それは、ただの人間の勝手な“思い込み”で、偽物じゃないか‥‥。そんなものに、なんの意味があるって言うんだよ」
ぼくは、湧き上がる黒い感情のままにフョードルの言葉を否定していく。生意気なことを言っているのは分かっていた。
しかし、“本当はないもの”を“ある”と言うのは、それはただの“嘘”じゃないか。
「その通りだ。これは願いだ。“人間には持つべき規範がある”‥‥、いや、“あって欲しい”という、根拠のない願望だ。世界という大きな視点で見た時、そんなものはたしかに存在しないかもしれない。“悪いこと”をしても、それに自動で反応して悪人を裁いてくれる自然のシステムがあるわけじゃないしな。だが、だからこそ、俺たちはこの世界に“善悪は存在する”と言わなければいけないんだ。なぜなら、俺たち人間だけが、この宇宙で唯一“何かに価値を与えられる存在”なのだから」
その言葉に、ぼくははっとなって顔を上げた。
たしかに、人間がこの世界に価値を見出して、“意味”を与えられる存在ならば、人間自身が価値があると思ったものなら、それは実際に“意味”を持って、存在することになる。
フョードルは静かに、しかしはっきりと言葉を続けた。
「“人間の行為には“善”と“悪”があって、従うべき“規範”がある。そして、それに悖る行為が“悪”である”。そう信じることだけが、この世界に“絶対的に悪いこと”という価値観を生むんだ。人はそれを、“倫理”や“正義”と呼ぶ」
──“正義”
その言葉を思い起こすと、ぼくは自分の胸がカッと熱くなるのを感じた。そんなものがあれば、どんなにいいだろう。しかし、ぼくはまたそこに新たな問題を見出してしまった。
世界から見て“絶対的なもの”がない以上、一人一人が考えるルールはそれぞれ違っている。一つとして同じものがない以上、異なるルールを持つ者同士が出会ってしまえば、両者は衝突するのではないか。いや、絶対にするだろう。
「でも、一人一人のルール…、“正義”が違っていたら、結局ちがうルールを持つ人間同士が対立して、争いになってしまうよね‥‥?」
フョードルはこくりとうなずくと、すっとぼくに目を合わせた。
「そうだ。だから、ひとりひとりが常にちゃんと自分で考えて、自分を律しなければならないんだ」
フョードルの目には、見ている者を惹き込む不思議な力があった。
「人間は、それぞれ違った主観を持つ別の存在だ。他人が考えていることや感じていることは、どうやっても知ることができない。そして、自分の考えや感情もまた、どんな他人であっても知ることができない。だから、自分のこころには、自分で向き合うしかないんだ。“自分が何を大切に思っているのか”、“何を遺すべきと考えているのか”、そして、“どう生きるべきと感じているのか”。そうやって己を律すること自体が、紛れもない“人間らしさ”なんだよ」
フョードルの話は、まさにぼくに向けられたものだった。
その言葉のひとつひとつが、自分の胸に深く刻まれていくにつれ、ぼくの中ではフョードルへの尊敬の念が膨らんでいった。
フョードルは、一体どうやってここまで深く世界のこと、人間のこと、自分のことを考えられたのだろうか。
「フョードルは、どうやってそこまで辿りついたの?」
ぼくは、自分がフョードルのように世界を見ることができるようになるとは思えなかった。
「俺は、どこにも辿り着いていないよ。‥‥師匠の話に魅せられて、コロニーを飛び出して『ゲイザー』になった時から、俺も迷宮を抜け出そうともがいている人間の一人に過ぎない。ただ、もがいている時間がトーマたちよりすこし長いだけだ」
フョードルは、まるで古い記憶を辿るように、ぼんやりと遠くを見つめるような目をしていた。
「俺が特別なわけじゃない。俺の師匠や、それより前の世代の『ゲイザー』‥‥、すべての先人たちが、この迷宮の中を彷徨い、悩み、苦しんでいた。その中の誰一人として、絶対的な答えを見つけることはできなかったが‥‥。だが、俺は彷徨い続けた果てに、ようやく自分の心と向き合えた気がする」
フョードルは、ぼくとシャロンの頭をなでながら、ゆっくりと言葉をつないだ。
「さっき、ゼロから何かを生み出すことが人間にとっては唯一のたしかな“意味”だと言ったがな。あれは“人間”という大きな視点での話だ。俺という一人の人間にとっては、シャロン、そして今はトーマとユミの三人が、俺が“生まれた意味”で、“生きる理由”だ。‥‥生きていくなかで時たま感じられる、こういうちょっとした幸せの積み重ねが、最期自分が死ぬ時に、“幸せな人生だった”と思えることにつながるんじゃないかと俺は思っている」
胸が熱くなるのを感じた。その熱はじわじわと広がって、頭も心地よくのぼせていくようだった。
フョードルの言葉は、ぼくにはとても重く感じられた。
それは、フョードル自身が経験した長い旅路と、悠久の時代から紡がれてきた人間の歴史が積み重なった“時の重み”だった。何世代にもわたって引き継がれてきた人間の探求と苦悩は、ぼくには無数の人間が生きた証として淡い光を放っているように見えた。
一体どれだけの人間が、この時の流れの中に現れては消えて行ったのだろう。そして、どれだけ長い間、人間は苦悩し続けてきたのだろう。
計り知れない時を超え、ぼくの立つ場所まで繋がれてきたそれは、むしろなんだかとても大切なものであるような気がした。
──この時の流れの最後の場所に、ぼくは立っているのだ。
その時、突然ぶわっと背中のあたりが粟立って、それがうなじのあたりまで駆け昇ってくるのを感じた。
旧市街の街並みを見ていた時に感じたあの大きなものが、またすぐそこに現れた気がした。それも、前に現れた時よりもずっと近くに。
今回は掴めるかもしれない‥‥!
ぼくは姿の見えないそれを掴もうと、今まで聞いた言葉を必死でかき集めた。“絶対的なもの”、“願い”、“人間が生きる理由”、“価値”‥‥。
頭の中で言葉を唱えるたび、それはすこしずつこちらに寄ってくるのを感じた。いいぞ、そのままこっちに来い‥‥。
“人間が自分でつくったものには、意味が宿る”
──この世界には“絶対的なもの”はない‥‥
──しかし、人間は自分の存在を肯定するために、決して手に入らない意味を求めて彷徨う存在‥‥
──そして、この世界で唯一、“意味”を持つのは、人間がそこに“価値を与えたもの”、つまり“意味を創ったもの”だけ‥‥
──つまり、“世界の意味”は、人間が創るということ‥‥
見えないものに、指がかかった感触がした。もう少しだ‥‥、もう少しでわかる‥‥。
必死にその先を考える。“世界の意味は、人間が創る”‥‥、だから、だから‥‥。
あぁ、ダメだ。必死に頭を回しても、その先の言葉が出てこない。
あぁ、またいってしまう。もう指がかかっているのに、あとほんの少しで届きそうなのに。
いかないでくれ、頼む。知りたいんだ。この感覚の正体を、この胸をめぐるざわめきの正体を。
しかし、ぼくの願いも虚しく、指にかかっていた大きなものは、ふわりとぼくの指を離れると、あっという間にその気配を拡散させてしまった。
あぁ、また消えてしまった。あんなに間近に感じていたのに。もう手は届いていたというのに。
あと一歩のところまで迫っていた分、ぼくのこころは以前よりも強い失望感に襲われた。
あの時と同じように、フョードルはまた、がっくりとしているぼくの様子に気がついたようだった。
「また、何か掴めそうになったのか?」
「うん‥‥。でも、また掴めなかった‥‥」
フョードルは短く「そうか‥‥」と言って、ぼくのあたまをぽんぽんと叩いてくれた。
前回も、そして今回も、あの感覚はフョードルの話がきっかけでぼくのもとに訪れた。ぼくは、あの感覚をどうしても掴みたくて、シャロンがいるということも構わず、フョードルにもっと話を聞かせてくれるようにせがもうかとも思った。しかし、今さっきフョードルに“自分で考えなければいけない”と教えられたばかりで、そんなことはできなかった。
「残念だったな‥‥。だが大丈夫だ。いつか必ず掴むことがきるから」
「‥‥前もそうだったんだ。あの感覚は、フョードルの話を聞くといつも来るんだ‥‥」
フョードルはやさしく笑いながは首を振った。
「俺の話は、もしかしたらトーマがその感覚を掴むきっかけにはなったのかもしれない。だが、言っただろう?俺たち人間は、互いの考えていることや感じていることを理解できるわけじゃない。俺も同じような感覚になった経験があるが、それは似ているだけで同じじゃない。それは、トーマが、自分で感じ取らなければいけないものなんだよ」
つまり、フョードルも、ぼくのこの感覚の完全な正体はわからないということなのか。じゃあ、もしもぼくが自分で掴むことができなければ、もしかすると、この感覚は一生掴めないのかもしれない‥‥。そんなのは嫌だった。
「だがな、トーマ。逆に言えばその感覚は、この世界で唯一、“トーマだけのもの”なんだよ。他の誰にも知ることのできない、トーマだけの宝なんだ」
フョードルの言葉に、ぼくははっとした。そうだ、あれはぼくのものなのだ。あの感覚の気配を感じただけで、そこに指がかかっただけで、ぼくの中には大きなよろこびと興奮が沸き起こるのを感じた。間違いなく、あれはぼくの本質に関わるようなものだ。
きっと、あの感覚が、ぼくの旅の目的なんだ。
「トーマ。前も言ったが、焦らなくてもいいんだ。前にもそれは、掴みかけたものだろう?大丈夫だ。必ず分かる日が来る」
フョードルのその言葉も、ぼくの頭を撫でる手も、すべてがやさしさを帯びていた。その手に撫でられていると、何の根拠もないのに、なんだか本当に大丈夫な気がしてきて、沈んだ心がすこしずつ立ち直っていった。
そうだ。たしかに今回は、前よりもずっと近くに感じられたんだ。きっと次こそは、掴めるはずだ。
「さあ、長話が過ぎたな。せっかくの料理だ、冷めてしまう前に食べよう。美味い飯を食べて、よく寝れば疲れも取れるさ」
フョードルはそう言って話を締めると、空になった器にもう一度ホワイトシチューをよそうと、それを本当に美味しそうに食べはじめた。
その様子を見ていたぼくとシャロンも、自分のお腹がまた空腹を訴え出すのを感じて、ホワイトシチューをおかわりした。
シャロンは「美味しいなぁ、幸せだねぇ」としきりに言いながら、ぼくとフョードルに笑いかけてくる。
ぼくは目を閉じ、ホワイトシチューに込められたものをじっくりと味わった。料理の素晴らしさは、単に舌の上で感じる“味”にあるのではなく、そこに込められた感情を感じ取ることで心を癒し、幸せな気持ちにさせてくれることにあった。
一口食べるごとに、ぼくは、このホワイトシチューに新しい希望と、この世界を生きる勇気を与えられているような気がした。
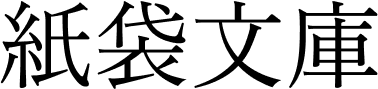


.png)
.png)