マルーン
第六章 兄弟子
シチューを食べてたっぷりと寝た次の日の移動は、まったく辛くなかった。
道は少しずつ険しくなって、長い坂や急な坂も増えていたけれど、疲労がすっかりなくなった足は、ぐんぐん先へ進むことができた。フョードルも「これはシャロンと同じようになるのも時間の問題か」と言って笑っていた。
ぼく自身、これが本当に自分の身体なのかと疑ってしまうくらい、身体に力がみなぎっているのを感じていた。
この日の移動も、これまでと同じように車を先行させた場所がゴールになるはずだったけれど、この日は空がまだ青く澄んでいる時間に車までたどり着いてしまった。
シャロンは、ぼくが歩き切ったことを、ぴょんぴょん跳ね回りながら自分のことのように喜んでくれた。
「すごいよ、トーマ!休憩もほとんど取らなかったのに!」
「本当にすごいな‥‥。子どもの成長はこんなに早いのか‥‥」
フョードルは驚きつつも、シャロンと同じようにぼくのことを褒めてくれた。
ぼくは、そんなふたりの様子と、なによりはじめて自分の足でゴールまで辿り着けた事実に、心が達成感で満たされるのを感じた。なにかをやり遂げることはこんなに気持ちがいいことなんだと、はじめて知った。
それからの移動は、少しずつ距離を伸ばして、休憩を挟む回数も少なくなっていった。きっとこれが本来のふたりのペースだったのだろう。ふたりはぼくの様子を見ながら進んでくれたけれど、ぼくはちゃんとついていくことができた。
この日は、いつもよりも早い時間に移動をはじめた。フョードルが言うには、目的地までもう半分の位置を過ぎて、何も問題がなければあと三日ほどでフョードルとシャロンが拠点にしていた場所に着くらしい。今日一日で、進めるだけ進みたいということだった。
昨日から、ぼくたちが進む道には少しづつ傾斜が出てきて、周囲の地形もでこぼことしてきていた。平坦な大地が広がるコロニー周辺では見だことがないほど上下に起伏した土地だった。
しかし、どれだけ進んでも、石畳の道は途切れることなくどこまでも続いている。石畳は、車二台分くらいの幅の道から、広い場所だと十メートルくらいもありそうな幅の道に表面がなめらかな石がびっしりと敷き詰められていて、所々老朽化した場所が一部崩れていたり、そうしてできた隙間から雑草を生やしてはいたが、それでも道としての役割は十分に果たしていた。
はじめての傾斜は、平坦な道よりも歩きにくかったけれど、今のぼくは体力を削られることなく登っていくことができた。やがて、周囲の起伏が少し落ち着いて、遠くの景色まで広々と見渡せる場所に出ると、左側の視界に巨大な山の連なりが姿を現した。
ぼくは、その長大さと迫力に驚きを隠せず、感嘆の声をあげた。
「アルプス山脈だよ!すごいよねぇ」
シャロンは、興奮を抑えられないといったようにそう言うと、目をキラキラさせながら、ぼくと同じように遠く天を衝くように聳える山々を見渡した。
そうか、あれがシャロンの話に出てきたアルプス山脈なのか。ぼくたちの立つ平らな大地が下から突き上げられたかのように巨大に起伏したその連なりは、シャロンの話していた通り、あまりに大きく、悠々としていて、こころの裡に畏敬の念が溢れてくるのを感じる。その険しい山肌が描く稜線は美しく、尾根に散らされた真白い雪はまるで化粧のようで、山全体を美しく飾って神秘的な雰囲気を纏わせている。
まさか、実際に実物を見ることが叶うとは思っていなかったぼくは、今自分の目に映る巨大な自然の産物に胸が熱くなるのを感じた。
「あのアルプス山脈はヨーロッパとイタリア半島とを隔てるように東西に大きく広がる山脈でな。俺たちはずっとあの山脈に沿って歩いていたんだよ」
フョードルはそう言いながら、地図を見せてくれた。たしかに地図で見ると、ぼくたちが歩いてきた道の左側にはずっとあの山脈が続いていた。
「この道をずっと進んでいけば、湖に行き当たる。この湖を左から迂回して通り抜けた先、ライン川という川を渡った対岸の先が今日のゴールだ」
「六時間くらいかな」
フョードルは地図を指し示しながら教えてくれる。フョードルが示した道筋を辿ると、たしかに大きな湖がここから山一つ向こうに広がっているようだった。
「大きな湖だね」
「ボーデン湖だ。氷河によってできたU字型の谷に水が溜まってできた氷河湖だ」
氷河湖‥‥。はじめて聞いた言葉だった。
「氷河湖って?」
「氷河がつくった湖のことだよ!」
得意気に答えたシャロンの言葉を継いで、フョードルは、地図の地形を示しながら話しはじめた。
「もともと、俺たちが歩いてきた道も含めて、この北アルプス山脈沿い一帯は大昔氷河に覆われていたんだ。だから、あちこちU字型の谷や窪地が多かっただろう?」
たしかに、これまでぼくたちが歩いてきた道は、幅の広さは大小あっても、両側を高い丘や山に挟まれた場所が多かった。あれは、氷河の動きでできた地形だったのか。
「分厚く広がった氷河が大地を削って出来た窪みに、溶けた氷河の水が溜まって出来たのが氷河湖だ。北アルプス山脈沿いにはこういった氷河湖が点在している。ボーデン湖はその中でも大きな氷河湖なんだ」
こんなに広い範囲の大地を削り取り、溶ければ湖になってしまうほどの巨大な氷‥‥。
ぼくは、このあたり一帯を覆っていた氷河の姿を想像してみた。
雪が吹雪いて、あたり一面が白く染め上がった極寒の世界。分厚く降り積もった雪は、やがて氷へと変化し、自分の重さでゆっくりと移動をはじめる。人間の目では捉えられないほどゆっくりと、しかし確実に大地を削り、地形を変えていき、やがて地球の気温が上がると、氷河はにわかに溶け出して、自らがつくった窪みへと流れ込んで湖となっていく‥‥。
やっぱり、自然はすごい。ぼくは、これだけ広い大地を削り取ってしまった氷河の力強さにも驚愕したけれど、なによりそんな巨大な氷が永遠に残ることなく、今は見る影もなく溶かし尽くされてしまったということに、世界というものの大きさを感じずにはいられなかった。
ぼくたちは、アルプス山脈を左に望みながら道を進んだ。道中は、フョードルが言っていたようにU字型になった地形が多く、それらの道一つ一つが氷河がつくり出したものだと考えると、心の底からこの自然に対する畏怖の念が湧き上がってくる。
上下にくねくねとした道を歩き進むと、小高い丘に出て、突然ぱっと視界が開けた。
遮るものがなくなったぼくたちの目に、大きな湖が映った。春の暖かく明るい日差しを受けて、湖面が青く澄んで輝いている。
「綺麗だ‥‥」
ぼくは、思わずつぶやいていた。同じ青に類する色でも、ぼくたちの頭上に広がる空の色とは違ったブルーグリーンをたたえた湖は、まるでどこまでも深く鮮やかな青を抱いた空と若い草木が萌える若緑の大地とがそこで交わっているかのようで、その景色を一枚の絵画のように仕立てあげていた。
「あの湖を、左手側から迂回していくんだ。ずっと昔は、対岸とこちら側の岸とを繋ぐ船が出ていたらしいんだが、少なくとも俺が『ゲイザー』になったときにはもうなくなっていたな。‥‥まあ、今ではそんな船を使う人間はもういないからな」
「残念だよね。その船にも乗ってみたかったなぁ」
美しい景色に名残惜しさを感じながら、ぼくたちは先へ進んだ。丘を下っていくにつれて、あの空と大地が溶け合った湖は、丘と山の向こうに姿を消してしまった。
なだらかな坂が続く道を下り続けていくと、旧市街が姿を現した。
コロニー5周辺の旧市街に比べると小さい規模の街だったけれど、若緑の大地の中で、くっきりとそこだけがくり抜かれたように様々な色の建物が建てられた街の光景は、なんだか異質なもの同士が混じり合いながらも、互いの美しさを引き立たせ合っているように感じて面白かった。
この旧市街には、モダンな建物が並ぶばかりで、バロック建築やゴシック建築といった派手な建物はほとんど見られなかった。静寂に包まれているのはどの旧市街も同じだが、ここはそもそも建物の数が少ないことと、緑が多いことで、なんだか他の場所よりも街としての生命が残っているような気がした。
旧市街をしばらく進んでいくと、フョードルの言っていたライン川がぼくたちの前に現れた。
川幅はそこまで大きくはなかったが、その流れはとっぷりと緩慢な動きをしていて、水深は深そうだった。川の対岸はこちら側の旧市街以上に建物の数が少なく、大きく盛り上がった緑の丘が列をなすように長く連なっている。
川に架けられたダムの橋を渡りながら、ぼくはこの川の流れが行き着く先を想像した。
この川はきっと、あのボーデン湖へと注いでいるのだろう。あの丘の上から見えたブルーグリーンの美しい湖に。
ぼくが今見ているこの水が、時間をかけながらあの丘から遠く望んだ美しい湖へと流れ込むところを想像すると、ぼくはなんだか不思議な気持ちになった。
──まるで、世界のすべてが繋がっているみたいだ。
絶え間なく流れ続ける川の流れの中に、ぼくは自分の姿を見た気がした。ぼくだけじゃない、上流から下流に至るすべての場所に、すべての人間の居場所があるような気がした。
ぼんやりと川面を眺めながらそんなことを感じていると、ぼくは、またあの大きな感覚の気配が現れたのを感じた。
けれど、不思議なことに今のぼくは、いつものように肌が粟立つこともなければ、焦燥にこころを焼かれるような感覚に襲われることもなかった。
今回現れたそれは、まるでぼくの身体をやさしく包むように纏わりついて、胸を心地よい温かさで満たしていくだけだ。
ぼくは、心臓から送り出される血がその温かみを増して、身体が穏やかで心地良い、ふわふわした感覚に包まれていくのを感じた。
「焦らなくてもいい」‥‥。ふとフョードルの言葉を思い出したぼくは、「たしかに、そうかもしれない」と思った。
たとえこの感覚の正体を掴めなくても、こんなふうにその気配に肌を撫でられながら世界を見ることも悪くないと思った。
ぼくは、フョードルとシャロンが気長に待ってくれるのに甘えて、そのまましばらくその流れを眺め続けた。
◆
昨日、ライン川を渡って旧市街に入ったぼくたちは、そのまましばらく進んで、開けた広場に止まっている車までたどり着き、昨日はそのままそこで夜を明かした。
ここからこの旅の目的地へは、もう二日ほどの距離らしい。
それを聞くと、ますますやる気が出てきたけれど、フョードルとシャロンが言うには、ここからは勾配がきつい場所も多くなってくるという。
ふたりの言っていた通り、凹凸があちこちに目立つようになってきた。丘の上り下りを繰り返し、くねくねと曲がりくねった道をぼくたちは歩き続けた。
今日の移動は少し長くなる予定だ。ぼくたちの今日の目的地は車ではない。いや、車はそこに着いているはずだから車がある場所がゴールではあるのだけれど、そこにはフョードルの古い友人が住んでいるらしい。
その人はフョードルの兄弟子にあたる人物で、もともとはふたりの師匠が亡くなった後も一緒に各地を旅していたのだそうだ。けれど、彼は今住んでいる場所で出会った女性と夫婦になって、その場所に身を落ち着けたらしい。
フョードルは「俺はあいつに振られたのさ」と笑いながら言っていたけれど、その様子からして、その兄弟子の選択にフョードルは満足しているようだった。ふたりはコロニー5へ来る時も、そこでお世話になったらしい。
ぼくは、その兄弟子という人物がどんな人なのか聞いてみたけれど、シャロンにホワイトシチューを作った時のように「実際に会うまでのお楽しみでーす」と笑いながら言われてしまった。
ただ、フョードルの言葉の節々から、フョードルはその兄弟子に敬意を抱いているようだった。
フョードルが尊敬するような人だ。凄い人なのは間違いない。
ただ、どんな風に凄いのだろう。やっぱりとても賢い人なのだろうか。それとも、フョードル以上に体力のある人なのだろうか。はたまたその両方を兼ね備えた完璧な人なのだろうか。
どんな人物かとあれこれ想像していると、ぼくはその実際に会うのが楽しみになってきた。
わくわくとした気持ちを胸に、どこまでも続く道を歩く足に力を込めた。
ぼくたちが今歩いている道の景色は、どこも似ているように見えて、一つ一つがたしかに違っていた。車に乗っていたなら、見分けなんてとっくにつかなくなってしまっていただろう。
ただ、それでも次々現れる似たような景色は、すぐにぼくの記憶から消えていってしまう。
そして、ぼくの目はすこしずつその景色の見分けがつかなくなってきてしまっていた。目で見た景色の情報は、まるで煙のようにそのまま頭をすり抜けていってしまう。
はじめはなんだか残念な気がしたけれど、歩みを進めているうちにいつの間にかそんなことは気にならなくなっていった。
空が朱を帯びて影が伸びてきた頃、なだらかな丘の頂上から、石畳の道が緩く降っていった先にいくつかの建物が集まった小さな集落が見えた。そのうちの一つの建物の庭の一点が、不自然に白い陶器のような光を放っている。ようやく今日の目的地が見えた。
車が止まっているのは、一般的な石造りの民家に、よく目立つ大きな赤い屋根の建物が連結した複合的な建物だった。大きな建物の外壁は白く、つるりとなめらかな素材で塗り固められていて、そのあちこちにアーチ窓がはめ込まれている。その建物には灯りがつけられているようで、ぼんやりと暖かみのある光がアーチ窓から広がっている。
あそこに、フョードルの兄弟子が住んでいるはずだ。
以前のように足が震えて歩けなくなるなんてことはなかったけれど、それでもかなり疲れていたぼくは、ようやく着いた、と思ってほっと安堵した。陽もちょうど地平線の向こうへと沈みかかっている。
丘の上から車の止まっている建物へと続く道を下りながら、ぼくはふとフョードルの兄弟子夫婦はこんな場所に住んでいて寂しくはならないのだろうかと思った。
ここは街というにはとても小さいけれど、夫婦一組で住むには十分すぎるほどに広い。そのうえ、あたりには他にも建物がまだぽつぽつと残っている。
もし、ぼくがこの場所に住めば、そういう人間のいなくなった建物を見るたびに、そこにはもう自分以外の人間がいないことを突きつけられるようで、なんだか恐ろしかったり寂しい気持ちになるような気がしたのだ。
旧市街のような人間がいなくなった街というのは、なにか大切なものが抜け落ちてしまったような、独特の空気感がある。時々訪れる分には新鮮な気持ちになるけれど、ずっと長いことそこにいると、なんだか目に見えない何かに心を押しつぶされるような気持ちになるのだ。
しかし、突然あたり一帯の建物にもぽつりぽつりと灯りがつきはじめた。
一つ一つの建物に、あの大きな建物と同じ暖かな光が宿っていくのを見て、ぼくは驚きの声をあげた。
「ここにはまだ人が住んでいるの!?」
「そういえば言っていなかったな。ここは『ゲイザー』の子孫がつくった集落でな、引退した元『ゲイザー』も多く住んでいる場所なんだ」
「といっても人の数はもう大分少ないんだけどね」
そうか。ということは、ここはフョードルの師匠が住んでいたという『ゲイザー』の集落と同じようなところなのか。どおりで、これまで通ってきた旧市街や集落の建物とくらべて綺麗に残っているわけだ。
また歩き出したフョードルとシャロンについて歩きながら、ぼくはこの集落の建物を見回した。
どの家も急勾配な屋根が広く軒先を垂らしている。赤屋根の建物が多かったけれど、赤以外にもさまざまな色の屋根がかかっていた。どの家も古くはあったけれど、ちゃんと手入れがなされているようで綺麗な印象を受けた。
ぼくがそうして建物を観察していると、突然大きな声が響いてきた。
「フョードル!フョードルじゃないか!」
声のした方を見ると、灯りがついたばかりの建物から人が出てきていた。
彼はフョードルのもとへ駆け寄ってきて、フョードルを固く抱きしめた。
「まさかまた会えるとは思っていなかったよ!コロニー5へ行くと言っていたのに、戻ってきたのかい?」
「色々あってな。悩んだんだが、結局シュヴィーツのあの場所へ帰ろうと思っているんだ」
その人はフョードルの胸元で眠るユミと、シャロンと並んで立つぼくのことを見とめると、すっと顔がこわばってしまった。
彼が考えたことがわかったぼくは、むずがゆい気持ちになった。同情や憐憫のまなざしで見られた経験は何度もあるとはいえ、この感覚にはいつまで経っても慣れなかった。
「そうか‥‥、大変だったんだな‥‥。ロレンツォさんのところに行くんだろう?今はちょうど夕の祈りが終わる時間のはずだ」
「ああ。今日一日世話になって、明日出発するつもりだ」
「そうなのか‥‥。‥‥そういうことなら、兄弟水入らずの楽しみを邪魔するわけにはいかないな。存分に語り合って、楽しんでくれよ」
「コロニー5へ向かう時に、もう別れの言葉は十分に交わしたはずだったんだがな」
フョードルは笑いながらそう言うと、その人ともう一度固く抱擁を交わして、ぼくたちはその場を後にした。
さっきの人の家から少し離れたところで、シャロンが口を開いた。
「一日しか泊まらないの?」
「ああ、そのつもりだ」
シャロンの質問に、フョードルはきっぱりと短く答えた。
しかし、シャロンはその答えに納得せずに、大きな声で文句を言いはじめた。
「えー!なんでよー!」
「家を空けてからしばらく経っているからな。出来るだけ早く行って手入れをしないといけないだろう?人が住まなくなった家は急速に汚れて弱っていくからな」
たしかに、家は常に自然や時間の経過による劣化と戦っているから、人間の手入れは必須だ。人が住まなくなった家は、定期的な掃除や換気もされないからすぐに埃やカビが溜まるし、害虫や動物たちが家に入り込んで荒らされる可能性もある。なにより、雨風や日光は継続的に家を劣化させていく。
フョードルの言ったことに納得していると、しかしぼくはそう言ったフョードルの顔に、一瞬違和感を抱いた。
フョードルの顔がどこか暗い色を帯びたような気がしたのだ。
けれど、それは一瞬のことで、瞬きをして目をもう一度開いた時にはいつものフョードルに戻っていた。シャロンはその顔を見なかったようで、まだ文句を言っている。
「あーあ、ロレンツォさんとソフィさんのとこなら、もっと長くいたかったなぁ」
“ロレンツォ”。それがフョードルの兄弟子の名前だった。ソフィというのはロレンツォさんの奥さんの名前だ。
いよいよ目の前まで迫った家を前に、ぼくは一体どんな人が出てくるのかと期待で胸がわくわくするのを感じた。
車の止まった敷地内に入り、平側に備え付けられた玄関の前に立つ。
フョードルがノックをしてしばらく待っていると、木製の扉が硬い音を立てて開かれた。
「やあ。思っていたよりも早かったね」
扉の向こうから現れた人は、そう言ってにこやかに笑うと、ぼくたちを家の中に招き入れてくれた。
「ロレンツォさーん!久しぶりー!!」
家の中に入ると、シャロンが勢いよく、あの鋭いタックルを繰り出した。
扉を開けてくれた時からきっとそうだろうと思っていたけれど、この人がロレンツォさんか。
ロレンツォさんはシャロンのタックルによろけながらも、それをちゃんと受け切ってシャロンに笑いかけた。
「久しぶりだね、シャロン。変わらず元気なようで安心したよ。フョードルも、無事に着いて何よりだ。しかし本当に早かったね。てっきり着くのは日が暮れてからになると思っていたけれど」
「この子たちが頑張ってくれたからな。まったく、子どもというのは凄いものだよ。めきめきと成長していく」
ロレンツォさんは笑顔でうんうんとうなずきながら、フョードルの後ろにいるぼくの姿を見とめたらしかった。
「はじめまして。君がトーマだね、フョードルから話は聞いているよ。私はロレンツォ、よろしくね」
ロレンツォさんはそう言ってまた柔らかい笑顔を浮かべながら手を差し出してきた。握手をするのだと察して、ぼくも慌てて手を差し出した。握った手はフョードルほどじゃないけれど、大きくて力強さが伝わってくるような手だった。この人が、フョードルの兄弟子‥‥。
ぼくは、自分の想像していた人と、目の前の人とを頭の中で照らし合わせた。
長い移動のなかで、ぼくの中の想像は煮詰まっていた。
ぼくの中でのロレンツォさんは、フョードルと同じくらい賢くて、フョードルのように丁寧な喋り方で話し、フョードルに似た筋骨隆々の体をしているという、何から何までがフョードルに似た、フョードルみたいな人、という想像だった。それはもはやフョードル自身じゃないかと自分でも思っていたけれど、ぼくには、フョードルほどの人間が尊敬するのがどんな人なのか想像もできなかったのだから仕方ない。
そして、今ぼくの目の前にいる現実のロレンツォさんは、ぼくの想像とはまったく違っていた。
実際のロレンツォさんは、フョードルほどの身体の大きさはないけれど、オリーブ色の肌に整った顔立ちをしたハンサムな人だった。顎も頬骨も鼻も、顔のパーツの一つ一つがはっきりと綺麗な輪郭を描いていて、服の上からでもわかるくらいに引き締まった身体も相まって、まるで彫刻のようだった。上下が一続きになったふわりとした真っ白なローブのような服を着ていて、それがなんだかロレンツォさんのまとう雰囲気を不思議なものに仕立てあげていた。
唯一、ぼくの想像通りだったところは、フョードル以上に丁寧な言葉遣いと柔らかな物腰だけだった。
「しかし、いきなり家の前に無人の浮上式自動車が現れた時には驚いたよ。何事かと思って中を確認してみたら、『AlicE』の音声記録に君からのメッセージが入っていたから尚更だ。いつあんなに立派な車を手に入れたんだい?」
「コロニー5を出る時に、コロニー長から頂いたんだ。律儀な人でな。必要になった時に使うように、と」
「なるほど、だから自動運転モードで先行させているのか。君らしいな」
フョードルとロレンツォさんが玄関先で談笑していると、家の奥から女性が出てきた。
「みなさんいらっしゃい。立ち話なんてしていないで、中に入ってくださいな。今日は賑やかになりますね」
「ソフィさん!!」
シャロンが今度はロレンツォさんから離れて女性の方へ飛び込んで行った。
女の人にあのタックルは耐えられないのではと一瞬心配になったけれど、シャロンも流石に加減したようで、お腹の辺りにぽふんと顔を埋めただけだった。
‥‥できればぼくに飛び込んでくれる時もあれくらいの勢いでしてもらいたい。
「あらあらシャロン。しばらく見ないうちにまた美人さんになったわね。元気そうでなによりよ」
褒められたシャロンは「えへへ」と嬉しそうに笑っている。
ぎゅっと抱きしめ合うふたりは、なんだか本当の親娘のように見えた。
ソフィさんは、綺麗な人だった。フョードルと同じ真っ白な肌に緑色の瞳が映えて、まるで物語の中に出てくる妖精のようだった。鎖骨あたりまで伸びた亜麻色の髪を一つに編み込んで、それを首の右側から垂らした髪型がよく似合っている。
ソフィさんもロレンツォさんと同じ上下一続きの白一色のローブを着ていた。夫婦でお揃いの服を着るなんて、とても仲が良いのだろう。ローブの白さがふたりの美しさを引き立たせていて、そこには神々しさすら感じた。
「ふたりとも疲れただろう。ソフィと夕食の支度をしておくから、先にシャワーを浴びておいで」
ロレンツォさんはそう言うと、ぼくにシャワー室の場所を教えてくれた。
「フョードルはまだ元気そうだから、私たちの手伝いをしてくれるかな?色々と話も聞きたいしね」
ロレンツォさんはフョードルに、ぼくたちに向けるのと変わらない笑顔を向けて言った。
けれど、フョードルはすこし唇を歪めてロレンツォさんから目を逸らしてしまった。ぼくは、その表情に見覚えがあった。
「‥‥あぁ、もちろん」
ぼくは、フョードルがあんな罰が悪そうな顔をするところを見たことがなかった。シャロンも同じようで、フョードルとロレンツォさんの顔を交互に見比べている。
ぼくたちは、フョードルのその様子が気になっていたけれど、ソフィさんに「さあ、入っていらっしゃい」とタオルを渡されてしまったので渋々シャワーに向かった。
ぼくは、ロレンツォさんが指し示した場所へ続く広い廊下に入る前に、ちらりとフョードルの顔をもう一度見た。
やっぱり、あの顔はそうだ。
フョードルのあの表情は、ぼくがコロニーにいた頃、おじいが小言を言いにきた時のぼくの表情と同じものだった。
シャワー室は廊下の突き当たりにあった。
室内にはガラス戸に覆われたシャワーブースと、すこし離れた場所にジャグジーが備え付けられていた。ただ、ジャグジーは普段使われていないようで、浴槽の中にいろいろなものが入れられていた。
ぼくは、ここに来てようやくシャワーは一人ずつでなければ浴びられないことに気がついた。どうしてぼくは、今の今までそのことに気が付かなかったのだろう。
慌ててシャロンに先に入るように言って、シャワー室を出ようとした。けれど、シャロンはそんなことは気にしていなかったようで、あっけらかんと「わたしは一緒に入ってもいいんだよ?」なんて言われてしまった。
いや、ダメだろう。ぼくはシャロンを残して急いで外に出た。
しばらくするとシャワー室の扉越しに水が流れる音が聞こえてきて、なんとなく居心地が悪くなったぼくは、扉から少し離れた場所に移動した。
前々から思っていたことではあるけれど、きっとぼくは、シャロンに“男”として認識されていない。
自分でも、それはそうだろうなと納得できてしまうところがまた情けなかったけれど、事実ぼくはシャロンと出会った時から、彼女に一方的に何かをもらってばかりで、ぼくからは何もシャロンにあげられていない。これではシャロンに意識してもらえなくて当然だろう。
ただ、まさか一緒にシャワーを浴びることにも抵抗がないほどに意識されていないとは思わなかった。
ぼくは、自分の恋が想像以上に前途多難であることにがっくりとしながら、シャロンが出てくるのを待った。
シャワーを浴び終えたぼくたちは、シャロンの案内でダイニングに向かった。
廊下の反対側のダイニングに入ると、部屋中が甘さと酸味が混じり合ったような良い匂いに包まれていた。
ロレンツォさんとソフィさんがキッチンで忙しなくテキパキと動いていて、フョードルはふたりが作った料理を盛り付けているところだった。ユミは今は抱っこ紐から外されて、ダイニングに簡易的につくられたベビーベッドの上で静かに寝息を立てていた。
フョードルの顔からは、シャワーを浴びる前のあの表情は消えていて、どこかスッキリしたような顔をしていた。
「おや、ちょうど良い所に来たね」
「さっぱりしたみたいでよかったわ。ふたりとも、料理を運んでくれる?」
ソフィさんに言われた通り、ぼくたちはフョードルが盛り付けた料理を受け取って、白いテーブルクロスの敷かれたテーブルへとそれを運んだ。
皿の上に盛りつけられていたのは、スパゲッティだった。黄色がかった小麦色の麺の上に、ひき肉がゴロゴロと乗った赤みのあるトマトソースがたっぷりとかけられていて、ふわりと立ち昇る湯気に乗ってトマトの甘い匂いが漂ってくる。別のお皿には、ピザが盛り付けられている。こちらの料理も、真っ赤なトマトソースがたっぷりと塗り込まれた生地の上に、緑のバジルと真っ白なチーズが色鮮やかにピザを彩っていて、その色合いが目に映えた。
テーブルの上にすべての料理を並べ終わると、ぼくたちは席についた。
目の前の色とりどりの料理にぼくはすっかり食欲を刺激されて、フォークとスプーンを手に食べはじめることを許されるのを今か今かと待っていた。
しかし、席についたロレンツォさんとソフィさんは食器には手を伸ばさず、テーブルの上で手を組むと目を閉じてしまった。いや、ふたりだけじゃない。フョードルとシャロンも、ふたりと同じように手を組んで目を閉じている。
にわかに厳かな雰囲気が食卓を包むのを感じた。
「すまないね、トーマ。少しだけ待っていてくれるかい」
なにが起こっているのか分からずに戸惑っていたぼくにロレンツォさんが気がついて、優しい声でそう言われた。
ぼくもみんなと同じようにするべきか迷っていると、ソフィさんが静かに、しかし凛とした声で言葉を紡ぎはじめた。
「天にましますわれらの父よ、この豊かな食卓を前にして、私たちが再び共に集えた奇跡に感謝いたします。遠く離れていた私たちを再び結びつけてくださり、このようにして愛する家族と友人たちとともに食事を共にできる喜びを与えてくださったこと、深く感謝いたします。私たちの今夜の食事を祝福してください。この食事が、私たちの体だけでなく、魂をも育んでくれますように。そして、この食事を通して、私たちの心が一つに結ばれ、今この瞬間を最大限に楽しむことができますように。この世界に残された時間の中で、私たちが今日この食事を共にできることは、計り知れない恵みです。私たちの世界が直面している困難に、私たちが立ち向かう希望を与え、日々の小さな喜びを見出す力を授けてください。私たちが今、共にいられるこの瞬間を大切にし、愛と感謝の気持ちを持って一日一日を生きていくことができますように。私たちが互いに支え合い、愛と慈悲の心をもって行動できるように導いてください。全ての恵みを与えてくださるあなたに、心から感謝を捧げます。アーメン」
ソフィさんが言葉を終えると、ロレンツォさん、そしてフョードルとシャロンもそれに続いて「アーメン」と唱えた。
さっきまでこの場に漂っていた空気感はたちまち霧散して消えていった。
ぼくは、ソフィさんが言葉を唱えている間、ただただ呆然としているしかなかった。
ぼくは、外の世界のことはまだまだ知らないけれど、今ソフィさんやみんながしていたことが何なのかは知っていた。
今のは、“祈り”だ。祈りとは、人間が自分の願いや後悔を神に対して伝える行為‥‥。
つまり、ロレンツォさんとソフィさんは、神を信じている人だった。
「お待たせしたね。さあ、冷めないうちに食べよう」
「今日の料理は腕によりをかけて作ったのよ。報せが届いた時からずっとソースを煮込んでいたんだから」
「わー!嬉しい!わたし、ソフィさんの料理大好き!」
さっきまでまるで石のように空気の硬かったみんなは、その石が砕けたかのように、唐突にリラックスしはじめた。
シャロンはさっそくピザを一切れとると、それにかぶり付いて「美味しいー!」と頬をおさえてよろこびの声を出している。
みんなもそれぞれにスパゲッティやピザを取り分けて食べはじめていた。
ぼくだけが、一連の出来事についていけてなかった。
そんなぼくの様子に、ロレンツォさんとフョードルは気づいたようで、ふたりはちらと目を合わせるとロレンツォさんの方がぼくに話しかけてきた。
「驚かせてしまったみたいだね。私たちはキリスト教徒なんだ。この家の横につながっている赤い切妻屋根の建物があっただろう?あれは教会でね。私たちは、この集落で独自に教会の運営を行っているんだ」
ロレンツォさんはそう言うと、自分が着ている服を指差してみせた。
「これはアルブという衣装でね。私たちの制服のようなものなんだよ」
ぼくは、ロレンツォさんの説明を聞きながら、自分のこころがどこか遠い場所にあるような感覚になっていた。
ぼく自身はずっと神なんていないと考えていたし、今のこの世界に神を信じている人なんていないとも思っていた。フョードルの“絶対的なものはない”という話を聞いてから、ぼくはますます強くそう思うようになっていた。だから、神なんていうものを本気で信じていたむかしの人間のことを、こころの中で馬鹿にもしていた。
けれど、むかしフョードルと一緒に世界を旅して回り、そのフョードルが敬意を払うロレンツォさんと、その奥さんであるソフィさんは、ぼくが馬鹿にしていた“神を信じる人たち”だった。
ぼくの中に浮かんだのは、“どうして”という疑問だった。
まだ会って間もないけれど、ぼくはロレンツォさんとソフィさんのふたりからは、フョードルと同じ、とても知的な雰囲気を感じ取っていた。実際に話してみても、言葉遣い、話す内容、そこから垣間見える考え方のすべてが、ふたりの知性と教養の高さを物語っていた。
だからこそ、ぼくにはふたりが神を信じる理由が分からなかった。
だって、神なんていなかったじゃないか。
ぼくたちの世界は、あと八年で終わってしまう。
神は、宇宙の終わりが来ることを防げなかったじゃないか。
ロレンツォさんもソフィさんも、ぼくとシャロンほどではないけれど、十分若い。ふたりともが、ぼくたちと同じく最後まで生きることのできない『マルーン』だ。だから、コロニーの老人たちのように上から目線でぼくやシャロンのような存在を哀れんで、無責任に神なんてものを持ち出しているわけじゃないことはわかる。なぜなら、ふたりも宇宙の終わりにおいては当事者だからだ。
じゃあ、一体どうしてふたりは神なんてものを信じられるんだ。ぼくたちに何をしてくれるわけでもない、見せかけだけの空白の存在を。
ぼくは、もうなにがなんなのか分からなくなってしまって、せっかくの食卓だというのに一人暗い気持ちになってしまった。
せめてみんなの気分を悪くしないよう精一杯に上機嫌なフリをして卓上のスパゲッティやピザに手を伸ばすけれど、さっきまではあんなに美味しそうに映っていた食べ物が、今は色味が落ちたように映って、味もよくわからなくなってしまった。
その時、突然ユミの泣き声が響いてきた。こころが乱れていたぼくは、自分のこころを整理する時間が欲しくて、自分が行くと言って食卓を立ち上がり、ユミが眠るベビーベッドに向かった。
ベビーベッドの上で、ユミは小さな身体を震わせ、顔を真っ赤にして泣いていた。フョードルがさっきミルクをあげたと言っていたから、空腹な訳ではないのだろう。
ぼくはユミを抱き上げると、ゆっくりと揺らしたり、背中をトントンとやさしく叩いた。
しかし、今日のユミはなかなか泣き止まなかった。いつもならすぐに泣き止むというのに。
けれど、今のぼくはまだあの食卓に戻りたくなかったので、むしろ都合が良かった。「ユミは、もしかしたらぼくの気持ちを汲んでくれているのかもしれないな」、なんてことを思いながら、ぼくはユミをあやし続けた。
頭の中では、神という存在のことでいっぱいになりながら。
マルーン
第六章 兄弟子
シチューを食べてたっぷりと寝た次の日の移動は、まったく辛くなかった。
道は少しずつ険しくなって、長い坂や急な坂も増えていたけれど、疲労がすっかりなくなった足は、ぐんぐん先へ進むことができた。フョードルも「これはシャロンと同じようになるのも時間の問題か」と言って笑っていた。
ぼく自身、これが本当に自分の身体なのかと疑ってしまうくらい、身体に力がみなぎっているのを感じていた。
この日の移動も、これまでと同じように車を先行させた場所がゴールになるはずだったけれど、この日は空がまだ青く澄んでいる時間に車までたどり着いてしまった。
シャロンは、ぼくが歩き切ったことを、ぴょんぴょん跳ね回りながら自分のことのように喜んでくれた。
「すごいよ、トーマ!休憩もほとんど取らなかったのに!」
「本当にすごいな‥‥。子どもの成長はこんなに早いのか‥‥」
フョードルは驚きつつも、シャロンと同じようにぼくのことを褒めてくれた。
ぼくは、そんなふたりの様子と、なによりはじめて自分の足でゴールまで辿り着けた事実に、心が達成感で満たされるのを感じた。なにかをやり遂げることはこんなに気持ちがいいことなんだと、はじめて知った。
それからの移動は、少しずつ距離を伸ばして、休憩を挟む回数も少なくなっていった。きっとこれが本来のふたりのペースだったのだろう。ふたりはぼくの様子を見ながら進んでくれたけれど、ぼくはちゃんとついていくことができた。
この日は、いつもよりも早い時間に移動をはじめた。フョードルが言うには、目的地までもう半分の位置を過ぎて、何も問題がなければあと三日ほどでフョードルとシャロンが拠点にしていた場所に着くらしい。今日一日で、進めるだけ進みたいということだった。
昨日から、ぼくたちが進む道には少しづつ傾斜が出てきて、周囲の地形もでこぼことしてきていた。平坦な大地が広がるコロニー周辺では見だことがないほど上下に起伏した土地だった。
しかし、どれだけ進んでも、石畳の道は途切れることなくどこまでも続いている。石畳は、車二台分くらいの幅の道から、広い場所だと十メートルくらいもありそうな幅の道に表面がなめらかな石がびっしりと敷き詰められていて、所々老朽化した場所が一部崩れていたり、そうしてできた隙間から雑草を生やしてはいたが、それでも道としての役割は十分に果たしていた。
はじめての傾斜は、平坦な道よりも歩きにくかったけれど、今のぼくは体力を削られることなく登っていくことができた。やがて、周囲の起伏が少し落ち着いて、遠くの景色まで広々と見渡せる場所に出ると、左側の視界に巨大な山の連なりが姿を現した。
ぼくは、その長大さと迫力に驚きを隠せず、感嘆の声をあげた。
「アルプス山脈だよ!すごいよねぇ」
シャロンは、興奮を抑えられないといったようにそう言うと、目をキラキラさせながら、ぼくと同じように遠く天を衝くように聳える山々を見渡した。
そうか、あれがシャロンの話に出てきたアルプス山脈なのか。ぼくたちの立つ平らな大地が下から突き上げられたかのように巨大に起伏したその連なりは、シャロンの話していた通り、あまりに大きく、悠々としていて、こころの裡に畏敬の念が溢れてくるのを感じる。その険しい山肌が描く稜線は美しく、尾根に散らされた真白い雪はまるで化粧のようで、山全体を美しく飾って神秘的な雰囲気を纏わせている。
まさか、実際に実物を見ることが叶うとは思っていなかったぼくは、今自分の目に映る巨大な自然の産物に胸が熱くなるのを感じた。
「あのアルプス山脈はヨーロッパとイタリア半島とを隔てるように東西に大きく広がる山脈でな。俺たちはずっとあの山脈に沿って歩いていたんだよ」
フョードルはそう言いながら、地図を見せてくれた。たしかに地図で見ると、ぼくたちが歩いてきた道の左側にはずっとあの山脈が続いていた。
「この道をずっと進んでいけば、湖に行き当たる。この湖を左から迂回して通り抜けた先、ライン川という川を渡った対岸の先が今日のゴールだ」
「六時間くらいかな」
フョードルは地図を指し示しながら教えてくれる。フョードルが示した道筋を辿ると、たしかに大きな湖がここから山一つ向こうに広がっているようだった。
「大きな湖だね」
「ボーデン湖だ。氷河によってできたU字型の谷に水が溜まってできた氷河湖だ」
氷河湖‥‥。はじめて聞いた言葉だった。
「氷河湖って?」
「氷河がつくった湖のことだよ!」
得意気に答えたシャロンの言葉を継いで、フョードルは、地図の地形を示しながら話しはじめた。
「もともと、俺たちが歩いてきた道も含めて、この北アルプス山脈沿い一帯は大昔氷河に覆われていたんだ。だから、あちこちU字型の谷や窪地が多かっただろう?」
たしかに、これまでぼくたちが歩いてきた道は、幅の広さは大小あっても、両側を高い丘や山に挟まれた場所が多かった。あれは、氷河の動きでできた地形だったのか。
「分厚く広がった氷河が大地を削って出来た窪みに、溶けた氷河の水が溜まって出来たのが氷河湖だ。北アルプス山脈沿いにはこういった氷河湖が点在している。ボーデン湖はその中でも大きな氷河湖なんだ」
こんなに広い範囲の大地を削り取り、溶ければ湖になってしまうほどの巨大な氷‥‥。
ぼくは、このあたり一帯を覆っていた氷河の姿を想像してみた。
雪が吹雪いて、あたり一面が白く染め上がった極寒の世界。分厚く降り積もった雪は、やがて氷へと変化し、自分の重さでゆっくりと移動をはじめる。人間の目では捉えられないほどゆっくりと、しかし確実に大地を削り、地形を変えていき、やがて地球の気温が上がると、氷河はにわかに溶け出して、自らがつくった窪みへと流れ込んで湖となっていく‥‥。
やっぱり、自然はすごい。ぼくは、これだけ広い大地を削り取ってしまった氷河の力強さにも驚愕したけれど、なによりそんな巨大な氷が永遠に残ることなく、今は見る影もなく溶かし尽くされてしまったということに、世界というものの大きさを感じずにはいられなかった。
ぼくたちは、アルプス山脈を左に望みながら道を進んだ。道中は、フョードルが言っていたようにU字型になった地形が多く、それらの道一つ一つが氷河がつくり出したものだと考えると、心の底からこの自然に対する畏怖の念が湧き上がってくる。
上下にくねくねとした道を歩き進むと、小高い丘に出て、突然ぱっと視界が開けた。
遮るものがなくなったぼくたちの目に、大きな湖が映った。春の暖かく明るい日差しを受けて、湖面が青く澄んで輝いている。
「綺麗だ‥‥」
ぼくは、思わずつぶやいていた。同じ青に類する色でも、ぼくたちの頭上に広がる空の色とは違ったブルーグリーンをたたえた湖は、まるでどこまでも深く鮮やかな青を抱いた空と若い草木が萌える若緑の大地とがそこで交わっているかのようで、その景色を一枚の絵画のように仕立てあげていた。
「あの湖を、左手側から迂回していくんだ。ずっと昔は、対岸とこちら側の岸とを繋ぐ船が出ていたらしいんだが、少なくとも俺が『ゲイザー』になったときにはもうなくなっていたな。‥‥まあ、今ではそんな船を使う人間はもういないからな」
「残念だよね。その船にも乗ってみたかったなぁ」
美しい景色に名残惜しさを感じながら、ぼくたちは先へ進んだ。丘を下っていくにつれて、あの空と大地が溶け合った湖は、丘と山の向こうに姿を消してしまった。
なだらかな坂が続く道を下り続けていくと、旧市街が姿を現した。
コロニー5周辺の旧市街に比べると小さい規模の街だったけれど、若緑の大地の中で、くっきりとそこだけがくり抜かれたように様々な色の建物が建てられた街の光景は、なんだか異質なもの同士が混じり合いながらも、互いの美しさを引き立たせ合っているように感じて面白かった。
この旧市街には、モダンな建物が並ぶばかりで、バロック建築やゴシック建築といった派手な建物はほとんど見られなかった。静寂に包まれているのはどの旧市街も同じだが、ここはそもそも建物の数が少ないことと、緑が多いことで、なんだか他の場所よりも街としての生命が残っているような気がした。
旧市街をしばらく進んでいくと、フョードルの言っていたライン川がぼくたちの前に現れた。
川幅はそこまで大きくはなかったが、その流れはとっぷりと緩慢な動きをしていて、水深は深そうだった。川の対岸はこちら側の旧市街以上に建物の数が少なく、大きく盛り上がった緑の丘が列をなすように長く連なっている。
川に架けられたダムの橋を渡りながら、ぼくはこの川の流れが行き着く先を想像した。
この川はきっと、あのボーデン湖へと注いでいるのだろう。あの丘の上から見えたブルーグリーンの美しい湖に。
ぼくが今見ているこの水が、時間をかけながらあの丘から遠く望んだ美しい湖へと流れ込むところを想像すると、ぼくはなんだか不思議な気持ちになった。
──まるで、世界のすべてが繋がっているみたいだ。
絶え間なく流れ続ける川の流れの中に、ぼくは自分の姿を見た気がした。ぼくだけじゃない、上流から下流に至るすべての場所に、すべての人間の居場所があるような気がした。
ぼんやりと川面を眺めながらそんなことを感じていると、ぼくは、またあの大きな感覚の気配が現れたのを感じた。
けれど、不思議なことに今のぼくは、いつものように肌が粟立つこともなければ、焦燥にこころを焼かれるような感覚に襲われることもなかった。
今回現れたそれは、まるでぼくの身体をやさしく包むように纏わりついて、胸を心地よい温かさで満たしていくだけだ。
ぼくは、心臓から送り出される血がその温かみを増して、身体が穏やかで心地良い、ふわふわした感覚に包まれていくのを感じた。
「焦らなくてもいい」‥‥。ふとフョードルの言葉を思い出したぼくは、「たしかに、そうかもしれない」と思った。
たとえこの感覚の正体を掴めなくても、こんなふうにその気配に肌を撫でられながら世界を見ることも悪くないと思った。
ぼくは、フョードルとシャロンが気長に待ってくれるのに甘えて、そのまましばらくその流れを眺め続けた。
昨日、ライン川を渡って旧市街に入ったぼくたちは、そのまましばらく進んで、開けた広場に止まっている車までたどり着き、昨日はそのままそこで夜を明かした。
ここからこの旅の目的地へは、もう二日ほどの距離らしい。
それを聞くと、ますますやる気が出てきたけれど、フョードルとシャロンが言うには、ここからは勾配がきつい場所も多くなってくるという。
ふたりの言っていた通り、凹凸があちこちに目立つようになってきた。丘の上り下りを繰り返し、くねくねと曲がりくねった道をぼくたちは歩き続けた。
今日の移動は少し長くなる予定だ。ぼくたちの今日の目的地は車ではない。いや、車はそこに着いているはずだから車がある場所がゴールではあるのだけれど、そこにはフョードルの古い友人が住んでいるらしい。
その人はフョードルの兄弟子にあたる人物で、もともとはふたりの師匠が亡くなった後も一緒に各地を旅していたのだそうだ。けれど、彼は今住んでいる場所で出会った女性と夫婦になって、その場所に身を落ち着けたらしい。
フョードルは「俺はあいつに振られたのさ」と笑いながら言っていたけれど、その様子からして、その兄弟子の選択にフョードルは満足しているようだった。ふたりはコロニー5へ来る時も、そこでお世話になったらしい。
ぼくは、その兄弟子という人物がどんな人なのか聞いてみたけれど、シャロンにホワイトシチューを作った時のように「実際に会うまでのお楽しみでーす」と笑いながら言われてしまった。
ただ、フョードルの言葉の節々から、フョードルはその兄弟子に敬意を抱いているようだった。
フョードルが尊敬するような人だ。凄い人なのは間違いない。
ただ、どんな風に凄いのだろう。やっぱりとても賢い人なのだろうか。それとも、フョードル以上に体力のある人なのだろうか。はたまたその両方を兼ね備えた完璧な人なのだろうか。
どんな人物かとあれこれ想像していると、ぼくはその実際に会うのが楽しみになってきた。
わくわくとした気持ちを胸に、どこまでも続く道を歩く足に力を込めた。
ぼくたちが今歩いている道の景色は、どこも似ているように見えて、一つ一つがたしかに違っていた。車に乗っていたなら、見分けなんてとっくにつかなくなってしまっていただろう。
ただ、それでも次々現れる似たような景色は、すぐにぼくの記憶から消えていってしまう。
そして、ぼくの目はすこしずつその景色の見分けがつかなくなってきてしまっていた。目で見た景色の情報は、まるで煙のようにそのまま頭をすり抜けていってしまう。
はじめはなんだか残念な気がしたけれど、歩みを進めているうちにいつの間にかそんなことは気にならなくなっていった。
空が朱を帯びて影が伸びてきた頃、なだらかな丘の頂上から、石畳の道が緩く降っていった先にいくつかの建物が集まった小さな集落が見えた。そのうちの一つの建物の庭の一点が、不自然に白い陶器のような光を放っている。ようやく今日の目的地が見えた。
車が止まっているのは、一般的な石造りの民家に、よく目立つ大きな赤い屋根の建物が連結した複合的な建物だった。大きな建物の外壁は白く、つるりとなめらかな素材で塗り固められていて、そのあちこちにアーチ窓がはめ込まれている。その建物には灯りがつけられているようで、ぼんやりと暖かみのある光がアーチ窓から広がっている。
あそこに、フョードルの兄弟子が住んでいるはずだ。
以前のように足が震えて歩けなくなるなんてことはなかったけれど、それでもかなり疲れていたぼくは、ようやく着いた、と思ってほっと安堵した。陽もちょうど地平線の向こうへと沈みかかっている。
丘の上から車の止まっている建物へと続く道を下りながら、ぼくはふとフョードルの兄弟子夫婦はこんな場所に住んでいて寂しくはならないのだろうかと思った。
ここは街というにはとても小さいけれど、夫婦一組で住むには十分すぎるほどに広い。そのうえ、あたりには他にも建物がまだぽつぽつと残っている。
もし、ぼくがこの場所に住めば、そういう人間のいなくなった建物を見るたびに、そこにはもう自分以外の人間がいないことを突きつけられるようで、なんだか恐ろしかったり寂しい気持ちになるような気がしたのだ。
旧市街のような人間がいなくなった街というのは、なにか大切なものが抜け落ちてしまったような、独特の空気感がある。時々訪れる分には新鮮な気持ちになるけれど、ずっと長いことそこにいると、なんだか目に見えない何かに心を押しつぶされるような気持ちになるのだ。
しかし、突然あたり一帯の建物にもぽつりぽつりと灯りがつきはじめた。
一つ一つの建物に、あの大きな建物と同じ暖かな光が宿っていくのを見て、ぼくは驚きの声をあげた。
「ここにはまだ人が住んでいるの!?」
「そういえば言っていなかったな。ここは『ゲイザー』の子孫がつくった集落でな、引退した元『ゲイザー』も多く住んでいる場所なんだ」
「といっても人の数はもう大分少ないんだけどね」
そうか。ということは、ここはフョードルの師匠が住んでいたという『ゲイザー』の集落と同じようなところなのか。どおりで、これまで通ってきた旧市街や集落の建物とくらべて綺麗に残っているわけだ。
また歩き出したフョードルとシャロンについて歩きながら、ぼくはこの集落の建物を見回した。
どの家も急勾配な屋根が広く軒先を垂らしている。赤屋根の建物が多かったけれど、赤以外にもさまざまな色の屋根がかかっていた。どの家も古くはあったけれど、ちゃんと手入れがなされているようで綺麗な印象を受けた。
ぼくがそうして建物を観察していると、突然大きな声が響いてきた。
「フョードル!フョードルじゃないか!」
声のした方を見ると、灯りがついたばかりの建物から人が出てきていた。
彼はフョードルのもとへ駆け寄ってきて、フョードルを固く抱きしめた。
「まさかまた会えるとは思っていなかったよ!コロニー5へ行くと言っていたのに、戻ってきたのかい?」
「色々あってな。悩んだんだが、結局シュヴィーツのあの場所へ帰ろうと思っているんだ」
その人はフョードルの胸元で眠るユミと、シャロンと並んで立つぼくのことを見とめると、すっと顔がこわばってしまった。
彼が考えたことがわかったぼくは、むずがゆい気持ちになった。同情や憐憫のまなざしで見られた経験は何度もあるとはいえ、この感覚にはいつまで経っても慣れなかった。
「そうか‥‥、大変だったんだな‥‥。ロレンツォさんのところに行くんだろう?今はちょうど夕の祈りが終わる時間のはずだ」
「ああ。今日一日世話になって、明日出発するつもりだ」
「そうなのか‥‥。‥‥そういうことなら、兄弟水入らずの楽しみを邪魔するわけにはいかないな。存分に語り合って、楽しんでくれよ」
「コロニー5へ向かう時に、もう別れの言葉は十分に交わしたはずだったんだがな」
フョードルは笑いながらそう言うと、その人ともう一度固く抱擁を交わして、ぼくたちはその場を後にした。
さっきの人の家から少し離れたところで、シャロンが口を開いた。
「一日しか泊まらないの?」
「ああ、そのつもりだ」
シャロンの質問に、フョードルはきっぱりと短く答えた。
しかし、シャロンはその答えに納得せずに、大きな声で文句を言いはじめた。
「えー!なんでよー!」
「家を空けてからしばらく経っているからな。出来るだけ早く行って手入れをしないといけないだろう?人が住まなくなった家は急速に汚れて弱っていくからな」
たしかに、家は常に自然や時間の経過による劣化と戦っているから、人間の手入れは必須だ。人が住まなくなった家は、定期的な掃除や換気もされないからすぐに埃やカビが溜まるし、害虫や動物たちが家に入り込んで荒らされる可能性もある。なにより、雨風や日光は継続的に家を劣化させていく。
フョードルの言ったことに納得していると、しかしぼくはそう言ったフョードルの顔に、一瞬違和感を抱いた。
フョードルの顔がどこか暗い色を帯びたような気がしたのだ。
けれど、それは一瞬のことで、瞬きをして目をもう一度開いた時にはいつものフョードルに戻っていた。シャロンはその顔を見なかったようで、まだ文句を言っている。
「あーあ、ロレンツォさんとソフィさんのとこなら、もっと長くいたかったなぁ」
“ロレンツォ”。それがフョードルの兄弟子の名前だった。ソフィというのはロレンツォさんの奥さんの名前だ。
いよいよ目の前まで迫った家を前に、ぼくは一体どんな人が出てくるのかと期待で胸がわくわくするのを感じた。
車の止まった敷地内に入り、平側に備え付けられた玄関の前に立つ。
フョードルがノックをしてしばらく待っていると、木製の扉が硬い音を立てて開かれた。
「やあ。思っていたよりも早かったね」
扉の向こうから現れた人は、そう言ってにこやかに笑うと、ぼくたちを家の中に招き入れてくれた。
「ロレンツォさーん!久しぶりー!!」
家の中に入ると、シャロンが勢いよく、あの鋭いタックルを繰り出した。
扉を開けてくれた時からきっとそうだろうと思っていたけれど、この人がロレンツォさんか。
ロレンツォさんはシャロンのタックルによろけながらも、それをちゃんと受け切ってシャロンに笑いかけた。
「久しぶりだね、シャロン。変わらず元気なようで安心したよ。フョードルも、無事に着いて何よりだ。しかし本当に早かったね。てっきり着くのは日が暮れてからになると思っていたけれど」
「この子たちが頑張ってくれたからな。まったく、子どもというのは凄いものだよ。めきめきと成長していく」
ロレンツォさんは笑顔でうんうんとうなずきながら、フョードルの後ろにいるぼくの姿を見とめたらしかった。
「はじめまして。君がトーマだね、フョードルから話は聞いているよ。私はロレンツォ、よろしくね」
ロレンツォさんはそう言ってまた柔らかい笑顔を浮かべながら手を差し出してきた。握手をするのだと察して、ぼくも慌てて手を差し出した。握った手はフョードルほどじゃないけれど、大きくて力強さが伝わってくるような手だった。この人が、フョードルの兄弟子‥‥。
ぼくは、自分の想像していた人と、目の前の人とを頭の中で照らし合わせた。
長い移動のなかで、ぼくの中の想像は煮詰まっていた。
ぼくの中でのロレンツォさんは、フョードルと同じくらい賢くて、フョードルのように丁寧な喋り方で話し、フョードルに似た筋骨隆々の体をしているという、何から何までがフョードルに似た、フョードルみたいな人、という想像だった。それはもはやフョードル自身じゃないかと自分でも思っていたけれど、ぼくには、フョードルほどの人間が尊敬するのがどんな人なのか想像もできなかったのだから仕方ない。
そして、今ぼくの目の前にいる現実のロレンツォさんは、ぼくの想像とはまったく違っていた。
実際のロレンツォさんは、フョードルほどの身体の大きさはないけれど、オリーブ色の肌に整った顔立ちをしたハンサムな人だった。顎も頬骨も鼻も、顔のパーツの一つ一つがはっきりと綺麗な輪郭を描いていて、服の上からでもわかるくらいに引き締まった身体も相まって、まるで彫刻のようだった。上下が一続きになったふわりとした真っ白なローブのような服を着ていて、それがなんだかロレンツォさんのまとう雰囲気を不思議なものに仕立てあげていた。
唯一、ぼくの想像通りだったところは、フョードル以上に丁寧な言葉遣いと柔らかな物腰だけだった。
「しかし、いきなり家の前に無人の浮上式自動車が現れた時には驚いたよ。何事かと思って中を確認してみたら、『AlicE』の音声記録に君からのメッセージが入っていたから尚更だ。いつあんなに立派な車を手に入れたんだい?」
「コロニー5を出る時に、コロニー長から頂いたんだ。律儀な人でな。必要になった時に使うように、と」
「なるほど、だから自動運転モードで先行させているのか。君らしいな」
フョードルとロレンツォさんが玄関先で談笑していると、家の奥から女性が出てきた。
「みなさんいらっしゃい。立ち話なんてしていないで、中に入ってくださいな。今日は賑やかになりますね」
「ソフィさん!!」
シャロンが今度はロレンツォさんから離れて女性の方へ飛び込んで行った。
女の人にあのタックルは耐えられないのではと一瞬心配になったけれど、シャロンも流石に加減したようで、お腹の辺りにぽふんと顔を埋めただけだった。
‥‥できればぼくに飛び込んでくれる時もあれくらいの勢いでしてもらいたい。
「あらあらシャロン。しばらく見ないうちにまた美人さんになったわね。元気そうでなによりよ」
褒められたシャロンは「えへへ」と嬉しそうに笑っている。
ぎゅっと抱きしめ合うふたりは、なんだか本当の親娘のように見えた。
ソフィさんは、綺麗な人だった。フョードルと同じ真っ白な肌に緑色の瞳が映えて、まるで物語の中に出てくる妖精のようだった。鎖骨あたりまで伸びた亜麻色の髪を一つに編み込んで、それを首の右側から垂らした髪型がよく似合っている。
ソフィさんもロレンツォさんと同じ上下一続きの白一色のローブを着ていた。夫婦でお揃いの服を着るなんて、とても仲が良いのだろう。ローブの白さがふたりの美しさを引き立たせていて、そこには神々しさすら感じた。
「ふたりとも疲れただろう。ソフィと夕食の支度をしておくから、先にシャワーを浴びておいで」
ロレンツォさんはそう言うと、ぼくにシャワー室の場所を教えてくれた。
「フョードルはまだ元気そうだから、私たちの手伝いをしてくれるかな?色々と話も聞きたいしね」
ロレンツォさんはフョードルに、ぼくたちに向けるのと変わらない笑顔を向けて言った。
けれど、フョードルはすこし唇を歪めてロレンツォさんから目を逸らしてしまった。ぼくは、その表情に見覚えがあった。
「‥‥あぁ、もちろん」
ぼくは、フョードルがあんな罰が悪そうな顔をするところを見たことがなかった。シャロンも同じようで、フョードルとロレンツォさんの顔を交互に見比べている。
ぼくたちは、フョードルのその様子が気になっていたけれど、ソフィさんに「さあ、入っていらっしゃい」とタオルを渡されてしまったので渋々シャワーに向かった。
ぼくは、ロレンツォさんが指し示した場所へ続く広い廊下に入る前に、ちらりとフョードルの顔をもう一度見た。
やっぱり、あの顔はそうだ。
フョードルのあの表情は、ぼくがコロニーにいた頃、おじいが小言を言いにきた時のぼくの表情と同じものだった。
シャワー室は廊下の突き当たりにあった。
室内にはガラス戸に覆われたシャワーブースと、すこし離れた場所にジャグジーが備え付けられていた。ただ、ジャグジーは普段使われていないようで、浴槽の中にいろいろなものが入れられていた。
ぼくは、ここに来てようやくシャワーは一人ずつでなければ浴びられないことに気がついた。どうしてぼくは、今の今までそのことに気が付かなかったのだろう。
慌ててシャロンに先に入るように言って、シャワー室を出ようとした。けれど、シャロンはそんなことは気にしていなかったようで、あっけらかんと「わたしは一緒に入ってもいいんだよ?」なんて言われてしまった。
いや、ダメだろう。ぼくはシャロンを残して急いで外に出た。
しばらくするとシャワー室の扉越しに水が流れる音が聞こえてきて、なんとなく居心地が悪くなったぼくは、扉から少し離れた場所に移動した。
前々から思っていたことではあるけれど、きっとぼくは、シャロンに“男”として認識されていない。
自分でも、それはそうだろうなと納得できてしまうところがまた情けなかったけれど、事実ぼくはシャロンと出会った時から、彼女に一方的に何かをもらってばかりで、ぼくからは何もシャロンにあげられていない。これではシャロンに意識してもらえなくて当然だろう。
ただ、まさか一緒にシャワーを浴びることにも抵抗がないほどに意識されていないとは思わなかった。
ぼくは、自分の恋が想像以上に前途多難であることにがっくりとしながら、シャロンが出てくるのを待った。
シャワーを浴び終えたぼくたちは、シャロンの案内でダイニングに向かった。
廊下の反対側のダイニングに入ると、部屋中が甘さと酸味が混じり合ったような良い匂いに包まれていた。
ロレンツォさんとソフィさんがキッチンで忙しなくテキパキと動いていて、フョードルはふたりが作った料理を盛り付けているところだった。ユミは今は抱っこ紐から外されて、ダイニングに簡易的につくられたベビーベッドの上で静かに寝息を立てていた。
フョードルの顔からは、シャワーを浴びる前のあの表情は消えていて、どこかスッキリしたような顔をしていた。
「おや、ちょうど良い所に来たね」
「さっぱりしたみたいでよかったわ。ふたりとも、料理を運んでくれる?」
ソフィさんに言われた通り、ぼくたちはフョードルが盛り付けた料理を受け取って、白いテーブルクロスの敷かれたテーブルへとそれを運んだ。
皿の上に盛りつけられていたのは、スパゲッティだった。黄色がかった小麦色の麺の上に、ひき肉がゴロゴロと乗った赤みのあるトマトソースがたっぷりとかけられていて、ふわりと立ち昇る湯気に乗ってトマトの甘い匂いが漂ってくる。別のお皿には、ピザが盛り付けられている。こちらの料理も、真っ赤なトマトソースがたっぷりと塗り込まれた生地の上に、緑のバジルと真っ白なチーズが色鮮やかにピザを彩っていて、その色合いが目に映えた。
テーブルの上にすべての料理を並べ終わると、ぼくたちは席についた。
目の前の色とりどりの料理にぼくはすっかり食欲を刺激されて、フォークとスプーンを手に食べはじめることを許されるのを今か今かと待っていた。
しかし、席についたロレンツォさんとソフィさんは食器には手を伸ばさず、テーブルの上で手を組むと目を閉じてしまった。いや、ふたりだけじゃない。フョードルとシャロンも、ふたりと同じように手を組んで目を閉じている。
にわかに厳かな雰囲気が食卓を包むのを感じた。
「すまないね、トーマ。少しだけ待っていてくれるかい」
なにが起こっているのか分からずに戸惑っていたぼくにロレンツォさんが気がついて、優しい声でそう言われた。
ぼくもみんなと同じようにするべきか迷っていると、ソフィさんが静かに、しかし凛とした声で言葉を紡ぎはじめた。
「天にましますわれらの父よ、この豊かな食卓を前にして、私たちが再び共に集えた奇跡に感謝いたします。遠く離れていた私たちを再び結びつけてくださり、このようにして愛する家族と友人たちとともに食事を共にできる喜びを与えてくださったこと、深く感謝いたします。私たちの今夜の食事を祝福してください。この食事が、私たちの体だけでなく、魂をも育んでくれますように。そして、この食事を通して、私たちの心が一つに結ばれ、今この瞬間を最大限に楽しむことができますように。この世界に残された時間の中で、私たちが今日この食事を共にできることは、計り知れない恵みです。私たちの世界が直面している困難に、私たちが立ち向かう希望を与え、日々の小さな喜びを見出す力を授けてください。私たちが今、共にいられるこの瞬間を大切にし、愛と感謝の気持ちを持って一日一日を生きていくことができますように。私たちが互いに支え合い、愛と慈悲の心をもって行動できるように導いてください。全ての恵みを与えてくださるあなたに、心から感謝を捧げます。アーメン」
ソフィさんが言葉を終えると、ロレンツォさん、そしてフョードルとシャロンもそれに続いて「アーメン」と唱えた。
さっきまでこの場に漂っていた空気感はたちまち霧散して消えていった。
ぼくは、ソフィさんが言葉を唱えている間、ただただ呆然としているしかなかった。
ぼくは、外の世界のことはまだまだ知らないけれど、今ソフィさんやみんながしていたことが何なのかは知っていた。
今のは、“祈り”だ。祈りとは、人間が自分の願いや後悔を神に対して伝える行為‥‥。
つまり、ロレンツォさんとソフィさんは、神を信じている人だった。
「お待たせしたね。さあ、冷めないうちに食べよう」
「今日の料理は腕によりをかけて作ったのよ。報せが届いた時からずっとソースを煮込んでいたんだから」
「わー!嬉しい!わたし、ソフィさんの料理大好き!」
さっきまでまるで石のように空気の硬かったみんなは、その石が砕けたかのように、唐突にリラックスしはじめた。
シャロンはさっそくピザを一切れとると、それにかぶり付いて「美味しいー!」と頬をおさえてよろこびの声を出している。
みんなもそれぞれにスパゲッティやピザを取り分けて食べはじめていた。
ぼくだけが、一連の出来事についていけてなかった。
そんなぼくの様子に、ロレンツォさんとフョードルは気づいたようで、ふたりはちらと目を合わせるとロレンツォさんの方がぼくに話しかけてきた。
「驚かせてしまったみたいだね。私たちはキリスト教徒なんだ。この家の横につながっている赤い切妻屋根の建物があっただろう?あれは教会でね。私たちは、この集落で独自に教会の運営を行っているんだ」
ロレンツォさんはそう言うと、自分が着ている服を指差してみせた。
「これはアルブという衣装でね。私たちの制服のようなものなんだよ」
ぼくは、ロレンツォさんの説明を聞きながら、自分のこころがどこか遠い場所にあるような感覚になっていた。
ぼく自身はずっと神なんていないと考えていたし、今のこの世界に神を信じている人なんていないとも思っていた。フョードルの“絶対的なものはない”という話を聞いてから、ぼくはますます強くそう思うようになっていた。だから、神なんていうものを本気で信じていたむかしの人間のことを、こころの中で馬鹿にもしていた。
けれど、むかしフョードルと一緒に世界を旅して回り、そのフョードルが敬意を払うロレンツォさんと、その奥さんであるソフィさんは、ぼくが馬鹿にしていた“神を信じる人たち”だった。
ぼくの中に浮かんだのは、“どうして”という疑問だった。
まだ会って間もないけれど、ぼくはロレンツォさんとソフィさんのふたりからは、フョードルと同じ、とても知的な雰囲気を感じ取っていた。実際に話してみても、言葉遣い、話す内容、そこから垣間見える考え方のすべてが、ふたりの知性と教養の高さを物語っていた。
だからこそ、ぼくにはふたりが神を信じる理由が分からなかった。
だって、神なんていなかったじゃないか。
ぼくたちの世界は、あと八年で終わってしまう。
神は、宇宙の終わりが来ることを防げなかったじゃないか。
ロレンツォさんもソフィさんも、ぼくとシャロンほどではないけれど、十分若い。ふたりともが、ぼくたちと同じく最後まで生きることのできない『マルーン』だ。だから、コロニーの老人たちのように上から目線でぼくやシャロンのような存在を哀れんで、無責任に神なんてものを持ち出しているわけじゃないことはわかる。なぜなら、ふたりも宇宙の終わりにおいては当事者だからだ。
じゃあ、一体どうしてふたりは神なんてものを信じられるんだ。ぼくたちに何をしてくれるわけでもない、見せかけだけの空白の存在を。
ぼくは、もうなにがなんなのか分からなくなってしまって、せっかくの食卓だというのに一人暗い気持ちになってしまった。
せめてみんなの気分を悪くしないよう精一杯に上機嫌なフリをして卓上のスパゲッティやピザに手を伸ばすけれど、さっきまではあんなに美味しそうに映っていた食べ物が、今は色味が落ちたように映って、味もよくわからなくなってしまった。
その時、突然ユミの泣き声が響いてきた。こころが乱れていたぼくは、自分のこころを整理する時間が欲しくて、自分が行くと言って食卓を立ち上がり、ユミが眠るベビーベッドに向かった。
ベビーベッドの上で、ユミは小さな身体を震わせ、顔を真っ赤にして泣いていた。フョードルがさっきミルクをあげたと言っていたから、空腹な訳ではないのだろう。
ぼくはユミを抱き上げると、ゆっくりと揺らしたり、背中をトントンとやさしく叩いた。
しかし、今日のユミはなかなか泣き止まなかった。いつもならすぐに泣き止むというのに。
けれど、今のぼくはまだあの食卓に戻りたくなかったので、むしろ都合が良かった。「ユミは、もしかしたらぼくの気持ちを汲んでくれているのかもしれないな」、なんてことを思いながら、ぼくはユミをあやし続けた。
頭の中では、神という存在のことでいっぱいになりながら。
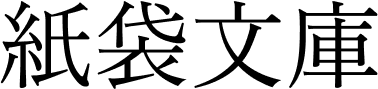


.png)
.png)