マルーン
第四章 旅立ち
5369年4月1日
その日はあっという間にやってきた。結局、あの日おじいの反応を見て自分の中に湧いた感情の正体は分からなかったけれど、時間が経つにつれてその感情はなりをひそめていった。
ぼくたちは、春を迎えて少しずつ暖かかくなってきたコロニーの外の空気を感じながら、コロニーと旧市街との境目に立っていた。コロニーの住人たちに見送られる形で、この場所をあとにする。
赤ちゃんは、抱っこ紐でくくられて、フョードルの胸の中で静かに眠っている。赤ちゃんは女の子で、ユミと名付けられた。あの日シャロンが歌ってくれた『いつも何度でも』の“ユミ・キムラ”の名前からとったのだ。ユミは産まれたばかりのころに比べて、ぷくぷくとあちこちが膨らんでいてとてもかわいい。
見送りに、おじいと何人かの老人たちが来ていた。
あの日以来、ぼくたちはほとんどの老人たちから快く思われていなかったので、その人数は多くはない。けれど、ぼくはたとえ数人でも老人たちが見送りに来たことに驚いていた。
「さすがに、こんなものまでいただけませんよ」
フョードルはさっきから、おじいが譲ると言って聞かない浮上式自動車を受け取る、受け取らないでおじいと揉めていた。
「わたし自身はもうこんなものを使う機会がない。事故で潰さない限り、宇宙の終わりが来るときまで走り続けられるだけの車だ。いくら旅に慣れていると言っても、これからは必要になることもあるだろう。元気のあるうちは使わなければいい。必要になったときに使えばいいさ。‥‥子どもたちのためでもある。受け取らないというのなら、出ていくことは許可できない」
おじいの強硬な態度に、フョードルは結局車を受け取った。
浮上式自動車は、太陽光とバイオエネルギーによる反重力で車体を浮かせることで、空中での走行を可能にした車だ。空中を進むので、どんな悪路でも物ともせずに進むことができる。また、この車にも『AlicE』が搭載されているので、自動運転モードで運転を任せることもできる。あるのとないのとでは大違いだ。
「‥‥くれぐれも、気をつけて行くんだよ」
おじいはぼくたちにそう言うと、目を伏せてしまった。
まわりの老人たちも、眉を下げてさびしそうにしている。
突然、その様子を見たぼくのこころにも、さびしさが噴き出してきた。
ぼくは、そのことに驚いて、自分の胸に手を当てた。なんだか胸が痛い。
その痛みは決して強くはないけれど、たしかな鈍痛が胸に起こっていた。
ぼくは、自分の中にこのコロニーへの愛着があったことに戸惑っていた。あんなに、哀れみのこもった視線を向けられるのが嫌だったはずなのに。
旅立ちを直前にした新しい発見だった。
けれど、ぼくは旅立つことを決めたのだ。外の世界で生きると。ぼくは、胸の痛みを振り切るようにして浮上式自動車に乗り込んだ。
「短い間でしたが、本当にお世話になりました。どうか皆さん、健やかであってください。からだも、こころも」
フョードルはそう言うと、おじいに向かって静かに頷いた。おじいはぼくの顔を見て、なにか言いたげな顔になったけれど、口を開けては閉めることを繰り返して、結局なにも言わなかった。
ぼくも、おじいに何か言わなければいけないという気持ちに駆られたけれど、こころの中を渦巻く感情は上手く言葉にすることができず、結局口から出たのはありきたりな別れの言葉だけだった。
「‥‥おじい。行ってくるよ」
フョードルがアクセルを踏み、車が走りはじめた。老人たちは口々に別れの言葉を叫んでいる。きっともう、この老人たちと会うことはないのだろう。
そう思うと、なぜだか無性におじいの顔が見たくなった。集団の中におじいの姿を探して、その顔を見た。
おじいは、ぼくがはじめて見るような、さびしそうな顔で笑っていた。さびしそうに笑いながら、その口元が動いた。
けれど、その口がなにを言ったのかはわからなかった。そもそも、それが言葉だったのかどうかすらも‥‥。
車はぐんぐん進んでいく。あっという間に見送りに来た老人たちの姿は小さくなって、やがて旧市街の街並みに隠されて見えなくなってしまった。
けれど、ぼくの脳裏には、おじいのあの寂しそうな笑顔が焼きついて離れなかった。
◆
コロニーを出て旧市街をしばらく進んだところで、フョードルは突然車を止めた。
何事かと思っていると、フョードルはぼくたちに車を降りるように言った。故障だろうか‥‥?けれど、おじいはさっき事故にあわない限りはずっと使えると言っていたし、おじいに限って不良品を人に渡すとは考えられなかった。
そんなことを考えていると、シャロンはいつの間に用意を終えたのか、あっという間に扉を開けて外に降り立っていしまった。
ぼくも慌てて自分の荷物をすべてまとめようとすると、フョードルに荷物はそのままで、水筒と服を詰め込んだリュックサック、そして日焼けを防ぐための帽子だけを持って降りるように言われた。
なにが起きているのかまったくわからないまま、戸惑いながらも言われたとおりにする。
車を降りると、ぼくと同じようにリュックサックを背負ったシャロンが、麦わらの帽子をあみだにかぶって、にこにこしていた。
シャロンはリュックサックの中からチューブを取り出して自分の顔や体に塗ると、それをぼくにも手渡してきた。
「なにこれ?」
「日焼け止め!春の日差しは強いから、ちゃんと塗らないと」
「ぼくはいいかな。長袖長ズボンでほとんど肌出てないし」
「そう?」と言いながら、シャロンは日焼け止めチューブをしまうと、こんどはスプレー缶を取り出して、長袖に覆われた体に噴きかけた。
「それは?」
「虫除けだよ。まだこの時期はそんなに多くないだろうけど、一応ね」
そうか、コロニーの外には虫がいるのか。コロニーには、ウイルスや菌を運ぶ虫や、住宅に住みつく虫の侵入と繁殖を防ぐための音波防虫機構と殺虫機構が存在しているので、コロニーやその周辺で虫を見たことはなかった。
ぼくは虫除けの方は受け取って、それをシャロンと同じように服の上から噴きかけたけれど、その時に煙を吸いこんでしまって激しく咳き込んだ。鼻と喉が焼けるようにしみて、涙が出てくる。
「息止めてないとだめだよー」
噴きかけた薬を伸ばしながら、シャロンが言った。
フョードルは運転席で『AlicE』になにか打ち込んでいたようだったけれど、それが終わると大きなリュックを背負って車から降りてきた。その胸元ではユミがまだ静かに寝息をたてていた。
フョードルは車から降りると、「行け」と短く言葉を発した。すると、車はひとりでにふわりと宙に浮かびあがって、そのままぼくたちの目の前からすっと滑るようにして動き出し、ぐんぐん速度をあげて、あっという間に見えなくなった‥‥。
え‥‥?
「ええぇぇぇ!?なんで!?」
あまりに自然に一連の出来事が行われたものだから、ぼくは、ほんとうに車がぼくたちの視界から消えるまで違和感を抱くことなく、ぼーっとそれを眺めてしまっていた。
しかし、フョードルもシャロンも平然としていて、あわてているのはぼくだけだ。
「御老功も言っていただろう?元気なときは使わなくていいと。今の俺たちには必要ない。歩いて行こう」
「そうそう!歩こう!」
頭が痛くなりそうだった。
「だからって、捨てなくてもいいじゃんか!荷物もほとんど乗せっぱなしだよ!」
「捨てたわけじゃない。俺たちの進行方向に先行させただけだ。今日一日俺たちが歩いて進める距離だけを進ませている。つまり、あの車があるところが、今日のゴールだ」
訳がわからなかった。どう考えても、歩くより車を使ったほうが便利で、楽じゃないか。
ぼくのそんな不満を見てとったフョードルは、短く言った。
「今の俺たちに、あの車は必要ない。今の俺たちは歩くべきだ」
そう言うと、フョードルはさっさと歩き始めてしまった。シャロンも跳ねるようにその後をついていく。
ここでいくら文句を言っても、車はもうすでに行ってしまったので、先へ進むにはいやでも歩くしかない。
けれど、なんでわざわざこんなことをするのか、理解ができなかった。どうして、便利な方法を使わず、わざわざ手間のかかる方法を選ぶのか。次から次へと浮かんでくる疑問の言葉をぐっと飲み込むと、ぼくも仕方なく自分の足を動かしはじめた。
歩きはじめるときには、面倒くさい気持ち一色だった感情は、しかし歩きはじめると、少しずつ薄れて消えていった。車に乗っていたときには、横から横へとあっという間に流れていった景色が、こうして自分の足で歩いているとよく見えることに気がついた。そんなことは当たり前かもしれないけれど、実際に歩いていると、今まで目につかなかったいろいろなものに目がいくようになった。
このあたりの建物は、ぼくが知っている建物にくらべてとても変わった形をしているものが多く、また建物同士の間隔がとても狭くつくられていた。コロニーにほど近い旧市街に建っていた建物たちは、コロニーのドーム型住宅ほど淡白なわけではないけれど、必要のない部分は極力削ってしまったような、シンプルで無機質な見た目の造りのものが多かった。機能的な面をより追求するような形の建物‥‥、ぼくは、それが旧市街の建物のすべてだと思っていた。
「このあたりには、いろんな形の建物があるね。それに、建物同士の隙間がものすごく狭いや」
静かに佇む街並みを見回しながら、そうつぶやく。
「ああ。この街は古くから人間が住み続けていたからな。さまざまな時代に、その時代の建築様式で建てられた建築物がそのまま残っているんだ。隣棟間隔が狭いのもそのせいだ。ヨーロッパは長い歴史のある地域だから、こういう場所は多い」
「そうそう」とシャロンがうなずく。
「わたしたちがコロニー5に行くときに通った街も同じような雰囲気だったよ。行きは少し北の方角から遠回りして、ウルム大聖堂を見て、アウクスブルクの旧市街を通ってきたんだ。でも、あっちの街の方が古めかしい雰囲気だったな」
「歴史的に見ると、アウクスブルクやネルトリンゲンといった自由都市の方が都市としての重要性が高い時代が続いていたんだ。このミュンヘンもたしかに歴史的に栄えてきた商業都市だったが、それらの自由都市には一歩劣る都市だった。あくまで重要都市としての域を出ない時代が続いていたんだ。だから、こちらの都市の方が比較的新しい時代の建物が多いんだよ」
ふたりの会話は、ぼくの知らない言葉だらけでよくわからなかった。都市や建物の名前は右耳から入って左耳へと抜けていってしまったが、話の最初にわからなかった単語だけは頭に残っていた。
「建築様式ってなんなの?」
「建築物というのは、時代や地域によってもちいられている建築手法や様式がちがう。建築様式は、その建築物が“どういう建築思想で”、“どういう建築手法をもちいて造られているのか”を示すものだ」
そう言うとフョードルは、比較的広い場所に立っているシンプルな建物を指差して言った。
「あの建築物のように、装飾がほとんどないシンプルな建物は、モダニズム建築といって比較的新しい時代の建築様式だ。19世紀末から20世紀にかけての建築様式で、装飾を嫌って機能的かつ合理的な造形を追求している。だから、見ての通り装飾らしいものがほとんど施されていなくて、シンプルな造りになっている」
「しかし、モダニズム建築は機能美を追求するあまり、だんだんと建物そのものが持っていた個性は弱まってしまった。それ自体が個性と言えなくもないんだが、そのことを批判して、モダニズム建築に装飾や特徴的な形を取り入れるようになったのが、ポストモダン建築だ。ちょうど、あの円柱形に造られた建物のようなものだな。不思議な形だろう?」
ぼくはうなずいた。フョードルが指し示したその円柱の建物は、モダニズム建築よりもさらに広い場所にぽつんと建っていた。その構造は上の方に行くにつれてすこしずつ膨らみ、ところどころに目立ちすぎない装飾がほどこされていて、フョードルが言うように不思議な形をしていた。
「しかし、この街の建築物はバロック様式とゴシック様式‥‥、特にゴシック様式が多いな。」
フョードルはそう言ってあたりを見回すと、目的のものを見つけたのか、街にならぶ建物のうちの一つを指さして示した。それは、モダニズム建築とは真逆で、そこかしこに豪華な装飾がふんだんにほどこされた、とても派手な建物だった。
その建物を見て、まずぼくが驚いたのは、その巨大さだった。高い壁が空を衝くかのようにそびえ立ち、壁面に埋め込まれた色とりどりの窓は宝石のように輝いて、建物を美しく飾り立てている。建物の側面からは、壁を支えるようにして外壁が張り出していて、屋根の上には鋭く尖った塔のようなものが高く伸びていて、その高さをより強調していた。まさに、青空に迫るような建物だった。
「あれがゴシック様式だ。ゴシック様式は、かつてこの世界で最も信じられていた宗教が、自分たちの教会‥‥、祈りを捧げたり、儀式をする場所のことだ。彼らがそれをつくる際に多用していた建築様式だ。だから、その建築思想は神聖性や神秘性を表現することに重点を置いているし、建築手法もいかにそれを再現するかを考えてつくられている」
フョードルはそう言うと、高くそびえる建物の上部を指差した。
「そして、その手法のうち最も大きなものがこの高さだ。垂直方向に大きく伸びる尖塔やアーチは、この教会という場所が、神のいる天空に最も近い場所であることを表現している。壁面にいくつもはめ込まれたステンドグラスも重要な演出装置だ。光の入る角度や時間帯をすべて計算して、内部に差し込む光が最も美しく、神聖な雰囲気を演出できるようになっているんだ。ほかにも聖人を象った彫像や、内部の身廊と側廊を形作るヴォールトといった数多くの特徴があるが、そのどれもが教会という場所の神聖性を演出することを目的につくられている」
「ただ、」とフョードルは言葉を区切った。
「この旧ドイツの街のゴシック建築は少し毛色が違っていてな。元々、旧ドイツは商業と貿易で栄えた商人たちの街が多い地域だった。だから、この地域におけるゴシック建築は、神や教会、ましてや国王や皇帝といった支配者を讃えるものじゃなく、商業経済の発展と商人たちの活躍を示すものが多いんだ。もちろん、中には教会も混ざっているが、歴史的に見るとその影響力は他の地域に比べて大きくなかったといえるだろう」
どうして、こんなにスラスラと知識が出てくるのだろう。フョードルは、頭に『AlicE』でも繋いでいるのだろうか?ぼくが知っている限り、人間の脳と『AlicE』の情報とを繋げようとした実験の結果は、人間の精神崩壊という悲惨な結果に終わり、それ以降はタブー扱いされていたはずだけれど。もしかしたら、フョードルはその実験の唯一の適合者なのかもしれない‥‥。
そんな馬鹿げたことを冗談半分、本気半分で思ってしまうくらい、フョードルは博識だった。フョードルの話は、はじめて聞くことばかりでぼくはその内容を全部覚えたくて必死に聞いていたけれど、結局ほとんど覚えられなかった。
でも神という言葉は知っている。むかしの人間が信じていた、人間よりもずっと偉い上位の存在のことだ。ただ、神にはいろいろな種類がいて、どんな存在で、どのくらいの数がいて、どんなことをするのかなど、それこそすべてが時代や地域によってバラバラで、結局のところよくわからない存在だった。‥‥いや、そんなものは本当は存在しないけれど。
むかしは神というものを信じていた人間は多かったらしいけれど、今この世界で神を信じている人間なんていないだろう。ぼくを含めて、コロニーの誰もそんなものの存在を信じていなかった。当然だ。だって、人間の上位の存在であるはずの神は、宇宙の終わりを防ぐことはできなかったんだから。人間の科学と一緒で、この世界の前ではひどく頼りない、どうしようもなく弱い存在だ。
逆に、神がほんとうに全知全能の存在だったとしたら、宇宙の終わりなんていう馬鹿げたスケールの現象は、その神が引き起こしたものにちがいない。だとしたら、そんなやつは人間の敵だ。信じるもくそもない。
──ぼくたちを助けてくれない神なら、たとえどこかに存在していたとしても、ぼくたちにはまったく関係がない。
いずれにしろ、ぼくたちが神なんてものを信じる理由は一つもなかった。‥‥神なんて、実際には何にもできないくせに人間の前でだけ偉そうに振る舞う、作り話の中の嫌な存在だ。
なんだか突然、むかしそんなものを信じていた人間たちのことが許せなくなってきた。
何に対する怒りなのか、どういう怒りなのかは自分ではわからなかったけれど、突然湧いたその感情は思いのほか強く、一気にぼくの頭を沸騰させた。
理由もわからない怒りに飲まれそうになった時、フョードルがぼくの様子を察してか、別の建物の話をはじめた。ぼくの怒りはまだ頭の中を占めていたけれど、意識がフョードルの話しの方に向いたことで、それは少しずつその熱を下げて、ゆっくりと消えていった。
「‥‥そして、あれがバロック様式だ」
こんどの建物も、ゴシック建築と同じく、そこかしこに豪華な装飾がふんだんにほどこされている。ただ、その装飾はゴシックのように“縦”を意識してつくられたものではなく、緻密な彫刻や模様が彫り込まれるなど、建物そのものを強調するようなものだった。表面に彫り込まれた複雑な模様は、光を受けることで影を生み、それが建物全体の奥行きを強調することで、建物はよりいっそう美しく見えた。
「16世紀末から18世紀にかけて、ヨーロッパ全体で広く使われていた建築様式だ。見ての通り、あちこちに彫刻やレリーフ、豊富な曲線装飾がふんだんに使用された建物で、ゴシック建築と同じように装飾性の強い建築様式だ。ただ、宗教的な建築思想がゴシックよりも弱かった。その根底に宗教的な思想と意味があったのはたしかなんだが、教会の人間にとってはゴシック様式の方が重要だったんだ。ただ、豪華さや華麗さ、贅沢さを示すにはうってつけの様式だったから、当時の支配者たちの住居や公共施設にも多く使われていた。ここから少し北へ行った場所にあるニンフェンブルク宮殿などがその例だな」
たしかに、ゴシック建築はなんだか縦にしゅっとしていて神秘的な印象を受けたのに対して、バロック様式は横と奥にどっしりと構えられていて、その装飾も重厚な印象だった。その姿は、シャロンの本やゲームに出てきた城や屋敷のようにも見える。
「こんなふうに、建築物そのもののデザインや構造、装飾といった要素から、建築様式を見分けるんだ」
「わたしは未だにうまくできないんだけどね。ほかにも建築様式はあるんだけど、中にはほかの様式を取り入れてるものもあって、見分けるのがちょーむずかしいんだ」
「それぞれの建築様式の境界線に曖昧な部分があることはたしかだ。ヨーロッパの文化は、さまざまな時代と地域が複雑に絡み合って形成されているからな。時代を遡れば、すべての地域が古代ギリシャや古代ローマの影響を受けていることも大きい。建築物も含めて、すべてのものがどこかしらかで少なからず互いに影響し合っているんだ」
途中、神なんていう不愉快な存在の話が出て、ぼくの気分もひどく不愉快になってしまったけれど、この短い間に、ぼくはまた自分の世界が変わったのを感じていた。
これまでのぼくの世界には、“コロニーのドーム型住宅”と、“旧市街の建物”という二種類の建築様式しかなかった。けれど、今はそこに“モダニズム建築”や“ポストモダン建築”、“バロック建築”、そして“ゴシック建築”という、まったく新しい認識が加わって、世界の解像度が一気に上がった。まるで、世界を見通すレンズが切り替わったように。
解像度の上がったぼくの世界は、前よりも明瞭で、ずっと広いように思えた。
けれど、驚くべきことに、ぼくの世界はまだこれ以上の可能性を秘めているようだ。まだほかにもぼくの知らない様式があるということは、それを知るたびにぼくのレンズの解像度はさらに上がっていくのだろう。
さっきと比べて、こんなに広くあざやかに見える世界でも、まだその可能性をすべて発揮しきってはいないのだ!
建築様式だけじゃない。これから先、ぼくが知る新しいことはすべて、ぼくのレンズの解像度を上げる情報として組み込まれ、ぼくの世界はどんどん鮮やかに広がっていくのだろう。
自分の見える世界を広げる、それは大きなよろこびで、今までにない感覚だった。
突然、コロニーでシャロンが言っていた「人間が自分で何かをつくることが大事な理由」の話が頭に浮かんだ。
なぜか、フョードルやシャロンがいま話してくれたことが、その話につながるような気がしたのだ。けれど、どうしてそれがつながると思ったのか、自分でもわからなかった。
なんだか、すごく大きなものをつかみかけている気がする。
けれど、すぐそこにまで迫っているはずのその答えは、いざ掴もうとすると、まるで木の葉のように腕のあいだをのらりくらりとすり抜けていってしまった。
──あぁ、いってしまう。
せっかくすぐそこまで近づいていたそれは、ゆるりゆるりとぼくのもとを離れると、すっと消えてしまった。もうその気配はどこにも感じられない。
「どうした?疲れたか」
いきなり落ち込んだぼくの様子に、フョードルが心配して声をかけてくれたけど、ぼくは逃したものの大きさに打ちのめされていた。
「ううん、ちがうんだ。なんだかいま、すごく大事なことが分かりそうだったんだけど、結局分からなくて‥‥。がっかりしただけなんだ」
ぼくは、自分がつかみかけていたものがなんだったのか、一生懸命に考えてみたけれど、その答えはまったく思い浮かばなかった。
諦めてため息をついたところで、ぼくはフョードルに相談してみることを思いついた。フョードルであれば、ぼくが言葉に表せないこのモヤモヤや、もしかするとぼくがつかめなかったものの正体も分かるかもしれない。
けれど、ぼくはシャロンにはこの話を聞かれたくなかった。できれば、自分一人で答えに辿りついたことにしたかったから。しょうもない見栄であることはわかっていた。けれど、やっぱり格好つけたいものは格好つけたいのだ。
だから、シャロンが少し離れたときを狙って、フョードルに相談する機会をうかがっていたけれど、今は全員で同じ方向に歩いているので、シャロンだけがいなくなるなんて状況になるわけもなかった。しばらくは諦めるしかないと思ったその時、突然もじもじしはじめたシャロンが、「ちょっとお花を摘みに‥‥」と言ってぼくたちから離れていった。
思いがけず、絶好の機会に恵まれたぼくは、「いまだ!!」と思って、急いでフョードルにことの経緯を説明し、期待しながら彼の言葉を待った。
しかし、フョードルはぼくの話しを聞き終わると、実に愉快そうに笑って「そうか、そうか」と言いながらぼくの頭を撫でつづけるばかりだった。
ぼくは、シャロンが戻ってくる前にフョードルの助言が聞きたくて、あたふたしていたけれど、そうこうしているうちにシャロンが戻ってきてしまった。
結局、まともに話をしてもらえなかったぼくは、ただずっとぼくの頭を撫でていたフョードルの行動に不満を抱いて、不貞腐れた態度をとってやった。
けれど、シャロンが「じゃあ、しゅっぱーつ!」と言って先に歩きはじめたところで、フョードルがシャロンには聞こえないくらいの声でぼくの名前を呼んだ。ぼくは、やっと教えてくれる気になったのかと期待して、フョードルの方へ顔を向けた。
振り返った先にいたフョードルは、その顔に優しい笑みを浮かべていた。その笑みは、なにかを懐かしむような、どこか寂しさを感じさせた。
「俺もその感覚に覚えがあるから、トーマが今どんな状態なのかはよくわかる。ただ、トーマがさっき逃したというそれは、俺が口で説明しても分かるようなものじゃないんだ。自分で掴まないと、本当にはわからないものなんだ。だから、今は説明できない。でも、大丈夫だ。その感覚があったなら、焦らなくてもいつか必ず分かる」
フョードルはそう言うと、ぼくの頭にもう一度手を乗せてぽんぽんとたたいた。安心しろ、というように。
「そのままこの世界をもっと見て、聞いて、感じて、楽しんでみなさい。そうすることが、一番大切なんだ」
その大きな手の、意外にやわらかな感触を感じながら、ぼくはその言葉をこころの中でなぞっていた。
◆
あれからぼくたちは、ずっと歩き続けていた。車を降りてからもう二時間くらいは経っている。太陽も少しずつその高さをまし、もうすぐ真上に来そうな時間になっていた。
一つ一つ形のちがう建物の並びの新鮮さも薄れてきたところで、突然、それまでずっと視界の先を塞いでいた旧市街の街並みがとぎれ、遠くの方に緑が広がっているのが見えた。
「やったー!もうすぐ街道だー!」
シャロンが嬉しそうに叫ぶ。ぼくも、目に飛び込んだきた緑にこころが踊って、少し疲れがたまって重くなっていた足に力が戻ってくるのを感じた。
遠くに見えていた緑は、歩くたびにどんどん近づいてきて、視界にしめる大きさもどんどん大きくなっていった。緑の草や葉が、風に吹かれてさわさわと影をつくりながらなびいている。その葉擦れの音が聞こえるところまで進むと、視界が一気に開けた。
ぼくの口からは、自然と「うわあ」と驚きの声が漏れていた。
目の前には、あたり一面に草花がそよぐ緑の大地と、その上にさらに大きく、白い雲を抱え、深い青をたたえた空の光景が広がっていた。
こんなに広い草原を、こんなに大きく青い空を、ぼくは見たことがなかった。
草や葉が力強く大地に根を張って広がった若緑色の中に、ぽつりぽつりといろとりどりの花たちが凜と咲いている。その上空には、深い、けれどどこまでも澄み渡るような群青色の空が広がっていて、その中で真っ白に膨らんだ雲が、まるでドレスのように風に揺らめいてその形を変えていた。
コロニーには、草原や森がなかったわけじゃないけれど、細菌やウイルスの住処になる可能性を考慮され、コロニーの郊外近くに『AlicE』の機体が動き回る人工林があるばかりだった。またコロニーの空には、落雷や風雪の被害を防ぐバリアを張るための巨大な支柱が大きくそびえているので、コロニーから見える空はとても小さかった。ここから見える何もかもが、コロニーから見える景色とはちがっていた。
建物がなくなったことで、風が気持ちよく感じられた。
「もう少しいったところで、昼飯にしよう」
体を広げて風を感じていると、フョードルがそう言った。たしかに、太陽はさっきよりもさらに高く昇ってほとんど真上に来ていたし、フョードルの胸の中でずっとおとなしく寝ていたユミもぐずりはじめて、時々「えっえっ」と泣きそうになるのを、フョードルがさかんにあやしていた。
けれど、ぼくは昼食と聞いて気分が沈んだ。もちろん、ぼくもお腹は減っていたけれど、正直なにも食べたくなかった。最近は、ますますあの感覚がひどくなってきて、食事をとるたび、その事実に直面しなければならないのが辛いのだ。
しかし、なにも食べないというわけにもいかないので、ぼくも仕方なくそれに賛成した。
そのまま一直線に伸びる石畳の道を、風が吹き渡る草原に挟まれながら進むと、木立が立ち並ぶ場所に行き当たったので、ぼくたちはそこで昼食をとることにした。
木陰になっている場所に座り込んで、足を前に投げ出すと、足にたまった熱がじんわりとのぼってくるのを感じた。かたくなったふくらはぎや太ももを手で揉み込んで、その熱を逃していく。自分で思っていたよりも、身体の方は相当疲れていたらしい。マッサージを続けると、足の疲労はだいぶ楽になった。
フョードルは、ぼくとシャロンにお昼を先に食べておくように言うと、ユミを抱っこしてすこし離れた場所に行ってしまった。おしめを変えようとしてくれているらしい。ぼくとシャロンも手伝おうと思って、自分たちも行くと言ったのだけれど、フョードルは「今は休みなさい」とだけ言ってさっさと行ってしまった。
手伝うことを断られたぼくたちは、フョードルに言われたとおり、おとなしく先にご飯を食べていようと思って、コロニーを出るときに老人たちから渡された袋を開いた。
ぼくたちはコロニーから『AlicE』の調理機体も持ってきていたので、べつに食べ物をもらう必要はなかったのだけれど、見送りにきてくれた老人たちはぼくたちにどうしても何かを渡したかったようだった。
フョードルとシャロンには、人を惹きつける不思議な魅力がある。ふたりはユミの事件が起きるまでの短い間にコロニーの老人たちとすっかり打ち解けていた。ユミをめぐる意見の対立から離れていってしまった人もいたけれど、それでもこうしてふたりになにか協力したいと思う老人たちも残っていたのだ。
袋の中には、BLTサンドウィッチが入っていて、パンの間からのぞく色あざやかな具がとても映えて見えた。‥‥やっぱり、見た目はとても美味しそうだ。
シャロンが隣で大きくかぶりついて「おいしいー!」と言っている。‥‥ぼくも、ちゃんと美味しく感じられればいいのに。
ぼくも渋々サンドウィッチを控えめにかじった。しかし、口に含んだ直後、ぼくは自分の感覚を疑った。
もう一口食べてみる‥‥。さらにもう一口‥‥、さらにさらにもう一口‥‥。
作られてから時間が経ってしまったパンは、水分を含んですこしぺっしょりとしていたが、このサンドウィッチは、とても美味しかった。
間違いない、美味しい。美味しいのだ。今のぼくは、このサンドウィッチをちゃんと美味しく感じている。
美味しい。ちゃんと美味しい!!
「美味しい!!」
いきなり大声を出したぼくに、シャロンはびくっと身体を跳ね上がらせた。喉にサンドウィッチを詰まらせてしまったらしく、苦しそうに胸を叩いている。
ぼくは慌てて水を差し出すと、シャロンはそれを勢いよく飲み干した。
「もう!いきなりなんなの!!びっくりしたじゃない!!」
「ご、ごめん。このサンドウィッチが美味しくて、嬉しくて、つい‥‥」
ぼくの言葉に、シャロンは不思議そうな顔をした。
「このサンドウィッチ、いつもぼくが使ってる『AlicE』と同じ調理機体がつくったはずなのに、いつもより美味しいんだ‥‥」
「たしかに美味しいけど‥‥、いつもと同じじゃない?」
「いや、絶対に美味しい」
こんなに食べ物を美味しいと感じたのは、ほんとうに久しぶりだった。‥‥最近のぼくは、少しずつ、しかし着実に、料理の味がわからなくなっていたから。
『Alice』がつくる料理は、すべての料理に初期設定が行われている。初期設定からこまかい設定を変えてしまえば、味を変えることができるが、とくに設定を変えない限りは何度同じ料理をつくっても、毎回まったく同じ味のものができる。シャロンもフョードルも、目立った好き嫌いはなかったので、老人たちが自分の好きな味をふたりに食べてもらいたくて設定を変えたのなら、ぼくの『AlicE』のつくった料理との違いに納得がいくけれど、老人たちが初期設定から変更を加えたとは考えにくかった。
なぜなら、老人たちは、ぼく以上に料理の味に鈍感になっていたから。
ぼくは、コロニーで暮らしている間に、老人たちがなにかを食べて「美味しい!」と言ったところを一度も見たことがなかった。みんながみんな、毎回てきとうに料理を選んでは、大して美味しくなさそうにそれを食べていた。
単純な好奇心で、その理由を聞いてみたことがある。そのときに老人たちが言っていたのは、“むかしは美味しかった食べ物が、いまでは美味しく感じられなくなってしまった”ということだった。
けれど、別に彼らは味覚自体を失っていたわけではなかった。“むかし好きだった味を感じた上で、それを美味しいと感じられなくなってしまった”のだ。その違和感は、ある時から少しずつ大きくなり、いまでは彼らはなにを食べても美味しいと感じられなくなってしまったという。
老人たちはその現象を『味覚薄化症(みかくはっかしょう)』と呼んでいた。言いにくいので、ぼく自身は『もう美味しくない病』と呼んでいたけれど、ぼくは言いにくいので勝手に『もう美味しくない病』と呼んでいたけれど。
‥‥そして、『もう美味しくない病』の兆候は、最近ぼくにも現れていた。
老人たちの言葉を聞いていたぼくは、いつかぼくも『もう美味しくない病』になってしまうんじゃないかとずっと恐れていた。コロニーに住む老人たちのほとんどが、同じ現象に悩まされていたから。だから、むかしはあんなに美味しかったラーメンが、もう美味しく感じられなくなったことを認めたあの日から、ぼくはどんな物を食べても美味しく感じることができなくなる未来に、一人静かに、けれど深く絶望していた。
しかし、このサンドウィッチは、ちゃんと美味しい。美味しく感じられたのだ。それは、ぼくにとって大きな感動だった。
「いっぱい動いたからよ、きっと。それと、外で食べるから美味しいんだわ」
シャロンはぼくと同じようにサンドウィッチにかぶりつきながら言った。たしかに、ぼくはいままでこんなに長い距離を、こんなに長い時間歩いたことはなかった。けれど、それだけであの呪いのような違和感が消えたのだろうか。考えても答えはわからなかった。ただ、今はこのサンドウィッチがたしかに美味しく感じられることが嬉しかった。
ぼくは残ったサンドウィッチにかぶりつくと、あっという間にサンドウィッチをたいらげてしまった。
からだに力が溢れてきたような気がしたぼくは、溢れ出るエネルギーを発散したくて、立ち上がってフョードルの方に行った。
フョードルは、ユミのおしめを変え終わって、今はミルクを作っていたところだった。ユミは不快な感触が消えたことですっかり機嫌をなおしたようで、「あうー」と言いながら手をあちこち伸ばして遊んでいる。
ユミのお世話を代わることを申し出ようとしたとき、フョードルが粉の状態からミルクを作っていることに気がついた。
それを見たぼくのあたまの中には、大きな疑問符が浮かんだ。どうして、わざわざ粉の状態からつくろうとしているのだろう?『AlicE』に頼んでしまえば、ものの数十秒で、あたたかくて美味しいミルクができあがるのに。
しかも、さらによくわからないことに、フョードルは、どうやら粉ミルク自体は『AlicE』につくらせたようだった。つまり、べつに『AlicE』を使わなかったわけじゃなく、“わざわざ完成品の一個手前の状態のものをつくらせて”、“それを使って最後に自分で”粉ミルクをつくっているのだ。
いったいどうして、そんな手のかかるようなことをわざわざしているのだろうか。
ぼくが不思議に思っていることに気がついたらしいフョードルは、ふっと笑った。
「俺がわざわざ面倒な手間をかけてミルクを作っているのを不思議に思っているな?」
ぼくは素直にうなずいた。純粋に、どうしてそんなことをするのか、その理由が知りたかった。
けれど、フョードルは「ふむ」とだけ言ってすこし考えるようなそぶりを見せると、またぼくの頭をぽんぽんと数回たたいて、「またあとで教えてやる」とだけ言って、出来上がったミルクをぼくに渡してシャロンの方へ行ってしまった。
答えが得られると期待して待っていたぼくは、またしてもその期待が空振りに終わったことにがっかりした。けれど、フョードルがこんな風にぼくが求めている答えをはぐらかすようなことは、これまでにもう何度もあったので、この感覚にももうだいぶ慣れてきていた。なにより、フョードルが意味もなくそういうことをするような人間でないことはよくわかっていたので、ぼくはフョードルが話すべき時だと判断するのをおとなしく待つことにした。
と、空腹を訴えるようにユミが一言大きく「あうあー」と声を出したので、ぼくはあわててユミにミルクをあげる準備をはじめた。
フョードルがつくってくれたミルクを哺乳瓶に移して、ユミを抱えると、ゆっくりと乳首を口に押し当ててあげた。ユミは顔をかがやかせて乳首に吸い付くと、見ているぼくがびっくりするくらいの勢いでミルクを飲み干していく。ほんとうに食いしん坊な子だった。
けれど、こうやってミルクをおいしそうに飲む姿や、この子を抱く腕から伝わってくるぬくもりは、この子が今ちゃんと生きていることを感じさせてくれた。
この子は、どんな子に育つのだろう。ミルクをこんなにおいしそうに飲むということは、食べることが好きな子になるのだろうか。もしかしたら、シャロンのように活発な子になるかもしれない。いろいろな想像をしてみたけれど、どんな子に育ってもいいから、元気に大きくなってほしかった。
ぼくは、自分のこころがあたたかいもので満たされていくのを感じながら、ユミがミルクを飲むのを見続けた。
◆
昼食を食べ終えたぼくたちは、ずっと先へと続いていく石畳の道をまた歩き始めた。
ユミはお腹がいっぱいになって元気が出たのか、フョードルの胸の中できゃっきゃと騒いで、フョードルのひげをしきりに引っ張ったり、胸を叩いたりしている。フョードルは苦笑いしながら「こらこら」と言ってなだめているが、そこまで気にしていないようだった。
シャロンもまだまだ元気なようで、その足取りは軽く、なんならたまに走り出している。すごい体力だ。フョードルですら、そんなシャロンを見て「本当に無尽蔵だな‥‥」となかば呆れるほどだった。
ぼくも、歩き出すときには昼食のおいしさに力をもらって張り切っていた。「足も休めたし、まだまだ歩ける」、そう思っていた。けれど、そうやって歩き出したぼくの足は、歩くのを再開して1時間も経つ前から、また疲労を訴えはじめていた。歩みを進めるたび、気力とはうらはらに足はどんどん重くなっていく。何度も足を止めては、ふくらはぎを揉んだり叩いたりする。けれど、疲れはまったくとれず、疲労は増すばかりだった。既に真上を通過した太陽は、午前中よりもその日差しを強めて、ぼくの体をじりじりと焼くように照らしている。春なので気温がまだ高くないのが唯一の救いだった。
ぼくが止まるたびに、フョードルとシャロンも歩みを止めて、何度も休憩をとってくれた。休憩中、フョードルが足を揉んだりしてくれたけれど、そうやって休んで回復しても、もう一度歩き出すとぼくの足はすぐに悲鳴をあげた。
ふたりはずっとぼくを心配してくれたけれど、ぼくは足の疲労よりも、ふたりの足を引っ張っていることの方が辛かった。
何度も休憩をとっている間に、日が傾いて、空が朱く焼けはじめた。車はまだ見えてこない。
いそがなければ、と思ってもう一度歩き出そうとすると、フョードルに止められた。どうしたのだろうかと思っていると、フョードルは懐から地図を取り出して、ぼくとシャロンにも見えるようにそれを広げた。
「この先には坂がある。そんなにきつい勾配じゃないが、坂の途中で止まるのは辛いからな。今日は、このあたりで休むことにしよう」
フョードルの言葉に、ぼくは呆然とした。
今日の移動はこれで終わり。そして、ぼくたちはまだ車の影も形も見つけていない。つまり、今日歩く予定だった距離の目標を達成できなかったということだ。
‥‥ぼくのせいで。ぼく一人が足を引っ張ったから、ふたりに迷惑をかけてしまった。だって、ふたりはまだ全然元気で、ぼくがいなければ、きっとふたりは今日のゴールにとっくに辿りついていたはずだから。
「すまない。俺としたことが、つい自分が歩けるだけの距離を目標にしてしまっていた。ずっとコロニーで気ままに過ごしていたから、すっかり鈍ってしまったようだ」
呆然とするぼくの頭を撫でながら、フョードルはやさしい声でそう言ってくれたけれど、そんなことが嘘なのはわかっていた。まわりのことをよく見ることができるフョードルが、そんなミスをするとは思えなかった。フョードルだって、旅に慣れていないぼくのことを考えて、きっと普段より短い距離に設定してくれていたはずなんだ。ただ、フョードルの想像以上にぼくの体力がなかっただけで‥‥。
そこまで考えて、ぼくは自分の目が熱くなるのを感じた。こぼれそうになったそれを、必死に抑えこむ。足を引っ張って、挙げ句の果てに泣き出すなんて、そんな情けないことは絶対にしたくなかった。
「気にするな。シュヴィーツまで帰るだけの時間はたっぷりある。それに、これから体力もどんどんついてくる。自分を責める必要なんてどこにもないぞ」
下を向いて唇を噛んでいたぼくに、フョードルはあくまでやさしく言葉をかけてくれる。けれど、今はそのやさしさも辛かった。こんなにやさしいフョードルの、期待に応えられなかったのが、辛かった。
「だいじょぶ、だいじょぶトーマ!今日はゆっくり休んで、また明日がんばろ!」
シャロンもぼくの背中をバシバシと叩いて励ましてくれる。その力は相当強かったけれど、それはきっと、ぼくが涙を流しそうなことに気がついていて、それを誤魔化す理由をくれようとしたんだ。
ぼくの中の情けない気持ちと、それを隠そうとする精一杯の見栄を、それを一番見抜かれたくない彼女にも見抜かれてしまっていると思うと、ぼくはさらに情けない気持ちになった。ぼくの中に生まれた負の感情は、ぐるぐると渦を巻いてどんどんと大きくなっていった。
フョードルはリュックサックを下ろすと、「多めに入れておいて助かったな」と言いながら、何枚かの服を取り出して、それをぼくとシャロンに渡してくれた。
「今日はそれにくるまって寝なさい。重ねれば、なかなか暖かくなるはずだ」
テントや寝袋などの寝具は大きくて重いので、すべて車の中に置いてきてしまっていた。今日はフョードルの服を寝袋代わりに巻いて寝るということだろう。
もちろん、調理型の『AlicE』も携帯シャワーもないので、今日は食べるものもないし、シャワーを浴びることもできない。
またぼくの中に申し訳ない気持ちがわいて、罪悪感に苛まれていると、フョードルがリュックサックのなかから昼のサンドウィッチの残りを取り出した。フョードルは身体が大きいので、老人たちはすごい量のサンドウィッチをフョードルに渡していたらしい。フョードルはそれが食べきれなくて、残しておいたようだ。
「内心、さすがに俺もこんなには食べられないと思っていたんだが、御老功たちに感謝だな」
「棚からぼたもちだ!いや、不幸中の幸い‥‥?まあ、いいや!ありがたく食べよー!」
ふたりは笑いながらサンドウィッチを取り分けて、ぼくにもそれを渡してくれた。
パンは昼ごろよりさらに水分を吸って、ぎゅっと縮んでいた。昼はあんなに美味しかったサンドウィッチが、今は全然美味しく感じられなかった。けれど、それはきっとこのサンドウィッチのせいじゃなくて、ぼくの気持ちの問題だ。
唾液がからからに乾いて喉を通らないサンドウィッチを、水で無理やり流し込んで食べた。
夕食を食べ終わって、歯を磨き終わった頃には、太陽はもう西の空に沈みかけて、あたりは暗くなってきていた。フョードルが電気式ランタンをつけると、明るい光がまわりを照らしたけれど、寒さの方はどうにもならなかった。
昼間は暖かかったのに、陽が沈むにつれて気温はどんどん下がっていって、今はとても寒かった。自分の服と、フョードルに貸してもらった服とにくるまっていなければ、ガタガタ震えてしまうような寒さだった。けれど、フョードルの大きな服は一枚一枚が布団のようで、とても温かかい。さらに、フョードルは布の上からぼくの足を揉み込んでくれたので、足からじんわりと昇ってきた熱が服の温もりとあいまって、とても気持ち良かった。
そこでふと、フョードル自身は一枚も布をかぶっていないことに気がついた。
ぼくとシャロンにくれた分で全部だったのだろう。そのことに今更気がついたぼくは飛び起きて、フョードルに服を返そうとした。けれど、フョードルは自分は大丈夫だからと言ってそれを受け取らない。
「俺の先祖はもっと寒い場所に住んでいたからな。その血を継いだ俺も寒さにはめっぽう強くて、この程度はまったく寒くない」
「本当にすごいんだよ。雪が降っていても半袖半ズボンでぴんぴんしてるの」
フョードルの言葉に続いて、シャロンも笑いながら言った。たしかに、フョードルが寒さに震えているような様子はまったくない。
ぼくに布をかけ直して「だから安心して休みなさい」と言うフョードルの言葉に、張り詰めていた意識がゆるゆると緩んでしまったぼくは、とたんに眠くなってきた。足の疲労もあいまって、その眠気はあらがうことができないほど強かった。それからすぐに外からもたらされる情報が途切れて、自分の足から伝わるじんじんとした熱だけを感じながら、ぼくの意識は眠りの底に落ちていった。
次の日の朝、ぼくは身体中にのしかかる怠さを感じながら目を覚ました。昨日の足の疲労は、筋肉痛へと変わっていて、足を動かすたびに痛みを感じた。昨日の夜にフョードルが念入りにマッサージをしてくれたので、そこまでひどい激痛ではなかったけれど、やはり完全に筋肉痛を防ぐことはできなかった。
いびきが聞こえて、その音がした方を見ると、シャロンが「ぐーぐー」と大きないびきをかいて寝ていた。昨日はちゃんと被って寝ていたはずのフョードルの服を蹴散らかして、身体のあちこちがはみ出している。
「おお、起きたか。おはよう。身体の調子はどうだ?」
フョードルはぼくよりも先に起きていた。その腕ではユミがぐずっていて、フョードルがせっせとあやしている。ぼくは、大丈夫だと答えると、ユミの顔をのぞき込んだ。
ユミはあまり夜泣きをしない子だった。たまにぐずってなかなか寝ないことはあるけれど、それでも『AlicE』に聞いていた一般的な赤ちゃんと比べれば、全然少ない方だろう。
けれど、今は髪と同じ茶色の眉を不機嫌そうにゆがめて、まだ歯の生えていない口から「えっえっ」とぐずり声をあげている。
「腹が減ったみたいでな。ミルクをつくろうと思っていたところだったんだ」
そう言うフョードルの手には粉ミルクと煮沸器が握られていた。
ぼくは、昨日の夜からずっとフョードルに負担をかけているのが申し訳なくて、少しでも休んでほしくて、代わりにミルクをつくらせてほしいと頼んだ。
フョードルは「なら、お願いしよう」と言ってミルクのつくり方をひとつひとつ教えてくれた。
「まず、煮沸器に水を入れて加熱する。沸騰する前に煮沸を終わらせて、少し冷ますように。その間に、哺乳瓶の方に粉ミルクの粉を10gだけ入れてくれ。あぁ、でももうその一杯分くらいしか残っていないか。全部入れてくれていい。お湯が冷めてきたら、出来上がり量の2/3くらいの量を哺乳瓶に入れて、蓋をつける。そうしたら、円を描くようにやさしく哺乳瓶を揺らして、粉をかき混ぜて溶かしていく。粉が溶けたら、最後に残ったお湯を出来上がり量だけ入れれば完成だ」
‥‥できた。フョードルの言う通りに進めていくと、ちゃんと粉ミルクが完成した。最初は自分でつくることが出来るか不安だったけれど、やってしまえば意外とできるものだった。
ふわふわとした心地よい達成感を味わいながら、フョードルからユミを引き受けると、ユミの口に哺乳瓶の乳首を持っていってやった。すると、ユミは待ってましたとばかりに乳首に吸い付いて、目をらんらんとさせながら夢中でミルクを飲みはじめた。
「本当にこの子はミルクが好きだな。いくらおとなしいと言っても、この様子じゃミルクをもらえなくなると泣き叫ぶかもしれん。もうミルクの残りはないから、はやいところ車まで行ってやらんとな」
フョードルは笑いながらそう言うと、シャロンが寝ているところに行って、シャロンを起こしはじめた。
ぼくは、ユミにミルクをあげながら、フョードルが言ったように、今日こそは絶対にゴールまで辿りつくのだとこころの中で固く誓った。
向こうでは、寝ぼけたシャロンがフョードルの顔面にパンチをお見舞いしていた‥‥。
◆
今日の移動は、昨日よりも早い時間にはじまった。サンドウィッチも昨日のうちに食べきってしまったので、朝食は抜きだ。
フョードルは地図を確認して、それをぼくとシャロンにも見せ、その読み方と使い方を教えながら、ぼくたちが今目指している場所を示してくれた。大体、車までの距離はあと六キロほどで、昨日と同じくらいのペースで歩けば三時間弱といった場所だった。
ユミの粉ミルクももう残っていないので、昼時までには絶対にここへ辿りつかなければならなかった。足の筋肉痛は、歩きはじめてしまえば意外と気にならなくなった。ぼくは、自分の足に「今日はもっと頑張ってくれ」と願いながら歩き続けた。
そうして歩き続けて、ぼくの足がまた疲労を訴え出したころ、若葉が萌える緑の大地の上に、ぽつんと不自然に白い点がぼくたちの視線の先に突然現れた。
一瞬、蜃気楼かなにかかと思ったそれは、近づいていくごとに少しずつ大きくなっていることから、幻ではなくたしかにそこにある実在の物だとわかった。その正体に気がついた時、ぼくの心は安堵と達成感に満たされた。あれは、車だ。
「車だー!やっと見つけたー!」
シャロンは、歓声を上げると、先に走り出してしまった。
ぼくはもうボロボロなのに、彼女のこの力は一体どこから来ているのだろう。心の底から尊敬の念を抱きながら、ぼくは自分のペースで歩き続けた。
車は、それまで一本道だった街道が二手に分かれる場所に静かに止まっていた。
日差しをさえぎる木陰もない場所だったので、日差しをめいいっぱいに受けた合成セラミックの白い外装はすこし熱を持っていた。
「よくがんばったな。昼は『AlicE』につくってもらったものを車の中で食べて、午後はそのまま車で移動しよう」
「さんせーい!お腹減ったよー‥‥、あ、でも先にシャワー浴びてくる!」
フョードルとシャロンに疲れた様子はなく、ふたりは車の中に乗り込むと、それぞれに準備をはじめた。きっとふたりは、ぼくがいなければそのまま歩き続けるつもりだったのだろう。
ぼくは、やっと休むことができるという喜びの気持ちより、ふたりの予定を変えてしまった申し訳なさが強かった。
昼食を終えたぼくたちは、フョードルが運転する車で先を進みはじめた。歩いているときにはゆっくりと流れていた景色が、今はあっという間に流れていく。
車はやっぱり快適だった。けれど、今のぼくは車を使っていることが、なんだかとても嫌だった。
はじめに車を使わず歩くことが決まったときには、歩くことのほうが嫌だったのに、今は、ぼくの目の前をまたたく間に流れていく景色が惜しくてたまらなかった。その景色の中に、まだ見ぬ宝が混じっているような気がして、車に乗っているとそれをみすみす見逃しているように思えて悔しかった。
けれど、車に乗って緊張の糸が緩んだことで、足の疲労は強力な睡魔となってぼくの意識を襲ってきた。
ぼくは、うとうとして自分の頭が揺れているのがわかったが、いくら目を開けていようとしても、まぶたはどんどん重くなっていく。
そんなぼくの様子に気がついたフョードルは、「少し休んでいなさい」と言って毛布を渡してくれた。
そのぬくもりは睡魔をさらに強め、車の外の景色にすがりついていたぼくを深い眠りへと落としていった。
マルーン
第四章 旅立ち
5369年4月1日
その日はあっという間にやってきた。結局、あの日おじいの反応を見て自分の中に湧いた感情の正体は分からなかったけれど、時間が経つにつれてその感情はなりをひそめていった。
ぼくたちは、春を迎えて少しずつ暖かかくなってきたコロニーの外の空気を感じながら、コロニーと旧市街との境目に立っていた。コロニーの住人たちに見送られる形で、この場所をあとにする。
赤ちゃんは、抱っこ紐でくくられて、フョードルの胸の中で静かに眠っている。赤ちゃんは女の子で、ユミと名付けられた。あの日シャロンが歌ってくれた『いつも何度でも』の“ユミ・キムラ”の名前からとったのだ。ユミは産まれたばかりのころに比べて、ぷくぷくとあちこちが膨らんでいてとてもかわいい。
見送りに、おじいと何人かの老人たちが来ていた。
あの日以来、ぼくたちはほとんどの老人たちから快く思われていなかったので、その人数は多くはない。けれど、ぼくはたとえ数人でも老人たちが見送りに来たことに驚いていた。
「さすがに、こんなものまでいただけませんよ」
フョードルはさっきから、おじいが譲ると言って聞かない浮上式自動車を受け取る、受け取らないでおじいと揉めていた。
「わたし自身はもうこんなものを使う機会がない。事故で潰さない限り、宇宙の終わりが来るときまで走り続けられるだけの車だ。いくら旅に慣れていると言っても、これからは必要になることもあるだろう。元気のあるうちは使わなければいい。必要になったときに使えばいいさ。‥‥子どもたちのためでもある。受け取らないというのなら、出ていくことは許可できない」
おじいの強硬な態度に、フョードルは結局車を受け取った。
浮上式自動車は、太陽光とバイオエネルギーによる反重力で車体を浮かせることで、空中での走行を可能にした車だ。空中を進むので、どんな悪路でも物ともせずに進むことができる。また、この車にも『AlicE』が搭載されているので、自動運転モードで運転を任せることもできる。あるのとないのとでは大違いだ。
「‥‥くれぐれも、気をつけて行くんだよ」
おじいはぼくたちにそう言うと、目を伏せてしまった。
まわりの老人たちも、眉を下げてさびしそうにしている。
突然、その様子を見たぼくのこころにも、さびしさが噴き出してきた。
ぼくは、そのことに驚いて、自分の胸に手を当てた。なんだか胸が痛い。
その痛みは決して強くはないけれど、たしかな鈍痛が胸に起こっていた。
ぼくは、自分の中にこのコロニーへの愛着があったことに戸惑っていた。あんなに、哀れみのこもった視線を向けられるのが嫌だったはずなのに。
旅立ちを直前にした新しい発見だった。
けれど、ぼくは旅立つことを決めたのだ。外の世界で生きると。ぼくは、胸の痛みを振り切るようにして浮上式自動車に乗り込んだ。
「短い間でしたが、本当にお世話になりました。どうか皆さん、健やかであってください。からだも、こころも」
フョードルはそう言うと、おじいに向かって静かに頷いた。おじいはぼくの顔を見て、なにか言いたげな顔になったけれど、口を開けては閉めることを繰り返して、結局なにも言わなかった。
ぼくも、おじいに何か言わなければいけないという気持ちに駆られたけれど、こころの中を渦巻く感情は上手く言葉にすることができず、結局口から出たのはありきたりな別れの言葉だけだった。
「‥‥おじい。行ってくるよ」
フョードルがアクセルを踏み、車が走りはじめた。老人たちは口々に別れの言葉を叫んでいる。きっともう、この老人たちと会うことはないのだろう。
そう思うと、なぜだか無性におじいの顔が見たくなった。集団の中におじいの姿を探して、その顔を見た。
おじいは、ぼくがはじめて見るような、さびしそうな顔で笑っていた。さびしそうに笑いながら、その口元が動いた。
けれど、その口がなにを言ったのかはわからなかった。そもそも、それが言葉だったのかどうかすらも‥‥。
車はぐんぐん進んでいく。あっという間に見送りに来た老人たちの姿は小さくなって、やがて旧市街の街並みに隠されて見えなくなってしまった。
けれど、ぼくの脳裏には、おじいのあの寂しそうな笑顔が焼きついて離れなかった。
◆
コロニーを出て旧市街をしばらく進んだところで、フョードルは突然車を止めた。
何事かと思っていると、フョードルはぼくたちに車を降りるように言った。故障だろうか‥‥?けれど、おじいはさっき事故にあわない限りはずっと使えると言っていたし、おじいに限って不良品を人に渡すとは考えられなかった。
そんなことを考えていると、シャロンはいつの間に用意を終えたのか、あっという間に扉を開けて外に降り立っていしまった。
ぼくも慌てて自分の荷物をすべてまとめようとすると、フョードルに荷物はそのままで、水筒と服を詰め込んだリュックサック、そして日焼けを防ぐための帽子だけを持って降りるように言われた。
なにが起きているのかまったくわからないまま、戸惑いながらも言われたとおりにする。
車を降りると、ぼくと同じようにリュックサックを背負ったシャロンが、麦わらの帽子をあみだにかぶって、にこにこしていた。
シャロンはリュックサックの中からチューブを取り出して自分の顔や体に塗ると、それをぼくにも手渡してきた。
「なにこれ?」
「日焼け止め!春の日差しは強いから、ちゃんと塗らないと」
「ぼくはいいかな。長袖長ズボンでほとんど肌出てないし」
「そう?」と言いながら、シャロンは日焼け止めチューブをしまうと、こんどはスプレー缶を取り出して、長袖に覆われた体に噴きかけた。
「それは?」
「虫除けだよ。まだこの時期はそんなに多くないだろうけど、一応ね」
そうか、コロニーの外には虫がいるのか。コロニーには、ウイルスや菌を運ぶ虫や、住宅に住みつく虫の侵入と繁殖を防ぐための音波防虫機構と殺虫機構が存在しているので、コロニーやその周辺で虫を見たことはなかった。
ぼくは虫除けの方は受け取って、それをシャロンと同じように服の上から噴きかけたけれど、その時に煙を吸いこんでしまって激しく咳き込んだ。鼻と喉が焼けるようにしみて、涙が出てくる。
「息止めてないとだめだよー」
噴きかけた薬を伸ばしながら、シャロンが言った。
フョードルは運転席で『AlicE』になにか打ち込んでいたようだったけれど、それが終わると大きなリュックを背負って車から降りてきた。その胸元ではユミがまだ静かに寝息をたてていた。
フョードルは車から降りると、「行け」と短く言葉を発した。すると、車はひとりでにふわりと宙に浮かびあがって、そのままぼくたちの目の前からすっと滑るようにして動き出し、ぐんぐん速度をあげて、あっという間に見えなくなった‥‥。
え‥‥?
「ええぇぇぇ!?なんで!?」
あまりに自然に一連の出来事が行われたものだから、ぼくは、ほんとうに車がぼくたちの視界から消えるまで違和感を抱くことなく、ぼーっとそれを眺めてしまっていた。
しかし、フョードルもシャロンも平然としていて、あわてているのはぼくだけだ。
「御老功も言っていただろう?元気なときは使わなくていいと。今の俺たちには必要ない。歩いて行こう」
「そうそう!歩こう!」
頭が痛くなりそうだった。
「だからって、捨てなくてもいいじゃんか!荷物もほとんど乗せっぱなしだよ!」
「捨てたわけじゃない。俺たちの進行方向に先行させただけだ。今日一日俺たちが歩いて進める距離だけを進ませている。つまり、あの車があるところが、今日のゴールだ」
訳がわからなかった。どう考えても、歩くより車を使ったほうが便利で、楽じゃないか。
ぼくのそんな不満を見てとったフョードルは、短く言った。
「今の俺たちに、あの車は必要ない。今の俺たちは歩くべきだ」
そう言うと、フョードルはさっさと歩き始めてしまった。シャロンも跳ねるようにその後をついていく。
ここでいくら文句を言っても、車はもうすでに行ってしまったので、先へ進むにはいやでも歩くしかない。
けれど、なんでわざわざこんなことをするのか、理解ができなかった。どうして、便利な方法を使わず、わざわざ手間のかかる方法を選ぶのか。次から次へと浮かんでくる疑問の言葉をぐっと飲み込むと、ぼくも仕方なく自分の足を動かしはじめた。
歩きはじめるときには、面倒くさい気持ち一色だった感情は、しかし歩きはじめると、少しずつ薄れて消えていった。車に乗っていたときには、横から横へとあっという間に流れていった景色が、こうして自分の足で歩いているとよく見えることに気がついた。そんなことは当たり前かもしれないけれど、実際に歩いていると、今まで目につかなかったいろいろなものに目がいくようになった。
このあたりの建物は、ぼくが知っている建物にくらべてとても変わった形をしているものが多く、また建物同士の間隔がとても狭くつくられていた。コロニーにほど近い旧市街に建っていた建物たちは、コロニーのドーム型住宅ほど淡白なわけではないけれど、必要のない部分は極力削ってしまったような、シンプルで無機質な見た目の造りのものが多かった。機能的な面をより追求するような形の建物‥‥、ぼくは、それが旧市街の建物のすべてだと思っていた。
「このあたりには、いろんな形の建物があるね。それに、建物同士の隙間がものすごく狭いや」
静かに佇む街並みを見回しながら、そうつぶやく。
「ああ。この街は古くから人間が住み続けていたからな。さまざまな時代に、その時代の建築様式で建てられた建築物がそのまま残っているんだ。隣棟間隔が狭いのもそのせいだ。ヨーロッパは長い歴史のある地域だから、こういう場所は多い」
「そうそう」とシャロンがうなずく。
「わたしたちがコロニー5に行くときに通った街も同じような雰囲気だったよ。行きは少し北の方角から遠回りして、ウルム大聖堂を見て、アウクスブルクの旧市街を通ってきたんだ。でも、あっちの街の方が古めかしい雰囲気だったな」
「歴史的に見ると、アウクスブルクやネルトリンゲンといった自由都市の方が都市としての重要性が高い時代が続いていたんだ。このミュンヘンもたしかに歴史的に栄えてきた商業都市だったが、それらの自由都市には一歩劣る都市だった。あくまで重要都市としての域を出ない時代が続いていたんだ。だから、こちらの都市の方が比較的新しい時代の建物が多いんだよ」
ふたりの会話は、ぼくの知らない言葉だらけでよくわからなかった。都市や建物の名前は右耳から入って左耳へと抜けていってしまったが、話の最初にわからなかった単語だけは頭に残っていた。
「建築様式ってなんなの?」
「建築物というのは、時代や地域によってもちいられている建築手法や様式がちがう。建築様式は、その建築物が“どういう建築思想で”、“どういう建築手法をもちいて造られているのか”を示すものだ」
そう言うとフョードルは、比較的広い場所に立っているシンプルな建物を指差して言った。
「あの建築物のように、装飾がほとんどないシンプルな建物は、モダニズム建築といって比較的新しい時代の建築様式だ。19世紀末から20世紀にかけての建築様式で、装飾を嫌って機能的かつ合理的な造形を追求している。だから、見ての通り装飾らしいものがほとんど施されていなくて、シンプルな造りになっている」
「しかし、モダニズム建築は機能美を追求するあまり、だんだんと建物そのものが持っていた個性は弱まってしまった。それ自体が個性と言えなくもないんだが、そのことを批判して、モダニズム建築に装飾や特徴的な形を取り入れるようになったのが、ポストモダン建築だ。ちょうど、あの円柱形に造られた建物のようなものだな。不思議な形だろう?」
ぼくはうなずいた。フョードルが指し示したその円柱の建物は、モダニズム建築よりもさらに広い場所にぽつんと建っていた。その構造は上の方に行くにつれてすこしずつ膨らみ、ところどころに目立ちすぎない装飾がほどこされていて、フョードルが言うように不思議な形をしていた。
「しかし、この街の建築物はバロック様式とゴシック様式‥‥、特にゴシック様式が多いな。」
フョードルはそう言ってあたりを見回すと、目的のものを見つけたのか、街にならぶ建物のうちの一つを指さして示した。それは、モダニズム建築とは真逆で、そこかしこに豪華な装飾がふんだんにほどこされた、とても派手な建物だった。
その建物を見て、まずぼくが驚いたのは、その巨大さだった。高い壁が空を衝くかのようにそびえ立ち、壁面に埋め込まれた色とりどりの窓は宝石のように輝いて、建物を美しく飾り立てている。建物の側面からは、壁を支えるようにして外壁が張り出していて、屋根の上には鋭く尖った塔のようなものが高く伸びていて、その高さをより強調していた。まさに、青空に迫るような建物だった。
「あれがゴシック様式だ。ゴシック様式は、かつてこの世界で最も信じられていた宗教が、自分たちの教会‥‥、祈りを捧げたり、儀式をする場所のことだ。彼らがそれをつくる際に多用していた建築様式だ。だから、その建築思想は神聖性や神秘性を表現することに重点を置いているし、建築手法もいかにそれを再現するかを考えてつくられている」
フョードルはそう言うと、高くそびえる建物の上部を指差した。
「そして、その手法のうち最も大きなものがこの高さだ。垂直方向に大きく伸びる尖塔やアーチは、この教会という場所が、神のいる天空に最も近い場所であることを表現している。壁面にいくつもはめ込まれたステンドグラスも重要な演出装置だ。光の入る角度や時間帯をすべて計算して、内部に差し込む光が最も美しく、神聖な雰囲気を演出できるようになっているんだ。ほかにも聖人を象った彫像や、内部の身廊と側廊を形作るヴォールトといった数多くの特徴があるが、そのどれもが教会という場所の神聖性を演出することを目的につくられている」
「ただ、」とフョードルは言葉を区切った。
「この旧ドイツの街のゴシック建築は少し毛色が違っていてな。元々、旧ドイツは商業と貿易で栄えた商人たちの街が多い地域だった。だから、この地域におけるゴシック建築は、神や教会、ましてや国王や皇帝といった支配者を讃えるものじゃなく、商業経済の発展と商人たちの活躍を示すものが多いんだ。もちろん、中には教会も混ざっているが、歴史的に見るとその影響力は他の地域に比べて大きくなかったといえるだろう」
どうして、こんなにスラスラと知識が出てくるのだろう。フョードルは、頭に『AlicE』でも繋いでいるのだろうか?ぼくが知っている限り、人間の脳と『AlicE』の情報とを繋げようとした実験の結果は、人間の精神崩壊という悲惨な結果に終わり、それ以降はタブー扱いされていたはずだけれど。もしかしたら、フョードルはその実験の唯一の適合者なのかもしれない‥‥。
そんな馬鹿げたことを冗談半分、本気半分で思ってしまうくらい、フョードルは博識だった。フョードルの話は、はじめて聞くことばかりでぼくはその内容を全部覚えたくて必死に聞いていたけれど、結局ほとんど覚えられなかった。
でも神という言葉は知っている。むかしの人間が信じていた、人間よりもずっと偉い上位の存在のことだ。ただ、神にはいろいろな種類がいて、どんな存在で、どのくらいの数がいて、どんなことをするのかなど、それこそすべてが時代や地域によってバラバラで、結局のところよくわからない存在だった。‥‥いや、そんなものは本当は存在しないけれど。
むかしは神というものを信じていた人間は多かったらしいけれど、今この世界で神を信じている人間なんていないだろう。ぼくを含めて、コロニーの誰もそんなものの存在を信じていなかった。当然だ。だって、人間の上位の存在であるはずの神は、宇宙の終わりを防ぐことはできなかったんだから。人間の科学と一緒で、この世界の前ではひどく頼りない、どうしようもなく弱い存在だ。
逆に、神がほんとうに全知全能の存在だったとしたら、宇宙の終わりなんていう馬鹿げたスケールの現象は、その神が引き起こしたものにちがいない。だとしたら、そんなやつは人間の敵だ。信じるもくそもない。
──ぼくたちを助けてくれない神なら、たとえどこかに存在していたとしても、ぼくたちにはまったく関係がない。
いずれにしろ、ぼくたちが神なんてものを信じる理由は一つもなかった。‥‥神なんて、実際には何にもできないくせに人間の前でだけ偉そうに振る舞う、作り話の中の嫌な存在だ。
なんだか突然、むかしそんなものを信じていた人間たちのことが許せなくなってきた。
何に対する怒りなのか、どういう怒りなのかは自分ではわからなかったけれど、突然湧いたその感情は思いのほか強く、一気にぼくの頭を沸騰させた。
理由もわからない怒りに飲まれそうになった時、フョードルがぼくの様子を察してか、別の建物の話をはじめた。ぼくの怒りはまだ頭の中を占めていたけれど、意識がフョードルの話しの方に向いたことで、それは少しずつその熱を下げて、ゆっくりと消えていった。
「‥‥そして、あれがバロック様式だ」
こんどの建物も、ゴシック建築と同じく、そこかしこに豪華な装飾がふんだんにほどこされている。ただ、その装飾はゴシックのように“縦”を意識してつくられたものではなく、緻密な彫刻や模様が彫り込まれるなど、建物そのものを強調するようなものだった。表面に彫り込まれた複雑な模様は、光を受けることで影を生み、それが建物全体の奥行きを強調することで、建物はよりいっそう美しく見えた。
「16世紀末から18世紀にかけて、ヨーロッパ全体で広く使われていた建築様式だ。見ての通り、あちこちに彫刻やレリーフ、豊富な曲線装飾がふんだんに使用された建物で、ゴシック建築と同じように装飾性の強い建築様式だ。ただ、宗教的な建築思想がゴシックよりも弱かった。その根底に宗教的な思想と意味があったのはたしかなんだが、教会の人間にとってはゴシック様式の方が重要だったんだ。ただ、豪華さや華麗さ、贅沢さを示すにはうってつけの様式だったから、当時の支配者たちの住居や公共施設にも多く使われていた。ここから少し北へ行った場所にあるニンフェンブルク宮殿などがその例だな」
たしかに、ゴシック建築はなんだか縦にしゅっとしていて神秘的な印象を受けたのに対して、バロック様式は横と奥にどっしりと構えられていて、その装飾も重厚な印象だった。その姿は、シャロンの本やゲームに出てきた城や屋敷のようにも見える。
「こんなふうに、建築物そのもののデザインや構造、装飾といった要素から、建築様式を見分けるんだ」
「わたしは未だにうまくできないんだけどね。ほかにも建築様式はあるんだけど、中にはほかの様式を取り入れてるものもあって、見分けるのがちょーむずかしいんだ」
「それぞれの建築様式の境界線に曖昧な部分があることはたしかだ。ヨーロッパの文化は、さまざまな時代と地域が複雑に絡み合って形成されているからな。時代を遡れば、すべての地域が古代ギリシャや古代ローマの影響を受けていることも大きい。建築物も含めて、すべてのものがどこかしらかで少なからず互いに影響し合っているんだ」
途中、神なんていう不愉快な存在の話が出て、ぼくの気分もひどく不愉快になってしまったけれど、この短い間に、ぼくはまた自分の世界が変わったのを感じていた。
これまでのぼくの世界には、“コロニーのドーム型住宅”と、“旧市街の建物”という二種類の建築様式しかなかった。けれど、今はそこに“モダニズム建築”や“ポストモダン建築”、“バロック建築”、そして“ゴシック建築”という、まったく新しい認識が加わって、世界の解像度が一気に上がった。まるで、世界を見通すレンズが切り替わったように。
解像度の上がったぼくの世界は、前よりも明瞭で、ずっと広いように思えた。
けれど、驚くべきことに、ぼくの世界はまだこれ以上の可能性を秘めているようだ。まだほかにもぼくの知らない様式があるということは、それを知るたびにぼくのレンズの解像度はさらに上がっていくのだろう。
さっきと比べて、こんなに広くあざやかに見える世界でも、まだその可能性をすべて発揮しきってはいないのだ!
建築様式だけじゃない。これから先、ぼくが知る新しいことはすべて、ぼくのレンズの解像度を上げる情報として組み込まれ、ぼくの世界はどんどん鮮やかに広がっていくのだろう。
自分の見える世界を広げる、それは大きなよろこびで、今までにない感覚だった。
突然、コロニーでシャロンが言っていた「人間が自分で何かをつくることが大事な理由」の話が頭に浮かんだ。
なぜか、フョードルやシャロンがいま話してくれたことが、その話につながるような気がしたのだ。けれど、どうしてそれがつながると思ったのか、自分でもわからなかった。
なんだか、すごく大きなものをつかみかけている気がする。
けれど、すぐそこにまで迫っているはずのその答えは、いざ掴もうとすると、まるで木の葉のように腕のあいだをのらりくらりとすり抜けていってしまった。
──あぁ、いってしまう。
せっかくすぐそこまで近づいていたそれは、ゆるりゆるりとぼくのもとを離れると、すっと消えてしまった。もうその気配はどこにも感じられない。
「どうした?疲れたか」
いきなり落ち込んだぼくの様子に、フョードルが心配して声をかけてくれたけど、ぼくは逃したものの大きさに打ちのめされていた。
「ううん、ちがうんだ。なんだかいま、すごく大事なことが分かりそうだったんだけど、結局分からなくて‥‥。がっかりしただけなんだ」
ぼくは、自分がつかみかけていたものがなんだったのか、一生懸命に考えてみたけれど、その答えはまったく思い浮かばなかった。
諦めてため息をついたところで、ぼくはフョードルに相談してみることを思いついた。フョードルであれば、ぼくが言葉に表せないこのモヤモヤや、もしかするとぼくがつかめなかったものの正体も分かるかもしれない。
けれど、ぼくはシャロンにはこの話を聞かれたくなかった。できれば、自分一人で答えに辿りついたことにしたかったから。しょうもない見栄であることはわかっていた。けれど、やっぱり格好つけたいものは格好つけたいのだ。
だから、シャロンが少し離れたときを狙って、フョードルに相談する機会をうかがっていたけれど、今は全員で同じ方向に歩いているので、シャロンだけがいなくなるなんて状況になるわけもなかった。しばらくは諦めるしかないと思ったその時、突然もじもじしはじめたシャロンが、「ちょっとお花を摘みに‥‥」と言ってぼくたちから離れていった。
思いがけず、絶好の機会に恵まれたぼくは、「いまだ!!」と思って、急いでフョードルにことの経緯を説明し、期待しながら彼の言葉を待った。
しかし、フョードルはぼくの話しを聞き終わると、実に愉快そうに笑って「そうか、そうか」と言いながらぼくの頭を撫でつづけるばかりだった。
ぼくは、シャロンが戻ってくる前にフョードルの助言が聞きたくて、あたふたしていたけれど、そうこうしているうちにシャロンが戻ってきてしまった。
結局、まともに話をしてもらえなかったぼくは、ただずっとぼくの頭を撫でていたフョードルの行動に不満を抱いて、不貞腐れた態度をとってやった。
けれど、シャロンが「じゃあ、しゅっぱーつ!」と言って先に歩きはじめたところで、フョードルがシャロンには聞こえないくらいの声でぼくの名前を呼んだ。ぼくは、やっと教えてくれる気になったのかと期待して、フョードルの方へ顔を向けた。
振り返った先にいたフョードルは、その顔に優しい笑みを浮かべていた。その笑みは、なにかを懐かしむような、どこか寂しさを感じさせた。
「俺もその感覚に覚えがあるから、トーマが今どんな状態なのかはよくわかる。ただ、トーマがさっき逃したというそれは、俺が口で説明しても分かるようなものじゃないんだ。自分で掴まないと、本当にはわからないものなんだ。だから、今は説明できない。でも、大丈夫だ。その感覚があったなら、焦らなくてもいつか必ず分かる」
フョードルはそう言うと、ぼくの頭にもう一度手を乗せてぽんぽんとたたいた。安心しろ、というように。
「そのままこの世界をもっと見て、聞いて、感じて、楽しんでみなさい。そうすることが、一番大切なんだ」
その大きな手の、意外にやわらかな感触を感じながら、ぼくはその言葉をこころの中でなぞっていた。
◆
あれからぼくたちは、ずっと歩き続けていた。車を降りてからもう二時間くらいは経っている。太陽も少しずつその高さをまし、もうすぐ真上に来そうな時間になっていた。
一つ一つ形のちがう建物の並びの新鮮さも薄れてきたところで、突然、それまでずっと視界の先を塞いでいた旧市街の街並みがとぎれ、遠くの方に緑が広がっているのが見えた。
「やったー!もうすぐ街道だー!」
シャロンが嬉しそうに叫ぶ。ぼくも、目に飛び込んだきた緑にこころが踊って、少し疲れがたまって重くなっていた足に力が戻ってくるのを感じた。
遠くに見えていた緑は、歩くたびにどんどん近づいてきて、視界にしめる大きさもどんどん大きくなっていった。緑の草や葉が、風に吹かれてさわさわと影をつくりながらなびいている。その葉擦れの音が聞こえるところまで進むと、視界が一気に開けた。
ぼくの口からは、自然と「うわあ」と驚きの声が漏れていた。
目の前には、あたり一面に草花がそよぐ緑の大地と、その上にさらに大きく、白い雲を抱え、深い青をたたえた空の光景が広がっていた。
こんなに広い草原を、こんなに大きく青い空を、ぼくは見たことがなかった。
草や葉が力強く大地に根を張って広がった若緑色の中に、ぽつりぽつりといろとりどりの花たちが凜と咲いている。その上空には、深い、けれどどこまでも澄み渡るような群青色の空が広がっていて、その中で真っ白に膨らんだ雲が、まるでドレスのように風に揺らめいてその形を変えていた。
コロニーには、草原や森がなかったわけじゃないけれど、細菌やウイルスの住処になる可能性を考慮され、コロニーの郊外近くに『AlicE』の機体が動き回る人工林があるばかりだった。またコロニーの空には、落雷や風雪の被害を防ぐバリアを張るための巨大な支柱が大きくそびえているので、コロニーから見える空はとても小さかった。ここから見える何もかもが、コロニーから見える景色とはちがっていた。
建物がなくなったことで、風が気持ちよく感じられた。
「もう少しいったところで、昼飯にしよう」
体を広げて風を感じていると、フョードルがそう言った。たしかに、太陽はさっきよりもさらに高く昇ってほとんど真上に来ていたし、フョードルの胸の中でずっとおとなしく寝ていたユミもぐずりはじめて、時々「えっえっ」と泣きそうになるのを、フョードルがさかんにあやしていた。
けれど、ぼくは昼食と聞いて気分が沈んだ。もちろん、ぼくもお腹は減っていたけれど、正直なにも食べたくなかった。最近は、ますますあの感覚がひどくなってきて、食事をとるたび、その事実に直面しなければならないのが辛いのだ。
しかし、なにも食べないというわけにもいかないので、ぼくも仕方なくそれに賛成した。
そのまま一直線に伸びる石畳の道を、風が吹き渡る草原に挟まれながら進むと、木立が立ち並ぶ場所に行き当たったので、ぼくたちはそこで昼食をとることにした。
木陰になっている場所に座り込んで、足を前に投げ出すと、足にたまった熱がじんわりとのぼってくるのを感じた。かたくなったふくらはぎや太ももを手で揉み込んで、その熱を逃していく。自分で思っていたよりも、身体の方は相当疲れていたらしい。マッサージを続けると、足の疲労はだいぶ楽になった。
フョードルは、ぼくとシャロンにお昼を先に食べておくように言うと、ユミを抱っこしてすこし離れた場所に行ってしまった。おしめを変えようとしてくれているらしい。ぼくとシャロンも手伝おうと思って、自分たちも行くと言ったのだけれど、フョードルは「今は休みなさい」とだけ言ってさっさと行ってしまった。
手伝うことを断られたぼくたちは、フョードルに言われたとおり、おとなしく先にご飯を食べていようと思って、コロニーを出るときに老人たちから渡された袋を開いた。
ぼくたちはコロニーから『AlicE』の調理機体も持ってきていたので、べつに食べ物をもらう必要はなかったのだけれど、見送りにきてくれた老人たちはぼくたちにどうしても何かを渡したかったようだった。
フョードルとシャロンには、人を惹きつける不思議な魅力がある。ふたりはユミの事件が起きるまでの短い間にコロニーの老人たちとすっかり打ち解けていた。ユミをめぐる意見の対立から離れていってしまった人もいたけれど、それでもこうしてふたりになにか協力したいと思う老人たちも残っていたのだ。
袋の中には、BLTサンドウィッチが入っていて、パンの間からのぞく色あざやかな具がとても映えて見えた。‥‥やっぱり、見た目はとても美味しそうだ。
シャロンが隣で大きくかぶりついて「おいしいー!」と言っている。‥‥ぼくも、ちゃんと美味しく感じられればいいのに。
ぼくも渋々サンドウィッチを控えめにかじった。しかし、口に含んだ直後、ぼくは自分の感覚を疑った。
もう一口食べてみる‥‥。さらにもう一口‥‥、さらにさらにもう一口‥‥。
作られてから時間が経ってしまったパンは、水分を含んですこしぺっしょりとしていたが、このサンドウィッチは、とても美味しかった。
間違いない、美味しい。美味しいのだ。今のぼくは、このサンドウィッチをちゃんと美味しく感じている。
美味しい。ちゃんと美味しい!!
「美味しい!!」
いきなり大声を出したぼくに、シャロンはびくっと身体を跳ね上がらせた。喉にサンドウィッチを詰まらせてしまったらしく、苦しそうに胸を叩いている。
ぼくは慌てて水を差し出すと、シャロンはそれを勢いよく飲み干した。
「もう!いきなりなんなの!!びっくりしたじゃない!!」
「ご、ごめん。このサンドウィッチが美味しくて、嬉しくて、つい‥‥」
ぼくの言葉に、シャロンは不思議そうな顔をした。
「このサンドウィッチ、いつもぼくが使ってる『AlicE』と同じ調理機体がつくったはずなのに、いつもより美味しいんだ‥‥」
「たしかに美味しいけど‥‥、いつもと同じじゃない?」
「いや、絶対に美味しい」
こんなに食べ物を美味しいと感じたのは、ほんとうに久しぶりだった。‥‥最近のぼくは、少しずつ、しかし着実に、料理の味がわからなくなっていたから。
『Alice』がつくる料理は、すべての料理に初期設定が行われている。初期設定からこまかい設定を変えてしまえば、味を変えることができるが、とくに設定を変えない限りは何度同じ料理をつくっても、毎回まったく同じ味のものができる。シャロンもフョードルも、目立った好き嫌いはなかったので、老人たちが自分の好きな味をふたりに食べてもらいたくて設定を変えたのなら、ぼくの『AlicE』のつくった料理との違いに納得がいくけれど、老人たちが初期設定から変更を加えたとは考えにくかった。
なぜなら、老人たちは、ぼく以上に料理の味に鈍感になっていたから。
ぼくは、コロニーで暮らしている間に、老人たちがなにかを食べて「美味しい!」と言ったところを一度も見たことがなかった。みんながみんな、毎回てきとうに料理を選んでは、大して美味しくなさそうにそれを食べていた。
単純な好奇心で、その理由を聞いてみたことがある。そのときに老人たちが言っていたのは、“むかしは美味しかった食べ物が、いまでは美味しく感じられなくなってしまった”ということだった。
けれど、別に彼らは味覚自体を失っていたわけではなかった。“むかし好きだった味を感じた上で、それを美味しいと感じられなくなってしまった”のだ。その違和感は、ある時から少しずつ大きくなり、いまでは彼らはなにを食べても美味しいと感じられなくなってしまったという。
老人たちはその現象を『味覚薄化症(みかくはっかしょう)』と呼んでいた。言いにくいので、ぼく自身は『もう美味しくない病』と呼んでいたけれど、ぼくは言いにくいので勝手に『もう美味しくない病』と呼んでいたけれど。
‥‥そして、『もう美味しくない病』の兆候は、最近ぼくにも現れていた。
老人たちの言葉を聞いていたぼくは、いつかぼくも『もう美味しくない病』になってしまうんじゃないかとずっと恐れていた。コロニーに住む老人たちのほとんどが、同じ現象に悩まされていたから。だから、むかしはあんなに美味しかったラーメンが、もう美味しく感じられなくなったことを認めたあの日から、ぼくはどんな物を食べても美味しく感じることができなくなる未来に、一人静かに、けれど深く絶望していた。
しかし、このサンドウィッチは、ちゃんと美味しい。美味しく感じられたのだ。それは、ぼくにとって大きな感動だった。
「いっぱい動いたからよ、きっと。それと、外で食べるから美味しいんだわ」
シャロンはぼくと同じようにサンドウィッチにかぶりつきながら言った。たしかに、ぼくはいままでこんなに長い距離を、こんなに長い時間歩いたことはなかった。けれど、それだけであの呪いのような違和感が消えたのだろうか。考えても答えはわからなかった。ただ、今はこのサンドウィッチがたしかに美味しく感じられることが嬉しかった。
ぼくは残ったサンドウィッチにかぶりつくと、あっという間にサンドウィッチをたいらげてしまった。
からだに力が溢れてきたような気がしたぼくは、溢れ出るエネルギーを発散したくて、立ち上がってフョードルの方に行った。
フョードルは、ユミのおしめを変え終わって、今はミルクを作っていたところだった。ユミは不快な感触が消えたことですっかり機嫌をなおしたようで、「あうー」と言いながら手をあちこち伸ばして遊んでいる。
ユミのお世話を代わることを申し出ようとしたとき、フョードルが粉の状態からミルクを作っていることに気がついた。
それを見たぼくのあたまの中には、大きな疑問符が浮かんだ。どうして、わざわざ粉の状態からつくろうとしているのだろう?『AlicE』に頼んでしまえば、ものの数十秒で、あたたかくて美味しいミルクができあがるのに。
しかも、さらによくわからないことに、フョードルは、どうやら粉ミルク自体は『AlicE』につくらせたようだった。つまり、べつに『AlicE』を使わなかったわけじゃなく、“わざわざ完成品の一個手前の状態のものをつくらせて”、“それを使って最後に自分で”粉ミルクをつくっているのだ。
いったいどうして、そんな手のかかるようなことをわざわざしているのだろうか。
ぼくが不思議に思っていることに気がついたらしいフョードルは、ふっと笑った。
「俺がわざわざ面倒な手間をかけてミルクを作っているのを不思議に思っているな?」
ぼくは素直にうなずいた。純粋に、どうしてそんなことをするのか、その理由が知りたかった。
けれど、フョードルは「ふむ」とだけ言ってすこし考えるようなそぶりを見せると、またぼくの頭をぽんぽんと数回たたいて、「またあとで教えてやる」とだけ言って、出来上がったミルクをぼくに渡してシャロンの方へ行ってしまった。
答えが得られると期待して待っていたぼくは、またしてもその期待が空振りに終わったことにがっかりした。けれど、フョードルがこんな風にぼくが求めている答えをはぐらかすようなことは、これまでにもう何度もあったので、この感覚にももうだいぶ慣れてきていた。なにより、フョードルが意味もなくそういうことをするような人間でないことはよくわかっていたので、ぼくはフョードルが話すべき時だと判断するのをおとなしく待つことにした。
と、空腹を訴えるようにユミが一言大きく「あうあー」と声を出したので、ぼくはあわててユミにミルクをあげる準備をはじめた。
フョードルがつくってくれたミルクを哺乳瓶に移して、ユミを抱えると、ゆっくりと乳首を口に押し当ててあげた。ユミは顔をかがやかせて乳首に吸い付くと、見ているぼくがびっくりするくらいの勢いでミルクを飲み干していく。ほんとうに食いしん坊な子だった。
けれど、こうやってミルクをおいしそうに飲む姿や、この子を抱く腕から伝わってくるぬくもりは、この子が今ちゃんと生きていることを感じさせてくれた。
この子は、どんな子に育つのだろう。ミルクをこんなにおいしそうに飲むということは、食べることが好きな子になるのだろうか。もしかしたら、シャロンのように活発な子になるかもしれない。いろいろな想像をしてみたけれど、どんな子に育ってもいいから、元気に大きくなってほしかった。
ぼくは、自分のこころがあたたかいもので満たされていくのを感じながら、ユミがミルクを飲むのを見続けた。
◆
昼食を食べ終えたぼくたちは、ずっと先へと続いていく石畳の道をまた歩き始めた。
ユミはお腹がいっぱいになって元気が出たのか、フョードルの胸の中できゃっきゃと騒いで、フョードルのひげをしきりに引っ張ったり、胸を叩いたりしている。フョードルは苦笑いしながら「こらこら」と言ってなだめているが、そこまで気にしていないようだった。
シャロンもまだまだ元気なようで、その足取りは軽く、なんならたまに走り出している。すごい体力だ。フョードルですら、そんなシャロンを見て「本当に無尽蔵だな‥‥」となかば呆れるほどだった。
ぼくも、歩き出すときには昼食のおいしさに力をもらって張り切っていた。「足も休めたし、まだまだ歩ける」、そう思っていた。けれど、そうやって歩き出したぼくの足は、歩くのを再開して1時間も経つ前から、また疲労を訴えはじめていた。歩みを進めるたび、気力とはうらはらに足はどんどん重くなっていく。何度も足を止めては、ふくらはぎを揉んだり叩いたりする。けれど、疲れはまったくとれず、疲労は増すばかりだった。既に真上を通過した太陽は、午前中よりもその日差しを強めて、ぼくの体をじりじりと焼くように照らしている。春なので気温がまだ高くないのが唯一の救いだった。
ぼくが止まるたびに、フョードルとシャロンも歩みを止めて、何度も休憩をとってくれた。休憩中、フョードルが足を揉んだりしてくれたけれど、そうやって休んで回復しても、もう一度歩き出すとぼくの足はすぐに悲鳴をあげた。
ふたりはずっとぼくを心配してくれたけれど、ぼくは足の疲労よりも、ふたりの足を引っ張っていることの方が辛かった。
何度も休憩をとっている間に、日が傾いて、空が朱く焼けはじめた。車はまだ見えてこない。
いそがなければ、と思ってもう一度歩き出そうとすると、フョードルに止められた。どうしたのだろうかと思っていると、フョードルは懐から地図を取り出して、ぼくとシャロンにも見えるようにそれを広げた。
「この先には坂がある。そんなにきつい勾配じゃないが、坂の途中で止まるのは辛いからな。今日は、このあたりで休むことにしよう」
フョードルの言葉に、ぼくは呆然とした。
今日の移動はこれで終わり。そして、ぼくたちはまだ車の影も形も見つけていない。つまり、今日歩く予定だった距離の目標を達成できなかったということだ。
‥‥ぼくのせいで。ぼく一人が足を引っ張ったから、ふたりに迷惑をかけてしまった。だって、ふたりはまだ全然元気で、ぼくがいなければ、きっとふたりは今日のゴールにとっくに辿りついていたはずだから。
「すまない。俺としたことが、つい自分が歩けるだけの距離を目標にしてしまっていた。ずっとコロニーで気ままに過ごしていたから、すっかり鈍ってしまったようだ」
呆然とするぼくの頭を撫でながら、フョードルはやさしい声でそう言ってくれたけれど、そんなことが嘘なのはわかっていた。まわりのことをよく見ることができるフョードルが、そんなミスをするとは思えなかった。フョードルだって、旅に慣れていないぼくのことを考えて、きっと普段より短い距離に設定してくれていたはずなんだ。ただ、フョードルの想像以上にぼくの体力がなかっただけで‥‥。
そこまで考えて、ぼくは自分の目が熱くなるのを感じた。こぼれそうになったそれを、必死に抑えこむ。足を引っ張って、挙げ句の果てに泣き出すなんて、そんな情けないことは絶対にしたくなかった。
「気にするな。シュヴィーツまで帰るだけの時間はたっぷりある。それに、これから体力もどんどんついてくる。自分を責める必要なんてどこにもないぞ」
下を向いて唇を噛んでいたぼくに、フョードルはあくまでやさしく言葉をかけてくれる。けれど、今はそのやさしさも辛かった。こんなにやさしいフョードルの、期待に応えられなかったのが、辛かった。
「だいじょぶ、だいじょぶトーマ!今日はゆっくり休んで、また明日がんばろ!」
シャロンもぼくの背中をバシバシと叩いて励ましてくれる。その力は相当強かったけれど、それはきっと、ぼくが涙を流しそうなことに気がついていて、それを誤魔化す理由をくれようとしたんだ。
ぼくの中の情けない気持ちと、それを隠そうとする精一杯の見栄を、それを一番見抜かれたくない彼女にも見抜かれてしまっていると思うと、ぼくはさらに情けない気持ちになった。ぼくの中に生まれた負の感情は、ぐるぐると渦を巻いてどんどんと大きくなっていった。
フョードルはリュックサックを下ろすと、「多めに入れておいて助かったな」と言いながら、何枚かの服を取り出して、それをぼくとシャロンに渡してくれた。
「今日はそれにくるまって寝なさい。重ねれば、なかなか暖かくなるはずだ」
テントや寝袋などの寝具は大きくて重いので、すべて車の中に置いてきてしまっていた。今日はフョードルの服を寝袋代わりに巻いて寝るということだろう。
もちろん、調理型の『AlicE』も携帯シャワーもないので、今日は食べるものもないし、シャワーを浴びることもできない。
またぼくの中に申し訳ない気持ちがわいて、罪悪感に苛まれていると、フョードルがリュックサックのなかから昼のサンドウィッチの残りを取り出した。フョードルは身体が大きいので、老人たちはすごい量のサンドウィッチをフョードルに渡していたらしい。フョードルはそれが食べきれなくて、残しておいたようだ。
「内心、さすがに俺もこんなには食べられないと思っていたんだが、御老功たちに感謝だな」
「棚からぼたもちだ!いや、不幸中の幸い‥‥?まあ、いいや!ありがたく食べよー!」
ふたりは笑いながらサンドウィッチを取り分けて、ぼくにもそれを渡してくれた。
パンは昼ごろよりさらに水分を吸って、ぎゅっと縮んでいた。昼はあんなに美味しかったサンドウィッチが、今は全然美味しく感じられなかった。けれど、それはきっとこのサンドウィッチのせいじゃなくて、ぼくの気持ちの問題だ。
唾液がからからに乾いて喉を通らないサンドウィッチを、水で無理やり流し込んで食べた。
夕食を食べ終わって、歯を磨き終わった頃には、太陽はもう西の空に沈みかけて、あたりは暗くなってきていた。フョードルが電気式ランタンをつけると、明るい光がまわりを照らしたけれど、寒さの方はどうにもならなかった。
昼間は暖かかったのに、陽が沈むにつれて気温はどんどん下がっていって、今はとても寒かった。自分の服と、フョードルに貸してもらった服とにくるまっていなければ、ガタガタ震えてしまうような寒さだった。けれど、フョードルの大きな服は一枚一枚が布団のようで、とても温かかい。さらに、フョードルは布の上からぼくの足を揉み込んでくれたので、足からじんわりと昇ってきた熱が服の温もりとあいまって、とても気持ち良かった。
そこでふと、フョードル自身は一枚も布をかぶっていないことに気がついた。
ぼくとシャロンにくれた分で全部だったのだろう。そのことに今更気がついたぼくは飛び起きて、フョードルに服を返そうとした。けれど、フョードルは自分は大丈夫だからと言ってそれを受け取らない。
「俺の先祖はもっと寒い場所に住んでいたからな。その血を継いだ俺も寒さにはめっぽう強くて、この程度はまったく寒くない」
「本当にすごいんだよ。雪が降っていても半袖半ズボンでぴんぴんしてるの」
フョードルの言葉に続いて、シャロンも笑いながら言った。たしかに、フョードルが寒さに震えているような様子はまったくない。
ぼくに布をかけ直して「だから安心して休みなさい」と言うフョードルの言葉に、張り詰めていた意識がゆるゆると緩んでしまったぼくは、とたんに眠くなってきた。足の疲労もあいまって、その眠気はあらがうことができないほど強かった。それからすぐに外からもたらされる情報が途切れて、自分の足から伝わるじんじんとした熱だけを感じながら、ぼくの意識は眠りの底に落ちていった。
次の日の朝、ぼくは身体中にのしかかる怠さを感じながら目を覚ました。昨日の足の疲労は、筋肉痛へと変わっていて、足を動かすたびに痛みを感じた。昨日の夜にフョードルが念入りにマッサージをしてくれたので、そこまでひどい激痛ではなかったけれど、やはり完全に筋肉痛を防ぐことはできなかった。
いびきが聞こえて、その音がした方を見ると、シャロンが「ぐーぐー」と大きないびきをかいて寝ていた。昨日はちゃんと被って寝ていたはずのフョードルの服を蹴散らかして、身体のあちこちがはみ出している。
「おお、起きたか。おはよう。身体の調子はどうだ?」
フョードルはぼくよりも先に起きていた。その腕ではユミがぐずっていて、フョードルがせっせとあやしている。ぼくは、大丈夫だと答えると、ユミの顔をのぞき込んだ。
ユミはあまり夜泣きをしない子だった。たまにぐずってなかなか寝ないことはあるけれど、それでも『AlicE』に聞いていた一般的な赤ちゃんと比べれば、全然少ない方だろう。
けれど、今は髪と同じ茶色の眉を不機嫌そうにゆがめて、まだ歯の生えていない口から「えっえっ」とぐずり声をあげている。
「腹が減ったみたいでな。ミルクをつくろうと思っていたところだったんだ」
そう言うフョードルの手には粉ミルクと煮沸器が握られていた。
ぼくは、昨日の夜からずっとフョードルに負担をかけているのが申し訳なくて、少しでも休んでほしくて、代わりにミルクをつくらせてほしいと頼んだ。
フョードルは「なら、お願いしよう」と言ってミルクのつくり方をひとつひとつ教えてくれた。
「まず、煮沸器に水を入れて加熱する。沸騰する前に煮沸を終わらせて、少し冷ますように。その間に、哺乳瓶の方に粉ミルクの粉を10gだけ入れてくれ。あぁ、でももうその一杯分くらいしか残っていないか。全部入れてくれていい。お湯が冷めてきたら、出来上がり量の2/3くらいの量を哺乳瓶に入れて、蓋をつける。そうしたら、円を描くようにやさしく哺乳瓶を揺らして、粉をかき混ぜて溶かしていく。粉が溶けたら、最後に残ったお湯を出来上がり量だけ入れれば完成だ」
‥‥できた。フョードルの言う通りに進めていくと、ちゃんと粉ミルクが完成した。最初は自分でつくることが出来るか不安だったけれど、やってしまえば意外とできるものだった。
ふわふわとした心地よい達成感を味わいながら、フョードルからユミを引き受けると、ユミの口に哺乳瓶の乳首を持っていってやった。すると、ユミは待ってましたとばかりに乳首に吸い付いて、目をらんらんとさせながら夢中でミルクを飲みはじめた。
「本当にこの子はミルクが好きだな。いくらおとなしいと言っても、この様子じゃミルクをもらえなくなると泣き叫ぶかもしれん。もうミルクの残りはないから、はやいところ車まで行ってやらんとな」
フョードルは笑いながらそう言うと、シャロンが寝ているところに行って、シャロンを起こしはじめた。
ぼくは、ユミにミルクをあげながら、フョードルが言ったように、今日こそは絶対にゴールまで辿りつくのだとこころの中で固く誓った。
向こうでは、寝ぼけたシャロンがフョードルの顔面にパンチをお見舞いしていた‥‥。
◆
今日の移動は、昨日よりも早い時間にはじまった。サンドウィッチも昨日のうちに食べきってしまったので、朝食は抜きだ。
フョードルは地図を確認して、それをぼくとシャロンにも見せ、その読み方と使い方を教えながら、ぼくたちが今目指している場所を示してくれた。大体、車までの距離はあと六キロほどで、昨日と同じくらいのペースで歩けば三時間弱といった場所だった。
ユミの粉ミルクももう残っていないので、昼時までには絶対にここへ辿りつかなければならなかった。足の筋肉痛は、歩きはじめてしまえば意外と気にならなくなった。ぼくは、自分の足に「今日はもっと頑張ってくれ」と願いながら歩き続けた。
そうして歩き続けて、ぼくの足がまた疲労を訴え出したころ、若葉が萌える緑の大地の上に、ぽつんと不自然に白い点がぼくたちの視線の先に突然現れた。
一瞬、蜃気楼かなにかかと思ったそれは、近づいていくごとに少しずつ大きくなっていることから、幻ではなくたしかにそこにある実在の物だとわかった。その正体に気がついた時、ぼくの心は安堵と達成感に満たされた。あれは、車だ。
「車だー!やっと見つけたー!」
シャロンは、歓声を上げると、先に走り出してしまった。
ぼくはもうボロボロなのに、彼女のこの力は一体どこから来ているのだろう。心の底から尊敬の念を抱きながら、ぼくは自分のペースで歩き続けた。
車は、それまで一本道だった街道が二手に分かれる場所に静かに止まっていた。
日差しをさえぎる木陰もない場所だったので、日差しをめいいっぱいに受けた合成セラミックの白い外装はすこし熱を持っていた。
「よくがんばったな。昼は『AlicE』につくってもらったものを車の中で食べて、午後はそのまま車で移動しよう」
「さんせーい!お腹減ったよー‥‥、あ、でも先にシャワー浴びてくる!」
フョードルとシャロンに疲れた様子はなく、ふたりは車の中に乗り込むと、それぞれに準備をはじめた。きっとふたりは、ぼくがいなければそのまま歩き続けるつもりだったのだろう。
ぼくは、やっと休むことができるという喜びの気持ちより、ふたりの予定を変えてしまった申し訳なさが強かった。
昼食を終えたぼくたちは、フョードルが運転する車で先を進みはじめた。歩いているときにはゆっくりと流れていた景色が、今はあっという間に流れていく。
車はやっぱり快適だった。けれど、今のぼくは車を使っていることが、なんだかとても嫌だった。
はじめに車を使わず歩くことが決まったときには、歩くことのほうが嫌だったのに、今は、ぼくの目の前をまたたく間に流れていく景色が惜しくてたまらなかった。その景色の中に、まだ見ぬ宝が混じっているような気がして、車に乗っているとそれをみすみす見逃しているように思えて悔しかった。
けれど、車に乗って緊張の糸が緩んだことで、足の疲労は強力な睡魔となってぼくの意識を襲ってきた。
ぼくは、うとうとして自分の頭が揺れているのがわかったが、いくら目を開けていようとしても、まぶたはどんどん重くなっていく。
そんなぼくの様子に気がついたフョードルは、「少し休んでいなさい」と言って毛布を渡してくれた。
そのぬくもりは睡魔をさらに強め、車の外の景色にすがりついていたぼくを深い眠りへと落としていった。
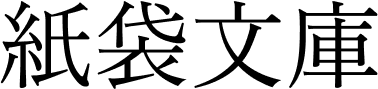


.png)
.png)