マルーン
第三章 ぼくが生まれた意味
生まれてはじめて赤ちゃんを見た。赤ちゃんは、『AlicE』によってすでに取り上げられ、白いふわふわの布に包まれて寝台の上に寝かされていた。赤ちゃんの体は信じられないほど小さくて、そのハムのように膨れて線が入った短い手足を縮こませて眠っている。ふっくらとした頬と、もごもごと動く小さな口は微笑んでいるように見えた。
そのかわいらしい姿に、ぼくは自分の頬が緩んでいるのがわかった。シャロンもその手にやさしく触れ、自分の指を握らせてうっとりとしている。
そっと手を伸ばし、赤ちゃんの柔らかな頭を撫でた。茶色の産毛が生えた頭は柔らかく、ポワポワとしていて温かかった。
この小さな存在が、信じられないほど愛おしかった。
ぼくたちが赤ちゃんに夢中になっている一方で、老人たちの顔は暗く憂鬱そうだ。ぼくにはその理由が分からなかった。こんなにかわいい赤ちゃんが産まれたのに、どうしてそんな暗い顔をしているんだろう?
赤ちゃんが寝ていることも気にせず、老人たちは話しはじめた。
「産まれてしまったか‥‥」
「ほんとうについさっき産まれたようですよ。病院で『AlicE』の無痛分娩を受けなかったから、陣痛に襲われて叫んでいたところを見つかったそうです」
「で、母親はあんな調子か」
赤ちゃんの母親は、ガリガリに痩せ細った若い女だった。若いと言っても30歳くらいで、ぼくやシャロンほどではないけれど、彼女も『残される者(マルーン)』の一人だった。
「アー、うるさいなァ。アタシだって産みたくて産んだわけじゃねーっての」
赤ちゃんと同じ茶色の髪の毛をがしがしと掻きまわしながら、母親は苛立ちを隠さないような声で怒鳴った。
「堕そうとしたんだけど上手くいかなかったんだよ」
母親が言っていることの意味はわからなかったけれど、この女がなにかとてもひどいことを言っているということは分かった。周りの老人たちも女を冷めた目で見ていたが、その視線にはどこか同情のようなものも含まれているようだった。
「じゃあ、この子を育てるつもりはないんだな?」
「ああ、ないない。好きにしなよ」
女は一度も赤ちゃんの方を見ることなく、心底煩わしそうに手を振ると、部屋に備えられた椅子に座ってノイズキャンセリング付きのヘッドフォンをつけてタブレットを見始めた。
「では、やはり安楽死しかないな」
「そうですな」
老人の一人が言い放った言葉に、ぼくとシャロンは同時に振り返った。いま、彼らはなんと言った?安楽死?だれを安楽死させるんだ‥‥?母親‥‥?老人の誰かか‥‥?いいや、さっきの会話の主体は赤ちゃんだったはずだ。ということは、彼らが話しているのは赤ちゃんのこと‥‥
一瞬のうちにそこまで思考が走って、彼らが赤ちゃんになにをしようとしているのか気がついたぼくは、赤ちゃんが寝ているのも忘れて、反射的に大声を出していた。
「なんでだよ!!」
はじめてこんな大声を出した。静かな寝息をたてて眠っていた赤ちゃんは泣き出してしまい、老人たちも、ぼくの大声に驚いて、ぼくの方へと顔を向けた。こんな大声で話すのははじめてで、自分の声にびっくりしながらも、ぼくはまくしたてた。
「元気じゃないか!なのに、なんで殺そうだなんて言うんだよ!せっかく産まれたのに!」
はじめのうちはぼくの怒声に慄いていた老人たちは、少しずつ落ち着きを取り戻したようで、老人たちの中でも特に体が衰え、全身を車椅子から伸びる管につながれた老人が、マイクロチップ越しで静かに話しはじめた。彼は、もう自分で口を動かすこともできないのだ。ぼくの激しい口調との差が、赤ちゃんの命に対する姿勢がそのまま表れているようで心底不愉快だった。
「まだ宇宙の終わりまであと八年もある。この子はこのまま育てばわずか八歳で宇宙の終わりを迎えることになるんだぞ。それは、とても苦しく辛いはずだ。しかし、今ならまだこの子に自我はないから、受ける苦しみは少なくてすむ」
老人の言葉に、ぼくはひるんでしまった。たしかに、この子はこのまま育てばあと八年しか生きられないことになる。八歳の自分を思い出してみると、たしかにその頃にはもう自我もあったし、記憶もはっきりとしている。物の好き嫌いもはっきり自覚していて、どんなときに自分が楽しいと思うかや、どんなときに自分が苦しいと感じるかもわかってきていた。八歳の自分は、いまの僕にとても近い存在だった。
考えてみれば当然のことだけれど、この子は今のぼくよりも幼くして死ななければならないのだ。それは、この子にとってはたしかに苦しいかもしれない。
でも‥‥、
「でも、いまはこんなに元気なのよ!それを殺すなんて‥‥、かわいそうじゃない!!」
シャロンが、ぼくの思っていたことを言ってくれた。そうだ、かわいそうなのだ。少なくとも今はこうして元気に生きている子が、なにもわからずに殺されるのは、どう考えてもかわいそうだ。たとえ、遠くない未来に死ぬことが決まっているとしても、今ここでこの子の命を奪うのは、間違っているはずだ。
けれど、ぼくたちのそんな主張は老人たちには届かなかった。
「しかし、もしこの先この子が育って、自分の最期のことを知ったらどうだ?それで絶望したらどうするんだ?八年という年月は、自我を育てはするが、死と向き合えるだけの長い時間ではない。長く生きてきたわたしたちですら、その恐怖と向き合えていない者がほとんどだ。成長して自我のある人間のことは、わたしたちも安楽死させられない。そもそもわたしたちの命はもう長くない。みんなもってあと二、三年だろう。この子をおいて先に死んでいく。そうなると、この子に残された道は、宇宙の終わりという悲劇にひとりで怯えながら死んでいくことだけ。もしくはそこの母親や他の『残される者(マルーン)』と同じように、やさぐれて薬におぼれるか、自殺するかだ。‥‥そんな未来を生きる方が、よっぽどかわいそうじゃないか?」
ずきり、と胸が痛んだ。死ぬ、薬におぼれる、自殺‥‥、突然出てきた強い言葉も恐ろしかったけれど、それよりもこの老人が、赤ちゃんを通してぼくを見て話していることに気がついて、そのことに傷ついた。
この言葉は、彼らが“ぼく”に対して抱いている感情だった。
“どうして産まれてきてしまったのだろう、かわいそうに”
“最後まで生きられないなんて、かわいそうに”
“遠くない未来に必ず死んでしまうことがわかっているなんて、かわいそうに”
“それまでは絶望して苦しむだろう、かわいそうに”
それが、ぼくがずっと、老人たちの視線の中に感じてきた哀れみの正体だった。
本人たちにそのつもりはないのだろう。あくまで赤ちゃんのことを指していっている。けれど、十一年の違いはあっても、ぼくもまた『残される者(マルーン)』だった。この子ほどじゃなくても、長くは生きられない。
「でも、だめなんだよ!!」
ぼくは、自分の身のうちに生まれた激情のまま叫ぶ。
「ぼくは、今みんなの言っていることを認めるわけにはいかないんだ!!」
あの子の命をぼくが否定するということは、ぼくや、シャロンが産まれたことを否定するということだから。
理屈の押し合いなんかで、大人に勝てるわけがなかった。そもそも、いまぼくを突き動かしているのは、理屈じゃなく感情だ。ここで引くわけにはいかなかった。
あの子の命を守らなければ、という一心でぼくはただ叫び続けた。
それは、もちろんあの子に生きてもらいたいからだけれど、ぼくを守るためでもあった。
言い争うぼくたちのところへ、おじいがやってきた。
ぼくは、おじいが来たことで、なにか話の流れが変わるのではないかと淡い希望を抱いて、おじいを見た。
周りの老人たちから話を聞いたおじいは、眉を寄せた顔になると、短く「そうか‥‥」とだけつぶやくと、ぼくたちの方へ来て、目線をぼくたちに合わせるために膝をおった。
その瞳の中には、やっぱりあの哀れみがたたずんでいた。
「あの子は安楽死させる」
全身の力が抜けていく。
膝が崩れて、眼の焦点が定まらない。
「病院へ運びなさい」
「やめて!!そんなのだめ!!」
「子どもは黙っていなさい」
おじいの賛成を得た老人たちは、諦めずにはげしく反抗するシャロンを押さえると、大人だけが使える、魔法の言葉を使った。ぼくたちの首を絞めて言葉を出せなくする、魔法の言葉を。
「生きてるのに!!今は生きてるのに!!」
シャロンが叫んだ。その言葉で、崩れかけたぼくのこころはもう一度形を取り戻して、叫びをあげた。
「おじい!!どうしてぼくのことは生かしたんだよ!!ぼくだって、かわいそうな子なんだろ!?」
答えを期待して言ったわけじゃない。ただ、なにもできない自分の無力さに耐えられなくてとっさに叫んだ言葉だった。しかし、その答えは思いがけないところから返ってきた。
ぼくの怒声に答えたのは、思うように事態が進まず、輪の端っこでイライラしていた老人だった。
「お前は産まれてから見つかるまでに時間がかかっちまって、見つけたときには自我の片鱗が確認されたんだよ。だから、安楽死させずにそのまま生かすことに決めたんだ。べつにお前が特別だったわけじゃない。満足したか?」
「おい!やめろ!!」
悪意に満ちた顔でぼくを見下ろす老人に、おじいが殴りかかるような勢いで止めに入った。
けれど、もうぜんぶ聞いてしまった。
こんどこそ、ぼくのこころは完全に崩れてしまった。形作っていたものがぼろぼろと大きく崩れて、その隙間からまるで血のように、悲しみや怒り、虚しさが噴き出した。
ぼくの問いに答えた老人を、おじいが平手打ちするのが見えた。これまで、そんなふうに暴力を振るっているところはもちろん、怒りをあらわにしているところさえ人に見せたことのないおじいのその行動に、叩かれた本人はもちろん、まわりの老人たちも驚いていたようだけれど、いまのぼくにはそんなことはどうでもよかった。
おじいは、ぼくの方に歩いてきて肩に手を乗せると「いまの言葉は忘れなさい」とだけ言い置いて、またまわりに指示を出しはじめた。
「行きなさい。処置は早い方がいい」
「しかし、『AlicE』の幼児用の安楽死システムは停止していて、再起動までに少し時間がかかってしまいます」
「なら、すぐに起動しなさい。絶対に不具合がないように。苦しみを味わせたくはない」
おじいの言葉で、ぼくたちを押さえていた老人たちとは別の老人たちが、泣き続けていた赤ちゃんを抱えると部屋を出て行ってしまった。
あとに残ったのは、シャロンの泣き叫ぶ声だけだった。
結局、母親はほんとうにただの一度も、赤ちゃんを見ることはなかった。
◆
老人たちが赤ちゃんを連れて行ってしばらくした後、ぼくたちも解放された。けれど、ぼくたちは顔を上げることができなかった。歩みは遅く、ぼくたちの周りの空気は言いようのない虚しさで満ちていた。
どこに向かおうという意思もなく、屍のように歩いていると、ほんとうにたまたま、シャロンがコロニーに来た日に一緒に話をした広場に行き当たったので、ぼくたちは重い足を引きずって、あの日と同じベンチに腰を下ろした。
しばらくの間、ぼくもシャロンも無言だったけれど、ぼくは、歩きながら自分のこころを整理していくなかで感じたことを、少しずつ話しはじめた。
「はじめて聞いたよ。ぼくが、本当ならあの子と同じように安楽死させられそうになっていたなんて。たしかに、おじいたちがぼくを見つけたのは、産まれてから少し経ってからだったことは聞いてた」
地面の一点をぼーっと見ながら、ぼくは言葉を続ける。
「‥‥でも、まさかもっと早く見つかってたら殺されてたなんて、思ってもいなかったよ」
ぼくの言葉に、シャロンは申し訳なさそうな顔になって、ますますしょんぼりとしてしまった。いつもの明るく天真爛漫な様子は見る影もない。
「わたしは、恵まれてたんだわ」
シャロンもまた、つぶやくように話しはじめた。
「わたしもね、ほんとうの親は知らないの。産まれてすぐに、ぼろ布にくるまれて捨てられていたところを、ほんとうにたまたま、フョードルが助けてくれたんだ」
はじめて聞く話だった。たしかに、シャロンの光を透かす綺麗な金髪は、フョードルの茶色の髪とは似ても似つかないし、体格など言わずもがなだ。けれど、それは単にシャロンは母親に似ているのだろうと思っていた。
それがまさか、本当の親子じゃなかったとは。
「『AlicE』の保育システムどころか、旧式の保育システムもなしに捨てられてたんだよ。生きてたのが不思議なくらいだったってフョードルには言われた。でも、逆に言えば、本当の親が捨ててくれたから、わたしはフョードルと親子になれたし、フョードルと一緒に、いろいろなものを見ることができた。‥‥生きることが楽しいと思えるようになった。だから、“わたしは恵まれていたんだな”って‥‥」
「だって、すぐに死んじゃったら、そういうことも思えないもの‥‥」
シャロンはそうつぶやいて顔を俯かせると、また黙り込んでしまった。
ぼくは、その通りだと思った。
あの赤ちゃんの母親の態度を見た時、ぼくはそこに自分の母の姿を見た気がした。母の記憶が残っているわけもないけれど、自分の産んだ赤ちゃんが連れて行かれてしまうというのに、まったく興味も関心も示さなかった母親を見て、「きっとぼくも、ああやって産まれてすぐに捨てられたのだろうな」と漠然と感じ取ったのだ。
ぼくはシャロンとはちがって、外の世界のことはまったく知らなかったけれど、それでも殺されることなく、今この時まで命をつなげることができた。
今にして思えば、これは奇跡のようなことだったのだ。
───外の世界のことは知らなかった。
今ではそれすら違っているように思う。
シャロンの話を聞いて、ぼくは外の世界へのあこがれを自覚したけれど、そもそもシャロンに話を聞く前にも、外の世界のことを知る手段はまったくなかったわけじゃない。ぼくは、“外の世界のことを知らなかった”んじゃなくて、そもそも“外の世界のことなんて知ろうとしてこなかった”んだ。
ぼくには、そのチャンスがあったのに。
「僕も、もっとこの世界を‥‥、“自分が生きる意味”を、知ろうとすればよかったな‥‥」
口をついて出たつぶやきは、言葉にすると、鈍い痛みとなってぼくのこころの中に広がっていった。
ぼくは、シャロンのようにたくさんの本を読んだわけでもなければ、音楽を聴いたわけでもない。『AlicE』のなかに残されたものは少なかったから。けれど、ゼロではなかったのだ。220年前の事件後、消失されたデータのうちで復元に成功したものが、数は少ないものの残されていた。
ひとつもなかったわけじゃないのに、ぼくはそれに触れてこなかった。
物語や音楽だけじゃない。ぼくに勇気さえあれば、この足でコロニーを出て、外の世界を見ることだってできたはずなんだ。
───もっと物語に触れていれば、
───もっと音楽を聴いておけば、
───もっと外の世界へと足を運んでいたら、
ぼくが見る世界も、シャロンが見る世界のように、輝いて見えたのだろうか。
───ぼくには、それをたしかめるだけの時間があったはずなのに。
そうだ。いくら最後まで生きられないとはいえ、僕には時間があったのだ。
すくなくともあの赤ちゃんのように、物心もつかぬうちに、腫れた瞼を開いて世界をその目で見る前に、その命を終えるようなことはなかった。
そのことに気が付いたとたん、せき止められていた水があふれ出すように、ぼくのこころに後悔の感情が流れ出した。
───どうして、ぼくはもっとこの世界のことを知ろうとしなかったのだろう
───どうして、ぼくはもっとこの世界に向き合ってこなかったんだろう
───どうして、ぼくはもっと自分の命と向き合ってこなかったんだろう
───どうして、ぼくは、今更そのことに気づいてしまったのだろう?
次から次へと押し寄せてやまない後悔の感情と自分への虚しさに、涙が溢れて止まらなかった。ぼくのこころは、もう取り戻すことができない過去に囚われて、もう何をすることもできなくなりそうだった。
「まだ!」
ただただ無力感と果てしない後悔にさいなまれていると、突然それを引き裂くような大きな声が響いた。
「まだ、間に合うよ!」
シャロンは震えた声で、ただ涙を流すことしかできないぼくの目を見ながら、言葉を繋いだ。
「まだ八年ある!たくさんのものを見て、聞いて、考える時間はあるよ!わたしたちと一緒に、外の世界を見に行こう!‥‥“わたしたちが生まれた意味”を、見つけに行こう!!」
また、ぼくの心の弱い部分が、「今更そんなもの見つかるわけない」と声を上げた。あの全身を管に繋がれていた老人が言った通り、八年という時間は短い。そんな時間で、いったい何を見つけられるというのだろう。あれだけ長い時間を生きた老人たちが、それを見つけられず、今ももがき苦しんでいるというのに。
けれど、その時、ぼくはシャロンの青い瞳が揺れ動いていることに気がついた。
目の前のシャロンは、いつもの自信満々な彼女ではなかった
その目は不安に揺れ動き、綺麗な形の眉がきゅっと少し眉間に寄って、口だけはぼくの前で強がるように、不器用に笑みを浮かべている。
彼女自身も、戦っているのだ。自分が生まれたことを、必死に肯定しようとしているのだ。
──ぼくは、、また逃げるのか?
そんなことをして、ぼくは最期に後悔しないか?いいや、必ず後悔する。だって、今さっきそれで後悔したばかりじゃないか。
過去は変えられない。この後悔を消すには、これから先の人生で同じ過ちを繰り返さないようにするしかない。
ぼくは、口から出かかっていた「無理だ」という言葉を飲み下し、心の中で静かに決意を固めた。
そうだ、ぼくは、ちゃんと生きるんだ。最期の時に、満足して眠れるように。
「二人とも、どうしたんだ?」
突然、広場の入り口の方から低く野太い声が響いた。これもまた、シャロンがやってきたあの日と同じだった。
広場の入り口で、フョードルが気遣わしげな様子でぼくたちのことを見ていた。
フョードルの姿をみとめたシャロンは、その瞳にぶわっと涙を溢れさせると、一目散にフョードルの方へ走って、ぼくがいままで見てきた中で、いちばん鋭いタックルでフョードルに向かって飛び込んでいった。
◆
「なるほどな。だから、病院がバタバタしていたわけか」
フョードルに一連の出来事を話すと、彼は納得したように頷いた。フョードルは、今まで病院に行っていたのだろうか?同じように疑問に思ったらしいシャロンが口に出して聞いた。
「フョードル、病院に行っていたの?」
「ん、ああ。まあ、ちょっとな。しかしそんなことより、大変なことになったものだな‥‥。赤ん坊か‥‥」
フョードルはシャロンに聞かれたことに曖昧な返事をすると、すぐに話を流してしまった。シャロンはその様子に若干の不満を感じたようだったけれど、フョードルが赤ちゃんの話をふったことで、シャロンもそっちの方に気を向けたようだった。
「なんとか、赤ちゃんを助けることはできない‥‥?」
「うむ‥‥」
フョードルは考え込むように腕を組んで口に手を当てて、唸りはじめた。しかし、しばらく考えたうえで、フョードルは首をゆるゆると振った。
「むずかしいと言わざるを得ないな‥‥。そもそも、御老公たちは、俺が反対したところで聞いてくれないだろう」
むかし、捨てられていたシャロンを拾ったフョードルのことだ。決して、赤ちゃんの安楽死に思うところがないわけではないのだろう。けれど、フョードルはこのコロニーでは新入りだった。仮にフョードルがぼくたちと一緒に、赤ちゃんの安楽死に反対したとしても、新入りの意見を老人たちが聞くとは思えない。
それに、もしフョードルやシャロンが、これから先もこのコロニーで生きていくのなら、老人たちの二人への印象も悪くなるだろう。
「そんなの、フョードルの怪力でぱぱっと助けちゃえばいいじゃない!」
「無茶を言わないでくれ‥‥、このコロニーにはいられなくなるぞ‥‥」
この街には、ぼくが知っている限り一度も使われたことはないが、治安維持用の防衛システムも備えている。いくらフョードルが強いと言っても、コロニー5のすべてを敵に回して生きていけるとは思えなかった。
「赤ちゃんを助けて、そのままコロニーを出ちゃえばいいじゃない!そもそもなんでコロニーになんか来たのよ!わたしはこのコロニーに未練はないわ!」
「トーマとはお別れしないといけなくなるぞ?」
シャロンは、はっとした様子でぼくの方を振り返った。そうしてぼくの顔を見て、視線を下げてしまう。
「それは‥‥」
今だ。言うなら、今しかない。ぼくは、震える喉で唾を飲みこんで、口を開いた。
「ぼくは、一緒に行くよ」
頭が沸騰するように熱くなるのを感じた。鳥肌が立って、身震いしそうになる。
ああ、言った。言えた。どうなるかは分からないけれど、とにかく言葉にすることができた。
シャロンはぱっと笑顔を浮かべ、フョードルは、ぼくがそんなことを言うとは思ってもいなかったのだろう。目を見開いて驚いた様子だった。
「トーマ!」
「‥‥本気か?この街は、トーマの故郷だろう」
「いいんだ。ぼくも、外の世界が見てみたいんだ。それに‥‥、」
飛びついてくるシャロンを押さえながら、フョードルの目を見る。
「あの子を絶対に助けたい」
最期まで生きられないから、数年の命だから、生きている意味がないだなんて、認めたくなかった。
幸せになれないだなんて、認めたくなかった。
ぼくは、それを諦めたくなかった。
「しかし、俺は‥‥」
口ごもってしまったフョードルに、シャロンが涙を流しながら言う。
「フョードル、わたしもあの子を見捨てられない。あの子を見捨てたら、わたしは、自分を許せなくなる‥‥。生きている意味を見失っちゃうわ‥‥」
顔を手で押さえながらうなり続けていたフョードルは、シャロンのその言葉であきらめたように天を仰ぐと、「これも俺に与えられた試練か‥‥」とつぶやいて、赤ちゃんを助けることに協力してくれると言ってくれた。
その目からは、さっきまでの迷いや苦悩は消えて、決意の光が宿っていた。
◆
病院は、集会所と同じようにコロニーの中心近くに建てられている。集会所よりもずっと大きく、コロニーのなかでは一番大きな建物だ。自宅での生活ができなくなった老人たちを受け入れるため、大きく設計されているのだ。
ぼくたちは、広場から病院へと急ぐと、赤ちゃんのいる場所を探した。広い院内で赤ちゃんのいる部屋を探すのは手間がかかるかと思ったが、人だかりとなった老人たちが目印になって、すぐに見つけることができた。
「また来たのか」
病室に入ってきたぼくたちを見て、老人の一人がつぶやいた。もうこれ以上、言い争うようなことはしたくないのだろう。その顔には疲れが浮かんでいた。しかし、ぼくたちの後ろにフョードルがいることがわかると、その顔はぴしりと固まった。この二ヶ月間で、老人たちはフョードルが暴力を振るうような乱暴な人間ではないと分かっているはずだったが、それでもぼくたちと一緒にやってきたフョードルを内心怖がっているようだった。
「どうしたんだい、フョードル」
固まってしまった老人たちの中で、おじいだけがきっぱりとした態度で前に進み出てきた。その目に、恐怖の感情はかけらも映っていない。
「突然、申し訳ありません。二人から事の一部始終を聞いて、いてもたってもいられなかったもので」
「わたしたちを止めるのかい?」
「止めなければと思っています」
フョードルの言葉に、老人たちの顔がさらに引きつるのがわかった。フョードルは片手をあげて静かに続ける。
「勘違いしないでください。暴力なんて使いません。話し合ったうえで、その子を私に任せていただきたいのです」
「わたしたちの意見は、もう固まっているよ」
「それでも、どうか私にその子をお預けください。わたしには、そう言わなければならない義務がある」
フョードルは、おじいやまわりの老人たちの目を見ながら、一点の曇りもない声で言った。
「なんの義務だい?」
「親としての義務です。私は、シャロンの親として、あなたたちの決定には反対しなければならない」
フョードルは、決然とした態度で言葉を告げた。フョードルもわかっているのだ。この赤ちゃんの命を否定することは、シャロンを否定すること、ひいてはフョードルがシャロンを助けたことをも否定することになると。
おじいは、フョードルの言葉にはじめて言葉をつまらせた。その顔は少し引きつっているようにも見えた。
「御老功たちの意見は理解できます。宇宙の終わりまでの時間は八年。八歳というと、個性も見えてきて、自己主張もする可愛い時期だ。そんな子が、死の恐怖に向き合って絶望するのが耐えられないという気持ちは、痛いほどわかります」
たしかに、老人たちのほとんどは、あの母親のように赤ちゃんに無関心だから殺そうとしているわけじゃない。むしろ、赤ちゃんのことを彼らなりに考えた結果がこれなのだ。
けれど、ぼくたちにはそれを否定しなければならない理由があった。
「しかし、その子が八年で幸せになって、自分の死にちゃんと向き合えるようにならないとは限りません」
「楽観的がすぎるよ。わたしたちほどでなくとも、長く生きてきたきみならわかるだろう。八年なんていう時間は、あっという間だ。ましてや子どもにとっての八年など、なにも考えられないに等しい。‥‥誰もが君のようになれるわけじゃないんだ」
おじいは、あくまで認めない。けれど、その言葉がただ感情に任せたものじゃないことは、ぼくにもわかる。おじいの言っていることはきっと“正しい”。ぼくは十一年生きてきたけれど、自分の命に向き合ったことなんて一度もなかった。ぼくだけじゃない。きっと、ほとんどの人間がそうだろう。だから、たった八年で自分の命と、死と向き合えるようになるはずがないというおじいの考えは、きっと”正しい”のだ‥‥。
「そもそも、きみがこの子の面倒を見るというが、きみはもう‥‥」
そこまで言って、おじいははっとすると、「すまない、言葉がすぎた」と言葉を切り上げた。その様子には違和感があったけれど、おじいがすぐに赤ちゃんの話に戻したので、その違和感のことはすぐに頭から離れてしまった。
「しかし、実際問題この子を育てていくとなると、いつかきみだけでは手が回らなくなるだろう。シャロンの手を借りるだけでも足りまい。それになにより、八年という短い時間のなかで、どうやってこの子に希望を与えるつもりなんだい。この閉ざされたコロニーの中で」
来た。いよいよ、ぼくたちの本題につながる切り口になりそうな話になった。ぶわっと鳥肌がたって、心臓の鼓動が耳にうるさく響く。喉もからからに乾いてきた。
「トーマが手を貸してくれるというので、彼の助力を得るのと、『AlicE』の保育機構を頂けないかと考えています」
「ふむ‥‥」
「『AlicE』の保育機構が、本来コロニーの共有財産であることは承知しています。しかし、今このコロニーにいる幼児はその子だけです。ですから、私たちに保育機構を譲っていただきた」
「‥‥そうだね。それならかまわないよ」
おじいは迷うことなくすぐに決断をくだすと、いよいよ本題とばかりに、赤ちゃんの未来の話に踏み込んだ。
「それじゃあ、肝心のこの子が生きる希望を見つける方法を聞いてもいいかな?」
どくん、どくん、と心臓の音がうるさい。鼓動するたびに、心臓が口から飛び出しそうだった。
「そのことなのですが」
フョードルは丁寧な口調で話を切り出した。
「わたしたちは、『見届ける者(ゲイザー)』として復帰するつもりです。その子と、‥‥トーマを連れて、もう一度コロニーの外で生きようと思っています」
フョードルの言葉に、おじいは今度こそ顔を引きつらせた。そして、ぼくの意思を確かめるかのように、勢いよくぼくの方へ顔を向けた。
ぼくは、体が震えるのを抑えながら、決しておじいから目をそらさずに、こくりと頷いた。
ぼくの反応を見たおじいは、もう一度フョードルの方へ向き直ると、今まで見たことがないほどの剣幕でフョードルに詰め寄った。
「馬鹿な!君は、自分の手に余るものを抱え込むつもりかい!?それは君の我儘でしかない!!そんなものに振り回されて何になる!!その先に待っているのは身と心の破滅だ!!それになにより、君の我儘のあとで放り出されるこの子たちはどうなる!!」
「御老功が仰られたとおり、これは私の我儘です。この子たちに、この理不尽な世界で、それでも生まれてきたことに喜びを見出してほしいという、私の我儘‥‥。私一人で考えていれば、きっと私はこの件についても見てみぬふりをして過ごしたでしょう。‥‥私自身もシャロンのことが気がかりで、同じ年頃のトーマがいるこのコロニーへとやってきましたから」
はじめて聞く話だった。フョードルは、ぼくがいたからこのコロニーにやって来たのか。
シャロンも、思いがけず自分たちがコロニーへ来た理由を知って驚いた顔をしている。
「二人からこの話を聞いた時にも、すぐに決断することはできなかった。あなたの言うように、これはあまりに無責任な行動だと思いましたから‥‥。しかし、トーマが決断してくれたおかげで、私も覚悟を決めることができました」
フョードルは、あの決意をたたえた強いまなざしでおじいをすっと見すえて、はっきりと言葉を告げた。
「私は、『見届ける者』へと戻ります。そして、この子たちに外の世界を見せます。彼らがそこに、生まれた喜びを見出せるように。‥‥十二年前にシャロンの親になることを決めた時から、私の道は決まっていたのでしょう」
おじいは、長いことフョードルのことを睨んでいたけれど、フョードルの決然とした態度に大きくため息をつくと、「君とは良い話友達になれると思ったのだけれどね‥‥」とつぶやいた。
「君の考えはわかった。もう止めはしないよ。‥‥わたしに止められるはずもない。けれど、最後にトーマの意思をちゃんと確認しておきたい。一時の気の迷いだった場合には、さすがに止めなければいけないからね」
おじいはそう言うと、フョードルからぼくへと目を移した。おじいの目は、ぼくの心の底まで見通そうとするかのように、静かに澄んでいる。ぼくのこころは、その目に射すくめられたように固まってしまった。
“やっぱりだめだ、言えない”、“おじいを納得させるだなんて、ぼくには無理だ”、“怖い”、“逃げたい”‥‥。次々とこころに弱音が浮かぶ。のしかかってくる重圧に、胃がひっくり返りそうだ。ぼくは、たまらなくなって、おじいの視線から目をそらしてしまった。ああ、やっぱり、ぼくはだめなやつだ‥‥。
恐怖と自分への失望感に思考が落ちていくなかで、ぎゅっと、腕を握られる感覚がした。はっとして、掴まれた腕を見ると、シャロンがぼくよりも強い不安に染まった顔で、ぼくの腕に縋りついていた。
その顔を目にした途端、ぼくの頭の中に、どこからともなく、熱湯のような熱さを持った思いが突然湧いてきた。それは、一瞬でぼくの頭を染め上げると、こんどはぼくのこころの中へと移って、その場所をも満たしていく。さっきまでその場所を満たしていた不安や恐れは、その思いがあっという間に飲み込んでいった。
“この子の前で、格好悪い姿は見せられない”。
それは見栄だった。好きな子の前で、カッコつけたいという、男のしょうもない見栄。けれど、それで十分だった。そんな見栄のおかげで、ぼくの心はもう一度立ち直った。
ぼくは、ぼくの腕を掴むシャロンの手の上に自分の手を重ね、その青い瞳に強くうなずいた。もう大丈夫だ、と伝えるために。
おじいの方へ向き直って、水のように静かにたたずむその目を見た。その目を見ると、また不安や恐怖が生まれてきたが、かまうものか。
おじいは、ぼくの目を見て問いかけてくる。
「本当に、フョードルたちについて行くつもりなのかい?」
「うん」
言葉を発し始めると、なんだか妙に頭が澄み渡っていくような気がした。こころはまだ熱く激っているのに、頭は冷たく澄んでいる。まるで、今まで見えなかったものが見えるようになったような、そんな感覚だった。
「外の世界は、このコロニーの中とちがって、生きていくのは大変かもしれないよ?」
「でも、行きたいんだ」
「‥‥どうしてだい?」
今なら、自分の気持ちをうまく言葉にできそうだった。
「さっき、赤ちゃんの家で、ぼくが本当はその子と同じように安楽死させられるはずだったって聞いたとき、ぼくは、「あぁ、ぼくが生まれてきた意味はなかったんだなぁ」って思ったんだ」
「そんなことは‥‥」
おじいが訂正しようしたのを遮って、ぼくは続けた。
「ないんだよ。今のぼくには。だって、誰からも望まれずに生まれて、誰からも愛されてないとしたら、他の誰かがぼくの命に意味を与えてくれるわけじゃないから」
鏡のような水面に風が吹いたように、おじいの瞳が揺らいだ。
「おじい言ったよね?「ぼくが本当は安楽死させられるはずだったことは、忘れなさい」って」
おじいは言葉を返さない。ぼくはかまわず続ける。
「でも、そんなことできないよ。自分が、誰からも必要とされずに生まれた存在で、今も生きている意味がないことを知ったのに、それを忘れるだなんて‥‥。そんなこと、できるわけない」
そうだ、ぼくは知ってしまった。自分の命が、たまたま繋がっているものなのだと。そして、ぼくの命はいま、どこにも寄る辺なく、ただ空を漂っているだけということも。
ぼくはこの命の寄る辺を、自分で見つけ出さなければならないのだ。
「だから、ぼくは自分で、ぼくが生まれた意味を見つけなくちゃならないんだ」
生まれながらに誰かに意味を与えてもらえないのなら、ぼくのような人間は、自分で自分の生まれた意味を見つけ出さなければならないのだ。他人に拠らない、自分を認められる理由を。
「このままここに住んでいたら、ぼくはきっと、一生自分が生まれたことを認められないまま死ぬんだ」
そんなのは嫌だった。生きる理由や意味なんて、今まで気にもしたことがなかったけれど、一度その意味を考えてしまったら、もうそこから目を逸らすことなんてできなかった。
「だから、ぼくも探してみたいんだ。ぼくが生まれた意味を、生きる理由を。外の世界で」
おじいはおずおずと口を開いた。
「‥‥そんなものがなかったとしたら?その道はもしかしたら、途中で行き止まりに当たるかもしれない」
「そうかもしれない。でも、なにも持たないいまのぼくは、それがあることを信じたいんだ。‥‥人生をかけて」
「‥‥」
「おじい。ぼくは、シャロンたちと外の世界に行くよ。そして、ぼくが生まれた理由を探すんだ。ぼくが、自分が生まれてよかったと思えるものを」
ぼくは、おじいの目から一度も目をそらすことなく、おじいに自分の思いを言い切ることができた。
おじいは静かにぼくを見つめていたけれど、やがて静かに息を吐き出すと、ぼくの目を見て言った。
「わかったよ」
ふっと緊張の糸がゆるんで、体から力が抜けるのを感じた。いつの間にか握り込んでいた拳の掌には、汗をびっしょりとかいていて、どっと疲れが押し寄せてきた。
「それでは、その子を私たちに任せていただけますね?」
「‥‥ああ」
おじいが院内の看護ロボットに指示を出すと、ロボットは綺麗な白い布で包まれて眠っている赤ちゃんをフョードルにやさしく手渡した。
フョードルの赤ちゃんの抱き方は様になっていて、赤ちゃんもぐずることなく気持ちよさそうに眠っている。
「ただ、私たちが来たシュヴィーツという場所は、アルプス山脈の麓にある山間の場所で、この時期に長距離を移動することはなるべく避けたいので、コロニーを出ていくのは春先まで待っていただけると助かります」
「‥‥かまわないよ。別にわたしたちは、きみたちを追い出したいわけじゃないからね。もし、気が変わればいつでも言ってくれ」
おじいはこくりと頷くと、もう一度ぼくの方へと顔を向けた。
「トーマも、本当にいいんだね」
ここが、分かれ道だと思った。ぼくは自分の決意に任せて、こくんと頷いてみせた。
おじいは、ふっと少し息を吐いて少しうつむくと、なにも言わなくなってしまった。その反応は、ぼくを責めているようなものではなかったけれど、それを見たぼくのこころは、なぜか無性にざわついて、うまく言葉にできない、複雑にからみ合った感情が胸におこったのを感じた。
沈黙のなかで、赤ちゃんの静かな寝息だけがかすかに聞こえていた。
マルーン
第三章 ぼくが生まれた意味
生まれてはじめて赤ちゃんを見た。赤ちゃんは、『AlicE』によってすでに取り上げられ、白いふわふわの布に包まれて寝台の上に寝かされていた。赤ちゃんの体は信じられないほど小さくて、そのハムのように膨れて線が入った短い手足を縮こませて眠っている。ふっくらとした頬と、もごもごと動く小さな口は微笑んでいるように見えた。
そのかわいらしい姿に、ぼくは自分の頬が緩んでいるのがわかった。シャロンもその手にやさしく触れ、自分の指を握らせてうっとりとしている。
そっと手を伸ばし、赤ちゃんの柔らかな頭を撫でた。茶色の産毛が生えた頭は柔らかく、ポワポワとしていて温かかった。
この小さな存在が、信じられないほど愛おしかった。
ぼくたちが赤ちゃんに夢中になっている一方で、老人たちの顔は暗く憂鬱そうだ。ぼくにはその理由が分からなかった。こんなにかわいい赤ちゃんが産まれたのに、どうしてそんな暗い顔をしているんだろう?
赤ちゃんが寝ていることも気にせず、老人たちは話しはじめた。
「産まれてしまったか‥‥」
「ほんとうについさっき産まれたようですよ。病院で『AlicE』の無痛分娩を受けなかったから、陣痛に襲われて叫んでいたところを見つかったそうです」
「で、母親はあんな調子か」
赤ちゃんの母親は、ガリガリに痩せ細った若い女だった。若いと言っても30歳くらいで、ぼくやシャロンほどではないけれど、彼女も『残される者(マルーン)』の一人だった。
「アー、うるさいなァ。アタシだって産みたくて産んだわけじゃねーっての」
赤ちゃんと同じ茶色の髪の毛をがしがしと掻きまわしながら、母親は苛立ちを隠さないような声で怒鳴った。
「堕そうとしたんだけど上手くいかなかったんだよ」
母親が言っていることの意味はわからなかったけれど、この女がなにかとてもひどいことを言っているということは分かった。周りの老人たちも女を冷めた目で見ていたが、その視線にはどこか同情のようなものも含まれているようだった。
「じゃあ、この子を育てるつもりはないんだな?」
「ああ、ないない。好きにしなよ」
女は一度も赤ちゃんの方を見ることなく、心底煩わしそうに手を振ると、部屋に備えられた椅子に座ってノイズキャンセリング付きのヘッドフォンをつけてタブレットを見始めた。
「では、やはり安楽死しかないな」
「そうですな」
老人の一人が言い放った言葉に、ぼくとシャロンは同時に振り返った。いま、彼らはなんと言った?安楽死?だれを安楽死させるんだ‥‥?母親‥‥?老人の誰かか‥‥?いいや、さっきの会話の主体は赤ちゃんだったはずだ。ということは、彼らが話しているのは赤ちゃんのこと‥‥
一瞬のうちにそこまで思考が走って、彼らが赤ちゃんになにをしようとしているのか気がついたぼくは、赤ちゃんが寝ているのも忘れて、反射的に大声を出していた。
「なんでだよ!!」
はじめてこんな大声を出した。静かな寝息をたてて眠っていた赤ちゃんは泣き出してしまい、老人たちも、ぼくの大声に驚いて、ぼくの方へと顔を向けた。こんな大声で話すのははじめてで、自分の声にびっくりしながらも、ぼくはまくしたてた。
「元気じゃないか!なのに、なんで殺そうだなんて言うんだよ!せっかく産まれたのに!」
はじめのうちはぼくの怒声に慄いていた老人たちは、少しずつ落ち着きを取り戻したようで、老人たちの中でも特に体が衰え、全身を車椅子から伸びる管につながれた老人が、マイクロチップ越しで静かに話しはじめた。彼は、もう自分で口を動かすこともできないのだ。ぼくの激しい口調との差が、赤ちゃんの命に対する姿勢がそのまま表れているようで心底不愉快だった。
「まだ宇宙の終わりまであと八年もある。この子はこのまま育てばわずか八歳で宇宙の終わりを迎えることになるんだぞ。それは、とても苦しく辛いはずだ。しかし、今ならまだこの子に自我はないから、受ける苦しみは少なくてすむ」
老人の言葉に、ぼくはひるんでしまった。たしかに、この子はこのまま育てばあと八年しか生きられないことになる。八歳の自分を思い出してみると、たしかにその頃にはもう自我もあったし、記憶もはっきりとしている。物の好き嫌いもはっきり自覚していて、どんなときに自分が楽しいと思うかや、どんなときに自分が苦しいと感じるかもわかってきていた。八歳の自分は、いまの僕にとても近い存在だった。
考えてみれば当然のことだけれど、この子は今のぼくよりも幼くして死ななければならないのだ。それは、この子にとってはたしかに苦しいかもしれない。
でも‥‥、
「でも、いまはこんなに元気なのよ!それを殺すなんて‥‥、かわいそうじゃない!!」
シャロンが、ぼくの思っていたことを言ってくれた。そうだ、かわいそうなのだ。少なくとも今はこうして元気に生きている子が、なにもわからずに殺されるのは、どう考えてもかわいそうだ。たとえ、遠くない未来に死ぬことが決まっているとしても、今ここでこの子の命を奪うのは、間違っているはずだ。
けれど、ぼくたちのそんな主張は老人たちには届かなかった。
「しかし、もしこの先この子が育って、自分の最期のことを知ったらどうだ?それで絶望したらどうするんだ?八年という年月は、自我を育てはするが、死と向き合えるだけの長い時間ではない。長く生きてきたわたしたちですら、その恐怖と向き合えていない者がほとんどだ。成長して自我のある人間のことは、わたしたちも安楽死させられない。そもそもわたしたちの命はもう長くない。みんなもってあと二、三年だろう。この子をおいて先に死んでいく。そうなると、この子に残された道は、宇宙の終わりという悲劇にひとりで怯えながら死んでいくことだけ。もしくはそこの母親や他の『残される者(マルーン)』と同じように、やさぐれて薬におぼれるか、自殺するかだ。‥‥そんな未来を生きる方が、よっぽどかわいそうじゃないか?」
ずきり、と胸が痛んだ。死ぬ、薬におぼれる、自殺‥‥、突然出てきた強い言葉も恐ろしかったけれど、それよりもこの老人が、赤ちゃんを通してぼくを見て話していることに気がついて、そのことに傷ついた。
この言葉は、彼らが“ぼく”に対して抱いている感情だった。
“どうして産まれてきてしまったのだろう、かわいそうに”
“最後まで生きられないなんて、かわいそうに”
“遠くない未来に必ず死んでしまうことがわかっているなんて、かわいそうに”
“それまでは絶望して苦しむだろう、かわいそうに”
それが、ぼくがずっと、老人たちの視線の中に感じてきた哀れみの正体だった。
本人たちにそのつもりはないのだろう。あくまで赤ちゃんのことを指していっている。けれど、十一年の違いはあっても、ぼくもまた『残される者(マルーン)』だった。この子ほどじゃなくても、長くは生きられない。
「でも、だめなんだよ!!」
ぼくは、自分の身のうちに生まれた激情のまま叫ぶ。
「ぼくは、今みんなの言っていることを認めるわけにはいかないんだ!!」
あの子の命をぼくが否定するということは、ぼくや、シャロンが産まれたことを否定するということだから。
理屈の押し合いなんかで、大人に勝てるわけがなかった。そもそも、いまぼくを突き動かしているのは、理屈じゃなく感情だ。ここで引くわけにはいかなかった。
あの子の命を守らなければ、という一心でぼくはただ叫び続けた。
それは、もちろんあの子に生きてもらいたいからだけれど、ぼくを守るためでもあった。
言い争うぼくたちのところへ、おじいがやってきた。
ぼくは、おじいが来たことで、なにか話の流れが変わるのではないかと淡い希望を抱いて、おじいを見た。
周りの老人たちから話を聞いたおじいは、眉を寄せた顔になると、短く「そうか‥‥」とだけつぶやくと、ぼくたちの方へ来て、目線をぼくたちに合わせるために膝をおった。
その瞳の中には、やっぱりあの哀れみがたたずんでいた。
「あの子は安楽死させる」
全身の力が抜けていく。
膝が崩れて、眼の焦点が定まらない。
「病院へ運びなさい」
「やめて!!そんなのだめ!!」
「子どもは黙っていなさい」
おじいの賛成を得た老人たちは、諦めずにはげしく反抗するシャロンを押さえると、大人だけが使える、魔法の言葉を使った。ぼくたちの首を絞めて言葉を出せなくする、魔法の言葉を。
「生きてるのに!!今は生きてるのに!!」
シャロンが叫んだ。その言葉で、崩れかけたぼくのこころはもう一度形を取り戻して、叫びをあげた。
「おじい!!どうしてぼくのことは生かしたんだよ!!ぼくだって、かわいそうな子なんだろ!?」
答えを期待して言ったわけじゃない。ただ、なにもできない自分の無力さに耐えられなくてとっさに叫んだ言葉だった。しかし、その答えは思いがけないところから返ってきた。
ぼくの怒声に答えたのは、思うように事態が進まず、輪の端っこでイライラしていた老人だった。
「お前は産まれてから見つかるまでに時間がかかっちまって、見つけたときには自我の片鱗が確認されたんだよ。だから、安楽死させずにそのまま生かすことに決めたんだ。べつにお前が特別だったわけじゃない。満足したか?」
「おい!やめろ!!」
悪意に満ちた顔でぼくを見下ろす老人に、おじいが殴りかかるような勢いで止めに入った。
けれど、もうぜんぶ聞いてしまった。
こんどこそ、ぼくのこころは完全に崩れてしまった。形作っていたものがぼろぼろと大きく崩れて、その隙間からまるで血のように、悲しみや怒り、虚しさが噴き出した。
ぼくの問いに答えた老人を、おじいが平手打ちするのが見えた。これまで、そんなふうに暴力を振るっているところはもちろん、怒りをあらわにしているところさえ人に見せたことのないおじいのその行動に、叩かれた本人はもちろん、まわりの老人たちも驚いていたようだけれど、いまのぼくにはそんなことはどうでもよかった。
おじいは、ぼくの方に歩いてきて肩に手を乗せると「いまの言葉は忘れなさい」とだけ言い置いて、またまわりに指示を出しはじめた。
「行きなさい。処置は早い方がいい」
「しかし、『AlicE』の幼児用の安楽死システムは停止していて、再起動までに少し時間がかかってしまいます」
「なら、すぐに起動しなさい。絶対に不具合がないように。苦しみを味わせたくはない」
おじいの言葉で、ぼくたちを押さえていた老人たちとは別の老人たちが、泣き続けていた赤ちゃんを抱えると部屋を出て行ってしまった。
あとに残ったのは、シャロンの泣き叫ぶ声だけだった。
結局、母親はほんとうにただの一度も、赤ちゃんを見ることはなかった。
◆
老人たちが赤ちゃんを連れて行ってしばらくした後、ぼくたちも解放された。けれど、ぼくたちは顔を上げることができなかった。歩みは遅く、ぼくたちの周りの空気は言いようのない虚しさで満ちていた。
どこに向かおうという意思もなく、屍のように歩いていると、ほんとうにたまたま、シャロンがコロニーに来た日に一緒に話をした広場に行き当たったので、ぼくたちは重い足を引きずって、あの日と同じベンチに腰を下ろした。
しばらくの間、ぼくもシャロンも無言だったけれど、ぼくは、歩きながら自分のこころを整理していくなかで感じたことを、少しずつ話しはじめた。
「はじめて聞いたよ。ぼくが、本当ならあの子と同じように安楽死させられそうになっていたなんて。たしかに、おじいたちがぼくを見つけたのは、産まれてから少し経ってからだったことは聞いてた」
地面の一点をぼーっと見ながら、ぼくは言葉を続ける。
「‥‥でも、まさかもっと早く見つかってたら殺されてたなんて、思ってもいなかったよ」
ぼくの言葉に、シャロンは申し訳なさそうな顔になって、ますますしょんぼりとしてしまった。いつもの明るく天真爛漫な様子は見る影もない。
「わたしは、恵まれてたんだわ」
シャロンもまた、つぶやくように話しはじめた。
「わたしもね、ほんとうの親は知らないの。産まれてすぐに、ぼろ布にくるまれて捨てられていたところを、ほんとうにたまたま、フョードルが助けてくれたんだ」
はじめて聞く話だった。たしかに、シャロンの光を透かす綺麗な金髪は、フョードルの茶色の髪とは似ても似つかないし、体格など言わずもがなだ。けれど、それは単にシャロンは母親に似ているのだろうと思っていた。
それがまさか、本当の親子じゃなかったとは。
「『AlicE』の保育システムどころか、旧式の保育システムもなしに捨てられてたんだよ。生きてたのが不思議なくらいだったってフョードルには言われた。でも、逆に言えば、本当の親が捨ててくれたから、わたしはフョードルと親子になれたし、フョードルと一緒に、いろいろなものを見ることができた。‥‥生きることが楽しいと思えるようになった。だから、“わたしは恵まれていたんだな”って‥‥」
「だって、すぐに死んじゃったら、そういうことも思えないもの‥‥」
シャロンはそうつぶやいて顔を俯かせると、また黙り込んでしまった。
ぼくは、その通りだと思った。
あの赤ちゃんの母親の態度を見た時、ぼくはそこに自分の母の姿を見た気がした。母の記憶が残っているわけもないけれど、自分の産んだ赤ちゃんが連れて行かれてしまうというのに、まったく興味も関心も示さなかった母親を見て、「きっとぼくも、ああやって産まれてすぐに捨てられたのだろうな」と漠然と感じ取ったのだ。
ぼくはシャロンとはちがって、外の世界のことはまったく知らなかったけれど、それでも殺されることなく、今この時まで命をつなげることができた。
今にして思えば、これは奇跡のようなことだったのだ。
───外の世界のことは知らなかった。
今ではそれすら違っているように思う。
シャロンの話を聞いて、ぼくは外の世界へのあこがれを自覚したけれど、そもそもシャロンに話を聞く前にも、外の世界のことを知る手段はまったくなかったわけじゃない。ぼくは、“外の世界のことを知らなかった”んじゃなくて、そもそも“外の世界のことなんて知ろうとしてこなかった”んだ。
ぼくには、そのチャンスがあったのに。
「僕も、もっとこの世界を‥‥、“自分が生きる意味”を、知ろうとすればよかったな‥‥」
口をついて出たつぶやきは、言葉にすると、鈍い痛みとなってぼくのこころの中に広がっていった。
ぼくは、シャロンのようにたくさんの本を読んだわけでもなければ、音楽を聴いたわけでもない。『AlicE』のなかに残されたものは少なかったから。けれど、ゼロではなかったのだ。220年前の事件後、消失されたデータのうちで復元に成功したものが、数は少ないものの残されていた。
ひとつもなかったわけじゃないのに、ぼくはそれに触れてこなかった。
物語や音楽だけじゃない。ぼくに勇気さえあれば、この足でコロニーを出て、外の世界を見ることだってできたはずなんだ。
───もっと物語に触れていれば、
───もっと音楽を聴いておけば、
───もっと外の世界へと足を運んでいたら、
ぼくが見る世界も、シャロンが見る世界のように、輝いて見えたのだろうか。
───ぼくには、それをたしかめるだけの時間があったはずなのに。
そうだ。いくら最後まで生きられないとはいえ、僕には時間があったのだ。
すくなくともあの赤ちゃんのように、物心もつかぬうちに、腫れた瞼を開いて世界をその目で見る前に、その命を終えるようなことはなかった。
そのことに気が付いたとたん、せき止められていた水があふれ出すように、ぼくのこころに後悔の感情が流れ出した。
───どうして、ぼくはもっとこの世界のことを知ろうとしなかったのだろう
───どうして、ぼくはもっとこの世界に向き合ってこなかったんだろう
───どうして、ぼくはもっと自分の命と向き合ってこなかったんだろう
───どうして、ぼくは、今更そのことに気づいてしまったのだろう?
次から次へと押し寄せてやまない後悔の感情と自分への虚しさに、涙が溢れて止まらなかった。ぼくのこころは、もう取り戻すことができない過去に囚われて、もう何をすることもできなくなりそうだった。
「まだ!」
ただただ無力感と果てしない後悔にさいなまれていると、突然それを引き裂くような大きな声が響いた。
「まだ、間に合うよ!」
シャロンは震えた声で、ただ涙を流すことしかできないぼくの目を見ながら、言葉を繋いだ。
「まだ八年ある!たくさんのものを見て、聞いて、考える時間はあるよ!わたしたちと一緒に、外の世界を見に行こう!‥‥“わたしたちが生まれた意味”を、見つけに行こう!!」
また、ぼくの心の弱い部分が、「今更そんなもの見つかるわけない」と声を上げた。あの全身を管に繋がれていた老人が言った通り、八年という時間は短い。そんな時間で、いったい何を見つけられるというのだろう。あれだけ長い時間を生きた老人たちが、それを見つけられず、今ももがき苦しんでいるというのに。
けれど、その時、ぼくはシャロンの青い瞳が揺れ動いていることに気がついた。
目の前のシャロンは、いつもの自信満々な彼女ではなかった
その目は不安に揺れ動き、綺麗な形の眉がきゅっと少し眉間に寄って、口だけはぼくの前で強がるように、不器用に笑みを浮かべている。
彼女自身も、戦っているのだ。自分が生まれたことを、必死に肯定しようとしているのだ。
──ぼくは、、また逃げるのか?
そんなことをして、ぼくは最期に後悔しないか?いいや、必ず後悔する。だって、今さっきそれで後悔したばかりじゃないか。
過去は変えられない。この後悔を消すには、これから先の人生で同じ過ちを繰り返さないようにするしかない。
ぼくは、口から出かかっていた「無理だ」という言葉を飲み下し、心の中で静かに決意を固めた。
そうだ、ぼくは、ちゃんと生きるんだ。最期の時に、満足して眠れるように。
「二人とも、どうしたんだ?」
突然、広場の入り口の方から低く野太い声が響いた。これもまた、シャロンがやってきたあの日と同じだった。
広場の入り口で、フョードルが気遣わしげな様子でぼくたちのことを見ていた。
フョードルの姿をみとめたシャロンは、その瞳にぶわっと涙を溢れさせると、一目散にフョードルの方へ走って、ぼくがいままで見てきた中で、いちばん鋭いタックルでフョードルに向かって飛び込んでいった。
◆
「なるほどな。だから、病院がバタバタしていたわけか」
フョードルに一連の出来事を話すと、彼は納得したように頷いた。フョードルは、今まで病院に行っていたのだろうか?同じように疑問に思ったらしいシャロンが口に出して聞いた。
「フョードル、病院に行っていたの?」
「ん、ああ。まあ、ちょっとな。しかしそんなことより、大変なことになったものだな‥‥。赤ん坊か‥‥」
フョードルはシャロンに聞かれたことに曖昧な返事をすると、すぐに話を流してしまった。シャロンはその様子に若干の不満を感じたようだったけれど、フョードルが赤ちゃんの話をふったことで、シャロンもそっちの方に気を向けたようだった。
「なんとか、赤ちゃんを助けることはできない‥‥?」
「うむ‥‥」
フョードルは考え込むように腕を組んで口に手を当てて、唸りはじめた。しかし、しばらく考えたうえで、フョードルは首をゆるゆると振った。
「むずかしいと言わざるを得ないな‥‥。そもそも、御老公たちは、俺が反対したところで聞いてくれないだろう」
むかし、捨てられていたシャロンを拾ったフョードルのことだ。決して、赤ちゃんの安楽死に思うところがないわけではないのだろう。けれど、フョードルはこのコロニーでは新入りだった。仮にフョードルがぼくたちと一緒に、赤ちゃんの安楽死に反対したとしても、新入りの意見を老人たちが聞くとは思えない。
それに、もしフョードルやシャロンが、これから先もこのコロニーで生きていくのなら、老人たちの二人への印象も悪くなるだろう。
「そんなの、フョードルの怪力でぱぱっと助けちゃえばいいじゃない!」
「無茶を言わないでくれ‥‥、このコロニーにはいられなくなるぞ‥‥」
この街には、ぼくが知っている限り一度も使われたことはないが、治安維持用の防衛システムも備えている。いくらフョードルが強いと言っても、コロニー5のすべてを敵に回して生きていけるとは思えなかった。
「赤ちゃんを助けて、そのままコロニーを出ちゃえばいいじゃない!そもそもなんでコロニーになんか来たのよ!わたしはこのコロニーに未練はないわ!」
「トーマとはお別れしないといけなくなるぞ?」
シャロンは、はっとした様子でぼくの方を振り返った。そうしてぼくの顔を見て、視線を下げてしまう。
「それは‥‥」
今だ。言うなら、今しかない。ぼくは、震える喉で唾を飲みこんで、口を開いた。
「ぼくは、一緒に行くよ」
頭が沸騰するように熱くなるのを感じた。鳥肌が立って、身震いしそうになる。
ああ、言った。言えた。どうなるかは分からないけれど、とにかく言葉にすることができた。
シャロンはぱっと笑顔を浮かべ、フョードルは、ぼくがそんなことを言うとは思ってもいなかったのだろう。目を見開いて驚いた様子だった。
「トーマ!」
「‥‥本気か?この街は、トーマの故郷だろう」
「いいんだ。ぼくも、外の世界が見てみたいんだ。それに‥‥、」
飛びついてくるシャロンを押さえながら、フョードルの目を見る。
「あの子を絶対に助けたい」
最期まで生きられないから、数年の命だから、生きている意味がないだなんて、認めたくなかった。
幸せになれないだなんて、認めたくなかった。
ぼくは、それを諦めたくなかった。
「しかし、俺は‥‥」
口ごもってしまったフョードルに、シャロンが涙を流しながら言う。
「フョードル、わたしもあの子を見捨てられない。あの子を見捨てたら、わたしは、自分を許せなくなる‥‥。生きている意味を見失っちゃうわ‥‥」
顔を手で押さえながらうなり続けていたフョードルは、シャロンのその言葉であきらめたように天を仰ぐと、「これも俺に与えられた試練か‥‥」とつぶやいて、赤ちゃんを助けることに協力してくれると言ってくれた。
その目からは、さっきまでの迷いや苦悩は消えて、決意の光が宿っていた。
◆
病院は、集会所と同じようにコロニーの中心近くに建てられている。集会所よりもずっと大きく、コロニーのなかでは一番大きな建物だ。自宅での生活ができなくなった老人たちを受け入れるため、大きく設計されているのだ。
ぼくたちは、広場から病院へと急ぐと、赤ちゃんのいる場所を探した。広い院内で赤ちゃんのいる部屋を探すのは手間がかかるかと思ったが、人だかりとなった老人たちが目印になって、すぐに見つけることができた。
「また来たのか」
病室に入ってきたぼくたちを見て、老人の一人がつぶやいた。もうこれ以上、言い争うようなことはしたくないのだろう。その顔には疲れが浮かんでいた。しかし、ぼくたちの後ろにフョードルがいることがわかると、その顔はぴしりと固まった。この二ヶ月間で、老人たちはフョードルが暴力を振るうような乱暴な人間ではないと分かっているはずだったが、それでもぼくたちと一緒にやってきたフョードルを内心怖がっているようだった。
「どうしたんだい、フョードル」
固まってしまった老人たちの中で、おじいだけがきっぱりとした態度で前に進み出てきた。その目に、恐怖の感情はかけらも映っていない。
「突然、申し訳ありません。二人から事の一部始終を聞いて、いてもたってもいられなかったもので」
「わたしたちを止めるのかい?」
「止めなければと思っています」
フョードルの言葉に、老人たちの顔がさらに引きつるのがわかった。フョードルは片手をあげて静かに続ける。
「勘違いしないでください。暴力なんて使いません。話し合ったうえで、その子を私に任せていただきたいのです」
「わたしたちの意見は、もう固まっているよ」
「それでも、どうか私にその子をお預けください。わたしには、そう言わなければならない義務がある」
フョードルは、おじいやまわりの老人たちの目を見ながら、一点の曇りもない声で言った。
「なんの義務だい?」
「親としての義務です。私は、シャロンの親として、あなたたちの決定には反対しなければならない」
フョードルは、決然とした態度で言葉を告げた。フョードルもわかっているのだ。この赤ちゃんの命を否定することは、シャロンを否定すること、ひいてはフョードルがシャロンを助けたことをも否定することになると。
おじいは、フョードルの言葉にはじめて言葉をつまらせた。その顔は少し引きつっているようにも見えた。
「御老功たちの意見は理解できます。宇宙の終わりまでの時間は八年。八歳というと、個性も見えてきて、自己主張もする可愛い時期だ。そんな子が、死の恐怖に向き合って絶望するのが耐えられないという気持ちは、痛いほどわかります」
たしかに、老人たちのほとんどは、あの母親のように赤ちゃんに無関心だから殺そうとしているわけじゃない。むしろ、赤ちゃんのことを彼らなりに考えた結果がこれなのだ。
けれど、ぼくたちにはそれを否定しなければならない理由があった。
「しかし、その子が八年で幸せになって、自分の死にちゃんと向き合えるようにならないとは限りません」
「楽観的がすぎるよ。わたしたちほどでなくとも、長く生きてきたきみならわかるだろう。八年なんていう時間は、あっという間だ。ましてや子どもにとっての八年など、なにも考えられないに等しい。‥‥誰もが君のようになれるわけじゃないんだ」
おじいは、あくまで認めない。けれど、その言葉がただ感情に任せたものじゃないことは、ぼくにもわかる。おじいの言っていることはきっと“正しい”。ぼくは十一年生きてきたけれど、自分の命に向き合ったことなんて一度もなかった。ぼくだけじゃない。きっと、ほとんどの人間がそうだろう。だから、たった八年で自分の命と、死と向き合えるようになるはずがないというおじいの考えは、きっと”正しい”のだ‥‥。
「そもそも、きみがこの子の面倒を見るというが、きみはもう‥‥」
そこまで言って、おじいははっとすると、「すまない、言葉がすぎた」と言葉を切り上げた。その様子には違和感があったけれど、おじいがすぐに赤ちゃんの話に戻したので、その違和感のことはすぐに頭から離れてしまった。
「しかし、実際問題この子を育てていくとなると、いつかきみだけでは手が回らなくなるだろう。シャロンの手を借りるだけでも足りまい。それになにより、八年という短い時間のなかで、どうやってこの子に希望を与えるつもりなんだい。この閉ざされたコロニーの中で」
来た。いよいよ、ぼくたちの本題につながる切り口になりそうな話になった。ぶわっと鳥肌がたって、心臓の鼓動が耳にうるさく響く。喉もからからに乾いてきた。
「トーマが手を貸してくれるというので、彼の助力を得るのと、『AlicE』の保育機構を頂けないかと考えています」
「ふむ‥‥」
「『AlicE』の保育機構が、本来コロニーの共有財産であることは承知しています。しかし、今このコロニーにいる幼児はその子だけです。ですから、私たちに保育機構を譲っていただきた」
「‥‥そうだね。それならかまわないよ」
おじいは迷うことなくすぐに決断をくだすと、いよいよ本題とばかりに、赤ちゃんの未来の話に踏み込んだ。
「それじゃあ、肝心のこの子が生きる希望を見つける方法を聞いてもいいかな?」
どくん、どくん、と心臓の音がうるさい。鼓動するたびに、心臓が口から飛び出しそうだった。
「そのことなのですが」
フョードルは丁寧な口調で話を切り出した。
「わたしたちは、『見届ける者(ゲイザー)』として復帰するつもりです。その子と、‥‥トーマを連れて、もう一度コロニーの外で生きようと思っています」
フョードルの言葉に、おじいは今度こそ顔を引きつらせた。そして、ぼくの意思を確かめるかのように、勢いよくぼくの方へ顔を向けた。
ぼくは、体が震えるのを抑えながら、決しておじいから目をそらさずに、こくりと頷いた。
ぼくの反応を見たおじいは、もう一度フョードルの方へ向き直ると、今まで見たことがないほどの剣幕でフョードルに詰め寄った。
「馬鹿な!君は、自分の手に余るものを抱え込むつもりかい!?それは君の我儘でしかない!!そんなものに振り回されて何になる!!その先に待っているのは身と心の破滅だ!!それになにより、君の我儘のあとで放り出されるこの子たちはどうなる!!」
「御老功が仰られたとおり、これは私の我儘です。この子たちに、この理不尽な世界で、それでも生まれてきたことに喜びを見出してほしいという、私の我儘‥‥。私一人で考えていれば、きっと私はこの件についても見てみぬふりをして過ごしたでしょう。‥‥私自身もシャロンのことが気がかりで、同じ年頃のトーマがいるこのコロニーへとやってきましたから」
はじめて聞く話だった。フョードルは、ぼくがいたからこのコロニーにやって来たのか。
シャロンも、思いがけず自分たちがコロニーへ来た理由を知って驚いた顔をしている。
「二人からこの話を聞いた時にも、すぐに決断することはできなかった。あなたの言うように、これはあまりに無責任な行動だと思いましたから‥‥。しかし、トーマが決断してくれたおかげで、私も覚悟を決めることができました」
フョードルは、あの決意をたたえた強いまなざしでおじいをすっと見すえて、はっきりと言葉を告げた。
「私は、『見届ける者』へと戻ります。そして、この子たちに外の世界を見せます。彼らがそこに、生まれた喜びを見出せるように。‥‥十二年前にシャロンの親になることを決めた時から、私の道は決まっていたのでしょう」
おじいは、長いことフョードルのことを睨んでいたけれど、フョードルの決然とした態度に大きくため息をつくと、「君とは良い話友達になれると思ったのだけれどね‥‥」とつぶやいた。
「君の考えはわかった。もう止めはしないよ。‥‥わたしに止められるはずもない。けれど、最後にトーマの意思をちゃんと確認しておきたい。一時の気の迷いだった場合には、さすがに止めなければいけないからね」
おじいはそう言うと、フョードルからぼくへと目を移した。おじいの目は、ぼくの心の底まで見通そうとするかのように、静かに澄んでいる。ぼくのこころは、その目に射すくめられたように固まってしまった。
“やっぱりだめだ、言えない”、“おじいを納得させるだなんて、ぼくには無理だ”、“怖い”、“逃げたい”‥‥。次々とこころに弱音が浮かぶ。のしかかってくる重圧に、胃がひっくり返りそうだ。ぼくは、たまらなくなって、おじいの視線から目をそらしてしまった。ああ、やっぱり、ぼくはだめなやつだ‥‥。
恐怖と自分への失望感に思考が落ちていくなかで、ぎゅっと、腕を握られる感覚がした。はっとして、掴まれた腕を見ると、シャロンがぼくよりも強い不安に染まった顔で、ぼくの腕に縋りついていた。
その顔を目にした途端、ぼくの頭の中に、どこからともなく、熱湯のような熱さを持った思いが突然湧いてきた。それは、一瞬でぼくの頭を染め上げると、こんどはぼくのこころの中へと移って、その場所をも満たしていく。さっきまでその場所を満たしていた不安や恐れは、その思いがあっという間に飲み込んでいった。
“この子の前で、格好悪い姿は見せられない”。
それは見栄だった。好きな子の前で、カッコつけたいという、男のしょうもない見栄。けれど、それで十分だった。そんな見栄のおかげで、ぼくの心はもう一度立ち直った。
ぼくは、ぼくの腕を掴むシャロンの手の上に自分の手を重ね、その青い瞳に強くうなずいた。もう大丈夫だ、と伝えるために。
おじいの方へ向き直って、水のように静かにたたずむその目を見た。その目を見ると、また不安や恐怖が生まれてきたが、かまうものか。
おじいは、ぼくの目を見て問いかけてくる。
「本当に、フョードルたちについて行くつもりなのかい?」
「うん」
言葉を発し始めると、なんだか妙に頭が澄み渡っていくような気がした。こころはまだ熱く激っているのに、頭は冷たく澄んでいる。まるで、今まで見えなかったものが見えるようになったような、そんな感覚だった。
「外の世界は、このコロニーの中とちがって、生きていくのは大変かもしれないよ?」
「でも、行きたいんだ」
「‥‥どうしてだい?」
今なら、自分の気持ちをうまく言葉にできそうだった。
「さっき、赤ちゃんの家で、ぼくが本当はその子と同じように安楽死させられるはずだったって聞いたとき、ぼくは、「あぁ、ぼくが生まれてきた意味はなかったんだなぁ」って思ったんだ」
「そんなことは‥‥」
おじいが訂正しようしたのを遮って、ぼくは続けた。
「ないんだよ。今のぼくには。だって、誰からも望まれずに生まれて、誰からも愛されてないとしたら、他の誰かがぼくの命に意味を与えてくれるわけじゃないから」
鏡のような水面に風が吹いたように、おじいの瞳が揺らいだ。
「おじい言ったよね?「ぼくが本当は安楽死させられるはずだったことは、忘れなさい」って」
おじいは言葉を返さない。ぼくはかまわず続ける。
「でも、そんなことできないよ。自分が、誰からも必要とされずに生まれた存在で、今も生きている意味がないことを知ったのに、それを忘れるだなんて‥‥。そんなこと、できるわけない」
そうだ、ぼくは知ってしまった。自分の命が、たまたま繋がっているものなのだと。そして、ぼくの命はいま、どこにも寄る辺なく、ただ空を漂っているだけということも。
ぼくはこの命の寄る辺を、自分で見つけ出さなければならないのだ。
「だから、ぼくは自分で、ぼくが生まれた意味を見つけなくちゃならないんだ」
生まれながらに誰かに意味を与えてもらえないのなら、ぼくのような人間は、自分で自分の生まれた意味を見つけ出さなければならないのだ。他人に拠らない、自分を認められる理由を。
「このままここに住んでいたら、ぼくはきっと、一生自分が生まれたことを認められないまま死ぬんだ」
そんなのは嫌だった。生きる理由や意味なんて、今まで気にもしたことがなかったけれど、一度その意味を考えてしまったら、もうそこから目を逸らすことなんてできなかった。
「だから、ぼくも探してみたいんだ。ぼくが生まれた意味を、生きる理由を。外の世界で」
おじいはおずおずと口を開いた。
「‥‥そんなものがなかったとしたら?その道はもしかしたら、途中で行き止まりに当たるかもしれない」
「そうかもしれない。でも、なにも持たないいまのぼくは、それがあることを信じたいんだ。‥‥人生をかけて」
「‥‥」
「おじい。ぼくは、シャロンたちと外の世界に行くよ。そして、ぼくが生まれた理由を探すんだ。ぼくが、自分が生まれてよかったと思えるものを」
ぼくは、おじいの目から一度も目をそらすことなく、おじいに自分の思いを言い切ることができた。
おじいは静かにぼくを見つめていたけれど、やがて静かに息を吐き出すと、ぼくの目を見て言った。
「わかったよ」
ふっと緊張の糸がゆるんで、体から力が抜けるのを感じた。いつの間にか握り込んでいた拳の掌には、汗をびっしょりとかいていて、どっと疲れが押し寄せてきた。
「それでは、その子を私たちに任せていただけますね?」
「‥‥ああ」
おじいが院内の看護ロボットに指示を出すと、ロボットは綺麗な白い布で包まれて眠っている赤ちゃんをフョードルにやさしく手渡した。
フョードルの赤ちゃんの抱き方は様になっていて、赤ちゃんもぐずることなく気持ちよさそうに眠っている。
「ただ、私たちが来たシュヴィーツという場所は、アルプス山脈の麓にある山間の場所で、この時期に長距離を移動することはなるべく避けたいので、コロニーを出ていくのは春先まで待っていただけると助かります」
「‥‥かまわないよ。別にわたしたちは、きみたちを追い出したいわけじゃないからね。もし、気が変わればいつでも言ってくれ」
おじいはこくりと頷くと、もう一度ぼくの方へと顔を向けた。
「トーマも、本当にいいんだね」
ここが、分かれ道だと思った。ぼくは自分の決意に任せて、こくんと頷いてみせた。
おじいは、ふっと少し息を吐いて少しうつむくと、なにも言わなくなってしまった。その反応は、ぼくを責めているようなものではなかったけれど、それを見たぼくのこころは、なぜか無性にざわついて、うまく言葉にできない、複雑にからみ合った感情が胸におこったのを感じた。
沈黙のなかで、赤ちゃんの静かな寝息だけがかすかに聞こえていた。
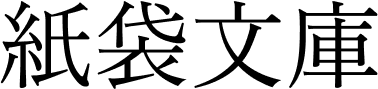


.png)
.png)