マルーン
第二章 『見届ける者』
5368年9月22日
ぼくは、走るのが苦手だった。走ることだけじゃなくて、運動自体、あまり得意じゃない。今も突然コロニーに来たという来訪者たちの話が気になって、急いでおじいたちの後を追いかけたのに、コロニーの中心につくられた集会所にようやく辿りついたときにはもうすでに老人たちが集まっていて、ちょっとした人だかりができていた。
その人だかりの中心では、周りの老人たちの二倍近い身長がある、これまで見たことがないほどの大男とおじいが話をしていた。おじいは老人の中ではしっかりとした体格だったけれど、大男の前ではほかの老人たちと変わらないほど小さく弱く見えた。大男はこちらに背を向けていて、その背中には、ぼく一人が入れそうなくらい大きなリュックサックを背負っている。背を向けているので顔は見えないけれど、男の低い声は、少し離れたぼくのいる場所にまで響いてきた。
ふとおじいが大男の背中越しにぼくの姿をみとめると、ぼくの方を指さして何か言ったようだった。大男が振り向こうとしたその時、
「わぁ!わたしと同じくらいの子がいる!」
突然後ろから金切り声が聞こえたかと思うと、振り返る間もなく腰のあたりに衝撃が走った。かと思うと、視点がひっくり返って地面が目の前に現れた。とっさに手を突き出して顔から着地するのはさけたが、そのあとすぐに更なる衝撃に背中を襲われる。ぼくの腕では耐えきれず、結局地面に潰れてしまった。潰れたぼくの背中には、何やらずっしりとした重みを感じる。
しかし、その重みはすぐになくなり、今度は腕をつかまれてひっくり返された。なにが起こっているのかまったく理解できず、戸惑いと恐怖で見開かれていたぼくの目に、金色のなにかが飛び込んできた。
それが髪だと気づくのに、すこし時間がかかった。太陽の光を透かして輝く、僕の黒い髪とは正反対の、綺麗な金髪。ふわりと空気をふくんでふくらんでいた髪から、少しずつ空気が抜けて、それがぼくの顔に向かって垂れ下がり、お菓子のような甘い匂いがふわりと漂ってきた。さらりとした髪の間から、こぼれんばかりの喜びに満ちた青い瞳がきらきらとぼくを見下ろしている。
心臓が、ひとつ大きく、どくんと脈打つのを感じた。
さっきの一連のめまぐるしい視点の変化が、彼女に後ろからタックルされたことによるものだと気づいたのは、さっきの大男の声で、彼女に見惚れていた意識が現実に戻されたあとだった。
「こら、シャロン。嬉しいのはわかるが危ないだろう。うちの娘がすまない、坊や」
女の子もまた、大男と同じように大きなリュックサックを背負っていた。大男はぼくにまたがっていた女の子のリュックサックを掴んで、それを背負った女の子ごと片手で軽々と持ち上げると、残った片腕でぼくのことも持ち上げて立たせてしまった。こんなにも力の強い人間をはじめて見たぼくは、その腕のあまりの太さに驚愕した。ぼくの体のどの部分よりも太く、大きく膨らんだ腕は、その気になればなんでも潰してしまえそうなほど強そうだったけれど、ぼくに触れるときにはこのうえなくやさしい力加減でぼくを立たせてくれた。
立ち上がってから改めて間近で男を見上げると、腕だけではなく、体のすべてが大きいことが見てとれた。ごつごつと筋肉が張り出した体に、茶色の毛むくじゃらの髭が伸びた顔がちょこんと乗っている。首についた筋肉が大きすぎて、首がないように見えるのだ。そのあまりに強そうな見た目に、ぼくの喉は緊張感から自然と唾を飲みこんでいた。けれど、男はその荒々しい見た目からは想像できないほど、とても礼儀正しく挨拶してきた。
「突然の訪問、申し訳ない。俺は、『ゲイザー(見届ける者)』のフョードル。そして、この子が…」
「シャロン!シャロンよ!」
フョードルと名乗った男の腕に、いまだにリュックサックごと抱えられて宙に浮いている女の子はそう叫ぶと、足をばたつかせて、またきゃーきゃーと騒ぎはじめた。どれだけ女の子が足をバタバタさせても、フョードルはまったく微動だにしなかったが、少し呆れた様子でぼくの方に向き直ると、興奮がとまらない彼女のこころを代弁するように言った。
「すまないね。自分と同じ年頃の子に会うのがはじめてなんだ。許してやってくれ」
そんなの、ぼくだって初めてだ。今までぼく以外の子どもの『マルーン(残される者)』なんて、見たことも聞いたこともなかった。‥‥ましてや、こんなに綺麗な子に会ったことなんて、ぼくにはない。
彼女の青い瞳と目が合うと、頰が熱くなるのを感じた。それを誤魔化すように、頭を振って「大丈夫」と伝えると、彼女はにっこりと笑って、「あなたの名前は?」と尋ねてくる。ぼくは自分の名前を名乗りながら、今ぼくの目に映っている世界が、なんだかさっきまでの世界よりも鮮やかになったような気がしていた。まるで、カメラのレンズが切り変わったかのように。
ぼくの名前を聞いて、またはしゃぎはじめた彼女を見て、心臓の鼓動は、さらに大きく響きはじめた。
◆
シャロンが騒ぎ続けたことで、場は話し合いどころではなくなり、おじいはぼくに、シャロンにコロニーを案内する役目を言いつけると、フョードルだけを連れて自宅に行ってしまった。
残されたぼくは、まともにシャロンの方を見ることができず、名前を呼ぶこともできなかった。はじめは面白がっていたシャロンだったけれど、いつまでも恥ずかしがっているぼくにしびれを切らしたようで、「ねえ、こっち見てよ」と言いながらぼくの視界に入ろうとしはじめた。しかし、それでもぼくが頑なに顔を向けなかったので、彼女はぼくの顔を手で挟んで顔を固定してしまうと、「ちゃんと顔見て、名前呼んで!」とただ一言、けれど絶対に逆らえない強い言葉をかけられてしまった。
ぼくは、あまりの恥ずかしさに言葉をつまらせながら、「シャロン」と彼女の名前を呼ぶと、彼女は満足したように優しく笑って、ぼくの手を取った。
「だいじょうぶ、緊張しなくていいよ」
やさしく諭されるように言われてしまった。ぼくは繋いだ手から感じるぬくもりと、彼女に気をつかわせてしまった恥ずかしさとで、ますます顔が赤くなるのを感じた。そこでふと、彼女の口の動きと、ぼくの耳に聞こえてくる音が違うことに気がついた。彼女の眼に見惚れていたとき以外は、ずっと彼女の顔を見ることができなかったので気が付かなかったが、どうやら彼女が話している言語は、ぼく話している言語とは違うもののようだった。
ぼくたち人間は、脳に埋め込まれたマイクロチップのおかげで、たとえ互いが使っている言語が違っていても、相手の言っていることが正しく理解できるようになっている。相手の言葉を耳で聞き取ると、その情報がマイクロチップへと送られ、それがどの言語にあたるのかを解析し、それを翻訳したうえで、相手の声を完全に再現した合成音声で再生してくれる。だから、たとえ相手がどんな言語を使っていようと、マイクロチップ内に保存されている言語データにその言語が含まれていれば、なんの問題もなく意思疎通することができる。
むかしはほかの言語の文字を読んだり、話したりすることができるようになるには、その言語を一から勉強して、十分に使えるように練習しなければいけなかったらしい。何度も何度も同じ単語や文章を使うことを繰り返して、ようやく習得できたそうだ。当然、言語ごとに文字も言葉もぜんぜん違うので、覚えようとする言語の数が多ければ、それに比例して訓練に必要な時間は増えていく。だから、むかしは複数の言語を喋れることが、ひとつのステータスになっていたこともあるらしい。
コロニー5にも、ぼくと違った言葉を話す人間は少なからずいる。今まではそんな人間に会っても気にも留めなかったけれど、今は、彼女が話しているのが何という言葉なのか、とても知りたかった。
「ね、このコロニーを案内してよ」
手を繋いだまま、シャロンはぼくを街の方へと引っ張って行く。どこになにがあるのかもまったくわからないだろうに、ずんずん先へ進んでいくその自信満々な様子に、なんだかぼくの方も勇気づけられて、がちがちになって言うことを聞かなかった身体が少し軽くなった気がした。
引っ張っられていた形から、小走りでシャロンの隣に並んで、彼女が背負っていた大きなリュックサックを代わりに持つことを申し出た。少しでも頼りがいのある男だと思われたかったから。
けれど、シャロンから手渡されたリュックサックは信じられないほど重く、それを背負ったぼくはあっという間に息切れして、足の進みはどんどん遅くなっていった。シャロンは笑いながら、「重いよね。だいじょうぶだよ、わたし持てるから」と言ってぼくの肩からリュックサックを外すと、もう一度自分で背負い直した。
肩から重荷は消えたけれど、そうして軽くなって喜んでいる自分の肩が、ぼくはとても恥ずかしくて、情けなかった。
シャロンは、コロニーを見ること自体がはじめてなようで、街のあちこちに目を奪われている。同じ形、大きさのドーム型の家が連なっているのを見て、巨大生物の卵だと勘違いしたり、街の整備をしている『AlicE』が入った人型の機体を、本物の人と間違えて後ろから話しかけたりと、何度もぎょっとさせられるくらい、コロニーのことを知らなかった。
しかし、彼女ははじめこそ、そういったものに目を奪われて、ぼくにいろいろ質問してきていたが、ぼくがそれらのものを説明していくと、徐々に興味をなくしていったのか、「ふーん」と言って、もう見ることはなくなってしまった。
街を案内して回るなかで、シャロンは彼女とフョードルのことを教えてくれた。どうやら彼女は、フョードルとふたりで旧スイスという、コロニーのない場所を拠点にしていたらしい。ただ、彼女たちは、そこを生活の拠点にしながら、あちこちに出掛けては、外の世界をめぐり歩く生活をしてきたという。フョードルの言っていた『ゲイザー(見届ける者)』という耳慣れない言葉についても教えてくれた。『ゲイザー』は、人間が『スリープ計画』によってその数を徐々に減らし、コロニーごとに集まっていく時代の流れに逆らって、コロニーの外に留まる、もしくは出ていった人たちのことらしい。彼らはコロニーの外に拠点を置いて、かつての人間のように暮らし、そして外の世界を探索する。コロニーの中にはないもの、人間が遺したものを見て、自分たちの最後の時までそれらを見届ける。だから、『見届ける者』という名前がつけられたのだと。
多くの『マルーン』が、むかしはコロニーを飛び出して『ゲイザー』になっていたらしい。フョードルもその一人で、彼が住んでいたコロニーを訪ねてきた『ゲイザー』の話のとりこになって、周りの反対を押し切って彼について行ったそうだ。
シャロンは外の世界のことをさかんにしゃべってくれた。彼女が住んでいたという場所のことも。そびえ立つ山々の雄大さ、力強く水を落とす滝の迫力、きらきらと輝く川のせせらぎと、その岸辺にそよぐ木々の美しさ。
話を聞いていくうちに、ぼくは、彼女がこんなにも夢中になって話す外の世界は、いったいどれほど美しいのだろうかと知りたくなった。彼女の話に出てくるような景色は、このコロニーにはない。すべてのコロニーは、人間が生活しやすい、なるべく平坦な大地が続く場所を選んでつくられているからだ。このコロニー5は、もともと旧市街があった場所のすぐ近くにつくられたので、コロニーを出てしばらくは、無人の古い街並みが続く。よくコロニーを抜け出していたぼくは、旧市街へはよく足を運んだが、その先へは行ったことがなかった。だから、シャロンが話すどの景色も、ぼくは見たことがなかった。
きらきらと顔を輝かせながら楽しそうに語るシャロンの話は、ぼくの心を大きく揺り動かした。そこにいけば、どんな音が聞こえるのだろう?どんなにおいがするのだろう?その景色を見ることができたら、ぼくは、どんな気持ちになるのだろう?まだ見たことのないものへの想像が膨らんで、妄想にはまりこんでいたぼくは、シャロンの一際大きな声で我に帰った。
「でもわたしは、人間がつくったものが一番だと思うの!」
「え?」
ぼくはきっと、すごく間抜けな顔をしていたんじゃないかと思う。だって、ぼくの顔を見たシャロンに笑われてしまったもの。でもぼくがそんな顔になったのは、彼女が言ったことがあまりに意外なことだったからだ。
人間がつくったものが、はたして今まで彼女が話していたもののなによりも魅力的だろうか?たしかに、人間はその知恵を使って、いろいろなものをつくり出してきた。このコロニーという場所は、そういうもので溢れかえっている。3Dプリンターで造られた、頑丈で過ごしやすい家、人間の指示がなくとも正常に街を管理してくれる、『Alice』が操るロボット体、菌やウイルスの侵入と繁殖を防ぎ、たとえ病気になったり介護が必要になっても最適な治療をしてくれる全自動医療システム。これらの人間の叡智の結晶は、たしかにすごいと思うし、ぼく自身もその恩恵を受けているから、感謝はしている。
でも、ぼくにはそれらのものが、ひどくか細く、空しいもののように思えた。
だって、そういうものは全部、意味がなかったじゃないか。
たしかに、人間はこの宇宙で、自分たちにできることをひとつひとつ増やして、時代を経るごとにそれを積み重ねていった。けれど、そうやって積み重ねたものは結局、世界‥‥、宇宙には勝てなかったじゃないか。
宇宙の終わりが来てしまえば、跡形もなく消え去ってしまうような、もろく、空しく、頼りないもの‥‥。そんなもの、この世界に比べてしまえば本当にちっぽけなものじゃないか。
そんなものの、いったいなにがすごいというのだろう?どう考えても、シャロンが話していたような、世界が生み出した自然の光景の方が人間の生み出したものよりもすごいじゃないか。
「ここにあるものがそんなに気に入ったの?」
しかしぼくは、シャロンが好きだというものを否定して彼女に嫌われたくなかったので、こころのなかで思ったことは口には出さず、シャロンの考えをうかがうように聞いた。するとシャロンは、一瞬きょとんとしたような顔になって、何を言っているのかわからないというような反応になった。
しかし、すぐになにかに思い至ったのか、はっとした顔になると、今度は笑いながらぼくの言ったことを否定した。
「ちがうちがう。わたしが言ってるのは、人間が“自分たちの手で創ったもの”のことだよ」
「“自分たちの手で”‥‥?」
シャロンの言っていることの意味がよくわからなかった。3Dプリンターや『AlicE』、全自動医療システムは、すべて人間がつくり出したものだ。たしかに、今の『AlicE』は、人間の指示を受けることなく、新しいシステムや医療を生み出すことができるが、元をたどれば『AlicE』をつくったのは人間なのだから、それらのものも人間がつくったと言っていいのではないか?
ぼくが彼女の言ったことをいまいち飲み込めていないのを見てとったシャロンは、「うーん」と言って悩んだあと、「よし」と言ってぼくの手を握った。
「わかった。じゃあ、見せてあげる!」
そう言うとシャロンは、またぼくのことを引っ張って、近くの広場へと入って行った。
◆
広場に入ったぼくたちは、入り口にほど近い場所に等間隔に設置されているベンチに向かい合うように座った。シャロンは背負っていたリュックサックをおろすと、その口を開いて中に手を入れ、ゴソゴソとしはじめた。
「じゃあ、まずはねー‥‥これ!」
シャロンは顔を輝かせて「じゃじゃーん」なんて言いながら、リュックサックに突っ込んでいた手を勢いよく取り出した。その手には、ぼくが今まで見たことがないなにかが握られている。四角い厚みがある形に、表面にはなにやら独特の装飾がされていた。なんだろう‥‥、電子機器の類ではなさそうだけれど‥‥。
「なに、これ?」
ぼくが聞くと、シャロンはにまにましながら嬉しそうに、その四角い物を前面に出してきた。
「これはねー、本です!」
「え、本‥‥!?」
ぼくが知っている本は、薄いタブレット端末だ。けれど、いまシャロンが手に持っているものは、どう見てもブロック一つ分くらいの分厚さがある。旧時代のタブレット端末はあんなに分厚かったのか‥‥?なんて思っていると、なんとブロック型の旧時代タブレットがいくつかに分裂した!‥‥のではなく、あの分厚さは何枚か同じものが重なっていたもので、それが今はバラバラになっただけだった。しかし、バラバラになっても、ひとつひとつがそこそこの厚みを持っている。見た目の質感から、やはりタブレットではないのだろうということだけは分かった。
シャロンはそのうちの一つを手に取ると、それを裂くように二つに開いてみせた。すると、その間には無数の薄いペラペラとしたものが挟まっていて、そこに文字が書いてあるのを見せてくれた。そこでようやく、この厚みのすべてが、その一枚一枚の薄いペラペラが積み重なってできた物だと分かった。
「そういう仕組みになってるのか!」
タブレットでは、すべての文章が一枚の横並びのページに表示されていて、画面をスワイプしてそれを読み進めるのに対して、このペラペラを重ねた本の場合は、積み重ねられたペラペラをめくっていけば、続きを読むことができるのだ。なるほど。これならたしかに同じ大きさのペラペラを何枚も重ねれば、どれだけ長い話もまとめることができる。
けれど、内容が長くなれば長くなるほど、ペラペラの量は増えて、本は分厚くなっていく。タブレットの方がいいのではないかと思った。
「でも、こんなに分厚いと持ち運ぶのが大変でしょ」
「むかしの人間も、そう考えたから、どんどん本をデータ化して『AlicE』のなかにデータを移していったんだろうね。たしかに、持ち運ぶにはタブレットの方が便利だから。でも、それで『紙』の本を大事にしなくなっちゃったから、『AlicE』の中にあったデータが消えちゃったとき、人間はほとんどの本を復元することができなかったんだよ」
たしかに、その通りだった。利便性だけを追求しすぎた結果が220年前の悲劇につながったことを考えると、タブレットの中に保存するデータ以外にも、なにかしらの形でそれを残すことは必要だったろう。便利なことを追い求めて、結局不便になってしまったら元も子もない。
「それにね。わたしはこの手触りも好きなんだ。さらさらしてて、めくっていると楽しいの」
そう言って、シャロンは『紙』と呼んだペラペラをつまんで左から右へ、右から左へとめくってみせる。たしかに、この独特の手触りは、ほかのものにはない感覚で、触っていて楽しいかもしれない。けれど、ぼくはやっぱり、同じものならタブレットでいいんじゃないかと思った。それは単にぼくが慣れているだけだからかもしれないけれど。
しかし、ふとシャロンが手にしている本と、ぼくたちの間に並べられている本に視線をやって、ぼくは違和感に気がついた。『ドラえもん』、『アルジャーノンに花束を』、『人間の土地』、『マジック・ツリーハウス』、『ギヴァー』、『風立ちぬ』、『息吹』、『獣の奏者』‥‥、脳に埋め込まれたマイクロチップは、目の前に並べられた、それぞれ異なる言語で書かれた言葉を一文字ずつ読み取っていく。けれど、そこにあるどの本も、ぼくが見たことも、聞いたこともないタイトルだった。
「どれも見たことも聞いたこともないや‥‥」
ぼくがつぶやいた言葉に、シャロンは笑いながら言った。
「あたりまえよ!だって、この本のデータは、『AlicE』のデータ消失事件で全部消えちゃったんだもん!」
ぼくは、自分の目も口も大きく見開かれていくのがわかった。それくらい、驚くべきことだったから。ぼくが知っている本というのは、約220年前の『AlicE』の大規模データ消失事件以降に記録されたものだけだった。それ以前の本が残されていたなんて、聞いたこともない。
基本的に、『AlicE』が知らないことはまずない。なぜなら、サービスが開始されてからの数百年の間に、人間の持つすべての知識やデータ、技術などが『AlicE』にダウンロードされているからだ。だから、人間がこれまでに知ったことやつくったものなら、“基本的に”『AlicE』が知らないことはない。しかし、そこにはある例外があった。それは、人間がつくり出してきた本や映像、音楽といった文化的なデータだ。
今から220年くらい前に、『AlicE』に保管されていた一部のデータ群のほとんどが消失するという大事件が発生した。当初は『AlicE』の自己管理システムの不具合や、そのほかの原因による事故が疑われていたようだけれど、後々になって『スリープ計画』の急進派グループによる、世界的な同時サイバー攻撃による事件だったことが分かった。
彼らは思うように進まない『スリープ計画』に腹を立てて、その原因が人間の娯楽や文化にあると考え、犯行に及んだそうだ。だから彼らはそれらのデータ、特に本やゲーム、音楽などのデータに標的をしぼった攻撃をおこなった。事件発覚後、犯人たちはひとり残らず捕まったそうだが、失われたデータが戻ることはなかった。
彼らが『AlicE』に入力されている街の管理システムや全自動医療システムといったものを狙わなかったのは、彼らの目的は『人間の殺害』ではなく、『安らかな安楽死』であるため、それらのシステムを破壊することで、人間が苦しんで死ぬことは望んでいなかったからだそうだ。捕まった犯人たちは、彼らの理念や理想といった、聞かれてもいないことまで得意気にぺらぺらと喋ったらしい。
悪意のある人物からの攻撃が原因だったとはいえ、結果的に人間は、それまでに蓄えてきたほとんどの本やゲーム、音楽、さらには食事といった文化をことごとく失ってしまった。もちろん、220年前の事件以降に生み出された新しい作品や知識は記録されてきたが、それまでに人間が蓄積してきたものと比べると、すずめの涙ほどの量しかなかった。220年前に失われたものは、もう永遠に見ることができなくなってしまった。
けれど今、その本が、ぼくの知っている形ではなくても目の前にある。これが驚かないでいられるだろうか?ほんとうにすごいと思った。こんな保管することが大変な本を残してきた人間のことも、それを見つけたシャロンのことも。
シャロンはぼくの反応に満足したのか、「こんど読ませてあげるね」と言って本をまとめると、またリュックサックのなかに手を突っ込んで、ガサゴソと中をあさりはじめた。
ぼくは、最初にとんでもない物を出されたことで、すっかり自分が、シャロンが次に出すものにわくわくしていることに気がついた。
「じゃあつぎは‥‥」
「これと‥‥、これと‥‥、これ!」
シャロンは、これまた見たこともないようなヘンテコな形をしたものを一気にいくつも取り出してみせた。
「ねえ、これはなんなの?」
「えっとねー。映画のDVDでしょ、ゲームでしょ、そして、なんとライアーです!」
また「じゃーん」と言いながら、最後のものを特に強調して見せてくれた。最初の『映画』と『ゲーム』の二つは知っている。映画は、『AlicE』が世界中の機体につけられたレンズを通して視た映像を記録して、それを合成していろいろな映像をつくったものだ。自分の好みのジャンルやストーリーを伝えれば、すぐにそれにあったものをつくってくれる。ゲームも同じで、『AlicE』がつくったものを、タブレットを使って遊ぶことができる。専用のヘルメットをつければ、あたり一面に仮想空間が広がった状態で遊ぶこともできて、これはとても迫力がある。けれど、そういった映画やゲームが映し出す世界は、映像は綺麗なのに、なぜかどこか味気ないように感じられて、ぼくはあまり好きではなかった。
最後のものだけ、なにをするものなのかわからなかった。ライアーと言っていたけれど、いったいなんだろう?リュックサックから取り出されたときには、ひとまわり大きなケースに入れられていたそれは、木製のようで、上の方に大きく穴の開いた、しなやかな曲線を描いた形をしていた。穴の上を通って、全体の上から下へ向かって細い糸が張り巡らされている。表面には、植物のような文様が彫り込まれていて、それがこの『ライアー』を美しく着飾らせているようだった。
「そのライアーって、なんなの?」
シャロンはさっきよりもずっと興奮した様子で、ずい、とぼくの顔の前に、『ライアー』と自分の顔を押し出してきた。顔の距離があまりに近くなったものだから、ぼくはすっかり忘れていたあの照れ臭さをまた思い出して、頰が熱くなるのを感じた。
シャロンはそんなぼくの様子には気がつかなかったようで、声を張り上げて説明を続ける。
「これはね、楽器なんだよ!」
楽器。音楽を奏でるもの。知識として、『AlicE』に教えてもらったことはある。けれど、実物は見たことがなかったし、それが実際にどのように音を出すのかもわからなかった。
音楽もまた、『AlicE』がつくることのできるものの一つだ。ぼくにもいくつかお気に入りの曲がある。けれど、ぼくはすぐに飽きてしまって、何度も新しい曲を『AlicE』につくってもらっていた。
旧時代の音楽、ましてやそれを奏でていた楽器というものの音を、ぼくはもちろん聴いたことがなかった。きっとぼくだけじゃなくて、このコロニーにいる老人全員がそうだ。少なくとも、このコロニーに旧時代の音楽は残っていないから。
「これ、音を出すことはできるの?」
その音を聴いてみたいという気持ちがはやり、ぼくは焦ったようにシャロンに聞いた。シャロンは笑顔で「もちろん」と言うと、上下に張り巡らせた糸に指を添え、おもむろにそれを弾きはじめた。すると、弾かれた糸が震えて、ろんろん、とやさしく澄んだ音が流れた。美しい音だった。
最初はただ単に音を鳴らしていたシャロンの指は、一つのメロディを奏ではじめた。そのメロディもまた、ぼくの知らないものだ。シャロンはメロディに合わせて、そこに自分の声をのせるように歌いはじめた。
“呼んでいる 胸のどこか奥で”
“いつも心踊る 夢を見たい”
“かなしみは 数えきれないけれど”
“その向こうで きっとあなたに会える”
シャロンの声は凛としていて、美しい形をなして空気を跳ねのけるように力強くあたりに響いた。シャロンがライアーの音色にのせて歌うその曲は、はじめて聴くはずなのに、どこか懐かしくなるような曲だった。無性にだれかの胸に飛び込んで、泣いてしまいたいような気持ちになる。実際、目頭が熱くなるのを感じたが、シャロンの前で泣くような格好悪いことはしたくなかったので、浮かんできた涙を必死に押しとどめた。
しかし、その曲には、ぼくには上手く理解できない歌詞がいくつかあった。その原因はたぶん、マイクロチップの翻訳機能の問題だ。
マイクロチップの翻訳機能は、まったく違う言語を使う人同士の言葉を、お互いの言語に置き換えてくれる。つまり、相手がちがう言語で「わたし」と言ったとき、それがぼくの言語における「わたし」にあたる言葉に変換されるのだ。その変換精度は高く、明確な意味を持つ言葉であれば、自分が言いたいことを完全に相手に伝えることができる。けれど、それぞれの言語が持つ雰囲気の違いや、独特の感覚といったものの解像度はまちまちで、言語同士の相性によって精度が左右されることもある。
おそらく、ぼくの使っている言語と、この曲が歌われている言語では、相性がよくないのだろう。だから、歌詞がうまく理解できなかったのだ。これまでも、コロニーの住人と話すなかでこういったことは何度かあり、そのたびにぼくは、それをささいな問題だと思って気にしてこなかった。
けれど、今のぼくはこの曲で歌われている言葉のほんとうの意味が知りたいと、心の底から思っていた。
「シャロンは、この曲の言葉がわかるの?」
「うん、わかるよ。フョードルに教えてもらったの!」
えへんと胸を張って得意げにシャロンは言った。
「わたしも最初この曲の歌詞がよくわからなかったわ。でもこの曲がほんとうに大好きだったからどうしても知りたくて、フョードルに教えてもらったの。『日本語』って言うんだって。東の果てにあった国の言葉らしいよ」
「今度、ぼくにもその言葉を教えてくれないかな?」
ぼくがひかえめに頼むと、シャロンは顔をよりいっそう輝かせて「もちろん!」と言ってくれた。
「この曲は、フョードルが持っていたCDプレイヤーではじめて聴いた曲なんだ。この曲を歌っていた人、『ユミ・キムラ』っていう人なんだけど、その人の歌声はほんとうに綺麗なの。こころが洗われる、っていうのかな。嫌なことがあっても忘れられちゃうんだ。このライアーは、その『ユミ・キムラ』がこの歌を歌うときに、自分で奏でていた楽器なんだって。だから、わたしもこの楽器が欲しくて、フョードルと一緒にあちこち探し回って、ようやく見つけたのがこれなの!いっぱい練習したのよ!」
「CDプレイヤーは、いまはフョードルの荷物の方に入れていて今はないから聴かせてあげられないけど、そっちの方もまた聞かせてあげるね。絶対感動するから」
シャロンは、ライアーを注意深くケースに戻すと、これまでに広げたものをひとつひとつリュックサックに丁寧に戻していった。
「ね、すごかったでしょ」
広げたものをリュックサックにすべて戻したシャロンは、ぼくの顔をのぞきこみながら言った。
「うん、すごかった」
今度はシャロンに気をつかったわけじゃなくて、本心からすごいと思って、ぼくは正直にそれを伝えた。
「いま私が見せたもののほかにも、世界にはすごいものがいっぱいあるんだよ。そしてそれは、『AlicE』やほかの機械が生まれる前は、人間が自分でつくっていたの」
「“人間が自分で”‥‥」
そこだけは、ぼくの中でいまも引っかかっていた。たしかに、人間は技術が進歩してからというもの、自分たちの手でなにかを直接生み出すということは少なくなったかもしれない。とくに、『AlicE』が誕生してからは、その流れが強くなったのは間違いない。けれど、人間が自分でなにかをつくることが、そんなに大事だろうか?ぼくにはよくわからなかった。
「人間が自分でなにかをつくることって、そんなに大切なことなの‥‥?」
なるべくシャロンの気を損ねないように、ひかえめに聞いてみる。しかし、シャロンはぼくのその言葉を聞いて、きっぱりと断言した。
「大事だよ!だって、人間が自分でつくったものには、一つ一つに“願い”と“意味”が込められているんだから!」
「“願い”‥‥?“意味”‥‥?」
やっぱりよくわかっていないぼくの反応に、シャロンは我慢ができなくなったように話しはじめた。
「たとえば、さっきのライアー!表面に模様が彫り込まれていたでしょう?」
「うん」
植物のツルや葉っぱのような形が複雑に彫り込まれていて、すごく綺麗だと思ったから、よく覚えている。
「あれはね、“アカンサス”っていう植物をモデルに掘られた模様なの。アカンサスは、何千年も前にこのヨーロッパにあった古代文明の神殿建築にも使われていた装飾で、その文明が滅んでしまったあとも、その古代文明のあとに続いた文明に受け継がれていったの。きっと、あとの時代の人たちも、この模様をきれいだと思ったから。それが、何千年も経った今、わたしのライアーにも受け継がれていると思うと、どう?すごいと思わない?」
その話を聞くと、たしかに何千年もの間同じ形を残してきたことはすごいと思ったけれど、それが願いや意味にどうして繋がるのだろう?やっぱりぼくにはよくわからなかった。
「ごめん、やっぱりよくわからないや」
ぼくが正直に言うと、シャロンは残念そうに眉を下げて、上げていた腰をぺたんとベンチに降ろしてしまった。その姿に、ぼくは心が痛むのを感じたけれど、わからないものはわからないのだ。今の話はよくわからなかったけれど、シャロンと話していくなかで、ぼくはこの短い間に、シャロンのことをほんとうにすごいと感じるようになっていた。だって、こんなに楽しそうに生きている人を、ぼくは見たことがなかったから。
‥‥彼女は、宇宙の終わりが怖くはないのだろうか。
「‥‥どうして、そんなに楽しそうにしていられるの?宇宙の終わりが来るのに」
気づいたらぼくは、思っていたことを口に出していた。言ってしまったあとで、しまったと思った。だって、こんな質問をするのはよくないと思ったから。宇宙の終わりに関係する話を、ぼくも同じ立場とはいえ、最後まで生きることのできない彼女に聞くのは、なんだか人のこころの踏みこんではいけない場所に踏みこむようなことに感じたから。
シャロンの顔からはさっきまでの花のような笑顔が消えて、口を引き結んだ表情になってしまった。
あぁ、やってしまった。
“嫌われる”と思って一気に気分が沈んだのを感じたが、シャロンはぼくの問いかけに、思いがけず答えてくれた。
「宇宙の終わりなんて怖くなんてないよ。‥‥怖がってなんかいられない。だって、わたしたちが生きている意味はきっとあるから」
そう言ったシャロンの目には、強い決意のようなものが光っていた。その決意がなにに対するものなのかは、ぼくにはわからなかったけれど。
ぼくは、宇宙の終わりの恐怖すらもはねのけてしまうような、彼女が見てきたもの、聞いてきたものがとても気になった。知りたいと思った。‥‥なぜなら、ぼく自身が、宇宙の終わりをとても恐れているから。
ぼくたちの間に、すこしの沈黙が漂った。
シャロンは、しばらくそのきれいな顔をうつむかせていたけれど、突然ぱっと顔を上げると、さっきぼくの質問に答えてくれた時と同じように真剣な表情でぼくの方に向き直った。
「ねえ、トーマ」
とても硬い声だった。
「わたしたちと一緒に、外の世界に行こうよ」
「え‥‥」
そんなことを言われるとは思ってもみなかった。
たしかに、シャロンの話を聞いたことで、ぼくの中では外の世界への憧れが大きく育っていた。“人間の手でつくられたもの”の素晴らしさというのは、ぼくにはよくわからなかったけれど、シャロンが見せてくれた本や映画、ゲーム、音楽のことは、もっと知りたいと思った。なにより、シャロンが話していた自然の光景が見たくてたまらなかった。
でも、無理だ‥‥。だって、もう宇宙の終わりはすぐそこまで迫っているじゃないか。今更、ぼくがコロニーの外で何かを見つけることができるとは思えなかった。さっきだって、シャロンの前で格好つけようとして、彼女のリュックサックを代わりに背負おうとしたけれど、女の子のシャロンにすら力で負けていたじゃないか。そんな非力なぼくに、外の世界に出て、いったい何ができるというのだろう?
それに何より、きっとおじいがそんなことは許してくれない。ぼくが外の世界へ行こうとすれば、おじいはきっとぼくを止める。そして、いつものように淡々と冷製に問い詰めてくるにちがいない。ぼくは、そんなおじいを説得できる気がしなかった。
「ぼくには、無理だよ‥‥」
「だって、ぼくは弱いから‥‥」
力なく呟いた言葉は、ぼくたちの間に重い沈黙となってのしかかった。
「‥‥そんなことないよ!外へ出るのに必要なのは、外の世界を知りたいっていう気持ちだけ!あとはそこに実際に行く勇気だけだよ!」
シャロンは諦めずにぼくを奮い立たせようとする。そこまでぼくを熱心に誘ってくれるのはうれしかったけれど、やっぱりぼくは、勇気が出なかった。
しかし、ぼくの家の前でおじいたちが話していたことによれば、フョードルはそもそもこのコロニーに永住するつもりじゃなかったか‥‥?おじいにフョードルたちの来訪を報せた老人が勘違いしているのか、シャロンが知らされていないだけなのか‥‥。けれど、一緒に移住するのにそれを秘密にする理由なんてあるだろうか?
ぼくは感じた疑問をシャロンに聞こうと口を開いたが、その疑問を口に出す前に、広場の外からぼくたちを呼ぶ声が聞こえてきて、会話が途切れてしまった。
「おーい、シャロン。話が終わったぞ」
顔を向けると、フョードルとおじいが並び立って広場の入り口に立っていた。並んでいるのを見ると、改めてフョードルの大きさがわかる。
ぼくたちは自然と話を切り上げて、ベンチから立ち上がった。シャロンはベンチから立ち上がると、ものすごい勢いで走って行って、フョードルに飛びついていた。隣のおじいが巻き込まれかけて、腰を抜かしかけていた。
「ああ、きっとぼくも、ああやってタックルされたんだろうな」、とその威力に内心おののきつつ、明るく華やかな彼女が来たことで、ぼくの日常が大きく変わっていく予感にひそかに喜びながら、彼女につづいて広場をあとにした。
◆
5368年11月16日
結局、フョードルとシャロンは、『見届ける者(ゲイザー)』を引退して、コロニー5に永住するらしい。3Dプリンターで造られたドーム型の家と、このコロニーに適応した『AlicE』のデータが渡されて、二人は正式にぼくたちの仲間として迎えられた。二人の家は、ぼくの家のすぐ近くで、歩いて2分もかからない距離にある。
けれど、シャロンはそのことに納得ができていないようで、あれから顔を合わせるたびに文句を言っている。なんでも、フョードルはある日突然、『見届ける者(ゲイザー)』をやめると言い出して、シャロンに荷物をまとめるように言いつけると、あっという間に身の回りの物の整理を済ましてしまって、このコロニー5にやってきたそうだ。シャロンは、引っ越しが決まったときからずっと、フョードルから突然の引退の理由を聞かされていなくて、それが余計に彼女の怒りと不満を大きくしているようだった。
「ほんと信じられないっ!もうここへ来て二ヶ月よ!?なんでずっと理由も聞かせてくれないのよ!」
今も、シャロンはぼくの前で怒りを爆発させている。シャロンたちの定住が決まってからというもの、フョードルが家にいない間はずっとこれだ。最近のフョードルは、決まった時間にどこかへ出て行っては、これまた決まった時間に帰ってくるらしい。放っておかれているシャロンは、毎日ぼくの家へ来ては、機嫌が良くて一緒にゲームをしたり映画を見たりするとき以外は、こうしてフョードルへの不満を吐き出している。
「そもそも!ほんとうに突然「引退する。コロニーに移り住むぞ。荷物をまとめろ」なんて言うだけ言って、どこに行くかも言わずに連れてくること自体おかしいじゃない!あの、でいだらぼっち!イエティ!足くさ巨人!」
「もういいわ!今日こそは絶対に聞き出してやるんだから!」
いつもと同じように意気込んでいるシャロンを見ながら、心の中で「今日も聞き出せないんだろうな」と思いながら、シャロンをなだめようとしたその時だった。
「たいへんだ!!」
突然、表の通りから、ひどくしわがれた大声が聞こえたかと思うと、息を乱した老人の一人が走ってきた。この老人も、おじいほどではないけれど、車椅子を使わずにすむくらいには健康なようだったが、それでも本気で走るのは辛かったのか、苦しそうに咳きこんでいる。それでも息も絶え絶えに、「たいへんだぞぅ」という言葉を繰り返している。
いったい何事かと、僕たち以外にも、周囲の住宅から人が顔をのぞかせてきた。
ぼくたちの視線を受けながら、汗だくになった老人は叫んだ。
「南地区の『マルーン』の女子が、赤ん坊を産んだらしい!!」
マルーン
第二章 『見届ける者』
5368年9月22日
ぼくは、走るのが苦手だった。走ることだけじゃなくて、運動自体、あまり得意じゃない。今も突然コロニーに来たという来訪者たちの話が気になって、急いでおじいたちの後を追いかけたのに、コロニーの中心につくられた集会所にようやく辿りついたときにはもうすでに老人たちが集まっていて、ちょっとした人だかりができていた。
その人だかりの中心では、周りの老人たちの二倍近い身長がある、これまで見たことがないほどの大男とおじいが話をしていた。おじいは老人の中ではしっかりとした体格だったけれど、大男の前ではほかの老人たちと変わらないほど小さく弱く見えた。大男はこっちに背中を向けていて、その背中には、ぼく一人が入れそうなくらい大きなリュックサックを背負っている。背を向けているので顔は見えないけれど、男の低い声は、少し離れたぼくのいる場所にまで響いてきた。
ふとおじいが大男の背中越しにぼくの姿をみとめると、ぼくの方を指さして何か言ったようだった。大男が振り向こうとしたその時、
「わぁ!わたしと同じくらいの子がいる!」
突然後ろから金切り声が聞こえたかと思うと、振り返る間もなく腰のあたりに衝撃が走った。かと思うと、視点がひっくり返って地面が目の前に現れた。とっさに手を突き出して顔から着地するのはさけたが、そのあとすぐに更なる衝撃に背中を襲われる。ぼくの腕では耐えきれず、結局地面に潰れてしまった。潰れたぼくの背中には、何やらずっしりとした重みを感じる。
しかし、その重みはすぐになくなり、今度は腕をつかまれてひっくり返された。なにが起こっているのかまったく理解できず、戸惑いと恐怖で見開かれていたぼくの目に、金色のなにかが飛び込んできた。
それが髪だと気づくのに、すこし時間がかかった。太陽の光を透かして輝く、僕の黒い髪とは正反対の、綺麗な金髪。ふわりと空気をふくんでふくらんでいた髪から、少しずつ空気が抜けて、それがぼくの顔に向かって垂れ下がり、お菓子のような甘い匂いがふわりと漂ってきた。さらりとした髪の間から、こぼれんばかりの喜びに満ちた青い瞳がきらきらとぼくを見下ろしている。
心臓が、ひとつ大きく、どくんと脈打つのを感じた。
さっきの一連のめまぐるしい視点の変化が、彼女に後ろからタックルされたことによるものだと気づいたのは、さっきの大男の声で、彼女に見惚れていた意識が現実に戻されたあとだった。
「こら、シャロン。嬉しいのはわかるが危ないだろう。うちの娘がすまない、坊や」
女の子もまた、大男と同じように大きなリュックサックを背負っていた。大男はぼくにまたがっていた女の子のリュックサックを掴んで、それを背負った女の子ごと片手で軽々と持ち上げると、残った片腕でぼくのことも持ち上げて立たせてしまった。こんなにも力の強い人間をはじめて見たぼくは、その腕のあまりの太さに驚愕した。ぼくの体のどの部分よりも太く、大きく膨らんだ腕は、その気になればなんでも潰してしまえそうなほど強そうだったけれど、ぼくに触れるときにはこのうえなくやさしい力加減でぼくを立たせてくれた。
立ち上がってから改めて間近で男を見上げると、腕だけではなく、体のすべてが大きいことが見てとれた。ごつごつと筋肉が張り出した体に、茶色の毛むくじゃらの髭が伸びた顔がちょこんと乗っている。首についた筋肉が大きすぎて、首がないように見えるのだ。そのあまりに強そうな見た目に、ぼくの喉は緊張感から自然と唾を飲みこんでいた。けれど、男はその荒々しい見た目からは想像できないほど、とても礼儀正しく挨拶してきた。
「突然の訪問、申し訳ない。俺は、『ゲイザー(見届ける者)』のフョードル。そして、この子が…」
「シャロン!シャロンよ!」
フョードルと名乗った男の腕に、いまだにリュックサックごと抱えられて宙に浮いている女の子はそう叫ぶと、足をばたつかせて、またきゃーきゃーと騒ぎはじめた。どれだけ女の子が足をバタバタさせても、フョードルはまったく微動だにしなかったが、少し呆れた様子でぼくの方に向き直ると、興奮がとまらない彼女のこころを代弁するように言った。
「すまないね。自分と同じ年頃の子に会うのがはじめてなんだ。許してやってくれ」
そんなの、ぼくだって初めてだ。今までぼく以外の子どもの『マルーン(残される者)』なんて、見たことも聞いたこともなかった。‥‥ましてや、こんなに綺麗な子に会ったことなんて、ぼくにはない。
彼女の青い瞳と目が合うと、頰が熱くなるのを感じた。それを誤魔化すように、頭を振って「大丈夫」と伝えると、彼女はにっこりと笑って、「あなたの名前は?」と尋ねてくる。ぼくは自分の名前を名乗りながら、今ぼくの目に映っている世界が、なんだかさっきまでの世界よりも鮮やかになったような気がしていた。まるで、カメラのレンズが切り変わったかのように。
ぼくの名前を聞いて、またはしゃぎはじめた彼女を見て、心臓の鼓動は、さらに大きく響きはじめた。
◆
シャロンが騒ぎ続けたことで、場は話し合いどころではなくなり、おじいはぼくに、シャロンにコロニーを案内する役目を言いつけると、フョードルだけを連れて自宅に行ってしまった。
残されたぼくは、まともにシャロンの方を見ることができず、名前を呼ぶこともできなかった。はじめは面白がっていたシャロンだったけれど、いつまでも恥ずかしがっているぼくにしびれを切らしたようで、「ねえ、こっち見てよ」と言いながらぼくの視界に入ろうとしはじめた。しかし、それでもぼくが頑なに顔を向けなかったので、彼女はぼくの顔を手で挟んで顔を固定してしまうと、「ちゃんと顔見て、名前呼んで!」とただ一言、けれど絶対に逆らえない強い言葉をかけられてしまった。
ぼくは、あまりの恥ずかしさに言葉をつまらせながら、「シャロン」と彼女の名前を呼ぶと、彼女は満足したように優しく笑って、ぼくの手を取った。
「だいじょうぶ、緊張しなくていいよ」
やさしく諭されるように言われてしまった。ぼくは繋いだ手から感じるぬくもりと、彼女に気をつかわせてしまった恥ずかしさとで、ますます顔が赤くなるのを感じた。そこでふと、彼女の口の動きと、ぼくの耳に聞こえてくる音が違うことに気がついた。彼女の眼に見惚れていたとき以外は、ずっと彼女の顔を見ることができなかったので気が付かなかったが、どうやら彼女が話している言語は、ぼく話している言語とは違うもののようだった。
ぼくたち人間は、脳に埋め込まれたマイクロチップのおかげで、たとえ互いが使っている言語が違っていても、相手の言っていることが正しく理解できるようになっている。相手の言葉を耳で聞き取ると、その情報がマイクロチップへと送られ、それがどの言語にあたるのかを解析し、それを翻訳したうえで、相手の声を完全に再現した合成音声で再生してくれる。だから、たとえ相手がどんな言語を使っていようと、マイクロチップ内に保存されている言語データにその言語が含まれていれば、なんの問題もなく意思疎通することができる。
むかしはほかの言語の文字を読んだり、話したりすることができるようになるには、その言語を一から勉強して、十分に使えるように練習しなければいけなかったらしい。何度も何度も同じ単語や文章を使うことを繰り返して、ようやく習得できたそうだ。当然、言語ごとに文字も言葉もぜんぜん違うので、覚えようとする言語の数が多ければ、それに比例して訓練に必要な時間は増えていく。だから、むかしは複数の言語を喋れることが、ひとつのステータスになっていたこともあるらしい。
コロニー5にも、ぼくと違った言葉を話す人間は少なからずいる。今まではそんな人間に会っても気にも留めなかったけれど、今は、彼女が話しているのが何という言葉なのか、とても知りたかった。
「ね、このコロニーを案内してよ」
手を繋いだまま、シャロンはぼくを街の方へと引っ張って行く。どこになにがあるのかもまったくわからないだろうに、ずんずん先へ進んでいくその自信満々な様子に、なんだかぼくの方も勇気づけられて、がちがちになって言うことを聞かなかった身体が少し軽くなった気がした。
引っ張っられていた形から、小走りでシャロンの隣に並んで、彼女が背負っていた大きなリュックサックを代わりに持つことを申し出た。少しでも頼りがいのある男だと思われたかったから。
けれど、シャロンから手渡されたリュックサックは信じられないほど重く、それを背負ったぼくはあっという間に息切れして、足の進みはどんどん遅くなっていった。シャロンは笑いながら、「重いよね。だいじょうぶだよ、わたし持てるから」と言ってぼくの肩からリュックサックを外すと、もう一度自分で背負い直した。
肩から重荷は消えたけれど、そうして軽くなって喜んでいる自分の肩が、ぼくはとても恥ずかしくて、情けなかった。
シャロンは、コロニーを見ること自体がはじめてなようで、街のあちこちに目を奪われている。同じ形、大きさのドーム型の家が連なっているのを見て、巨大生物の卵だと勘違いしたり、街の整備をしている『AlicE』が入った人型の機体を、本物の人と間違えて後ろから話しかけたりと、何度もぎょっとさせられるくらい、コロニーのことを知らなかった。
しかし、彼女ははじめこそ、そういったものに目を奪われて、ぼくにいろいろ質問してきていたが、ぼくがそれらのものを説明していくと、徐々に興味をなくしていったのか、「ふーん」と言って、もう見ることはなくなってしまった。
街を案内して回るなかで、シャロンは彼女とフョードルのことを教えてくれた。どうやら彼女は、フョードルとふたりで旧スイスという、コロニーのない場所を拠点にしていたらしい。ただ、彼女たちは、そこを生活の拠点にしながら、あちこちに出掛けては、外の世界をめぐり歩く生活をしてきたという。フョードルの言っていた『ゲイザー(見届ける者)』という耳慣れない言葉についても教えてくれた。『ゲイザー』は、人間が『スリープ計画』によってその数を徐々に減らし、コロニーごとに集まっていく時代の流れに逆らって、コロニーの外に留まる、もしくは出ていった人たちのことらしい。彼らはコロニーの外に拠点を置いて、かつての人間のように暮らし、そして外の世界を探索する。コロニーの中にはないもの、人間が遺したものを見て、自分たちの最後の時までそれらを見届ける。だから、『見届ける者』という名前がつけられたのだと。
多くの『マルーン』が、むかしはコロニーを飛び出して『ゲイザー』になっていたらしい。フョードルもその一人で、彼が住んでいたコロニーを訪ねてきた『ゲイザー』の話のとりこになって、周りの反対を押し切って彼について行ったそうだ。
シャロンは外の世界のことをさかんにしゃべってくれた。彼女が住んでいたという場所のことも。そびえ立つ山々の雄大さ、力強く水を落とす滝の迫力、きらきらと輝く川のせせらぎと、その岸辺にそよぐ木々の美しさ。
話を聞いていくうちに、ぼくは、彼女がこんなにも夢中になって話す外の世界は、いったいどれほど美しいのだろうかと知りたくなった。彼女の話に出てくるような景色は、このコロニーにはない。すべてのコロニーは、人間が生活しやすい、なるべく平坦な大地が続く場所を選んでつくられているからだ。このコロニー5は、もともと旧市街があった場所のすぐ近くにつくられたので、コロニーを出てしばらくは、無人の古い街並みが続く。よくコロニーを抜け出していたぼくは、旧市街へはよく足を運んだが、その先へは行ったことがなかった。だから、シャロンが話すどの景色も、ぼくは見たことがなかった。
きらきらと顔を輝かせながら楽しそうに語るシャロンの話は、ぼくの心を大きく揺り動かした。そこにいけば、どんな音が聞こえるのだろう?どんなにおいがするのだろう?その景色を見ることができたら、ぼくは、どんな気持ちになるのだろう?まだ見たことのないものへの想像が膨らんで、妄想にはまりこんでいたぼくは、シャロンの一際大きな声で我に帰った。
「でもわたしは、人間がつくったものが一番だと思うの!」
「え?」
ぼくはきっと、すごく間抜けな顔をしていたんじゃないかと思う。だって、ぼくの顔を見たシャロンに笑われてしまったもの。でもぼくがそんな顔になったのは、彼女が言ったことがあまりに意外なことだったからだ。
人間がつくったものが、はたして今まで彼女が話していたもののなによりも魅力的だろうか?たしかに、人間はその知恵を使って、いろいろなものをつくり出してきた。このコロニーという場所は、そういうもので溢れかえっている。3Dプリンターで造られた、頑丈で過ごしやすい家、人間の指示がなくとも正常に街を管理してくれる、『Alice』が操るロボット体、菌やウイルスの侵入と繁殖を防ぎ、たとえ病気になったり介護が必要になっても最適な治療をしてくれる全自動医療システム。これらの人間の叡智の結晶は、たしかにすごいと思うし、ぼく自身もその恩恵を受けているから、感謝はしている。
でも、ぼくにはそれらのものが、ひどくか細く、空しいもののように思えた。
だって、そういうものは全部、意味がなかったじゃないか。
たしかに、人間はこの宇宙で、自分たちにできることをひとつひとつ増やして、時代を経るごとにそれを積み重ねていった。けれど、そうやって積み重ねたものは結局、世界‥‥、宇宙には勝てなかったじゃないか。
宇宙の終わりが来てしまえば、跡形もなく消え去ってしまうような、もろく、空しく、頼りないもの‥‥。そんなもの、この世界に比べてしまえば本当にちっぽけなものじゃないか。
そんなものの、いったいなにがすごいというのだろう?どう考えても、シャロンが話していたような、世界が生み出した自然の光景の方が人間の生み出したものよりもすごいじゃないか。
「ここにあるものがそんなに気に入ったの?」
しかしぼくは、シャロンが好きだというものを否定して彼女に嫌われたくなかったので、こころのなかで思ったことは口には出さず、シャロンの考えをうかがうように聞いた。するとシャロンは、一瞬きょとんとしたような顔になって、何を言っているのかわからないというような反応になった。
しかし、すぐになにかに思い至ったのか、はっとした顔になると、今度は笑いながらぼくの言ったことを否定した。
「ちがうちがう。わたしが言ってるのは、人間が“自分たちの手で創ったもの”のことだよ」
「“自分たちの手で”‥‥?」
シャロンの言っていることの意味がよくわからなかった。3Dプリンターや『AlicE』、全自動医療システムは、すべて人間がつくり出したものだ。たしかに、今の『AlicE』は、人間の指示を受けることなく、新しいシステムや医療を生み出すことができるが、元をたどれば『AlicE』をつくったのは人間なのだから、それらのものも人間がつくったと言っていいのではないか?
ぼくが彼女の言ったことをいまいち飲み込めていないのを見てとったシャロンは、「うーん」と言って悩んだあと、「よし」と言ってぼくの手を握った。
「わかった。じゃあ、見せてあげる!」
そう言うとシャロンは、またぼくのことを引っ張って、近くの広場へと入って行った。
◆
広場に入ったぼくたちは、入り口にほど近い場所に等間隔に設置されているベンチに向かい合うように座った。シャロンは背負っていたリュックサックをおろすと、その口を開いて中に手を入れ、ゴソゴソとしはじめた。
「じゃあ、まずはねー‥‥これ!」
シャロンは顔を輝かせて「じゃじゃーん」なんて言いながら、リュックサックに突っ込んでいた手を勢いよく取り出した。その手には、ぼくが今まで見たことがないなにかが握られている。四角い厚みがある形に、表面にはなにやら独特の装飾がされていた。なんだろう‥‥、電子機器の類ではなさそうだけれど‥‥。
「なに、これ?」
ぼくが聞くと、シャロンはにまにましながら嬉しそうに、その四角い物を前面に出してきた。
「これはねー、本です!」
「え、本‥‥!?」
ぼくが知っている本は、薄いタブレット端末だ。けれど、いまシャロンが手に持っているものは、どう見てもブロック一つ分くらいの分厚さがある。旧時代のタブレット端末はあんなに分厚かったのか‥‥?なんて思っていると、なんとブロック型の旧時代タブレットがいくつかに分裂した!‥‥のではなく、あの分厚さは何枚か同じものが重なっていたもので、それが今はバラバラになっただけだった。しかし、バラバラになっても、ひとつひとつがそこそこの厚みを持っている。見た目の質感から、やはりタブレットではないのだろうということだけは分かった。
シャロンはそのうちの一つを手に取ると、それを裂くように二つに開いてみせた。すると、その間には無数の薄いペラペラとしたものが挟まっていて、そこに文字が書いてあるのを見せてくれた。そこでようやく、この厚みのすべてが、その一枚一枚の薄いペラペラが積み重なってできた物だと分かった。
「そういう仕組みになってるのか!」
タブレットでは、すべての文章が一枚の横並びのページに表示されていて、画面をスワイプしてそれを読み進めるのに対して、このペラペラを重ねた本の場合は、積み重ねられたペラペラをめくっていけば、続きを読むことができるのだ。なるほど。これならたしかに同じ大きさのペラペラを何枚も重ねれば、どれだけ長い話もまとめることができる。
けれど、内容が長くなれば長くなるほど、ペラペラの量は増えて、本は分厚くなっていく。タブレットの方がいいのではないかと思った。
「でも、こんなに分厚いと持ち運ぶのが大変でしょ」
「むかしの人間も、そう考えたから、どんどん本をデータ化して『AlicE』のなかにデータを移していったんだろうね。たしかに、持ち運ぶにはタブレットの方が便利だから。でも、それで『紙』の本を大事にしなくなっちゃったから、『AlicE』の中にあったデータが消えちゃったとき、人間はほとんどの本を復元することができなかったんだよ」
たしかに、その通りだった。利便性だけを追求しすぎた結果が220年前の悲劇につながったことを考えると、タブレットの中に保存するデータ以外にも、なにかしらの形でそれを残すことは必要だったろう。便利なことを追い求めて、結局不便になってしまったら元も子もない。
「それにね。わたしはこの手触りも好きなんだ。さらさらしてて、めくっていると楽しいの」
そう言って、シャロンは『紙』と呼んだペラペラをつまんで左から右へ、右から左へとめくってみせる。たしかに、この独特の手触りは、ほかのものにはない感覚で、触っていて楽しいかもしれない。けれど、ぼくはやっぱり、同じものならタブレットでいいんじゃないかと思った。それは単にぼくが慣れているだけだからかもしれないけれど。
しかし、ふとシャロンが手にしている本と、ぼくたちの間に並べられている本に視線をやって、ぼくは違和感に気がついた。『ドラえもん』、『アルジャーノンに花束を』、『人間の土地』、『マジック・ツリーハウス』、『ギヴァー』、『風立ちぬ』、『息吹』、『獣の奏者』‥‥、脳に埋め込まれたマイクロチップは、目の前に並べられた、それぞれ異なる言語で書かれた言葉を一文字ずつ読み取っていく。けれど、そこにあるどの本も、ぼくが見たことも、聞いたこともないタイトルだった。
「どれも見たことも聞いたこともないや‥‥」
ぼくがつぶやいた言葉に、シャロンは笑いながら言った。
「あたりまえよ!だって、この本のデータは、『AlicE』のデータ消失事件で全部消えちゃったんだもん!」
ぼくは、自分の目も口も大きく見開かれていくのがわかった。それくらい、驚くべきことだったから。ぼくが知っている本というのは、約220年前の『AlicE』の大規模データ消失事件以降に記録されたものだけだった。それ以前の本が残されていたなんて、聞いたこともない。
基本的に、『AlicE』が知らないことはまずない。なぜなら、サービスが開始されてからの数百年の間に、人間の持つすべての知識やデータ、技術などが『AlicE』にダウンロードされているからだ。だから、人間がこれまでに知ったことやつくったものなら、“基本的に”『AlicE』が知らないことはない。しかし、そこにはある例外があった。それは、人間がつくり出してきた本や映像、音楽といった文化的なデータだ。
今から220年くらい前に、『AlicE』に保管されていた一部のデータ群のほとんどが消失するという大事件が発生した。当初は『AlicE』の自己管理システムの不具合や、そのほかの原因による事故が疑われていたようだけれど、後々になって『スリープ計画』の急進派グループによる、世界的な同時サイバー攻撃による事件だったことが分かった。
彼らは思うように進まない『スリープ計画』に腹を立てて、その原因が人間の娯楽や文化にあると考え、犯行に及んだそうだ。だから彼らはそれらのデータ、特に本やゲーム、音楽などのデータに標的をしぼった攻撃をおこなった。事件発覚後、犯人たちはひとり残らず捕まったそうだが、失われたデータが戻ることはなかった。
彼らが『AlicE』に入力されている街の管理システムや全自動医療システムといったものを狙わなかったのは、彼らの目的は『人間の殺害』ではなく、『安らかな安楽死』であるため、それらのシステムを破壊することで、人間が苦しんで死ぬことは望んでいなかったからだそうだ。捕まった犯人たちは、彼らの理念や理想といった、聞かれてもいないことまで得意気にぺらぺらと喋ったらしい。
悪意のある人物からの攻撃が原因だったとはいえ、結果的に人間は、それまでに蓄えてきたほとんどの本やゲーム、音楽、さらには食事といった文化をことごとく失ってしまった。もちろん、220年前の事件以降に生み出された新しい作品や知識は記録されてきたが、それまでに人間が蓄積してきたものと比べると、すずめの涙ほどの量しかなかった。220年前に失われたものは、もう永遠に見ることができなくなってしまった。
けれど今、その本が、ぼくの知っている形ではなくても目の前にある。これが驚かないでいられるだろうか?ほんとうにすごいと思った。こんな保管することが大変な本を残してきた人間のことも、それを見つけたシャロンのことも。
シャロンはぼくの反応に満足したのか、「こんど読ませてあげるね」と言って本をまとめると、またリュックサックのなかに手を突っ込んで、ガサゴソと中をあさりはじめた。
ぼくは、最初にとんでもない物を出されたことで、すっかり自分が、シャロンが次に出すものにわくわくしていることに気がついた。
「じゃあつぎは‥‥」
「これと‥‥、これと‥‥、これ!」
シャロンは、これまた見たこともないようなヘンテコな形をしたものを一気にいくつも取り出してみせた。
「ねえ、これはなんなの?」
「えっとねー。映画のDVDでしょ、ゲームでしょ、そして、なんとライアーです!」
また「じゃーん」と言いながら、最後のものを特に強調して見せてくれた。最初の『映画』と『ゲーム』の二つは知っている。映画は、『AlicE』が世界中の機体につけられたレンズを通して視た映像を記録して、それを合成していろいろな映像をつくったものだ。自分の好みのジャンルやストーリーを伝えれば、すぐにそれにあったものをつくってくれる。ゲームも同じで、『AlicE』がつくったものを、タブレットを使って遊ぶことができる。専用のヘルメットをつければ、あたり一面に仮想空間が広がった状態で遊ぶこともできて、これはとても迫力がある。けれど、そういった映画やゲームが映し出す世界は、映像は綺麗なのに、なぜかどこか味気ないように感じられて、ぼくはあまり好きではなかった。
最後のものだけ、なにをするものなのかわからなかった。ライアーと言っていたけれど、いったいなんだろう?リュックサックから取り出されたときには、ひとまわり大きなケースに入れられていたそれは、木製のようで、上の方に大きく穴の開いた、しなやかな曲線を描いた形をしていた。穴の上を通って、全体の上から下へ向かって細い糸が張り巡らされている。表面には、植物のような文様が彫り込まれていて、それがこの『ライアー』を美しく着飾らせているようだった。
「そのライアーって、なんなの?」
シャロンはさっきよりもずっと興奮した様子で、ずい、とぼくの顔の前に、『ライアー』と自分の顔を押し出してきた。顔の距離があまりに近くなったものだから、ぼくはすっかり忘れていたあの照れ臭さをまた思い出して、頰が熱くなるのを感じた。
シャロンはそんなぼくの様子には気がつかなかったようで、声を張り上げて説明を続ける。
「これはね、楽器なんだよ!」
楽器。音楽を奏でるもの。知識として、『AlicE』に教えてもらったことはある。けれど、実物は見たことがなかったし、それが実際にどのように音を出すのかもわからなかった。
音楽もまた、『AlicE』がつくることのできるものの一つだ。ぼくにもいくつかお気に入りの曲がある。けれど、ぼくはすぐに飽きてしまって、何度も新しい曲を『AlicE』につくってもらっていた。
旧時代の音楽、ましてやそれを奏でていた楽器というものの音を、ぼくはもちろん聴いたことがなかった。きっとぼくだけじゃなくて、このコロニーにいる老人全員がそうだ。少なくとも、このコロニーに旧時代の音楽は残っていないから。
「これ、音を出すことはできるの?」
その音を聴いてみたいという気持ちがはやり、ぼくは焦ったようにシャロンに聞いた。シャロンは笑顔で「もちろん」と言うと、上下に張り巡らせた糸に指を添え、おもむろにそれを弾きはじめた。すると、弾かれた糸が震えて、ろんろん、とやさしく澄んだ音が流れた。美しい音だった。
最初はただ単に音を鳴らしていたシャロンの指は、一つのメロディを奏ではじめた。そのメロディもまた、ぼくの知らないものだ。シャロンはメロディに合わせて、そこに自分の声をのせるように歌いはじめた。
“呼んでいる 胸のどこか奥で”
“いつも心踊る 夢を見たい”
“かなしみは 数えきれないけれど”
“その向こうで きっとあなたに会える”
シャロンの声は凛としていて、美しい形をなして空気を跳ねのけるように力強くあたりに響いた。シャロンがライアーの音色にのせて歌うその曲は、はじめて聴くはずなのに、どこか懐かしくなるような曲だった。無性にだれかの胸に飛び込んで、泣いてしまいたいような気持ちになる。実際、目頭が熱くなるのを感じたが、シャロンの前で泣くような格好悪いことはしたくなかったので、浮かんできた涙を必死に押しとどめた。
しかし、その曲には、ぼくには上手く理解できない歌詞がいくつかあった。その原因はたぶん、マイクロチップの翻訳機能の問題だ。
マイクロチップの翻訳機能は、まったく違う言語を使う人同士の言葉を、お互いの言語に置き換えてくれる。つまり、相手がちがう言語で「わたし」と言ったとき、それがぼくの言語における「わたし」にあたる言葉に変換されるのだ。その変換精度は高く、明確な意味を持つ言葉であれば、自分が言いたいことを完全に相手に伝えることができる。けれど、それぞれの言語が持つ雰囲気の違いや、独特の感覚といったものの解像度はまちまちで、言語同士の相性によって精度が左右されることもある。
おそらく、ぼくの使っている言語と、この曲が歌われている言語では、相性がよくないのだろう。だから、歌詞がうまく理解できなかったのだ。これまでも、コロニーの住人と話すなかでこういったことは何度かあり、そのたびにぼくは、それをささいな問題だと思って気にしてこなかった。
けれど、今のぼくはこの曲で歌われている言葉のほんとうの意味が知りたいと、心の底から思っていた。
「シャロンは、この曲の言葉がわかるの?」
「うん、わかるよ。フョードルに教えてもらったの!」
えへんと胸を張って得意げにシャロンは言った。
「わたしも最初この曲の歌詞がよくわからなかったわ。でもこの曲がほんとうに大好きだったからどうしても知りたくて、フョードルに教えてもらったの。『日本語』って言うんだって。東の果てにあった国の言葉らしいよ」
「今度、ぼくにもその言葉を教えてくれないかな?」
ぼくがひかえめに頼むと、シャロンは顔をよりいっそう輝かせて「もちろん!」と言ってくれた。
「この曲は、フョードルが持っていたCDプレイヤーではじめて聴いた曲なんだ。この曲を歌っていた人、『ユミ・キムラ』っていう人なんだけど、その人の歌声はほんとうに綺麗なの。こころが洗われる、っていうのかな。嫌なことがあっても忘れられちゃうんだ。このライアーは、その『ユミ・キムラ』がこの歌を歌うときに、自分で奏でていた楽器なんだって。だから、わたしもこの楽器が欲しくて、フョードルと一緒にあちこち探し回って、ようやく見つけたのがこれなの!いっぱい練習したのよ!」
「CDプレイヤーは、いまはフョードルの荷物の方に入れていて今はないから聴かせてあげられないけど、そっちの方もまた聞かせてあげるね。絶対感動するから」
シャロンは、ライアーを注意深くケースに戻すと、これまでに広げたものをひとつひとつリュックサックに丁寧に戻していった。
「ね、すごかったでしょ」
広げたものをリュックサックにすべて戻したシャロンは、ぼくの顔をのぞきこみながら言った。
「うん、すごかった」
今度はシャロンに気をつかったわけじゃなくて、本心からすごいと思って、ぼくは正直にそれを伝えた。
「いま私が見せたもののほかにも、世界にはすごいものがいっぱいあるんだよ。そしてそれは、『AlicE』やほかの機械が生まれる前は、人間が自分でつくっていたの」
「“人間が自分で”‥‥」
そこだけは、ぼくの中でいまも引っかかっていた。たしかに、人間は技術が進歩してからというもの、自分たちの手でなにかを直接生み出すということは少なくなったかもしれない。とくに、『AlicE』が誕生してからは、その流れが強くなったのは間違いない。けれど、人間が自分でなにかをつくることが、そんなに大事だろうか?ぼくにはよくわからなかった。
「人間が自分でなにかをつくることって、そんなに大切なことなの‥‥?」
なるべくシャロンの気を損ねないように、ひかえめに聞いてみる。しかし、シャロンはぼくのその言葉を聞いて、きっぱりと断言した。
「大事だよ!だって、人間が自分でつくったものには、一つ一つに“願い”と“意味”が込められているんだから!」
「“願い”‥‥?“意味”‥‥?」
やっぱりよくわかっていないぼくの反応に、シャロンは我慢ができなくなったように話しはじめた。
「たとえば、さっきのライアー!表面に模様が彫り込まれていたでしょう?」
「うん」
植物のツルや葉っぱのような形が複雑に彫り込まれていて、すごく綺麗だと思ったから、よく覚えている。
「あれはね、“アカンサス”っていう植物をモデルに掘られた模様なの。アカンサスは、何千年も前にこのヨーロッパにあった古代文明の神殿建築にも使われていた装飾で、その文明が滅んでしまったあとも、その古代文明のあとに続いた文明に受け継がれていったの。きっと、あとの時代の人たちも、この模様をきれいだと思ったから。それが、何千年も経った今、わたしのライアーにも受け継がれていると思うと、どう?すごいと思わない?」
その話を聞くと、たしかに何千年もの間同じ形を残してきたことはすごいと思ったけれど、それが願いや意味にどうして繋がるのだろう?やっぱりぼくにはよくわからなかった。
「ごめん、やっぱりよくわからないや」
ぼくが正直に言うと、シャロンは残念そうに眉を下げて、上げていた腰をぺたんとベンチに降ろしてしまった。その姿に、ぼくは心が痛むのを感じたけれど、わからないものはわからないのだ。今の話はよくわからなかったけれど、シャロンと話していくなかで、ぼくはこの短い間に、シャロンのことをほんとうにすごいと感じるようになっていた。だって、こんなに楽しそうに生きている人を、ぼくは見たことがなかったから。
‥‥彼女は、宇宙の終わりが怖くはないのだろうか。
「‥‥どうして、そんなに楽しそうにしていられるの?宇宙の終わりが来るのに」
気づいたらぼくは、思っていたことを口に出していた。言ってしまったあとで、しまったと思った。だって、こんな質問をするのはよくないと思ったから。宇宙の終わりに関係する話を、ぼくも同じ立場とはいえ、最後まで生きることのできない彼女に聞くのは、なんだか人のこころの踏みこんではいけない場所に踏みこむようなことに感じたから。
シャロンの顔からはさっきまでの花のような笑顔が消えて、口を引き結んだ表情になってしまった。
あぁ、やってしまった。
“嫌われる”と思って一気に気分が沈んだのを感じたが、シャロンはぼくの問いかけに、思いがけず答えてくれた。
「宇宙の終わりなんて怖くなんてないよ。‥‥怖がってなんかいられない。だって、わたしたちが生きている意味はきっとあるから」
そう言ったシャロンの目には、強い決意のようなものが光っていた。その決意がなにに対するものなのかは、ぼくにはわからなかったけれど。
ぼくは、宇宙の終わりの恐怖すらもはねのけてしまうような、彼女が見てきたもの、聞いてきたものがとても気になった。知りたいと思った。‥‥なぜなら、ぼく自身が、宇宙の終わりをとても恐れているから。
ぼくたちの間に、すこしの沈黙が漂った。
シャロンは、しばらくそのきれいな顔をうつむかせていたけれど、突然ぱっと顔を上げると、さっきぼくの質問に答えてくれた時と同じように真剣な表情でぼくの方に向き直った。
「ねえ、トーマ」
とても硬い声だった。
「わたしたちと一緒に、外の世界に行こうよ」
「え‥‥」
そんなことを言われるとは思ってもみなかった。
たしかに、シャロンの話を聞いたことで、ぼくの中では外の世界への憧れが大きく育っていた。“人間の手でつくられたもの”の素晴らしさというのは、ぼくにはよくわからなかったけれど、シャロンが見せてくれた本や映画、ゲーム、音楽のことを、もっと知りたいと思った。なにより、シャロンが話していた自然の光景が見たくてたまらなかった。
でも、無理だ‥‥。だって、もう宇宙の終わりはすぐそこまで迫っているじゃないか。今更、ぼくがコロニーの外で何かを見つけることができるとは思えなかった。さっきだって、シャロンの前で格好つけようとして、彼女のリュックサックを代わりに背負おうとしたけれど、女の子のシャロンにすら力で負けていたじゃないか。そんな非力なぼくに、外の世界に出て、いったい何ができるというのだろう?
それに何より、きっとおじいがそんなことは許してくれない。ぼくが外の世界へ行こうとすれば、おじいはきっとぼくを止める。そして、いつものように淡々と冷製に問い詰めてくるにちがいない。ぼくは、そんなおじいを説得できる気がしなかった。
「ぼくには、無理だよ‥‥」
「だって、ぼくは弱いから‥‥」
力なく呟いた言葉は、ぼくたちの間に重い沈黙となってのしかかった。
「‥‥そんなことないよ!外へ出るのに必要なのは、外の世界を知りたいっていう気持ちだけ!あとは一歩を踏み出す勇気だけだよ!」
シャロンは諦めずにぼくを奮い立たせようとする。そこまでぼくを熱心に誘ってくれるのはうれしかったけれど、やっぱりぼくは、勇気が出なかった。
しかし、ぼくの家の前でおじいたちが話していたことによれば、フョードルはそもそもこのコロニーに永住するつもりじゃなかったか‥‥?おじいにフョードルたちの来訪を報せた老人が勘違いしているのか、シャロンが知らされていないだけなのか‥‥。けれど、一緒に移住するのにそれを秘密にする理由なんてあるだろうか?
ぼくは感じた疑問をシャロンに聞こうと口を開いたが、その疑問を口に出す前に、広場の外からぼくたちを呼ぶ声が聞こえてきて、会話が途切れてしまった。
「おーい、シャロン。話が終わったぞ」
顔を向けると、フョードルとおじいが並び立って広場の入り口に立っていた。並んでいるのを見ると、改めてフョードルの大きさがわかる。
ぼくたちは自然と話を切り上げて、ベンチから立ち上がった。シャロンはベンチから立ち上がると、ものすごい勢いで走って行って、フョードルに飛びついていた。隣のおじいが巻き込まれかけて、腰を抜かしかけていた。
「ああ、きっとぼくも、ああやってタックルされたんだろうな」、とその威力に内心おののきつつ、明るく華やかな彼女が来たことで、ぼくの日常が大きく変わっていく予感にひそかに喜びながら、彼女につづいて広場をあとにした。
◆
5368年11月16日
結局、フョードルとシャロンは、『見届ける者(ゲイザー)』を引退して、コロニー5に永住するらしい。3Dプリンターで造られたドーム型の家と、このコロニーに適応した『AlicE』のデータが渡されて、二人は正式にぼくたちの仲間として迎えられた。二人の家は、ぼくの家のすぐ近くで、歩いて2分もかからない距離にある。
けれど、シャロンはそのことに納得ができていないようで、あれから顔を合わせるたびに文句を言っている。なんでも、フョードルはある日突然、『見届ける者(ゲイザー)』をやめると言い出して、シャロンに荷物をまとめるように言いつけると、あっという間に身の回りの物の整理を済ましてしまって、このコロニー5にやってきたそうだ。シャロンは、引っ越しが決まったときからずっと、フョードルから突然の引退の理由を聞かされていなくて、それが余計に彼女の怒りと不満を大きくしているようだった。
「ほんと信じられないっ!もうここへ来て二ヶ月よ!?なんでずっと理由も聞かせてくれないのよ!」
今も、シャロンはぼくの前で怒りを爆発させている。シャロンたちの定住が決まってからというもの、フョードルが家にいない間はずっとこれだ。最近のフョードルは、決まった時間にどこかへ出て行っては、これまた決まった時間に帰ってくるらしい。放っておかれているシャロンは、毎日ぼくの家へ来ては、機嫌が良くて一緒にゲームをしたり映画を見たりするとき以外は、こうしてフョードルへの不満を吐き出している。
「そもそも!ほんとうに突然「引退する。コロニーに移り住むぞ。荷物をまとめろ」なんて言うだけ言って、どこに行くかも言わずに連れてくること自体おかしいじゃない!あの、でいだらぼっち!イエティ!足くさ巨人!」
「もういいわ!今日こそは絶対に聞き出してやるんだから!」
いつもと同じように意気込んでいるシャロンを見ながら、心の中で「今日も聞き出せないんだろうな」と思いながら、シャロンをなだめようとしたその時だった。
「たいへんだ!!」
突然、表の通りから、ひどくしわがれた大声が聞こえたかと思うと、息を乱した老人の一人が走ってきた。この老人も、おじいほどではないけれど、車椅子を使わずにすむくらいには健康なようだったが、それでも本気で走るのは辛かったのか、苦しそうに咳きこんでいる。それでも息も絶え絶えに、「たいへんだぞぅ」という言葉を繰り返している。
いったい何事かと、僕たち以外にも、周囲の住宅から人が顔をのぞかせてきた。
ぼくたちの視線を受けながら、汗だくになった老人は叫んだ。
「南地区の『マルーン』の女子が、赤ん坊を産んだらしい!!」
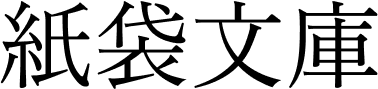


.png)
.png)