マルーン
第一章 宇宙の終わり
ぼくが歩くたびに、道に積もったほこりが舞い上がっては、太陽の光を浴びて視界の中できらきらと輝いた。
いまはもう誰も住んでいない旧市街はとても静かだ。街全体が、鼓動を止めてひっそりと眠りについているかのように、ほこりと静寂の中に沈んでいる。
なぜだかわからないけれど、ぼくはこの場所へ来るのが好きだった。とはいえ、点検もされていないこんな建物たちがいつ倒れてくるともかぎらないので、ぼく以外のコロニーの人間は誰も近づかない。
ぼくが最初にここへ行こうとしたときにだけ、コロニーの老人たちは、本当に一度だけ「危ないから行かないほうがいい」と告げただけで、それ以降はなにも言ってくることはなかった。…ただ一人をのぞいて。
なにか目的があるわけでもない。しかし、それでもぼくはこの場所へと足を運んでしまう。ことばでは言い表せない、立ち止まることを許さない、強い追い風のような何かに背中を押されるように。
太陽はもう傾きはじめ、昼の力強い、さんさんと輝く光とは違う、こげつくような光が町を照らして、ぼくの影を長く伸ばしている。腕に巻いた時計にちらりと目をやると、ぼくの視線を感知した端末が光の画面を空中に映し出し、ぼくのプロフィール情報が並んだページが表示された。
『トーマ 5357年3月3日 11歳6ヶ月』
画面をスライドすると、四角い画面の真ん中に(5368年9月19日)17時20分13秒と、今の時間が表示されている。あと1時間くらいで暗くなってくる時間だ。
今の時間表示の右上にも数字が、けれど時間をあらわす数字よりもずっと長いものが、少し小さく映っている。その数字にぱっと目を映すと、一瞬時が止まったかのように表示が固まって見えた。けれど、それはただの気のせいで、すぐにまた時間は流れて、1秒ごとに数字を1つずつ減らしていく。 8年3ヶ月18日9時間34分23、22、21…。減っていく数字を見ているのが嫌になって視線を外すと、画面はすぐに消えてしまった。
いつの間にか、まわりの景色を朱く焼いていた光も徐々に弱まり、空は藍の色へと変わっていく。
(また星の数が減ったな‥‥)
太陽の強い光が消えて、星の輝きが見えるようになった夜空からは、一年前はそこにあったはずの星たちがその姿を消していた。去年はあったはずの、ペガサス座の脚の部分が欠けている。ほかにも、魚座の片方の魚、カシオペヤ座の真ん中の星などが消えてしまっていた。おひつじ座なんか、頭の部分二つの星が消えて、ただの線だ。
少しずつ星が見えなくなっていく夜空をみると、あまりに話が大きすぎてまったく現実味のわかなかったあの話が、遠くない未来に本当に訪れるものだということを感じて、背筋がきゅっと冷えるような感覚になる。
──宇宙の終わり
この宇宙のすべてがその活動をとめて、宇宙が死んでしまうという、信じられない話。
しかし、今ぼくの目の前に広がるこの空が、それが嘘でもデタラメでもなく、紛れもない現実の話であるということをぼくに突きつけていた。
普段あまり気にしていないからこそ、こうして目に見える形で現実を見せつけられると、とても怖くなる。
恐怖をまぎらわすように頭を振って、ぼくはもう一度夜空を見上げた。まだ空の上で輝く星たちの、その最後を想像しながら。
◆
旧市街からコロニーの自分の家へと帰ったぼくは、『AlicE』に食事の用意をしてもらおうとしていた。
今日ぼくが食べようと思っているのは、ラーメンだ。
ラーメンというのは、むかし、このコロニーからずっと東に離れたところにあった日本という国で人気のあった料理だそうだ。
いろいろな味の種類があるあたたかいスープに、つるりとした食感の麺と、パリッとした海苔、柔らかくほぐれたチャーシューに、とろりとした半熟に仕上げられた煮卵が乗った色とりどりの器は、見るだけでお腹が空いてくる。麺をすすれば、絡み付いたスープの旨みが口の中に広がってたまらないのだ。
『AlicE』に登録されている料理のなかでは、この料理がむかしからぼくの一番のお気に入りだった。
…ただ、最近は少し飽きてきたのか、むかしより美味しいと感じられなくなってしまったので、少しの間食べることを我慢していたのだ。しばらく食べなければ、きっとまた美味しく感じられるだろうと思ったから。
そうしてしばらく食べずに我慢して、今日は久しぶりにそれを食べようと思っていた日だった。
しばらく食べていなかったラーメンの美味しさを想像して、いまからとても楽しみで、わくわくしている。
こういう料理は、人間が自分で料理をしていた時代には、下準備などがとても大変だったらしいけれど、いまでは『AlicE』のデータベースに登録されてさえいれば、ラーメン以外のどんな料理であっても、ほんの数十秒くらいで出来立てのものを作ってくれる。
『AlicE』は、人間が積み重ねてきた知識を持った、万能サポート型人工知能だ。
正式名称は、『All-purpose (万能) Life-supporting (生活支援) Intelligent (知的な) Computing (計算) Engine(エンジン)』で、それぞれの単語から頭文字を一つずつ取ってその名前がつけられた。
彼女たちは人間が用意したいろいろな形のロボット体に入ることもできて、サービスが開始されてから数百年もの間、コロニーの管理や整備、物の運搬、人間の手術や介護といった医療全般、そして食事など、人間の身の回りのあらゆることをサポートしてくれている。
『AlicE』が生まれたことで、人間の生活はおおきく変わった。食べ物にしても、今は調理型の機体さえあれば、彼女たちは空気中に散らばる原子からなんでも作り出してくれるが、『AlicE』が生まれる前の人間は、農業や牧畜などで自分たちで一から食べ物を作らなければならなかったというから大変だ。
『AlicE』はタブレットなどの筐体で呼び出すこともできるけれど、ぼくたちの頭の中には『AlicE』と通信できるマイクロチップが入っているので、一人で話すときや、周りの人に聞かれたくないような話を相談するときには、こっちの方が便利なのだ。
ぼくは、頭の中で『Alice』の名前を呼んだ。
すると、すぐに頭の中に、ぼくではない誰かの気配があらわれたのを感じた。
「『AlicE』」
「はい、トーマさん。お呼びでしょうか」
若い女性の声で返事が返ってくる。設定を変えれば男性の声にすることもできるのだけど、ぼくはどちらでもよかったので、そのままの設定にしている。
「ラーメンをつくって。いつもと同じ塩ラーメンで、ほかの設定もいつもと同じものをお願い」
「わかりました。30秒ほどお待ちください」
調理型の機体に入った『AlicE』が動き出し、ぼくの好みに合わせたラーメンを作っているのを待ちながら、ぼくは旧市街で見た星空のことを考えていた。
宇宙が終わる詳しい理由は、ぼくにはよくわからなかった。話がむずかしすぎるのだ。
ただ、『AlicE』の説明によると、宇宙のすべての動きが止まってしまうらしい。まるで、宇宙全体が眠りに落ちるように。
いつもなら、そのくらいの認識をしていれば満足できるのだけれど、一度宇宙の終わりについて考えてしまうと、どうしても詳しい理由が知りたくなる。
ぼくは、頭の中でもう一度『Alice』の名前を呼んだ。すると、すぐに頭の中に返事が返ってきた。
「『AlicE』」
「はい、トーマさん。お呼びでしょうか」
「宇宙が終わる理由を、もう一度教えて」
ぼくの質問に、『AlicE』はすぐに答えてくれた。
「分かりました。宇宙は今から128億年前、ビッグバンによって誕生しました。宇宙は誕生直後は超高温かつ超高密度の火の玉で、これが急膨張したものが今の姿です。この急膨張と同時に、ビッグバンによって生じた熱エネルギーが宇宙空間内に拡散されました。宇宙に存在する恒星や惑星を含めたすべての天体は、このときに発散された熱エネルギーによって循環しています。このエネルギーは膨張し続ける宇宙のあちこちで絡み合い、互いに作用し合うことで、宇宙の姿を形創ってきました。かつての人類はこの熱エネルギーのすべてを観測できるだけの技術を保有しておらず、このエネルギーの行末については明らかになっていませんでした。
しかし今から4000年ほど前に、人類は長距離惑星間移動技術、超遠光距離観測技術の確立に成功し、多惑星存在となったことで宇宙の隅々までの調査が可能となりました。その後の調査によって、宇宙の複数の場所で温度が急激に低下していることが発見されました。もともと宇宙の温度は均一ではなく、高い温度の場所もあれば低い温度の場所も存在することは分かっていましたが、人類の予想をはるかに超える勢いで宇宙は冷却されていたのです。
この現象は宇宙が膨張を続けている為に、『熱は高温から低温へ不可逆的に移動し、その逆は起こり得ない』という熱力学第二法則に基づいて熱エネルギーが分散、均一化されていることで起こっています。宇宙全体のエネルギーが完全な均一になるということは、あらゆる活動に必要な熱エネルギーが不足し、やがてこの地球やそこに住む生物を含む宇宙のすべての活動が停止します。ご存知の通り、トーマさんの時計に表示されている数字は、その冷却の波が地球に到達し、地球がその活動を停止するまでの残り時間を表したものです。以上が『宇宙の死』についての情報です。また、残念ながら現在の人類にこの現象を食い止めるだけの技術力はありません」
わかったような、わからないような。
とにかく、宇宙が冷えてしまうことで、生き物はもちろん、星でさえも、この世界のすべてのものは動けなくなってしまうということらしい。
夜空の星たちが消えてしまったのは、きっと宇宙が冷えて、光を出せなくなってしまったのだろう。
冷えるということは、ぼくたちは最後、凍死するのだろうか?寒くて死ぬのは苦しそうだ。
「『AlicE』。宇宙が死ぬとき、ぼくたちは凍死で死ぬの?」
「いいえ。トーマさんたちの死因は凍死ではありません。活動できるだけのエネルギーの欠如による生命活動の停止です。また、トーマさんたちは宇宙の温度の低下を気温の低下として感じることはありません。なぜならトーマさんたちの脳が気温の低下としてそれを認識する前に活動限界に至るからです。
しかし宇宙の冷却範囲が地球にまで及んでからトーマさんたちが活動限界に至るまでには少しばかり時間差がある為、その間のトーマさんたちの外部世界の認識は大きく変わるでしょう。なぜなら外部世界の認識を司るトーマさんたちの脳もまた、万物と同じく熱エネルギーを消費した電気信号伝達によって活動しているからです。エネルギーの枯渇によってトーマさんたちの脳機能は著しく低下する為、外部世界の認識、身体操作、思考能力といった機能に大きな影響を与えます。身体操作の電気信号伝達の遅延によってトーマさんたちの身体的動作はそれに比例して遅延し、これが外部世界の認識能力の低下と結びついて、感覚的には外部世界がとてつもない速さで流転するように認識されます。やがて脳の活動に必要な最低限の熱エネルギーすらなくなると脳は機能を緩やかに停止します。しかしこれらの現象がトーマさんたちに身体的な苦痛をもたらすということはありません。その感覚は入眠と極めて似たものであると言えます」
眠るように死ぬ。そんな死に方なら、どうやって死ぬのかも分からなかったさっきより怖くないし、それはそんなに悪い死に方ではないような気がした。
ただ、ぼくの最後の時に、まわりに誰もいなくて、一人ぼっちだということには変わらないのだけれど‥‥。
ぼくは、物心ついたころからずっと一人だ。
産まれてからすぐに母に見放され、旧時代の機械育児機能でなんとか生き延びていたところを、おじいたちコロニーの老人に見つかって、保護されたらしい。生まれて間もない頃のことなので、ぼくはよく覚えていないのだけれど。
ただ、保護といっても誰かが引き取ってくれたわけじゃなく、コロニー内に3Dプリンターで造られた家と、もはや使われることのなくなった『AlicE』の保育機構を与えられただけだ。
もちろん、命を救ってもらっただけじゃなく、『AlicE』をもらったおかげで教育を受けることもできたので、おじいたちには感謝している。ただ、ぼくのこころの中ではずっと、もやもやとした寂しさがわだかまっていた。
コロニーの老人たちは、みんな同じ年頃なので、友達がいっぱいいる。だけど、ぼくは、同じくらいの年頃の子に会ったこともなかった。
仕方がないことだとは分かっている。ぼくは、『マルーン(残される者)』───本来は産まれるはずのなかった子どもだから‥‥。
そこまで考えて、胸にじわりと痛みを感じた。布にこぼしたシミのように、それが少しずつ広がりはじめたところで、調理が終わったことを知らせる音が鳴った。
こころのなかに生じたそれを振り払うように、ぼくは調理型の機体から出来立てのラーメンを取り出すと、麺を大きくすすった。麺に絡みついたスープが一緒に口の中に入ってくる。
しかし、口にふくんだものを咀嚼していくうちに、やっぱりあの違和感に襲われた。
咀嚼するのをやめて、ラーメンを見下ろす。
…やっぱりだ。べつに飽きてしまったわけじゃなかった。
前に食べたときからそんな気はしていたけれど、信じたくなくて、飽きたと思い込むようにしていた。
けれど、今回でわかった。これはもう認めなければいけない。
‥‥むかしはあんなに美味しかったラーメンが、もうあのころのように美味しく感じられなくなっていた。
◆
今から10万年以上前、ぼくたちの祖先はこの星のアフリカ大陸で生まれ、またたく間に惑星全体へと広がっていった。地上世界を探索しつくした人間は、次は宇宙へと探究の場を変え、そうして今から3000年くらい前に、他の惑星との間を移動できる技術を生み出した。
その頃の人間たちは、いまとは比べものにならないくらい活気に満ち溢れていたらしい。そうだろうと思う。それまでできなかったことをできるようになったときには、心がおどって、なんでもできるような気分になるから。靴紐を結べるようになったときや、それまで解けなかった問題が解けたときのように。
空を飛ぶことのできなかったむかしの人間は、その知恵で空を飛び、さらにその先の宇宙へも飛び出した。
そのときの彼らの喜びは、きっとぼくのそんなささいな喜びとは比べものにならないくらいに大きく、彼らを強く勇気づけたにちがいない。
惑星探索が進んで、地球とよく似た環境の惑星がいくつか見つかると、当時の人間たちはその星へどんどん人を送っていった。
新しい惑星の環境が整えられて、地球との間に連絡船が行き来するようになると、人間はますます活気づいていった。そのときの人間はきっと、宇宙が自分たちのために作られたのだと、本気で信じていたんじゃないだろうか。
人間は、宇宙についての調査をさらに進めていった。どうしてこの世界は生まれたのか?どうして自分たちは生まれたのか?いつかこの世界のすべてを知ることができると信じて。
しかし、宇宙の闇の中で彼らが知ったことは、宇宙の終わりが迫っているということだった。
宇宙の終わりという情報は、はじめは一般の人々には隠されていたようだけれど、そんな話がいつまでも隠し通せるわけもなく、それからすぐに流出して、人々の間に一気に広まった。
そこで起こった反応はさまざまで、宇宙の終わりなんて信じなかった人間や、すぐに信じてなげき悲しむ人間、宇宙開拓や調査に関わっていた人たちに怒りをぶつけて八つ当たりする人間、大きすぎる話についていけず、ただただ混乱する人間‥‥。「ようやく世界の終わりが訪れる」といって喜んでいた人間もいたらしい。
そんなふうに、はじめはいろいろな反応があったみたいだけれど、その情報が本当らしいということがいよいよ広まると、大きな混乱が人々の間で巻き起こった。
けっして少なくない数の人間が、地球を含めたほかの惑星のあちこちで暴れ回り、犯罪の数も急増して、世界の治安は悪化した。政治家や宇宙開拓者、その家族が襲われたり、あちこちでお金を狙った強盗が起きた。それになにより、世界の終わりを前にして、多くの人が働くのをやめてしまった。
そうしてどんどん社会がまわらなくなっていった。宇宙の終わりを待つまでもなく、人間は自分たちの手で、自分たちを終わらせるかもしれなかった。
けれど結局、人間は自分を滅ぼさなかった。
一年近く続いた激しいパニックは、その一年でぴたりと止んだらしい。犯罪の数も徐々に減り、治安が戻っていった。
『AlicE』が言うには、人間が起こすパニックは、短い時間で大きな怒りや混乱を吐き出すものがほとんどで、それを全部吐き出してしまえば、いつかは自然と落ち着くものらしい。
調査が進むにつれて、宇宙の終わりの影響が地球にまで及ぶのが観測当時から数千年後であることがわかったことも、パニックがおさまることにつながった。
ぼくは、彼らは一通り暴れたあとに少し冷静になって、そもそもなにに対して怒って、暴力を振るっていたのか、わからなくなったんじゃないかと思っている。
だって、宇宙の終わりなんてことは、国の一つや二つ、ましてや個人の人間が引き起こせるようなことじゃないのだから。人間の考えや行動に関係なく、自然に起こったことなのだから、誰に怒りをぶつけても解決なんてしない。怒りにまかせて暴れ続けていたら、結局困るのは自分たちだということに気がついたんじゃないだろうか。
ぼくは、恐怖に負けて好き勝手に振る舞ったその人たちのことを考えると、いつも心底不快な気持ちになる。
彼らの行動を見聞きするたびに、なんだか、人間そのものがどうしようもなく愚かな存在で、同じ人間であるぼくも、その仲間だと突きつけられているかのように思えるのだ。
‥‥いや、実際にぼくは、人間というのはどうしようもない存在だと思っている。‥‥ぼくの存在が、その何よりの証拠だった。
落ち着きを取り戻した人間たちは、それまでの生活をまた送り始めた。寝て、起きて、働いて、家族と過ごす。ただそれだけの平和な日々を、もう一度過ごしはじめていた。
しかし、当時の権力者たちは、人間という種の未来について考えていた。たとえ、自分たちの生きている間には来なくとも、自分たちの子孫が将来必ず向き合うことになる問題について考えていたのだ。
話し合いは長い間続き、やがて彼らは一つの計画を考え出した。
それは、『宇宙の終わりが止められない場合、その影響が地球に及ぶ前に自分たちで種を終わらせる』ということだった。
この計画は、“ある時期までは宇宙の終わりを防ぐための方法を、すべての人間で団結して探すが、それでも宇宙の終わりが避けられなかった場合、宇宙の終わりの影響が地球に及ぶ前に、計画的に子どもの出生数を減らしていき、自ら種を終わらせる”というものだった。
3000年前の当時、この計画が公表されると、一部の人々からの批判はあったらしいが、数を減らしていく決定をするまでには時間があったこと、それになにより当時の状況ではこれ以外に出来ることはなかったので、最終的にはこの計画が認められた。
しかし、それ以降、世界中の叡智に溢れる科学者たちが集まって行ったどんな仮説や研究も、それらの結果はすべて“なにをどうやっても宇宙の終わりは避けられない”ということを裏付ける証拠として積み上がっていくばかりだった。
やがて当初の計画において、子どもの数を減らしていくかを判断するはずだった時期になった。
過去の計画通りに計画を進めるべきかどうか、当時の権力者たちがもう一度話し合い、その結果、子どもの数を減らしていくかどうか見極める期限を延ばすことに決めた。
“人間の可能性はまだ残されている。諦めずに道を探し続ければ必ず何か方法は見つかるはずだ。だから、みんなでもっと頑張ろう!”
その時代の権力者たちは、こんな言葉を合言葉に、人々に子どもを産み続けるよう呼びかけていた。
当時の人々はその言葉を信じて、それまで通りに子どもを産んで、育て続けていたけれど、そのあとも宇宙の終わりを食い止める方法が見つかることはなかった。
ただ、この時代は新しい技術が次々と発表された時代で、『AlicE』が生まれたのも、ちょうどこの頃だった。
『AlicE』は当初、人間を超える完璧な知能として、宇宙の終わりを食い止める方法を見つけることを期待して生み出された人工知能だった。『AlicE』をつくった人たちは、人間の絶滅をどうしても止めたかったらしい。
そうして期限の延長から数十年ほどが経ったあるとき、とんでもない事件が起こる。
人々には子どもを産み続けるように呼びかけていた権力者たちのほとんどが、自分たちだけは子どもを産むことをやめていたことが分かったのだ。
その時代の権力者たちは、宇宙の終わりを止める方法を探すことを早々に諦めていた。ただ、社会を回すには人が必要だから、人々には子どもを産み続けるように呼びかけていたのだ。
このことが知れ渡ったときの、人々の怒りはすさまじかったらしい。
人々を騙していた権力者たちは、もう全員がよぼよぼの老人になっていたにもかかわらず、仕事もお金も奪われて、国や街から追い出されてしまった。
裏切り者を追い出したあとの人々は、そのあとのことをすぐにでも考えなければいけなかった。子どもの数を減らしていくのなら、その計画をはじめなければいけない時期をだいぶ過ぎてしまっていたからだ。
当時の人々は急いで話し合いの場をつくると、宇宙の終わりという未来を前に、自分たちで種を終わらせる道を選ぶことを正式に決定した。
地球よりも遅く宇宙の終わりがくる他の惑星へと移住する道もあったが、多くの人々はそのまま地球に残ることを決断した。
この大きな変化を実現することができたのは、『AlicE』のおかげだった。
人間の生活のすべてをサポートしてくれる『AlicE』が登場したことで、人間の数が減っても、最後の世代に負担をかけることなく種を絶えさせることができるようになったのだ。皮肉なことに、開発者たちが『人間を絶えさせないために』と願って生み出された『AlicE』は、結果的に人間を安全に絶滅させられる道具として、その決定の後押しとなってしまった。
人間の技術が、宇宙に敗れた瞬間だった。
人間が取るべき方針が決まると、それからすぐに、具体的な出生数の減らし方についての計画をまとめた、『スリープ計画』が立ち上げられた。
これが、今から大体300年くらい前の出来事だ。
“理性ある人間らしく、自分たちの手で歴史に幕を下ろそうじゃないか”
人間は、今度はこの言葉を合言葉に、子どもを産まなくなっていった。
『スリープ計画』が進むにつれて、人口は当然どんどん減っていくので、当時人間が形作っていた『国』や『都市』という集団は、維持することができなくなっていった。
そこで、人間は『国』という集団の形と、いくつかの都市を捨てて、そこに住んでいた人々をいくつかの地域にまとめてしまい、『コロニー』という新しい集団の形を生みだした。ぼくが今住んでいるのは、旧ドイツと呼ばれる『コロニー5』だ。
ぼくたちの脳に埋め込まれているマイクロチップの翻訳機能のおかげで、言語のちがいについては問題にならなかった。
しかし、言語以外の部分、価値観や文化のちがいというのは、マイクロチップでは解決できない大きな問題だった。
はじめは、そういうまったくちがった文化や価値観を持った人同士が衝突することも少なくなかったらしいけれど、時間が経つにつれて、そういったちがいは徐々にすり合わされ、どのコロニーもほとんど同じような形にまとまっていった。
コロニーの大きさは、だいたいむかしの人間たちにとっての都市一つ分くらいで、その大きさは時代を経るごとにどんどんと狭くなっていった。
いまでは、地球のほとんどの場所に人は住んでいなくて、旧市街とよばれる大勢の人が退去した無人の廃墟が広がっている。
コロニーという新しい集団の形を得た人間は、『スリープ計画』に従って順調に数を減らしていった。
計画がはじまった最初のころは、そのまま子どもの数が減り続ければ、宇宙の終わりが地球へとやってくる前に余裕をもって種を絶えさせることができると考えられていた。
しかし、その見込みは途中で大きく外れることになる。
ある時期を境に、突然子どもの数が増え始めたのだ。
『スリープ計画』に反対する人間や、教育制度の廃止によって教育を受けなかった人間‥‥。そういった一部の人間たちが、『スリープ計画』を無視して、それぞれで勝手に子どもを産み続けていたのだ。
『スリープ計画』に従っていた人間たちは、彼らの行動に戸惑い、計画に従うように呼びかけていた。
“あなたたちのその行動で苦しむのは、あなたたちの子孫なんですよ”と。
けれど、彼らはそんな忠告を聞くことはなく、自分勝手な行動を続けた。彼らの子どもや子孫たちもまた、彼らと同じように子どもを産んだ。
それが積み重なった結果、宇宙の終わりを生きてむかえる世代が誕生してしまった。ぼくの親の世代だ。
これは、計画の失敗を意味していた。
人々は、計画の失敗に落胆し、宇宙の終わりとともに死ななければならない者たちを哀れんだ。
『マルーン(残される者)』──本来産まれるはずのなかった者たち。それが、ぼくたちにつけられた名前だった。
ぼくの母もまた、『マルーン』だった。ぼくを産んですぐにぼくを放り出した後、よくない薬を飲みすぎて死んでしまったらしい。父親は誰だったのか、よくわからないとコロニーの老人たちは言っていた。
ぼくは、『マルーン』のなかでも一番若い世代だ。ぼく以外には会ったこともないくらいに。
コロニーの老人たちは、本当なら『スリープ計画』で最後の世代になるはずだった世代で、彼らは『マルーン』を、特にぼくのことを、心の底からかわいそうなものを見るような目で見てくる。その視線が嫌いだったぼくは、その目のなかになるべく入らないように、老人たちと顔を合わせなくてすむように隠れるように生きていた。
ぼくたちは、地球に残った人間の子孫だけれど、他の惑星に移住していった人々がどうなったのかはわからない。今では多惑星との交流は完全に途絶えてしまっていた。
彼らはうまく種を終わらせたのだろうか。それとも、地球のぼくたちと同じように、『マルーン』が生まれたのだろうか。
ぼくにそんなことが分かるわけもないけれど、さびしい思いの中で死んでいく人がいなければいいと思う。だってぼくは、そんな最期を迎えるのがこんなにも恐ろしいから。
ぼくたちは、寿命をまっとうすることなく、宇宙とともに死んでいく。そういう運命にあるのだ。
◆
5368年9月22日
家でくつろいでいると、突然、来客をしらせる音が鳴った。
マイクロチップから伝えられる情報から来客が誰だか分かると、ぼくは応じたくない気持ちに襲われたけれど、そんなわけにもいかないので渋々扉をあけた。扉の前には、おじい‥‥、コロニー長がいた。
おじいは車椅子を使っている老人が多いコロニーのなかでは、体がまだしっかりしている方で、自分の足で歩き、背筋もしゃんと伸びている。身だしなみにも気を使って、着ている服はいつも綺麗にアイロンがけされていて、実年齢よりもずっと若く見えた。
ただ、最近では少しずつ体が痩せて、歩くのもみるみるうちに遅くなってきていた。植物が枯れていくように、急速に身体におとろえがきているようだった。
それでも、最期は生命維持装置は絶対につけないと言い続けている。
「また、コロニーの外に出たそうだね」
目が合って一番にそんなことを言われた。
決して強い言い方ではないけれど、その言葉にはぼくの行動を責めるような色がふくまれているのを感じた。
「コロニーの外は、洗浄も行き届いていないのだから、あまり出ないようにしなさい」
基本的にぼくに関わろうとしないコロニーの老人たちの中で、おじいだけはこうしてぼくのところへ来てその行動をとがめてくる。
ただ、なにがなんでもぼくを止める気はないようで、言葉でのお説教にとどまっている。
おじいに限った話ではないのだけれど、このコロニーに住む老人たちは、みんな何ごとにも強い関心を抱くことがないようだった。
彼らの過去を知っているわけではないけれど、最後の世代として宇宙の終わりと向き合い続けたことで、他人や何かに興味を持つだけの気力も失ってしまったのかもしれない。
ぼくは、おじいの言ったことに返事をしないことで、おじいの説教に従うつもりがないことを示す。
ぼくたちの間に、気まずい沈黙が流れた。
おじいはその間もぼくから目をそらさず、じっとぼくの顔を見つめている。
たまらなくなって、ぼくの方が目を逸らした。
目を逸らした先にある鏡に映った自分の顔は、一目で決まりが悪そうにしているのがわかるような酷い顔をしていた。
おじいの目はいつも純水のように澄んでいて、まるでこちらのこころの中を奥底まで見通すような視線を放ってくる。きつい言葉を投げかけられるわけでも、激しく怒られるわけでもないけれど、ぼくはおじいのそんな視線にいつも耐えられないのだ。
だから、結局いつもぼくはおじいに自分の考えを伝えたり、ましてや説得するなんてこともできずに、なあなあで話が流れてしまう。
‥‥自分が逃げているだけだということはわかっている。けれど、やっぱり怖いものは怖いのだ。
いつまで経ってもうんともすんとも言わないぼくの様子から、らちが明かないと思ったのか、おじいは突然まったく違う話をふってきた。
「ほかの『マルーン』たちは、定期的に集会のようなものを開いて集まっているらしい。‥‥トーマは彼らとは話さないのか」
「みんなずっと年上の大人だよ?話すことなんてないよ‥‥」
同じマルーンと言っても、コロニー5にいる『マルーン』のほとんどは、ぼくの母親と同じくらいの歳なのだ。そんな年上の人と話せることなんて、ぼくにはない。
おじいはただ一言、「そうか」と言うと、ため息をついた。
‥‥なんなんだろう。いつも突然来て、説教をして、心配しているつもりなのか?普段は放ったらかしのくせに。たまに家を訪れては偉そうに説教をしてくるだけで、どうしてぼくが従うと思っているのだろう?
考えていたら、怒りが湧いてきた。その怒りをぶつけてやろうと口を開きかけたとき、べつの老人がおじいを呼ぶ声が聞こえてきた。
老人は車椅子に座っていて、そこから伸びる管が体のあちこちに繋がっている。生命維持装置をつけているのだ。
「おぉい、コロニー長や。旧市街の方から『ゲイザー』が来ましたぜ」
「なに?」
おじいは、ぼくから目を離すと、声をかけにきた老人の方に顔を向けた。ぼくはラッキーだと思って、「それじゃあ」と一言声をかけると、扉を閉めた。
おじいは慌てたようにこちらに視線を戻したようだったけれど、もうそのときには扉が閉まろうとしていたのを見て、諦めたようにまた視線を老人の方に向けたようだった。
がちゃん、と扉が閉まると、扉の向こうでおじいと車椅子の老人が話しているのが聞こえてきて、なんとなく、扉の前でそのまま話を聞いていた。
「何人の隊なんだ?」
「それが、一人の大男と、小さい女の子の二人だけなんですわ」
「いやに少ないな。しかし、もうずいぶん長い間見かけなかったから、すっかり廃れたものだと思っていたが」
「わたしもそう思ってたんですがね。でもどうやら一時的な滞在ってわけじゃなく、大男の方が言うには永住したいということなんですわ」
「すぐに行く。ともかく話を聞いてみなければ」
「とりあえず身体と持ち物の殺菌はしてもらって、今は集会所の方に案内してますよ」
その言葉を最後に、車椅子の駆動音と足音が鳴って、それが扉の前から離れていく気配がした。
コロニーへの来訪者なんて、ぼくが産まれてからはじめてのことだ。
いったい誰が、どんな目的で来たのだろう?
好奇心にかられたぼくは、さっきはおじいを拒絶するように閉めた扉をもう一度開けて外の様子をうかがうと、ぱっと外に飛び出して、コロニーの集会所へと続く道を走り始めた。
マルーン
第一章 宇宙の終わり
ぼくが歩くたびに、道に積もったほこりが舞い上がっては、太陽の光を浴びて視界の中できらきらと輝いた。
いまはもう誰も住んでいない旧市街はとても静かだ。街全体が、鼓動を止めてひっそりと眠りについているかのように、ほこりと静寂の中に沈んでいる。
なぜだかわからないけれど、ぼくはこの場所へ来るのが好きだった。とはいえ、点検もされていないこんな建物たちがいつ倒れてくるともかぎらないので、ぼく以外のコロニーの人間は誰も近づかない。
ぼくが最初にここへ行こうとしたときにだけ、コロニーの老人たちは、本当に一度だけ「危ないから行かないほうがいい」と告げただけで、それ以降はなにも言ってくることはなかった。…ただ一人をのぞいて。
なにか目的があるわけでもない。しかし、それでもぼくはこの場所へと足を運んでしまう。ことばでは言い表せない、立ち止まることを許さない、強い追い風のような何かに背中を押されるように。
太陽はもう傾きはじめ、昼の力強い、さんさんと輝く光とは違う、こげつくような光が町を照らして、ぼくの影を長く伸ばしている。腕に巻いた時計にちらりと目をやると、ぼくの視線を感知した端末が光の画面を空中に映し出し、ぼくのプロフィール情報が並んだページが表示された。
『トーマ 5357年3月3日 11歳6ヶ月』
画面をスライドすると、四角い画面の真ん中に(5368年9月19日)17時20分13秒と、今の時間が表示されている。あと1時間くらいで暗くなってくる時間だ。
今の時間表示の右上にも数字が、けれど時間をあらわす数字よりもずっと長いものが、少し小さく映っている。その数字にぱっと目を映すと、一瞬時が止まったかのように表示が固まって見えた。けれど、それはただの気のせいで、すぐにまた時間は流れて、1秒ごとに数字を1つずつ減らしていく。 8年3ヶ月18日9時間34分23、22、21…。減っていく数字を見ているのが嫌になって視線を外すと、画面はすぐに消えてしまった。
いつの間にか、まわりの景色を朱く焼いていた光も徐々に弱まり、空は藍の色へと変わっていく。
(また星の数が減ったな‥‥)
太陽の強い光が消えて、星の輝きが見えるようになった夜空からは、一年前はそこにあったはずの星たちがその姿を消していた。去年はあったはずの、ペガサス座の脚の部分が欠けている。ほかにも、魚座の片方の魚、カシオペヤ座の真ん中の星などが消えてしまっていた。おひつじ座なんか、頭の部分二つの星が消えて、ただの線だ。
少しずつ星が見えなくなっていく夜空をみると、あまりに話が大きすぎてまったく現実味のわかなかったあの話が、遠くない未来に本当に訪れるものだということを感じて、背筋がきゅっと冷えるような感覚になる。
──宇宙の終わり
この宇宙のすべてがその活動をとめて、宇宙が死んでしまうという、信じられない話。
しかし、今ぼくの目の前に広がるこの空が、それが嘘でもデタラメでもなく、紛れもない現実の話であるということをぼくに突きつけていた。
普段あまり気にしていないからこそ、こうして目に見える形で現実を見せつけられると、とても怖くなる。
恐怖をまぎらわすように頭を振って、ぼくはもう一度夜空を見上げた。まだ空の上で輝く星たちの、その最後を想像しながら。
◆
旧市街からコロニーの自分の家へと帰ったぼくは、『AlicE』に食事の用意をしてもらおうとしていた。
今日ぼくが食べようと思っているのは、ラーメンだ。
ラーメンというのは、むかし、このコロニーからずっと東に離れたところにあった日本という国で人気のあった料理だそうだ。
いろいろな味の種類があるあたたかいスープに、つるりとした食感の麺と、パリッとした海苔、柔らかくほぐれたチャーシューに、とろりとした半熟に仕上げられた煮卵が乗った色とりどりの器は、見るだけでお腹が空いてくる。麺をすすれば、絡み付いたスープの旨みが口の中に広がってたまらないのだ。
『AlicE』に登録されている料理のなかでは、この料理がむかしからぼくの一番のお気に入りだった。
…ただ、最近は少し飽きてきたのか、むかしより美味しいと感じられなくなってしまったので、少しの間食べることを我慢していたのだ。しばらく食べなければ、きっとまた美味しく感じられるだろうと思ったから。
そうしてしばらく食べずに我慢して、今日は久しぶりにそれを食べようと思っていた日だった。
しばらく食べていなかったラーメンの美味しさを想像して、いまからとても楽しみで、わくわくしている。
こういう料理は、人間が自分で料理をしていた時代には、下準備などがとても大変だったらしいけれど、いまでは『AlicE』のデータベースに登録されてさえいれば、ラーメン以外のどんな料理であっても、ほんの数十秒くらいで出来立てのものを作ってくれる。
『AlicE』は、人間が積み重ねてきた知識を持った、万能サポート型人工知能だ。
正式名称は、『All-purpose (万能) Life-supporting (生活支援) Intelligent (知的な) Computing (計算) Engine(エンジン)』で、それぞれの単語から頭文字を一つずつ取ってその名前がつけられた。
彼女たちは人間が用意したいろいろな形のロボット体に入ることもできて、サービスが開始されてから数百年もの間、コロニーの管理や整備、物の運搬、人間の手術や介護といった医療全般、そして食事など、人間の身の回りのあらゆることをサポートしてくれている。
『AlicE』が生まれたことで、人間の生活はおおきく変わった。食べ物にしても、今は調理型の機体さえあれば、彼女たちは空気中に散らばる原子からなんでも作り出してくれるが、『AlicE』が生まれる前の人間は、農業や牧畜などで自分たちで一から食べ物を作らなければならなかったというから大変だ。
『AlicE』はタブレットなどの筐体で呼び出すこともできるけれど、ぼくたちの頭の中には『AlicE』と通信できるマイクロチップが入っているので、一人で話すときや、周りの人に聞かれたくないような話を相談するときには、こっちの方が便利なのだ。
ぼくは、頭の中で『Alice』の名前を呼んだ。
すると、すぐに頭の中に、ぼくではない誰かの気配があらわれたのを感じた。
「『AlicE』」
「はい、トーマさん。お呼びでしょうか」
若い女性の声で返事が返ってくる。設定を変えれば男性の声にすることもできるのだけど、ぼくはどちらでもよかったので、そのままの設定にしている。
「ラーメンをつくって。いつもと同じ塩ラーメンで、ほかの設定もいつもと同じものをお願い」
「わかりました。30秒ほどお待ちください」
調理型の機体に入った『AlicE』が動き出し、ぼくの好みに合わせたラーメンを作っているのを待ちながら、ぼくは旧市街で見た星空のことを考えていた。
宇宙が終わる詳しい理由は、ぼくにはよくわからなかった。話がむずかしすぎるのだ。
ただ、『AlicE』の説明によると、宇宙のすべての動きが止まってしまうらしい。まるで、宇宙全体が眠りに落ちるように。
いつもなら、そのくらいの認識をしていれば満足できるのだけれど、一度宇宙の終わりについて考えてしまうと、どうしても詳しい理由が知りたくなる。
ぼくは、頭の中でもう一度『Alice』の名前を呼んだ。すると、すぐに頭の中に返事が返ってきた。
「『AlicE』」
「はい、トーマさん。お呼びでしょうか」
「宇宙が終わる理由を、もう一度教えて」
ぼくの質問に、『AlicE』はすぐに答えてくれた。
「分かりました。宇宙は今から128億年前、ビッグバンによって誕生しました。宇宙は誕生直後は超高温かつ超高密度の火の玉で、これが急膨張したものが今の姿です。この急膨張と同時に、ビッグバンによって生じた熱エネルギーが宇宙空間内に拡散されました。宇宙に存在する恒星や惑星を含めたすべての天体は、このときに発散された熱エネルギーによって循環しています。このエネルギーは膨張し続ける宇宙のあちこちで絡み合い、互いに作用し合うことで、宇宙の姿を形創ってきました。かつての人類はこの熱エネルギーのすべてを観測できるだけの技術を保有しておらず、このエネルギーの行末については明らかになっていませんでした。
しかし今から4000年ほど前に、人類は長距離惑星間移動技術、超遠光距離観測技術の確立に成功し、多惑星存在となったことで宇宙の隅々までの調査が可能となりました。その後の調査によって、宇宙の複数の場所で温度が急激に低下していることが発見されました。もともと宇宙の温度は均一ではなく、高い温度の場所もあれば低い温度の場所も存在することは分かっていましたが、人類の予想をはるかに超える勢いで宇宙は冷却されていたのです。
この現象は宇宙が膨張を続けている為に、『熱は高温から低温へ不可逆的に移動し、その逆は起こり得ない』という熱力学第二法則に基づいて熱エネルギーが分散、均一化されていることで起こっています。宇宙全体のエネルギーが完全な均一になるということは、あらゆる活動に必要な熱エネルギーが不足し、やがてこの地球やそこに住む生物を含む宇宙のすべての活動が停止します。ご存知の通り、トーマさんの時計に表示されている数字は、その冷却の波が地球に到達し、地球がその活動を停止するまでの残り時間を表したものです。以上が『宇宙の死』についての情報です。また、残念ながら現在の人類にこの現象を食い止めるだけの技術力はありません」
わかったような、わからないような。
とにかく、宇宙が冷えてしまうことで、生き物はもちろん、星でさえも、この世界のすべてのものは動けなくなってしまうということらしい。
夜空の星たちが消えてしまったのは、きっと宇宙が冷えて、光を出せなくなってしまったのだろう。
冷えるということは、ぼくたちは最後、凍死するのだろうか?寒くて死ぬのは苦しそうだ。
「『AlicE』。宇宙が死ぬとき、ぼくたちは凍死で死ぬの?」
「いいえ。トーマさんたちの死因は凍死ではありません。活動できるだけのエネルギーの欠如による生命活動の停止です。また、トーマさんたちは宇宙の温度の低下を気温の低下として感じることはありません。なぜならトーマさんたちの脳が気温の低下としてそれを認識する前に活動限界に至るからです。
しかし宇宙の冷却範囲が地球にまで及んでからトーマさんたちが活動限界に至るまでには少しばかり時間差がある為、その間のトーマさんたちの外部世界の認識は大きく変わるでしょう。なぜなら外部世界の認識を司るトーマさんたちの脳もまた、万物と同じく熱エネルギーを消費した電気信号伝達によって活動しているからです。エネルギーの枯渇によってトーマさんたちの脳機能は著しく低下する為、外部世界の認識、身体操作、思考能力といった機能に大きな影響を与えます。身体操作の電気信号伝達の遅延によってトーマさんたちの身体的動作はそれに比例して遅延し、これが外部世界の認識能力の低下と結びついて、感覚的には外部世界がとてつもない速さで流転するように認識されます。やがて脳の活動に必要な最低限の熱エネルギーすらなくなると脳は機能を緩やかに停止します。しかしこれらの現象がトーマさんたちに身体的な苦痛をもたらすということはありません。その感覚は入眠と極めて似たものであると言えます」
眠るように死ぬ。そんな死に方なら、どうやって死ぬのかも分からなかったさっきより怖くないし、それはそんなに悪い死に方ではないような気がした。
ただ、ぼくの最後の時に、まわりに誰もいなくて、一人ぼっちだということには変わらないのだけれど‥‥。
ぼくは、物心ついたころからずっと一人だ。
産まれてからすぐに母に見放され、旧時代の機械育児機能でなんとか生き延びていたところを、おじいたちコロニーの老人に見つかって、保護されたらしい。生まれて間もない頃のことなので、ぼくはよく覚えていないのだけれど。
ただ、保護といっても誰かが引き取ってくれたわけじゃなく、コロニー内に3Dプリンターで造られた家と、もはや使われることのなくなった『AlicE』の保育機構を与えられただけだ。
もちろん、命を救ってもらっただけじゃなく、『AlicE』をもらったおかげで教育を受けることもできたので、おじいたちには感謝している。ただ、ぼくのこころの中ではずっと、もやもやとした寂しさがわだかまっていた。
コロニーの老人たちは、みんな同じ年頃なので、友達がいっぱいいる。だけど、ぼくは、同じくらいの年頃の子に会ったこともなかった。
仕方がないことだとは分かっている。ぼくは、『マルーン(残される者)』───本来は産まれるはずのなかった子どもだから‥‥。
そこまで考えて、胸にじわりと痛みを感じた。布にこぼしたシミのように、それが少しずつ広がりはじめたところで、調理が終わったことを知らせる音が鳴った。
こころのなかに生じたそれを振り払うように、ぼくは調理型の機体から出来立てのラーメンを取り出すと、麺を大きくすすった。麺に絡みついたスープが一緒に口の中に入ってくる。
しかし、口にふくんだものを咀嚼していくうちに、やっぱりあの違和感に襲われた。
咀嚼するのをやめて、ラーメンを見下ろす。
‥‥やっぱりだ。べつに飽きてしまったわけじゃなかった。
前に食べたときからそんな気はしていたけれど、信じたくなくて、飽きたと思い込むようにしていた。
けれど、今回でわかった。これはもう認めなければいけない。
‥‥むかしはあんなに美味しかったラーメンが、もうあのころのように美味しく感じられなくなっていた。
◆
今から10万年以上前、ぼくたちの祖先はこの星のアフリカ大陸で生まれ、またたく間に惑星全体へと広がっていった。地上世界を探索しつくした人間は、次は宇宙へと探究の場を変え、そうして今から3000年くらい前に、他の惑星との間を移動できる技術を生み出した。
その頃の人間たちは、いまとは比べものにならないくらい活気に満ち溢れていたらしい。そうだろうと思う。それまでできなかったことをできるようになったときには、心がおどって、なんでもできるような気分になるから。靴紐を結べるようになったときや、それまで解けなかった問題が解けたときのように。
空を飛ぶことのできなかったむかしの人間は、その知恵で空を飛び、さらにその先の宇宙へも飛び出した。
そのときの彼らの喜びは、きっとぼくのそんなささいな喜びとは比べものにならないくらいに大きく、彼らを強く勇気づけたにちがいない。
惑星探索が進んで、地球とよく似た環境の惑星がいくつか見つかると、当時の人間たちはその星へどんどん人を送っていった。
新しい惑星の環境が整えられて、地球との間に連絡船が行き来するようになると、人間はますます活気づいていった。そのときの人間はきっと、宇宙が自分たちのために作られたのだと、本気で信じていたんじゃないだろうか。
人間は、宇宙についての調査をさらに進めていった。どうしてこの世界は生まれたのか?どうして自分たちは生まれたのか?いつかこの世界のすべてを知ることができると信じて。
しかし、宇宙の闇の中で彼らが知ったことは、宇宙の終わりが迫っているということだった。
宇宙の終わりという情報は、はじめは一般の人々には隠されていたようだけれど、そんな話がいつまでも隠し通せるわけもなく、それからすぐに流出して、人々の間に一気に広まった。
そこで起こった反応はさまざまで、宇宙の終わりなんて信じなかった人間や、すぐに信じてなげき悲しむ人間、宇宙開拓や調査に関わっていた人たちに怒りをぶつけて八つ当たりする人間、大きすぎる話についていけず、ただただ混乱する人間‥‥。「ようやく世界の終わりが訪れる」といって喜んでいた人間もいたらしい。
そんなふうに、はじめはいろいろな反応があったみたいだけれど、その情報が本当らしいということがいよいよ広まると、大きな混乱が人々の間で巻き起こった。
けっして少なくない数の人間が、地球を含めたほかの惑星のあちこちで暴れ回り、犯罪の数も急増して、世界の治安は悪化した。政治家や宇宙開拓者、その家族が襲われたり、あちこちでお金を狙った強盗が起きた。それになにより、世界の終わりを前にして、多くの人が働くのをやめてしまった。
そうしてどんどん社会がまわらなくなっていった。宇宙の終わりを待つまでもなく、人間は自分たちの手で、自分たちを終わらせるかもしれなかった。
けれど結局、人間は自分を滅ぼさなかった。
一年近く続いた激しいパニックは、その一年でぴたりと止んだらしい。犯罪の数も徐々に減り、治安が戻っていった。
『AlicE』が言うには、人間が起こすパニックは、短い時間で大きな怒りや混乱を吐き出すものがほとんどで、それを全部吐き出してしまえば、いつかは自然と落ち着くものらしい。
調査が進むにつれて、宇宙の終わりの影響が地球にまで及ぶのが観測当時から数千年後であることがわかったことも、パニックがおさまることにつながった。
ぼくは、彼らは一通り暴れたあとに少し冷静になって、そもそもなにに対して怒って、暴力を振るっていたのか、わからなくなったんじゃないかと思っている。
だって、宇宙の終わりなんてことは、国の一つや二つ、ましてや個人の人間が引き起こせるようなことじゃないのだから。人間の考えや行動に関係なく、自然に起こったことなのだから、誰に怒りをぶつけても解決なんてしない。怒りにまかせて暴れ続けていたら、結局困るのは自分たちだということに気がついたんじゃないだろうか。
ぼくは、恐怖に負けて好き勝手に振る舞ったその人たちのことを考えると、いつも心底不快な気持ちになる。
彼らの行動を見聞きするたびに、なんだか、人間そのものがどうしようもなく愚かな存在で、同じ人間であるぼくも、その仲間だと突きつけられているかのように思えるのだ。
‥‥いや、実際にぼくは、人間というのはどうしようもない存在だと思っている。‥‥ぼくの存在が、その何よりの証拠だった。
落ち着きを取り戻した人間たちは、それまでの生活をまた送り始めた。寝て、起きて、働いて、家族と過ごす。ただそれだけの平和な日々を、もう一度過ごしはじめていた。
しかし、当時の権力者たちは、人間という種の未来について考えていた。たとえ、自分たちの生きている間には来なくとも、自分たちの子孫が将来必ず向き合うことになる問題について考えていたのだ。
話し合いは長い間続き、やがて彼らは一つの計画を考え出した。
それは、『宇宙の終わりが止められない場合、その影響が地球に及ぶ前に自分たちで種を終わらせる』ということだった。
この計画は、“ある時期までは宇宙の終わりを防ぐための方法を、すべての人間で団結して探すが、それでも宇宙の終わりが避けられなかった場合、宇宙の終わりの影響が地球に及ぶ前に、計画的に子どもの出生数を減らしていき、自ら種を終わらせる”というものだった。
3000年前の当時、この計画が公表されると、一部の人々からの批判はあったらしいが、数を減らしていく決定をするまでには時間があったこと、それになにより当時の状況ではこれ以外に出来ることはなかったので、最終的にはこの計画が認められた。
しかし、それ以降、世界中の叡智に溢れる科学者たちが集まって行ったどんな仮説や研究も、それらの結果はすべて“なにをどうやっても宇宙の終わりは避けられない”ということを裏付ける証拠として積み上がっていくばかりだった。
やがて当初の計画において、子どもの数を減らしていくかを判断するはずだった時期になった。
過去の計画通りに計画を進めるべきかどうか、当時の権力者たちがもう一度話し合い、その結果、子どもの数を減らしていくかどうか見極める期限を延ばすことに決めた。
“人間の可能性はまだ残されている。諦めずに道を探し続ければ必ず何か方法は見つかるはずだ。だから、みんなでもっと頑張ろう!”
その時代の権力者たちは、こんな言葉を合言葉に、人々に子どもを産み続けるよう呼びかけていた。
当時の人々はその言葉を信じて、それまで通りに子どもを産んで、育て続けていたけれど、そのあとも宇宙の終わりを食い止める方法が見つかることはなかった。
ただ、この時代は新しい技術が次々と発表された時代で、『AlicE』が生まれたのも、ちょうどこの頃だった。
『AlicE』は当初、人間を超える完璧な知能として、宇宙の終わりを食い止める方法を見つけることを期待して生み出された人工知能だった。『AlicE』をつくった人たちは、人間の絶滅をどうしても止めたかったらしい。
そうして期限の延長から数十年ほどが経ったあるとき、とんでもない事件が起こる。
人々には子どもを産み続けるように呼びかけていた権力者たちのほとんどが、自分たちだけは子どもを産むことをやめていたことが分かったのだ。
その時代の権力者たちは、宇宙の終わりを止める方法を探すことを早々に諦めていた。ただ、社会を回すには人が必要だから、人々には子どもを産み続けるように呼びかけていたのだ。
このことが知れ渡ったときの、人々の怒りはすさまじかったらしい。
人々を騙していた権力者たちは、もう全員がよぼよぼの老人になっていたにもかかわらず、仕事もお金も奪われて、国や街から追い出されてしまった。
裏切り者を追い出したあとの人々は、そのあとのことをすぐにでも考えなければいけなかった。子どもの数を減らしていくのなら、その計画をはじめなければいけない時期をだいぶ過ぎてしまっていたからだ。
当時の人々は急いで話し合いの場をつくると、宇宙の終わりという未来を前に、自分たちで種を終わらせる道を選ぶことを正式に決定した。
地球よりも遅く宇宙の終わりがくる他の惑星へと移住する道もあったが、多くの人々はそのまま地球に残ることを決断した。
この大きな変化を実現することができたのは、『AlicE』のおかげだった。
人間の生活のすべてをサポートしてくれる『AlicE』が登場したことで、人間の数が減っても、最後の世代に負担をかけることなく種を絶えさせることができるようになったのだ。皮肉なことに、開発者たちが『人間を絶えさせないために』と願って生み出された『AlicE』は、結果的に人間を安全に絶滅させられる道具として、その決定の後押しとなってしまった。
人間の技術が、宇宙に敗れた瞬間だった。
人間が取るべき方針が決まると、それからすぐに、具体的な出生数の減らし方についての計画をまとめた、『スリープ計画』が立ち上げられた。
これが、今から大体300年くらい前の出来事だ。
“理性ある人間らしく、自分たちの手で歴史に幕を下ろそうじゃないか”
人間は、今度はこの言葉を合言葉に、子どもを産まなくなっていった。
『スリープ計画』が進むにつれて、人口は当然どんどん減っていくので、当時人間が形作っていた『国』や『都市』という集団は、維持することができなくなっていった。
そこで、人間は『国』という集団の形と、いくつかの都市を捨てて、そこに住んでいた人々をいくつかの地域にまとめてしまい、『コロニー』という新しい集団の形を生みだした。ぼくが今住んでいるのは、旧ドイツと呼ばれる『コロニー5』だ。
ぼくたちの脳に埋め込まれているマイクロチップの翻訳機能のおかげで、言語のちがいについては問題にならなかった。
しかし、言語以外の部分、価値観や文化のちがいというのは、マイクロチップでは解決できない大きな問題だった。
はじめは、そういうまったくちがった文化や価値観を持った人同士が衝突することも少なくなかったらしいけれど、時間が経つにつれて、そういったちがいは徐々にすり合わされ、どのコロニーもほとんど同じような形にまとまっていった。
コロニーの大きさは、だいたいむかしの人間たちにとっての都市一つ分くらいで、その大きさは時代を経るごとにどんどんと狭くなっていった。
いまでは、地球のほとんどの場所に人は住んでいなくて、旧市街とよばれる大勢の人が退去した無人の廃墟が広がっている。
コロニーという新しい集団の形を得た人間は、『スリープ計画』に従って順調に数を減らしていった。
計画がはじまった最初のころは、そのまま子どもの数が減り続ければ、宇宙の終わりが地球へとやってくる前に余裕をもって種を絶えさせることができると考えられていた。
しかし、その見込みは途中で大きく外れることになる。
ある時期を境に、突然子どもの数が増え始めたのだ。
『スリープ計画』に反対する人間や、教育制度の廃止によって教育を受けなかった人間‥‥。そういった一部の人間たちが、『スリープ計画』を無視して、それぞれで勝手に子どもを産み続けていたのだ。
『スリープ計画』に従っていた人間たちは、彼らの行動に戸惑い、計画に従うように呼びかけていた。
“あなたたちのその行動で苦しむのは、あなたたちの子孫なんですよ”と。
けれど、彼らはそんな忠告を聞くことはなく、自分勝手な行動を続けた。彼らの子どもや子孫たちもまた、彼らと同じように子どもを産んだ。
それが積み重なった結果、宇宙の終わりを生きてむかえる世代が誕生してしまった。ぼくの親の世代だ。
これは、計画の失敗を意味していた。
人々は、計画の失敗に落胆し、宇宙の終わりとともに死ななければならない者たちを哀れんだ。
『マルーン(残される者)』──本来産まれるはずのなかった者たち。それが、ぼくたちにつけられた名前だった。
ぼくの母もまた、『マルーン』だった。ぼくを産んですぐにぼくを放り出した後、よくない薬を飲みすぎて死んでしまったらしい。父親は誰だったのか、よくわからないとコロニーの老人たちは言っていた。
ぼくは、『マルーン』のなかでも一番若い世代だ。ぼく以外には会ったこともないくらいに。
コロニーの老人たちは、本当なら『スリープ計画』で最後の世代になるはずだった世代で、彼らは『マルーン』を、特にぼくのことを、心の底からかわいそうなものを見るような目で見てくる。その視線が嫌いだったぼくは、その目のなかになるべく入らないように、老人たちと顔を合わせなくてすむように隠れるように生きていた。
ぼくたちは、地球に残った人間の子孫だけれど、他の惑星に移住していった人々がどうなったのかはわからない。今では多惑星との交流は完全に途絶えてしまっていた。
彼らはうまく種を終わらせたのだろうか。それとも、地球のぼくたちと同じように、『マルーン』が生まれたのだろうか。
ぼくにそんなことが分かるわけもないけれど、さびしい思いの中で死んでいく人がいなければいいと思う。だってぼくは、そんな最期を迎えるのがこんなにも恐ろしいから。
ぼくたちは、寿命をまっとうすることなく、宇宙とともに死んでいく。そういう運命にあるのだ。
◆
5368年9月22日
家でくつろいでいると、突然、来客をしらせる音が鳴った。
マイクロチップから伝えられる情報から来客が誰だか分かると、ぼくは応じたくない気持ちに襲われたけれど、そんなわけにもいかないので渋々扉をあけた。扉の前には、おじい‥‥、コロニー長がいた。
おじいは車椅子を使っている老人が多いコロニーのなかでは、体がまだしっかりしている方で、自分の足で歩き、背筋もしゃんと伸びている。身だしなみにも気を使って、着ている服はいつも綺麗にアイロンがけされていて、実年齢よりもずっと若く見えた。
ただ、最近では少しずつ体が痩せて、歩くのもみるみるうちに遅くなってきていた。植物が枯れていくように、急速に身体におとろえがきているようだった。
それでも、最期は生命維持装置は絶対につけないと言い続けている。
「また、コロニーの外に出たそうだね」
目が合って一番にそんなことを言われた。
決して強い言い方ではないけれど、その言葉にはぼくの行動を責めるような色がふくまれているのを感じた。
「コロニーの外は、洗浄も行き届いていないのだから、あまり出ないようにしなさい」
基本的にぼくに関わろうとしないコロニーの老人たちの中で、おじいだけはこうしてぼくのところへ来てその行動をとがめてくる。
ただ、なにがなんでもぼくを止める気はないようで、言葉でのお説教にとどまっている。
おじいに限った話ではないのだけれど、このコロニーに住む老人たちは、みんな何ごとにも強い関心を抱くことがないようだった。
彼らの過去を知っているわけではないけれど、最後の世代として宇宙の終わりと向き合い続けたことで、他人や何かに興味を持つだけの気力も失ってしまったのかもしれない。
ぼくは、おじいの言ったことに返事をしないことで、おじいの説教に従うつもりがないことを示す。
ぼくたちの間に、気まずい沈黙が流れた。
おじいはその間もぼくから目をそらさず、じっとぼくの顔を見つめている。
たまらなくなって、ぼくの方が目を逸らした。
目を逸らした先にある鏡に映った自分の顔は、一目で決まりが悪そうにしているのがわかるような酷い顔をしていた。
おじいの目はいつも純水のように澄んでいて、まるでこちらのこころの中を奥底まで見通すような視線を放ってくる。きつい言葉を投げかけられるわけでも、激しく怒られるわけでもないけれど、ぼくはおじいのそんな視線にいつも耐えられないのだ。
だから、結局いつもぼくはおじいに自分の考えを伝えたり、ましてや説得するなんてこともできずに、なあなあで話が流れてしまう。
‥‥自分が逃げているだけだということはわかっている。けれど、やっぱり怖いものは怖いのだ。
いつまで経ってもうんともすんとも言わないぼくの様子から、らちが明かないと思ったのか、おじいは突然まったく違う話をふってきた。
「ほかの『マルーン』たちは、定期的に集会のようなものを開いて集まっているらしい。‥‥トーマは彼らとは話さないのか」
「みんなずっと年上の大人だよ?話すことなんてないよ‥‥」
同じマルーンと言っても、コロニー5にいる『マルーン』のほとんどは、ぼくの母親と同じくらいの歳なのだ。そんな年上の人と話せることなんて、ぼくにはない。
おじいはただ一言、「そうか」と言うと、ため息をついた。
‥‥なんなんだろう。いつも突然来て、説教をして、心配しているつもりなのか?普段は放ったらかしのくせに。たまに家を訪れては偉そうに説教をしてくるだけで、どうしてぼくが従うと思っているのだろう?
考えていたら、怒りが湧いてきた。その怒りをぶつけてやろうと口を開きかけたとき、べつの老人がおじいを呼ぶ声が聞こえてきた。
老人は車椅子に座っていて、そこから伸びる管が体のあちこちに繋がっている。生命維持装置をつけているのだ。
「おぉい、コロニー長や。旧市街の方から『ゲイザー』が来ましたぜ」
「なに?」
おじいは、ぼくから目を離すと、声をかけにきた老人の方に顔を向けた。ぼくはラッキーだと思って、「それじゃあ」と一言声をかけると、扉を閉めた。
おじいは慌てたようにこちらに視線を戻したようだったけれど、もうそのときには扉が閉まろうとしていたのを見て、諦めたようにまた視線を老人の方に向けたようだった。
がちゃん、と扉が閉まると、扉の向こうでおじいと車椅子の老人が話しているのが聞こえてきて、なんとなく、扉の前でそのまま話を聞いていた。
「何人の隊なんだ?」
「それが、一人の大男と、小さい女の子の二人だけなんですわ」
「いやに少ないな。しかし、もうずいぶん長い間見かけなかったから、すっかり廃れたものだと思っていたが」
「わたしもそう思ってたんですがね。でもどうやら一時的な滞在ってわけじゃなく、大男の方が言うには永住したいということなんですわ」
「すぐに行く。ともかく話を聞いてみなければ」
「とりあえず身体と持ち物の殺菌はしてもらって、今は集会所の方に案内してますよ」
その言葉を最後に、車椅子の駆動音と足音が鳴って、それが扉の前から離れていく気配がした。
コロニーへの来訪者なんて、ぼくが産まれてからはじめてのことだ。
いったい誰が、どんな目的で来たのだろう?
好奇心にかられたぼくは、さっきはおじいを拒絶するように閉めた扉をもう一度開けて外の様子をうかがうと、ぱっと外に飛び出して、コロニーの集会所へと続く道を走り始めた。
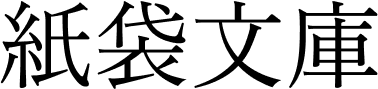


.png)
.png)